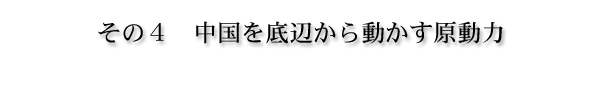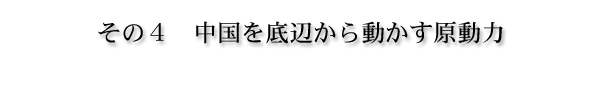|
 |
| No.23-4 |
平成20年12月19日 |
 |
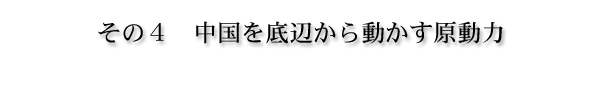 |
 |
|
田母神俊雄の「日本は侵略国家であったのか」と題する論文は、体裁・内容とも酷い代物である。まともな学者や研究者であれば、これを正面から取り上げようと言う気は恐らく起こらないだろう。「刀の錆」であると同時に時間の無駄だからだ。
にもかかわらず、私はこれを看過できないと感じている。田母神個人の思惑やアパグループ代表某の個人的な言動は別として、田母神を道化者に仕立てて、彼らのイデオロギーを強烈に社会にアピールしようという見えざるものの意志を感じるからだ・・・。
前回まで引用した「田母神論文」の続きを引用しよう。
| 『 |
・・・これ(蒋介石国民党の頻繁なるテロ行為)に対し、日本政府は辛抱強く和平を追求するが、その都度蒋介石に裏切られるのである。実は蒋介石はコミンテルンに動かされていた。1936年の第2次国共合作によりコミンテルンの手先である毛沢東共産党のゲリラが国民党内に多数入り込んでいた。コミンテルンの目的は日本軍と国民党を戦わせ、両者を疲弊させ、最終的に毛沢東共産党に中国大陸を支配させることであった。我が国は国民党の度重なる挑発にがまんしきれなくなって、1937年8月15日、日本の近衛文麿内閣は「支那軍の暴戻(ぼうれい)を膺懲(ようちょう)し以って南京政府の反省を促す為、今や断乎たる措置をとる」という声明を発表した。我が国は蒋介石により日中戦争に引きずりこまれた被害者なのである。』 |
もうどこから手をつけていいかわからない支離滅裂な文章である。ただはっきりいえることは、田母神は日本語表現能力に問題があるだけでなく、中国近現代史の素養も知識も全く持ち合わせていないことだ。
第2次国共合作成立はあとでも見るように、1937年(昭和12年)9月である。1936年(昭和11年)12月に生起したのは、第2次国共合作のきっかけとなった「西安事変(事件)」である。
年代を間違えるのは構わない。われわれ歴史の素人には良くあることだ。(しかしいくら素人でも、書き物にして発表するときは、信頼できる文献に当たって確認するだけの慎重さはもっているが・・・。)
しかしいくら素人でも生起の順番は間違えない。歴史には事件相互に連関があるからだ。
1936年12月、奉天軍閥の張学良は、国共が相争うべき時ではない、共同して「抗日戦争」にあたるべきだとして、西安で蒋介石を監禁し「8項目の要求」を突きつける。蒋介石は結局この要求をのむ形で釈放される。
1937年(昭和12年)2月、この西安事件の結末を受けた形で中国共産党が、4項目の国共合作へ向けた妥協提案を示す。
|
|
1937年(昭和12年)7月7日、問題解決を一気に行おうとした日本の支那駐屯軍は、蘆溝橋事件をきっかけに一斉に華北で軍事行動を起こす。これを見て日本政府は、同じ8月に上海に増軍、一気に全面戦争に拡大し、日中戦争となる。
近衛がいわゆる「近衛声明」を発したのはこの時、1937年8月である。正確に引用すると、
| 『 |
支那軍の暴戻を膺懲し、もって南京政府の反省をうながすため、今や断固たる措置をとるのやむなきに至れり』 |
である。
この全面戦争化で加速したのが、第2次国共合作の動きである。
近衛声明に対して、同じ8月、それまで対日抗戦に消極的だった蒋介石もついに、「日本軍の止まる事なき侵略に対して自衛抗戦」声明を発する。中国共産党もこれに呼応するかのようにこれも同じ8月、陝西省洛川で中央政治局拡大会議を開き(洛川会議)「抗日救国十大綱領」を発表する。 |
 |
【蘆溝橋事件当時の写真。
歩いているのは日本軍】
(蘆溝橋歴史博物館の展示写真より) |
 |
【現在の蘆溝橋。
欄干・橋の真ん中の石は
昔のまま残されている。】
クリックすると大きな写真で
ご覧いただけます。
photo by sarah amino |
|
|
1937年9月、中国共産党が「国共合作宣言」を行い、蒋介石国民党がこれを受け入れる形で「第2次国共合作」が成立する。
1937年8月15日の「近衛膺懲声明」に触れる限り、「第2次国共合作」がそれ以前に生起することはあり得ないのだ。
ただ一つ可能な説明は、1936年の西安事変(事件)を、田母神は「第2次国共合作」だ、と思いこんでいたというところだろう。また第2次国共合作と近衛声明に象徴される日中全面戦争化の関係も理解できていない。
| ( |
教養人であり、自らも相当な学識をもっていた岸信介もあの世で、「とんま、間抜け、だからオレは田母神を使うのはイヤだ、といったんだ。」とぼやいていることだろう。) |
|
|
 |
|
前に引用した田母神の文章はどこから手をつけていいかわからないほど支離滅裂なので、例によって田母神はほっておいて、中国の歴史をたどってみよう。
話は「21ヶ条の要求」の後、中国人民の矛先が帝政ロシアから日本の帝国主義に移行した第一次世界大戦中にさかのぼる。
日本と妥協した袁世凱は、1915年(大正4年)12月、念願の帝政復活を行い、自ら皇帝の位に就こうとする。「21ヶ条」の要求を飲んだ袁世凱を中国人民が完全に見放していることに袁はまったく気づいていない。袁世凱が皇帝についた途端、麾下の軍人や高官が次々に辞職したばかりか、反対党に結集し始めた。15年12月雲南で帝政反対の蜂起が起こるとたちまち10省が呼応した。袁世凱は16年3月帝政取り消しを行ったが、反対勢力は袁世凱の大総統辞職を要求して対立した。その年の6月袁世凱は死去する。
袁世凱の死去によって、統一政権に空白がうまれた中国は、この後軍閥割拠の時代を迎える。軍閥というのは地元地元の地主や有力者の支持と自前の軍隊をもった地方権力である。軍閥の長は勢い半封建的な専制君主とならざるを得ない。
袁世凱の場合は、清朝滅亡後に生まれた政治権力だから、清朝の後継者という意味での正統性は持ち得ない。彼は曲がりなりにも正当な手続きを経て成立した中華民国の大総統だから、政治的正統性を持っている。しかし彼の軍事基盤は北洋軍閥と呼ばれている。いわば軍閥の親玉的存在のように見なされている。ここは私がよく分かっていないところだが、彼が帝政をめざしいったん帝政が成立した時点で、中華民国に由来する政治的正統性を放棄したこと、それから彼の体質や政治スタイルが軍閥のスタイルそのものだったからではないか、と考えている。(どなたか教えてくださるとありがたい。) |
|
 |
|
袁世凱の北洋財閥は、大きく2つに分裂する。一つは段祺瑞(だんきずい)を長とする安徽派で日本の支援を受けている。一つは馮国璋(ふうこくしょう)を長とする直隷派で英米の支援を受けている。また満州には張作霖の奉天派、山西省には閻錫山(えんしゃくざん)を長とする軍閥が存在していた。そう言う意味では蒋介石も浙江省を地盤とする軍閥の長である。このうち張作霖は日本と結びついており、蒋介石は英米と結びついていた。このほか雲南には唐継尭(とうけいぎょう)、広西には陸栄廷(りくえいてい)、湖南には譚延(門に豈と書く)(たんえんがい)、広東には陳炯明(ちんけいめい)などが割拠していた。
つまり中国大陸全体は、袁世凱亡き後全国に統一政権が生まれず軍閥が地方地方を支配する体制に移行し始め、しかもその軍閥の背景には、列強が控えているという極めて不安定な、半植民地状態になった。
半植民地状態になったというのは、こうした軍閥は自身の利益のために背後の列強に、自身の権力の及ぶ範囲で権益を売り渡していったからである。その他、こうした軍閥は自身の軍事費調達のために支配地域の人民から搾取を強めていった。
|
|
 |
|
代表的な例は『西原借款』である。
「21ヶ条の要求」で強硬姿勢を見せた大隈重信内閣に変わって、1916年(大正5年)10月には寺内正毅内閣が成立した。この寺内の私的な使節が西原亀三
(http://ja.wikipedia.org/wiki/西原亀三)である。
その頃、北京政府は段祺瑞(国務総理)が実権を握っていた。寺内内閣は段に対して強硬姿勢ではなく懐柔姿勢で臨んだ。つまり中国の「ハード支配」政策から、ひも付き「ソフト支配」政策に転換する。こうして発生したのが『西原借款』だ。
1917年(大正6年)1月から1年半の間に約3億円の資金が段政権に与えられた。借款の形はとっているものの、実際には資金投入でほとんど返還されなかった。見返りに日本には様々な利権が日本へ流れ込んだ。
要するに「日本の大陸侵略」とは、日本(の帝国主義勢力)のための、一方的利益のための経済的・政治的・軍事的支配拡大努力の総称であり、大隈のように軍事力を露骨にちらつかせながら侵略する場合もあるし、寺内のように金で政権を買うようにして侵略する場合もあった。
これ以降、大隈流の「ハード支配」、寺内流の「ソフト支配」の2つの流れが、日本の大陸支配の大きな潮流になり、昭和の幣原外交が完全に息の根を止められるまで、あざなえる縄のように「大陸侵略」が進行していく。
| ( |
皮肉なことに「ハードの大隈」は財閥にバックアップされた政党政治家であり、「ソフトの寺内」は藩閥勢力を代表する陸軍元帥であった。なお、中国の『軍閥』という言葉を念頭に置いてみると、正当な政治性を欠くと言う意味で、『藩閥』『財閥』という言葉はその本質を言い当てたうまいネーミングのように思える。) |
段祺瑞は対独参戦のための軍備力増強を名目に『西原借款』を行い、結局自己勢力拡張を図るのだが、これに対して軍閥間の勢力争いの様相を呈していく。 |
|
 |
|
しかしこうした軍閥間の勢力争いにばかり目を奪われていると、結局中国の勝利者となっていく勢力がいかにして生まれ、いかなる努力を重ね、何をめざして戦ったかが見えなくなる。一番肝心な点は、何が主要な要因となって彼らを勝利に導いたかが分からなくなる。それは現在の中国の政権基盤の中心潮流でもある。つまり現在の中国が分からないと言うことでもある。
「コミンテルンの手先の毛沢東」などという我が田母神クンなど典型である。
| ( |
それにしても彼の理解はあまりに幼稚でマンガ的だ。それにしても、また繰り返しになるが、彼のような幼稚な男がどうして航空幕僚長になったのか。自衛隊自体が幼稚なのか。だとすれば何故税金で自衛隊を養って置かねばならないのか。「田母神論文」が自衛隊廃止論の導火線になぜならないのか。本当に不思議である。) |
袁世凱の帝政運動が進められている中で、儒学の教養に裏打ちされた、中国伝統の「知識人」にも大きな変化が現れてきた。象徴的には1915年(大正4年)上海で陳独秀らが「青年雑誌」(のち「新青年」と改題)を創刊したことだろう。
1905年(明治38年)すでに科挙は廃止されており、その時代の若い人たちは近代的学校教育を受けて育っていた。列強の侵略に悩み苦しむこうした若い層に、ヨーロッパで生まれた近代民主主義の思想と文化の必要性を訴える「新青年」は、希望の光をともしたといえるだろう。実はこうした中国の近代的知識人の育成には日本も大きく貢献している。
前掲の「中国近現代史」(岩波新書)59Pに記された註によると、1901年(明治34年)にわずか280人だった日本の中国人留学生は、4年後の1905年には約8000人(うち女子100人)、翌1906年(明治35年)には、1万7860人余りと激増したという。
こうした留学生の中から、新しい民主主義の思想や革命の思想を学んで中国に帰り、中国の近代化に貢献し革命家になったものも多くいた。この時の日本の役割は誇りに思っていいだろう。
この動き(「新文化運動」という名の思想革新運動)は、北京大学の改革を実現する。
1907年1月(明治40年)、北京大学の学長に就任した蔡元培(さいげんばい)は、北京大学の大改革を行う。すなわち清朝末期の学制改革で清朝高級官吏養成機関として世俗的な立身出世を気風としていた北京大学を、真に学問研究の場にしていこうという目的をもったこの改革は、当代一級の人物の招聘に全力を注いだのである。
『新青年』を創刊した陳独秀、文学者だった胡適(こてき)、後に中国共産党初期の指導者になる李大釗(りたいしょう)、周作人(魯迅の弟)などが北京大学に集まり北京大学は、「新文化運動」の中心地になっていくのである。 |
|
 |
|
一方伝統的に農民社会だった中国社会にも急速に労働者階級が産生していた。欧州が第一次世界大戦に忙殺されている間に、関税自主権や様々な不平等な取り決めにも拘わらず、中国国内では軽工業を中心に民族産業資本が発展した。一方鉄鋼、石炭、機械など社会の基幹産業はほとんど外国資本に押さえられていた。大戦期間中に日本とアメリカは対中国投資を激増させていた。日本は1913年(大正3年)から1919年(大正8年)の間に対中国投資をほぼ2倍半に増やし、紡績業に例をとると13年の紡錘数11万錘から19年には33万錘となり、ほぼ全中国紡錘数の5割近くを占めた。アメリカも同じ時期に対中国投資を2倍にしている。(以上前掲書「中国近現代史」P84-P85)
この間工場労働者も約60万人から約200万人へと増えている。しかも彼らは、低賃金・長時間労働の上、集会・結社・労働運動は刑事罰を以て禁止されていた。
われわれが「侵略」の概念を扱うとき、その軍事的側面に目を奪われるのではなく、その経済的側面に目をしっかり据えねばならない。「侵略」の動機は「経済的利益」である。政治が経済的利害を調整し得なくなったときにはじめて軍事的暴力が発動され、軍事的暴力の下に政治を支配し、経済的利益を獲得するのである。これが侵略のパターンである。 |
|
 |
|
中国社会がこうした列強資本やその傀儡政権による収奪に対して激しく抗議し立ち上がるのは、はや時間の問題だった、と言うことができよう。
1919年(大正8年)5月4日、北京大学の学生が列強の収奪に抗議して立ち上がった「5・4」運動には最低限、以上のような中国内部の条件があったのである。
「5・4」運動にはこのほか、最低限2つの外的条件をあげておかねばならない。
一つは「ウイルソンの14ヶ条の提案」である。
第一次世界大戦も終末に近い、1918年(大正7年)1月18日、アメリカの大統領ウッドロー・ウイルソン(Woodrow Wilson http://en.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson )は、上下両院合同会議で演説を行った。これは第一次世界大戦後の世界秩序に関する提案で「14ヶ条の提案」と呼ばれている。(日本語訳全文は次のサイトで読むことができる。http://ww1.m78.com/topix/fourteen%20points.html)
この演説のうち、ウイルソンが明確に示した14ヶ条の提案部分をこのサイトの訳から抜き出しておく。
| 『 |
1. |
平和条約はいかなる国際間の秘密とりきめがあってはならない。外交は常に正直に実行され、公開されなくてはならない。 |
|
2. |
領海外の公海における通行は、国際条約の実行のため強制措置が実施された場合を除き自由でなければならない。 |
|
3. |
経済障壁は出来得る限り除去すること、および平和について合意し維持しようとする全ての国の交易条件を平等化すること。 |
|
4. |
国内治安の維持に必要な最低の範囲までの軍縮の適正な保証。 |
|
5. |
国内治安の維持に必要な最低の範囲までの軍縮の適正な保証。 |
|
6. |
ロシア領からの撤退。ロシアに影響する全ての問題の解決に当たっては、世界の国々の最良で自由なる協力により困難でないまた名誉ある方法で、自らの政治発展と国策を決定できるようにしまた自ら選んだ政府のもとで、独立国家の社会に誠意をもって迎え入れること。そして歓迎以上にロシアが必要としまた欲するあらゆる援助を行うこと。数ヶ月以内にロシアにあたえられる旧同盟国の援助はその善意、自らの利害から離れた必要性の理解そして知識と利己的でない同情を計るうえでの厳しい試金石となろう。 |
|
7. |
ベルギーからの撤退と復旧。これは世界中が支持すると思うが、他の独立国が共通してもつ主権をいかなる形でも損ねてはならない。これほど、互いの政府間の関係を決定する国際法における国家間の信頼を回復させる手段はない。この修復措置なくしては国際法のすべての構造と有効性は永遠に損なわれるだろう。 |
|
8. |
全フランス領土は解放されねばならない。そして被害を受けた部分は復旧されねばならない。アルザス・ロレーヌについて1871年になされたプロシャのフランスにたいする悪事は正されるべきだろう。この措置は世界を50年間近く不安定に陥れた。その矯正は全ての関係者に平和をもたらすだろう。 |
|
9. |
イタリーの国境線の修正は国民の国籍に基づき明らかに認識できる線で決定される。 |
|
10. |
国家間における地位は保全されかつ保証されるが、オーストリア-ハンガリーの各民族には自治政府の設立の機会が与えられるべきである。 |
|
11. |
ルーマニア、セルビアそしてモンテネグロからの撤退。占領地域は復旧されねばならない。セルビアには海への出口が与えられる。バルカン諸国の国境線は国籍や忠誠による歴史的に定められた線にもとづき、友好的な話し合いで決定されよう。そしてバルカン諸国の政治的経済的独立と領土保全の国際的保証は含まれねばならない。 |
|
12. |
いまあるオスマン帝国のトルコ部分の主権は尊重される。だがトルコ支配にある他の国籍の人々は生存の保証と決して損なわれることのない自治政府設立の機会が与えられる。ダーダネルス海峡は全ての国の船舶と通商へ、自由通行路として開放されるべきだ。 |
|
13. |
ポーランド人による独立国家が建設されるべきで、疑いなくポーランド人が住む地域が含まれるべきである。そして海への出口が確保され、政治的経済的独立が領土保全とともに国際的条約で保証されるべきだ。 |
|
14. |
大小の国に政治的独立と領土保全の供与を目的として特別の条約で形成される国家間の全般的団体が設立されねばならない。 』 |
|
|
 |
|
この演説時アメリカの上下両院議会の圧倒的多数は支持だったという。
中国への直接の言及はしていないものの、ウイルソンの提案は、帝国主義的侵略への反対、民独独立・自決の原則を高らかに謳っており、永年列強の侵略に苦しめられてきた中国の人民とって、この演説は暗闇の中の一条の希望の光として映ったことは想像に難くない。
この演説から丁度1年後の1919年(大正8年)、第一次世界大戦の講和会議である「ベルサイユ講和会議」に世界の植民地・半植民地国の人たちの期待が集まったのは当然であろう。
しかしベルサイユ会議は、あからさまな報復主義、帝国列強の利権・植民地獲得合戦に終始した。「ウイルソンの14ヶ条」への裏切りである。
いったん希望を抱いた中国人民の失望は、希望の分だけ大きかった。と同時に侵略者は自分たちの力で追い出さなければならないことをあらためて思い知ったのである。
というのは中国人民は目の前でロシア革命を見たからである。
ロシアの10月革命は、1917年(大正8年)11月に起こる。ウイルソンの演説は、実にロシア革命の3ヶ月後に行われる。革命政府はドイツと直ちに休戦にはいる。
|
|
 |
|
以下長い引用になるが、ご辛抱願いたい。著者はイギリスのピューリタン革命の研究者として著名なオクスフォード大学のクリストファー・ヒルで、本のタイトルは「レーニンとロシア革命」(岩波新書 訳者岡稔 1971年5月20日第23刷)である。
| 「 |
ロシアの人民は1917年に二つの革命をおこして皇帝(ツアーリ)を廃位し、国教会を廃止し、貴族を収奪した。イギリスやフランスでは、こういうことがもっと早くにおこなわれた――つまりイギリスでは17世紀の内乱の時(*ピューリタン革命を頂点とするブルジュア革命のこと)、フランスでは1789年の革命(*フランス革命のこと)のときに、おこなわれたのである。だから、ロシア革命を研究するばあいに、まず、われわれがたてるべき問題は、1919年に――つまり西ヨーロッパがわりあい平和的・立憲的に発展していたときに――何故にロシアではこういう暴力沙汰がおこったのか?と言う問題ではなくて、ロシアではこういう事件が、西ヨーロッパよりも、何故にこんなにおくれていたのか?と言う問題である。
初めのような問題の立て方をすると、流血の革命がなにかロシア特有のもののように考えがちである。そうすると、まだろくに何もわからないうちに、スラブ魂がどうのこうのという、愚にもつかぬおしゃべりをはじめてしまうことになる。
1917年の革命にはたしかにロシア独特の点もある。しかしロシアはこの革命によって、ちょうどわれわれイギリス人が1640年に、フランス人が1789年にしたのと同じ仕方で、中世と縁を切ったのだということをまず、最初に、はっきりさせておく必要がある。そうすればわれわれはロシアの発展が何故にこのようにおくれていたのかという問題をたてることができる。
ロシアの発展が遅れていた主な理由は、ロシアに独立した中産階級が生まれなかったことにある。西ヨーロッパでは、17、18、19世紀は資本主義的発展の黄金時代で、この時代に、商工業階級が地主貴族と絶対王政から、まず最初に経済上の権力を奪い取り、ついで政治上の権力を奪い取った。西欧の資本主義がはなばなしい発展をとげていた間、ずっとロシアは経済的に停滞状態にあった。ロシアの商業は外国人の手に握られ、ロシアの貧弱な工業は皇帝や地主によって運営されていた。ロシアの中産階級は発展が非常に緩慢で、おくれていて、活動の規模も小さく、政治的な独立性は全くなかった。だから、西欧の勃興期のブルジュアジーの哲学であった自由主義が、ロシアでは全然社会的に根付かなかった。
権力は昔のままの専制的な皇帝の手に集中されていて、皇帝は貴族に支持されながら、融通の利かない腐敗した官僚を通して国を統治していた。貴族は農村では全能の権力を持ち、文武のあらゆる要職を占めていた。」(12P-13P) |
|
|
 |
|
| 「 |
・・・それまでに(*ロシア)国内に浸透していた自由主義思想は、裕福な人々だけしか接するこのできない外来思想の一部として、入ってきたものであった。ところが西欧では、これらの思想は誰も異論を唱えないものとして、確立していたのである。」(P13) |
| 「 |
・・・保守的なスラブ主義者は、『良き古きスラブ的風習』を理想化し、ロシアの社会発展が西欧より300年もおくれていることを、まるで美点のように見なそうとした。もうすこし民主的な学派の思想家は、ロシアが工業化を抜きにして、直接に、一種の農民的な無政府主義的社会主義に進むことを夢見ていた。」(P13-P14) |
| 「 |
農民の抱いていた政治思想と言えば、要するに、彼らにとっては神と同じくらい仮説的な存在である皇帝が、将来いつかは、彼らの不幸を救い、抑圧者を罰してくれるだろうという、漠然とした宗教的な願望に過ぎなかった。」(P14) |
| 「 |
19世紀の終わりの30年間の急速な工業の発展に伴って、社会的変化が起こった。だが、工業の発展が主として外国資本によってまかなわれたので、土着の中産階級の地位はほとんど変わらなかった。資本も技師も政治思想も皆西欧に依存していたロシアのブルジュアジーは、自分より経済的に強力な競争相手から保護してくれるように帝政国家に頼まなければならなかった。ロシアのブルジュアジーにとっては、君主制と地主貴族の政治的支配に挑戦することなど全然思いもよらないことだった。20世紀に入って、近代戦の重圧によって、当時の体制が全く無力で腐敗していて秩序を維持し、財政を安定させることさえできないことが、もう一度、明るみに出るまではそうであった。」(P14-P15) |
| 「 |
今度は、前と違った勢力が舞台に出てきた。それは工業化によって生み出された、労働者階級の運動である。ロシアのプリレタリアートは、貧弱なひとかけらの土地から引き離されて、工場や鉱山に投げ込まれて、不衛生なバラックに群れをなして住み、酷い低賃金と過度の労働を強いられていたから、団結と階級連帯と組織化と大衆的革命運動の発展には、この上なく好都合な状態にあったので、急速にひとりでに自覚するようになった。ロシアでは資本主義的発展がひじょうにおくれてはじまったので、多くの工業部門が手工業段階からもっとも近代的な設備のある大工場へ一足飛びに移った。工場を経営していたのは、外国の商社か、またはそれより能率の悪い民族資本家で、外国の商社は早く収益を上げることを第一に考えていたし、また、民族資本家は費用を切り詰める以外に競争に耐える力がなかった。そこで、1877年から8年の露土戦争の死傷者よりも多くの人々が、毎年ロシアの工場で死傷すると言うことになった。そのため、階級闘争が特に露骨になった。」(15P-16P) |
|
|
 |
|
| 「 |
中産階級の場合と違って、ロシアのプロレタリアートは西欧から、まだ生命力の尽きていないイデオロギーを、受け継いだ。1848年の革命(*1848年革命。ヨーロッパ各地に起こった。革命の主体はブルジュアジー主体からプロレタリアート主体に移行しつつあった。つぎの日本語Wikipediaの記述は優れている。http://ja.wikipedia.org/wiki/1848年革命 )と1871年のパリ・コミューン(*世界最初の労働者による自治政権。次の記述は参考になる。http://ja.wikipedia.org/wiki/パリ・コミューン )とマルクス、エンゲルスの理論的著作と第二インターナショナル等の政治的経験――これがあいまって、一個の社会主義学説となって労働者階級特有の革命的伝統が生み出された。マルクス主義理論によると――レーニンはこの理論の立場に立っていたのだが――『プロレタリアート革命』は丁度1640年(イギリス・ピューリタン革命の年)や1789年の『ブルジュア革命』が、中産階級の支配に導いたように、労働者階級の支配を通して、社会主義を打ち立てるべきものであった。」(P16) |
ここで、ヒルが描写するロシア革命前夜のロシア社会の基本構造(社会の下部構造または土台)は、ロシア的要因や中国的要因などの表層的要因、日本の侵略などといった外部的要因を取り除いて考えれば、一卵性双生児のようにそっくりの構造を持っていたことが分かる。
ずいぶん「5・4運動」にたどり着くまで手間がかかって申し訳なかったが、こうした中国人民にとって、眼前に繰り広げられた『ロシア革命の成功』は大きな励ましと勇気づけとなったにちがいない。
|
|
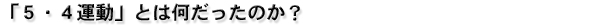 |
|
ここでもう一度まとめてみれば、
日本の「21ヶ条の要求」に代表される屈辱的な侵略の状況を基本にしながら、
| 1. |
袁世凱なきあと半封建的な軍閥割拠で、収奪と搾取が極めて強められていたこと。 |
| 2. |
雑誌「新青年」や北京大学の改革に代表されるような、近代的思想を身につけた知識人が育っていたこと。 |
| 3. |
外国資本(アメリカ資本や日本資本が急激な成長を見せていた。)や民族資本(そのほとんどは旧地主層から転化した新興資本で、外国資本への従属を強めていた)の急速に労働者階級が登場し、ほとんど半奴隷的重労働に苦しんでいたこと。 |
などの条件を内的条件とし、
| 4. |
列強の「ウイルソンの14ヶ条の提案」に対するの「裏切り」への激しい失望感と怒り。 |
| 5. |
ロシア革命成功がもたらした励ましと勇気づけ。 |
などを外的要因としながら、1919年(大正8年)5月4日、「5・4運動」が始まるのである。
「5・4運動」とは一体何だったのか、またまた長い引用になるが、「中国近現代史」(前掲書)から、関係箇所の抜き書きをする。 |
|
 |
|
| 「 |
第一次世界大戦処理のためのベルサイユ講和会議は1919年(*大正8年)1月に開かれ、中国民衆はウイルソンの14ヶ条原則に大きな期待をかけた。中国の南北両政府代表団(*南北両政府代表団とは、軍閥の流れをくむ北京政府と、孫文の流れをくむ、後に国民党と名称をかえる南京政府のことである。)は、不平等条約の撤廃と共に、山東省における旧ドイツ権益の返還、日華協約(いわゆる21ヶ条条約)の無効を希望条件として、5大国会議(米・英・日・仏・伊)に提出した。
しかし日本はすでに大戦中から英・仏・伊の各国との間に、講和会議に置いて相互に利権要求を認め合うことを密約しており、さらに北京政府との間にも山東問題処理に関する交換公文を交わして、山東利権を正式に承認させていた。
| (* |
つまり北京政府は、ベルサイユ講和会議に臨むにあたって、すでに中国人民を裏切っていたことになる。) |
北京政府はこの交換公文の中で『欣然同意する』と述べ、また山東省における鉄道敷設の援助金前渡し分2000万円をすでに日本から受け取っていた。この金はほとんど大総統除世昌(じょせいしょう)の政治資金に費消されたという。21ヶ条交渉及び山東交換公文に直接携わった曹汝霖(そうじょりん)、章宗祥(しょうそうしょう)、陸宗輿(りくそうよ)の3人は『5・4運動』の中で、『売国賊』として激しい糾弾を受けた。
結局4月29日(*1919年)のイタリアを除く4大国会議は、中国の要求を退けて日本の主張をほぼ全面的に承認することを決定した。
外交敗北のニュースは5月1日に北京に届き、国民各階層に危機感が拡がった。その中で真っ先に立ち上がったのが北京大学を初めとする、北京各大学・高専の学生たちであった。彼らは5月7日の国恥記念日に予定していたデモを急遽繰り上げ、5月4日天安門広場に3000人が集まって、『21ヶ条を取り消せ』『青島を返せ』『売国賊を懲罰せよ』と書いた小旗を振りながら市内をデモ行進し、亡国の危機を訴えるビラを市民に配った。デモ隊はやがて交通総長曹汝霖の家に向かい、警官隊の警備を破って邸内に侵入、家に放火し、居合わせた章宗祥を殴打して重傷を負わせた。この事件で学生32人が逮捕された。
我が身を犠牲に民族の危機を救おうとする学生の姿勢は、国民に強烈な衝撃を与えた。北京だけでなく上海・天津など諸団体から、学生の釈放、売国賊の罷免、講和条約調印拒否を要求する声が上がり、この事件を契機として全国至る所で大衆集会、デモ、街頭演説、日本製品ボイコットなどの民衆運動が展開された。」(同書P88-P89) |
|
|
 |
|
桜美林学園の創始者、清水安三はこの時北京にいた。同志社大学神学部を卒業した清水はアメリカに留学したあと、中国に渡り旅順・大連で布教活動をした後、北京に移り、1920年貧困に喘ぐ女子を対象とする実務教育機関・崇貞平民工読学校を開校していた。そして「5・4運動」を目撃するのである。
清水の著書「支那新人と黎明運動」(1924年・大阪屋号書店)には次のような記述がある
| ( |
そうだ。私はこの本を読んでいない。次の記述は前掲「中国近現代史」からの受け売りである。) |
| 『 |
小山をなせる日本貨物には一缶の石油がぶっかけられた。何人かの学生はマッチをすった。見る見るうちに丸みのある雲の形した紫色の煙がぽかぽか上がってゆく。・・・一人の中学生がこの日自転車にのってやって来ていた。よほど感じたものかその自転車を火の中に投げ込んだ。この自転車も日本製品だった!彼はこう叫んだ、・・・その中学生は泣いていた。私達は頭の心に寒いような刺すようなショックがぴんと響いた。』 |
清水は優れた宗教者・人道主義者の直観で、道理と正義が日本の帝国主義の側にはなく。中国人民の側にあることを見抜いていたに違いない。
「5・4運動」は6月にはいると新たな展開を見せる。日本公使館から「排日運動」取り締まりの要求が出され、これを受ける形で北京政府は学生運動禁止の大総統令を出していたから、北京学生連合会が6月3日、一斉に街頭にでて演説会を開くのは、当然逮捕覚悟である。
軍警が学生を次々逮捕し、あまりに逮捕者が多かったので、北京大学の講堂を臨時留置場にしなければならなかったほどだった。
「6月3日、北京で学生が大量逮捕」のニュースが伝わると、運動は一挙に全国に拡がった。上海では、学生のスト(罷課)をおこなっていたが、商店が一斉に閉店(罷市)、労働者もスト(罷工)に入った。港湾労働者は日本船の荷揚げを拒否した。さらに交通・通信労働者もストに入り、上海はぞの都市機能を失った。当時上海にいた北一輝も「ヴェランダの下は・・・日本を怒り憎みて叫び狂う群衆の大怒濤である。」と回想している(そうだ。これも前掲書からの受け売りである。) |
|
 |
|
日本製品ボイコット運動はそれから1年間中国各地で続けられた。特に1919年11月福州で起こった「福州事件」は、日本の帝国主義ばかりでなく、中国に進出していた日本の一部大衆も、日本の帝国主義の凶暴な尖兵となっていたことを証明する事件であった。
これは1919年11月日本製品ボイコット運動に腹を立てた福建省福州の在留日本人数十名が武装し、日本製品ボイコット運動を進めていた中国人学生を襲撃した事件である。学生といあわせた中国人警官を負傷させた事件である。襲撃した日本人集団は逮捕されたが、日本政府はこの日本人の釈放を要求して、軍艦3隻を派遣、威圧を加えたが、中国民衆の断固たる姿勢にそれ以上の行動が取れず、結局陳謝・賠償することで決着した。
しかし全体としてみれば、中国全国に割拠していた地方軍閥は、この民衆運動を弾圧していったのである。それは、一部日本の傀儡化が進んでいたためでもあるが、今日本の帝国主義に向かっている中国人民の矛先がやがては自分に向いてくることを予感したためでもある。天津・斉南ではこうした軍閥の弾圧で死傷者も出た。
こうして、「反日運動」は、半封建的な軍閥に対する「民主化闘争」「軍閥打倒運動」の様相も帯びてくるのである。
やや「5・4運動」にのめり込みすぎたかもしれない。 |
|
 |
|
これまで「大平天国運動」や「義和団運動」「平英団」など、中国人民の半帝国主義的運動を見てきたが、「5・4運動」もまた、こうした系譜の中に位置づけられる中国人民の抵抗運動であると同時に、一線を画す抵抗運動でもあった。
それは運動の参加規模が全然違うと言う点である。確かに近代教育を身につけた学生たちが先鞭をつけたのであるが、商人や労働者など広汎な一般大衆の参加があったこと、そして彼らが団結をおこないながら底辺から政治を動かしていったことなどがあげられる。ベルサイユ講和会議で中国代表団が、中国を列強の分割に任せる最終条項についに調印できなかったのは好例といえる。
さらにこの運動の中で、中国史上初めて近代的な労働者(クリストファー・ヒルの言葉を借りればプロレタリアート階級)が、主人公の一人として登場したことであった。これが後の中国革命の原動力の一つと成長していく。
また、「5・4運動」を通じて、中国の知識人だけでなく、一般大衆レベルで「何が政治課題なのか」というテーマが深く自覚されたことも大きな要素としてあげられなければならない。すなわち中国の当面する課題は、「反帝国主義運動」(それは当時の情勢に照らして言えば反日運動、抗日運動とならざるを得ない)であり、半封建的勢力を打倒する運動たらざるを得ない、ということを明確に示したと言うことができよう。
こうした運動の性格を一言で表現すれば、「民族独立革命」であり「近代的民主主義革命」と言うことになる。クリストファー・ヒルの分析をここで援用すれば、たとえばアメリカが独立戦争で1776年に達成した課題であり、フランス革命やロシア革命が達成した課題ということになる。
|
 |
| 【北京大学のすぐ近く、五四大街に沿った公園に「5・4運動」の記念碑がある。いつも家族連れの憩いの場になっている。】 |
 |
| 【記念碑には、関連した人間や文などが刻まれている。】 |
 |
【記念碑の裏に刻まれた文章】
写真をクリックすると
大きな画像でご覧いただけます。
photo by Sarah Amino |
|
| ( |
日本は明治維新、太平洋戦争での敗戦後の戦後改革を通じて、大衆レベルでの、こうした近代的民主主義革命をついに経験しなかった。これからは分からないが、これまでのところそうだった。そのことが現在の日本の、民主主義を求める市民運動の決定的弱点となって現れている。市民運動自体が、今当面する政治課題は一体何なのかを自覚できていないと言ってもいい。) |
|
 |
|
こうした中国の民族独立革命の課題、人民民主主義革命の課題は、「5・4運動」を通じて、一般大衆レベルで意識され、自覚され、訓練され、また多くの指導者を育てる孵化器にもなったのである。
長沙で毛沢東が「新民学会」、天津で周恩来が「覚悟社」を組織して本格的に革命運動に身を投じていくのもこのころ(1918年、いずれも5月)である。
今、私がここで驚くのは、中国侵略を「国家の意志」として着々と既成事実を重ね、大正初期の大隈重信流「ハード・パワー」と寺内正毅流の「ソフト・パワー」を使いわけた日本の支配層が、「中国を底辺から動かしている人民の力」に最後の最後まで、全く気がついた兆候がない、ということだ。これは一体どうしたことなのか?
「遅れてきた帝国主義」と言うだけでは説明のつかない何かがある、と思わざるを得ない。
ヨーロッパ帝国主義列強は、1848年革命、1871年「パリ・コミューン」を通じて資本主義社会の中に「労働者階級」という新たな「モンスター」(それは自分自身で育んだものなのだが)が生まれつつあり、それが自分たちに取って代わる可能性をもった新たな階級であることを痛切に自覚した。
(『共産党宣言』が出版されるのは1848年である。)
その恐れは1917年のロシア革命で現実のものとなった。だから、この後、ヨーロッパ列強やアメリカの支配層は、こうした労働者階級に対して懐柔的政策を次々打ち出していく。生活水準の向上、社会福祉制度、労働者住宅の改善、新中間階級の創設、教育制度の充実・・・。こうして国内的には労働者階級を社会主義革命の方向に追いやらない努力を重ねつつ、植民地に対しては19世紀に見せた露骨な帝国主義的対応は表面影を潜め、もっとスマートな帝国主義的侵略へと姿を変えていく。
しかし日本の帝国主義はそうではなかった。目の前に人民の力をはっきり見せられ、そうした報告が集まっているにも拘わらず、人民の力に全く気づかず、「暴徒」「共産分子」としか見なかったのである。
実はこの歴史観は戦後も一貫して日本の支配層に流れている。戦中・戦後を通じて日本の支配層のホープの一人であり、戦後アメリカの期待を一身に背負った、秀才岸信介にもその歴史観は全く欠落している。
田母神に至っては、冒頭掲げた引用論文に示されているごとく、
| 『 |
・・・実は蒋介石はコミンテルンに動かされていた。1936年の第2次国共合作によりコミンテルンの手先である毛沢東共産党のゲリラが国民党内に多数入り込んでいた。コミンテルンの目的は日本軍と国民党を戦わせ、両者を疲弊させ、最終的に毛沢東共産党に中国大陸を支配させることであった。・・・我が国は蒋介石により日中戦争に引きずりこまれた被害者なのである。』 |
というお粗末極まる認識である。
| ( |
毛沢東や蒋介石が一人二人いたって中国がどうにかなるものではない。) |
ともあれ、日本の支配層が、中国を動かす決定的な原動力を最後の最後まで視野に入れなかったことが、日本を破滅の淵に追いやった一つの大きな要因であった・・・。 |
|
| (以下次回) |