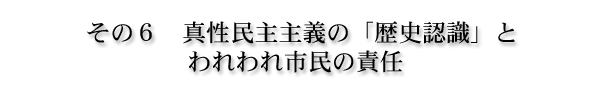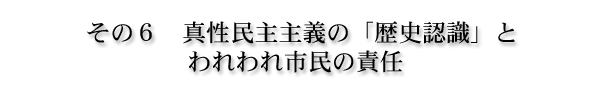|
 |
| No.23-6 |
����21�N1��1�� |
 |
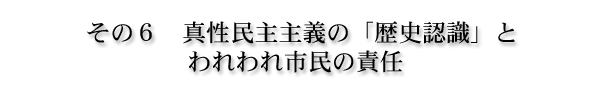
|
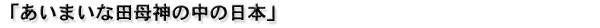 |
|
�@�c��_�́A���̘_���̒��ŁA�u�M�l�ɑ����K�͂Ȗ\�s�A�S�E�������J��Ԃ���������B�v�Ə����Ă���B���̕��͂̎��͂����܂������A���͂̂Ȃ��肩�猩�āu�Ӊ�����}�v���Ɖ��߂ł���B���邢�́u�����l�v�Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B���邢�͓c��_�̓��̒��ł͗��҂͓������ƂȂ̂����m��Ȃ��B
�@�u�Ӊ�����}�v���Ɖ��߂��悤�B�u�Ӊ�����}�v�Ƃ����̂́u�����}�R�v�Ƃ����R�����w���̂��ƍl���Ă݂悤�B
| ( |
���������ʒ����ߌ���j�������Ƃ��A�Ӊ�����}�Ƃ����A�������}�Ƃ��Ă̍����}���w���A�w�R�x�������Ƃ��́w�����}�R�x�Ƃ����B�������A�������}����w�����}�x���A�w�M�l�ɑ����K�͂Ȗ\�s�x�ł͕��ӂ��ʂ��Ȃ��B�]���Ă����͂Ƃ肠�����w�����}�R�x�Ɨ������Ă������B�Ȃɂ�珬�w�Z�̍���̎��Ԃ݂����ɂȂ��Ă������A��ނȂ��B�c��_�̓��{�ꂪ���w�����x�Ȃ̂�����B�����������܂Œ��J�ɂ������Ă��l�Ԃ͎����炢�Ȃ��̂��낤�B�j |
�@���Ɂu�M�l�v���l���Ă݂悤�B�M�l�Ƃ͒������n�ɂ������{�l�s���̂��Ƃ��낤���B���{���{�W�҂₻�̉Ƒ��A���Ɛl�₻�̊W�҂��܂�ł���낤���H�������낤�B�R�l�E�R���̂��Ƃł͂Ȃ����낤�B�u�Ӊ�����}�R�v�͌��n���{�R�ɖ\�s����������A�u�S�E�����v�����������肷��͂��͂Ȃ��A����́u�\�s�����v�Ƃ��u�S�E�����v�Ƃ����킸�Ɂu�퓬�s�ׁv�����炾�B
�@��������Ɓw�Ӊ�����}�R�x���w���n���{�l�s���x�ɑ��đ�K�͂Ȗ\�s�������������A�S�E�������w�J��Ԃ��x��������A�ƌ������͂ɂȂ�B
�@�����Ŏ��́u�͂āH�v�ƌ˘f�����ƂɂȂ�B�v��������Ȃ��̂��B����ɊY�����鎖�����B
�@�����Ŏ��͓c��_�ɂ��肢���邱�ƂɂȂ�B�u��������ł�������A����ɊY�����鎖���������ė~�����B�v�ƁB
�@�c��_�͈���������Ȃ��B�c��_�����c�����l���B����Ȏ����͂Ȃ��̂�����B���Ȃ��Ƃ����j�Ŋm�F�ł������́B
�@��������ƁA�c��_�Ƃ��̉����c�͎��̂悤�Ɍ��������m��Ȃ��B
�@�u�Ȃ������Ƃ��������̂��H�Ȃ��̂Ȃ炻����ؖ����Ă݂�B�v
�@���Ă�������́A���j�w�̖��ł͂Ȃ��A�����I�Ș_���w�̖��ƂȂ�B
�@�u����v���Ƃ͏ؖ��ł��邪�A�u�Ȃ��v���Ƃ͏ؖ��ł��Ȃ��B����͓��R�̂��Ƃł���B�]���ĂȂ����Ƃ́u�ؖ��v�����߂�l�Ԃ�����Ƃ���A���̐l�Ԃ͂܂Ƃ��ɋc�_�����邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��āA�ʂɉB���ꂽ�ړI������l�ԂƂ��āA�c�_�̊O�ɒu�����B�܂薳�������B
�@����ł́A�u�Ȃ��v���Ƃ��ؖ��ł��Ȃ��Ƃ���A�ǂ���������̂��H�ȒP�ł���B�u����v���Ƃ��w�E���A���̎�������������Ƒ����B�]���Ę_����c�_�́A���݂��Ɂu����v���Ƃ��o�������āA���̓��ۂ��A�Ó������r��������ƌ����葱���ɓ���B
�@�u�Ӊ�����}�R�v���u�����ɂ������{�l�s���ɑ�K�͂Ȗ\�s����������A�S�E���������v���A��ł�������c��_�͂���������̂ł���B���ؐӔC�͓c��_�ɂ���B
�@�c��_�͂������Ȃ��B���j�I�����Ƃ��ĂȂ������̂�����B
�@���j�I�����Ƃ��ĂȂ��������Ƃ��A���������̂悤�ɂ��ĕ`�ʂ���퓅��i������B�ł��邾���B���ɕ`�ʂ��邱�Ƃ��B�B���ɂ���퓅��i�́A���A�ǂ��ŁA���ꂪ�A����ɁA�Ȃ��A�������Ȃ����Ƃł���B�c��_�̕��͂��T�^�ł���B�c��_�̘_���Ŏ��ɋ�J����̂́A���̗��`���E���`���ł���B�������]���ǂ̂悤�ɂ����߂ł��邵�A�����]���Ă��Ȃ��ɂ��������B�ނ͎����̘_����v�z�A�����W��`�������̂ł͂Ȃ��A�����̊����Ă��错�R�Ƃ����C���[�W�������A�˂Ă���ɂ����Ȃ��B
�@������c��_�̓��{��\���\�͂����w���̂܂܂Ɏ~�܂��Ă���̂ł���B
�@�u�Ȃ������v���Ƃ��u�������v���̂悤�ɂ������Ƃ��u�E�\�v�����A�Ƃ����B���̃E�\������̖ړI�̂��߈Ӑ}�I�ɂȂ����A�u�f�}�v�����A�Ƃ����B
�@�c��_�́u�_���v���T�^�ł���B�i��������ɂ��Ă��A���̂��e���ȓ��{��\���\�͂͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����B�c��_�̕��͂������ɉ��߂��悤�Ƃ���A���̗��`���A���`���ɂقƂقƔ��ʂĂ�B�j
| �u |
���͏Ӊ�̓R�~���e�����ɓ�������Ă����B�P�X�R�U�N�̑�Q����������i�����������͂P�X�R�V�N�ł��邱�Ƃ́A��ɂ������Ƃ��肾���A�����̎��҂ɂ��w�E����Ă���B�j�R�~���e�����̎��ł���ё��Y�}�̃Q�����������}���ɑ������荞��ł����B�R�~���e�����̖ړI�͓��{�R�ƍ����}���킹�A���҂�敾�����A�ŏI�I�ɖёɒ����嗤���x�z�����邱�Ƃł������B�v |
�@���j�F���̌��A�Ƃ�����肠���炳�܂ȁu�f�}�v�Ƃ������ق����߂��B
�@�u���͏Ӊ�̓R�~���e�����ɓ�������Ă����B�v����݂Ă݂悤�B |
|
 |
|
�@��ɂ������悤�ɁA�R�~���e�����i��R���C���^�[�i�V���i���j�́A�����̍����}�𒆐S�ɂ��āA�������Y�}���܂߁A���鍑��`�E��������`�i���ڂɂ͔��R���j������ɁA�����Ŗ����������̌����������A����ɐ�������B���ꂪ�P�X�Q�S�N�i�吳�P�R�N�j�̑�ꎟ�������삾�����B���{�ł͐��Y������t���������A�c���q�T�m���v王{�M�F�̖��ǎq�i�Ȃ����j�ƌ����������낾�B
�@�Ƃ��낪�����������̎x�������́A���傤�ǂP�N��̂P�X�Q�T�N�i�吳�P�S�N�j�������Ȃ���������B
�@���̌�̑��������}�͂ǂ��Ȃ�̂��H�����}�͂P�X�Q�T�N�V�������q�i�������B���q�͍��j����ȁi�����}�햱�ψ����Ȍ��R���ψ����ȁj�Ƃ��āA�L���Ɂw�������{�x�𐬗�������B
�@��������Ȃ����Ƃ̖k�����{�͍ĂьR�����͂�����������A�i�Q�����������������B�i�Q�������́A��돂�ƂȂ���{��C�M���X�Ȃǂ̗鍑��`���́A�C�M���X�̍��`�����A����ɒ����A���n��Ԃɂ��Ă����������o�ϓI�ɓs���̂����ꕔ�����厑�{�Ƒw�i���َ��{�Ƃ���������������j�ȂǂƋ������āA���̍L���������{�Ɉ����������͂��߂�B
�@�܂�P���ɐ}��������ƁA�����Ɨ�����Ɏx����ꂽ�L���������{�i�������Y�}���Q�����Ă���j�Ɨ鍑��`���͂Ɣ��َ��{�Ɏx����ꂽ�k���R�������Ƃ����\�}�ƂȂ�B
�@�Ƃ��낪���Ƃ͂����P���ł͂Ȃ��B���̕��G���́A�����}�����̕��G���ł�����B�����}�́A�����̎O����`�ɋ����������Ɨ��h�A�������Y�}�h�A����ɗƂ̋��͊W���m�肷��u���W���A�W�[�i���ɉE�h�Ƃ��Ă����j�Ȃǂ̊�荇�����тł������B���S�ɘJ���҂ƒ����_���̓}�Ƃ����킯�ł͂Ȃ������B
�@���ɂ͌R�����x�����鐨�͂ƊK���I���v�����L���鐨�͂�����܂܂�Ă����̂ł���B
�@�P�X�Q�T�N�W���A�L���������{�����̗����A�}�����h�̜@���āi��傤���イ�����j
�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�@���āj���A�C�M���X���͂ƌ��}���E�h�ɈÎE�����Ƃ����������N����B
�@�P�X�Q�T�N�P�P���A�����}�E�h�̒��ŁA�k���x�O�̐��R�ɏW�܂��āA�w�����}�̒����狤�Y�}���͂�ǂ��o���x�ƌ��R�ƍL���������{�ɔ�����|�����͂�����ꂽ�B�i���R�����j
�@�������������}������̒��ŁA�߂��߂����p���������̂��Ӊ�ł���B�Ӊ�̌��͂̌���́A�ނ��R�������Ă������Ƃł���B��ꎟ��������̎��A�����}�����O�̌R���͂������߂ɉ����R���w�Z��n�����ďӉ�����̍Z���ɏA�C�������Ƃ͑O�ɂ����������B���������o�������Ӊ�́A�����}�̌R�������肻�̌R���I�w�i�̌��ɓ}�����͂��ێ����Ă������B
�@�P�X�Q�U�N�i�吳�P�T�N�j�R���A�Ӊ�͍����}�C�R�̒��̋��Y�}���q����������Ă��ƌ��������̂��Ƃɉ����߂�~���āA�}�����Y�}����ߕ߂��A�R�~���e�������瑗��ꂽ�\�A�l�ږ�c�̏Z���Əȍ`��H�ψ�����͂����B���ꂪ���R�͎����ł���B
�@���̎�����ʂ��āA�����}�R�̒P�ɑ��Ăɂ����Ȃ������Ӊ���A�R���ψ����ȂɏA�C����ȂǁA�R���͂�w�i�ɍ����}���������Ă����̂ł���B |
|
 |
|
�@�����Ő���Ƃ��Ӊ���ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�Ӊ�j�̐����I���i���݂Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@�Ӊ�͂P�W�W�V�N�i�����Q�O�N�j���܂�B�P�X�̎��ɖѕ��~�ƌ������A�ޏ��Ƃ̊Ԃɏӌo�������܂�Ă���B�h��v���ɎQ���������̒m�������Ƃ���̓]�@�ɂȂ����B�����ɖ������ă\�A�̌R�������@����ȂǁA�����}�R�̒��S�l���Ƃ��Đ������Ă������B������̓]�@�́A�ѕ��~�Ɨ����������ƁA���]�����̑n�n�҂ƌ�����v�Î��̖��A�v�����ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�v����j�ƂP�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�Ɍ����������Ƃ��낤�B���̌����͏Ӊ�̐����I���i������Â��邱�ƂɂȂ����B���Ȃ킿�A�Ӊ�̌��͊�Ղ͋���ȌR���͂ƂƂ��ɁA���]�����ɑ�\������u���W���A�W�[�w�̎x���Ƃ������i�����߂Ă����B
�@���]�����Ƃ͏�C��{���Ƃ������Z���{�ƁE�Y�Ǝ��{�Ƃ̑��̂ŁA���̒��S���]�h�E���]�ȏo�g�҂���������ł���B�Ӊ�����]�̏o�g�ł���B�����͗m���^���ɋN�������������{�ƊO�����{�ɏ]���������َ��{���琬���������̂ŁA�{���鍑��`�ƓG�ΊW�������̂ł͂Ȃ��B�����ɕK�R�I�ɒn��E�����ݎ��{�Ƃ���̉����Ă����B�]���ďӐ����͑�u���W���A�W�[����ՂƂ��Ȃ���A�������I�n��K���̌R���I���i�����̂܂p�����R���ł��������B
�@���̓_�A�Ӊ�̐^�̓G�͓��{�ɑ�\�����鍑��`�ł͂Ȃ��A�厑�{�Ƒw�E��n��w�̓G�ł���A�l�������`���͂ł������B�Ӊ�͏]���č�������̔�����`�҂ł���B
�����Ӑ��������̌R���ƈقȂ�_�́A�����ȗ��̒��������}�̐����I���������p���ł����_�ɂ���B���̂��Ƃ��A�Ӊ�����}���������ۓI�ɒ������������ƌ��Ȃ��ꂽ���R�ł��낤�B
���łɏӉ�́A�}�����Y��`�҂̑ߕ߂��͂��߂�ȂǁA���Y�}���͂Ƃ̑Ό��p����N���ɂ��Ă������A�P�X�Q�U�N�i�吳�P�T�N�j�U���A�����}�͖k�������肷��B
|
|
 |
|
�@�u�k���v�Ƃ́A�L���������{���A�k�����{�𒆐S�Ƃ���R�����͂��R���I�ɐ������A�����S�̂ꂷ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B�܂��R�����͂̂��߂ɋꂵ��ł���_���E�J���҂�������邽�߂ł�����B
�@�ɂ��ւ�炸�A�R�~���e��������̃\�A�l�ږ�c�A�������Y�}�́A�u���������v�Ƃ��Ă���ɔ��������B�Ӊ�̖k���̐^�̈Ӑ}���^���Ă�������ł���B�Ӊ�͖k���ɖ�����āA�S������𐬂���������A���Ȃ̐��͂�L���w�������Ƃ�̂ł͂Ȃ����E�E�E�B
�@���ۖk���ɂ����Ƃ��M�S�������̂͏Ӊ�ł���B�������L���������{�́A�k���ɓ��ݐ�Ȃ���Ȃ�Ȃ�������������B
�@�k�����{�̒��ɂ��A�������{�x���h���䓪���Ă���A�k�����{�̘��S���𐭍�Ƃ��Ă������{�́A��V�h�̒��������x�����Ă��̐��͂��R���I�Ɉ�|���悤�Ƃ����B�����_�������C�M���X�͒���h���x�����A��V�h�E����h�A���ŁA���̍������{�x���h�����S�Ɉ�|�����̂ł���B
�@�������{�́A�P�X�Q�S�N�i�吳�P�R�N�j�U���A������̉����������t���������Ĉȗ��A�����鐭�}�����̎���ɂ͂����Ă����B���ʑI���@�����Y�}��̎����ێ��@�ƃZ�b�g�̂悤�ɂ��Đ������A�܂����\��{�����������āA����ƃV�x���A�o�����I�����悤�Ƃ��Ă������낾�B���{�������猩��ƁA���������f���N���V�[�S���̂悤�Ɍ������B�i�吳�f���N���V�[�j
�@�����������������A��G���t�̎��̊O����b�ł���A�Q�P�����̗v�������������Ƃł�������悤�ɁA�Β����N������ɕύX���������킯�ł͂Ȃ��B�����́A���̔N�̕��a�C�Ŏ������A�Q�U�N�i�吳�P�T�N�j�P���A����X���Y���t���������Ă���B
�����ɗi�����ꂽ���������ɂ��Ă��A������������o�g�Ő��}�����Ƃɓ]��������X���Y�ɂ��Ă��A�����������̎s��Ƃ���Ƃ����ł����ӂ����������{�̎x�z�w�̕��j���ς��ʌ���A�����N������ɕύX������͂����Ȃ������B
�@�k�����{�̒��̍������{�x�����͂���|�����A��V�h�E����h�A�������́A���Ȑ��͒n������̍������{�x���h�̒e�����J�n�����B�Ƃ������Ƃ͔��鍑��`����^����e�����邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�P�X�Q�U�N�i�吳�P�T�N�j�T���ɊJ���ꂽ�u��O��S���J�����v���L���������{�ɁA�u���₩�Ȗk���v��v������ȂǁA�S���I�ɖk�������߂鐢�_���킫�オ���Ă����B�܂�u�k���v�͒����l���̂قڈ�v�����v���ł��������B
�@�������āA�P�X�Q�U�N�V���A�L���̍����v���R�i���i�߁E�Ӊ�j�́A�u�鍑��`�Ɣ����R����œ|���Đl���̓��ꐭ�{�����݂���B�v�Ƃ����������A�S�R�P�O���l�������Ėk�����J�n�����̂ł���B |
|
 |
|
�@���̌�͗�ɂ���āA�u�����ߌ���j�v�i��g�V���A�O�f���j�Ɍ���ĖႨ���B
| �w |
�k���R�i�������v���R�j�͓{���̐����Ői�������B���������s�������Ă�����ɑ��݂ɗ��Q���Η����Ă����R���R�́A�v���̈ӋC�ɔR����k���R�̑O�Ɏ��X�Ɗe���j����Ă������B
|
|
�܂��Γ�ɐi�o�����k���R�̎�͂́A�V���P�P���i���P�X�Q�U�N�j�ɒ������A�P�O���P�O���ɂ͕������̂��ČΓ�E�Ζk�̌��Λt�R����|�����B�X���ɌΓ삩��]���Ɍ����������H�R�i�Ӊ�Ύw���j�͒���h�̑��`�F�i������ł�ۂ��j�R�̎�͂ӂ��P�P���W���ɓ쏹��̂��č]���Ȃ��蒆�Ɏ��߂��B
����ɂP�O���ɍL�B���o�����ĕ����ɐi���H�R�i�������\����������[�w���j�͂P�Q���X�����B���A���N�Q���P�W���ɂ͍Y�B���̂��A���H�R�ƂƂ��ɂR���Q�S�����`�F�̖{���n�A�싞���ח��������B���̒��O�̂R���Q�P���ɂ͓��H�R�̈ꕔ���鍑��`�ő�̉���C�x�O�ɓ��������B |

�k���R�i�H�}�i�������p�u�����ߌ���j�v���j
�N���b�N����Ƒ傫�ȉ摜�ł������������܂��B |
|
�k���R�͂�����Ƃ���Ŗ��O�̊��}�����B���O�͓G��A���ē��A�����A���ɐϋɓI�ɋ��͂��A�R���R�̗A���E�ʐM��W�Q�����B���ɂ͖k���R�̓����O�ɖI�N���ČR���R��ǂ��U�炵���Ƃ��������B�R������|���ꂽ�n��ł͂ǂ��ł��J���ҁE�_�����͂��߂Ƃ��閯�O�^�����������R���オ�����B
���ł��_���^���̔��W�͂߂��܂������̂��������B�_��������̐���k���O�Ɗr�ׂ�ƁA�Γ�ł͂R�O������Q�O�O���ցA�Ζk�ł͂V������P�O�O���ɁA�L���ł͂U�O�O�O����R�W���ɁA���ꂼ�ꑝ�������B�_�������͒n��E���a���猠�͂�D�����A�n����������A�G�Ŕp�~��v�����A����ɂ͍����}�̎w�������z���Ēn��̓y�n�v���̓������������ꂽ�B
�J���҂��܂��e�n�ŗ����オ��A�������@����g�D���āA�鍑��`�E���v�����{�ƂƉs���Η������B�Ȃ��ł����Y�}����������Ɏw�����ꂽ��C�̘J���҂͉ߋ���x�̎��s�ɂ��߂����A�R���Q�P���[�l�X�g�ƕ����I�N�ŗ����オ��A�R�O���Ԃ̎s�X��̖��A�R���R����|���ėՎ����{�����������B
�������Ă킸���X�����Ŗk���R�͒��]�i�����]�̓`�x�b�g�����𐅌��Ƃ��A�ؒ����ї����ē��V�i�C�ւƒ��������ő�̐�B�S����U�O�O�O�����B�����n��͗g�q�]�Ƃ��Ă��B��v�ȓs�s�ɂ͐��s�A�����A�d�c�A�싞�A��C�Ȃǂ�����B�j��т𐧈����A���Ƃ���̍����n�L���A�L���ɉ����ČΓ�A�Ζk�A�]���A�����A���]�A���J�A�]�h�̋�Ȃ��v���̂�ڂƉ������̂ł���B�x |
�@�k���R�̈����ł���B�R�����{�͒����l���S�̂�G�ɉẮA�͂��߂��珟���ڂ͂Ȃ������B |
|
|
|
 |
|
�@�u�鍑��`�E�R���v�u�����l���E�L���������{�v�Ƃ����}�����猾���A�L���������{�E�k���R�̈����́A�鍑��`�ɂƂ��Ă͑傫�ȋ��Ђł���B�鍑��`�ƒ����l���̒��ڑΌ��A�Ƃ����Ă��Е��͌R���I�\�͑��u�������Ȃ����琸�X�ՓˁA�͔������Ȃ�����ł������B
�@�P�X�Q�V�N�P���i���a�Q�N�P���B�吳�V�c�Ðm�\�悵�ЂƁ[�̎����́A�P�X�Q�U�N�P�Q���Q�T���ł���A���Q�U�����珺�a���N���n�܂�B�N���ς��Ə��a�Q�N������A���a���N�͂킸���U���Ԃ������B�j�A�����Ƌ�]�ɂ������C�M���X�d�E�ŃC�M���X���Ɩ��O�̏Փˎ��������������B����ɃC�M���X�������C�������ߗ��������ƂȂ����B���V�������O�́A�d�E����芪�����͂ŃC�M���X�d�E����������̂ł���B���̎����͂Q���������{�ƃC�M���X�Ƃ̊Ԃ̌��ŁA�����ɂ��̂Q�̑d�E���������ɕԊ҂��ꂽ�B
| �i |
�d�E���������ɕԊ҂��ꂽ�P�[�X�͂��̎����͂��߂Ăł͂Ȃ����Ǝv���B���ƂłȂ����͊m�F�����i�������Ȃ��B�ǂȂ��������Ă�������Ƃ��肪�����B�j |
�@���N�R���ɂ́A�싞�������N����B���傤�ǂP�O�N��̂P�X�R�V�N�ɔ�������u�싞��s�E�����v�Ƃ͋�ʂ��ĒP�Ɂu�싞�����v�ƌĂ�Ă���B
| �i |
�}�K�Д��s�̗��j���ȏ��ł́u�싞�\���v�ƋL�q����Ă��邻�������A���͊m�F���Ă��Ȃ��B�j |
�@��ɂ������悤�ɍL���������{�̖k���R�́A���̂���싞��{���Ƃ��鑷�`�F�R���ɔ����Ă����B���̓싞�U�h��̍Œ��ɁA�O���̎��فE�Z��E����P������ăC�M���X�l�E�t�����X�l�E�A�����J�l���v�U�l���E�����Ƃ����������N�������B���ꂪ���`�F�R�ɂ����̂Ȃ̂��A�������{�R�ɂ����̂Ȃ̂��A���邢�͈�ʒ������O�ɂ����̂Ȃ̂��A�����ɂ͂����肵�Ă��Ȃ��B
�@�������{��v�����������������u�싞�����i�P�X�Q�V�N�j�v�̍��ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�싞����_(1927�N)�j������ƁA
| �w |
�@�܂��Ȃ��A���鍑��`�����ԌR�l�▯�O�̈ꕔ���O���̗̎��ق⋏���n�Ȃǂ��P�����Ė\�s�E���D�E�j��Ȃǂ��s���A��1�l�A�p2�l�A��1�l�A��1�l�A��1�l�A��1�l�̎��ҁA2�l�̍s���s���҂��o���B���̍ہA���{�̎��ق��P������A�\�s�◩�D�A�̎��v�l���ːJ�����Ƃ������ԂƂȂ�A�̎��ق������グ�R�͂Ɏ��e���ꂽ�B�@�x |
�Ƃ��Ȃ�f��I�ɏ����Ă���B
�@�܂��p��v�����������������uNanjing Incident�v�̍��ihttp://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing_Incident�j�ɂ��u�����}�R�v�����{�����Ə����Ă���B�������m�ɂ͂��̎��͂܂��u�����}�R�v�ł͂Ȃ��āu�������{�R�v�܂��́u�����v���R�v�Ȃ̂����E�E�E�B
�@�ǂ���ɂ���A�L���������{�̖k���̉ߒ��ŋN�������u�����l���v�Ɓu�鍑��`���́v�̏Փˎ����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�������ɍs���ɏo���̂��A�C�M���X�ƃA�����J�ł���B�R�͂����]����싞�s����C�����āA�����l�R�E����Q�O�O�O�l���E�����ꂽ�B |
|
 |
|
�@�����͎���X���Y���t�ŁA�O����b�͕�����d�Y�ł������B���L���ł��낤���A�Q�P�����̗v���̎��ɁA��G���t�͌R���͂�w�i�ɂ������d�H���Œ��ځA������N������u�n�[�h�h�v�ł������Ƃ���A���̎������B���t�́A�����ɓ��{�ɓs���̂������S���������ĂĐN������u�\�t�g�h�v���������ƁA�����Ĉȍ~�A���́u�n�[�h�h�v�Ɓu�\�t�g�h�v���Ȃ������ɂȂ�Ȃ���A���{�̒鍑��`�̒����N�����i�s���Ă������Ƃ��B
�@�����̓\�t�g�h�������B�ނ̌��ʂ��ł́A���{�̒����N���ɂ������čő�̓G�́A�u�N���Ǝ��D�ɔ�����l���v�Ƃ�����o�b�N�A�b�v����u�������Y�}�v�������B�ނ���Ӊ�́A���{�̒鍑��`�I�N���ɂƂ��Ă͋��͂��čs�����Ƃ̂ł��鑊��ƌ��Ă����B
| �i |
���̕����̌��ʂ��́A���̌�̓W�J���獡���U��Ԃ��Ă��Ă��ɂ߂ēI�m�Ȃ��̂������B�j |
�@���̎����̎��������͗���̋����o���̗U����f���Ă���B�u�Ӊ�̂悤�Ȑl���𒆐S�ɂ��Ď��ǂ����E������ׂ����B�v�Ƃ����̂ł���B
�@�O�f���u�����ߌ���j�v�́A�o�P�P�U�̒��Łu�����͂��̎����łɏӉ���h�������ՋG���i���������Ƃ��[�Ӊ�����}�E�h�j��ƐڐG���āA�ӂ��鍑��`�ƕ��͂őΌ�����Ӑ}�̂Ȃ����Ƃ�m�炳��Ă����̂ł���B�v�Ƃ��Ă���B
�@����A��قǂ̓��{��v�����������������ł́A
| �u |
�O���Ȃ͎�����������A�X���̎�������A���Y�}�̌v��ɂ��g�D�I�Ȕr�O�\���ł���Ƃ̕ɂ��A�싞�������Ӊ�̎��r���˂炤�ߌ����q�ɂ����̂Ɣ��f���Ă������A�����s����Ƃ�ΏӉ�̓G�𗘂�����̂��Ƃ��āA�����͈�т��ĕs��������Ƃ�A����������B�v |
�Ƃ��ĕ����̐����I�Ӑ}�Ƃ͎�I�O��Ȑ��������Ă���B�u�����O���v�̖{���𗝉����������Ƃ͂����Ȃ��B
�@�Ȃ����̕����̑Β�������A���Ȃ킿�A���ڌR���͂��g�킸�A�ł��邾���u�����v�����Ɏ~�߁A���S�������邢�͐e���������琬���Ȃ���A�����Ɍo�ϓI�N���̎��v�����悤�Ƃ�������́A�������{�����Łu���O���v�Ƃ��Ĕ��𗁂т��B
�@���{��v�����������������̍��u�����O���v�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�����O���j�ł́A�P�Ɂu�����ȑΊO�����O���v�Ƃ��Ă���B
�@�����O���́A�����I�ȌR���i�o�������A�����s����A�����J�ƕ������悤�Ƃ����_�ɂ��̖{��������Ǝ��͍l���Ă���B����̓��V���g���̐��̈ێ��E���W�ł���A�鍑��`���{�̐���Ƃ���Έ�Ԍ����������B�i���j�w�҂͂ǂ�Ȍ��������Ă���̂��E�E�E�B�j
�@
�@�������P�X�Q�V�N�S���A����X���Y���t���|���ƁA�������O����b��ނ��A���ʔh�̓c���`����t���������邱�ƂɂȂ�E�E�B |
|
 |
|
�@����������{�̖k���̐����́A�����ɍ������{�̎x����Ղɂ��T��𑖂点�邱�ƂɂȂ����B
�@�������{�̎x����Ղ́A�u���������������v�ł���A���̐����I�ۑ�́A�u���鍑��`�v�i���Ȃ킿�����̓Ɨ��j�������B���̂��߂ɁA�O���鍑��`�̘��S�ƂȂ��Ă���R����œ|����Ƃ������Ƃ������B
�@���������̉ߒ��̒��ŁA���R�u�T�E�S�^���v�ȗ��̂�����̐����I�ۑ�A�u�����l���̖����`�v���v�̉ۑ��B�����悤���铮�����łĂ���B���Ƃ��Β��N�A��n��ɋꂵ�߂��Ă����_�����A���̖k���̒��Łu�_�n����v�I�ȓ����������Ă������ƂȂǂ��������B�܂��s�s�J���҂��A�R���œ|�E�鍑��`�I���{�ƊK���ɑ��Đ키�Ƃ��́A�J���^���̌`���Ƃ炴��Ȃ��B���̖���͎��R�A���������̖����h���{�ƊK���ɂ������čs������Ȃ��B
�@�������������{�̎x����Ղł���A�����������̂Ȃ��ɂ́A���������n��w�▯�����{�Ƃ��܂܂�Ă����̂ł���B�������������h���{�Ƃ�n��w���A�����������̍s���ɕs�������̂��܂����R�̐���s���ł��낤�B
�@���Ƃ��A�����ł͑����̖������{����C�Ȃǂɓ����������A�_���ł͒n�傽�����s�s�ɔ��n�߂��B
�@�ʂȕ\���ł����A�����}�����x����Ղ̒��̊K���Η����\�ʉ����Ă����̂ł���B
�@���̎��_�ŁA�Ӊ�͓쏹�ɍ����v���R���i�ߕ���u���Ă����B����������{�͓싞������A�����ɐ��{��u�����B���̎��̍������{�́A��ꎟ��������ŁA�����}�E���Y�}�i���Y�}���j�Ȃǂō��A�����{�ł���B�܂��������{�̒����́A�����}���h�E���Y�}���Ȃǂ������h���߂Ă����B����Ӊ�Ƃ��̌��͂́A���Ȃ킿���̊K���I�{���́A��ɂ������悤�Ɂu�������{�Ƃ⟴�]��������ՂƂ��Ȃ���A�������I�n��K���̌R���I���i�����̂܂p�����v���̂������B���Y�}���⍑���}���h�̐����I�咣�Ƃ͑��e��Ȃ��B
�@�������Ӊ�Ύ��g�A���Y��`�ւ̔����������ĉB�����Ƃ��Ȃ������B�̂��ɂ͔�����`�̂��߂ɁA�s�E�ł��\�͒c�����ɂ����Ȃlj��ł�����悤�ɂȂ����B�����́A�u�����ł͏Ӊ�𒆐S�ɂ��ׂ����B�v�ƍl���Ă������A�鍑��`���{�̗��ꂩ�炷��A�܂��ɂ���͌d�Ⴞ�����B |
|
 |
|
�@���{��������`�̓`���͒����B���{��`�E�鍑��`�̘g���ŁA���������̑̐�����낤�Ƃ���A�u������`�v�͓��R�̃C�f�I���M�[�ł��낤�B�܂��ɓ��{�͒鍑��`�ҁE���{�ƊK�����x�z���鍑�Ȃ̂�����B�ނ�̔�����`�͂����Ƃ��ł���B�������Ȃ���A����鍑��`�҂⎑�{�ƊK���ł��Ȃ��A�����̘J���͂����u�̔����i�v�̂Ȃ��A��ʘJ�����i�܂�͈�ʎs���ł���B�j���u������`�ҁv�ƂȂ��Ă���Ƃ������͊��m�ł���B
�@���́u������`�ҁv�ł͂Ȃ��B�u������`�ҁv�ɂ͑��`���������āA�u���Y��`�v�z�ɔ�������́v�u���Y�}�ɔ�������́v�u���Y��`�̎Љ�̐��ɔ�������́v�Ƃ��낢��ł���B�u���Y��`�̐��̎Љ�ɔ�������́v�Ƃ����Ӗ��Łu������`�v���g���̂͌��ł��낤�B
�@�u���Y��`�v�́A���܂��n����ɑ��݂������Ƃ��Ȃ��B���ꂪ�ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��܂��N���m��Ȃ����A���̐ʐ^�i���f���j����A��̓I�ɂ͍��ӌ`������Ă��Ȃ��B�ё͈ꎞ���A�u�����͂��ꂩ��Љ��`���狤�Y��`�̒i�K�Ɉڍs����B�v�Ɛ錾�������Ƃ����������A����͔ގ��g�{�C�ŐM���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�����M���Ă����̂Ȃ�ё͐��_�����������̂��낤�B������ɂ��Ă����̖ё̐錾�͍��͌��Ƃ��Ĕے肳��Ă���B�܂�A�u���Y��`�̐��̎Љ�v�͈�̂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂������ɕ�����Ȃ��B������Ȃ����̂ɂ͔��ł��Ȃ��B���������Ď��͂��̈Ӗ��ł́u������`�ҁv�ł͂Ȃ��B
�@�u�Љ��`�v�ɂ͂��낢�낷�łɃ��f�������݂���B���Ȃ�ɔ�r�������Ă݂�ƁA�l�I�ɂ́A�s�������`�̗��ꂩ�炷��A�u���{��`�̐��v���u�Љ��`�̐��v�̕����D�ꂽ�d�g�݂��Ǝv���B
�@���̈Ӗ��ł͎��́u�Љ��`�ҁv���Ƃ����邪�A�Ȃɂ��Ȃ�ł��Љ��`�̐��ɂ��悤�Ƃ��v��Ȃ��B�v�͎��{��`�ł���A�Љ��`�ł���A����͈�̎�i�ɉ߂��Ȃ��B
�@�ړI�́A�s�����i�܂�͈��|�I�命���̈�ʐl�����j�A���a�ɁA�ł��邾���L���ɁA�a�C��n�R��A�V��̐S�z���ł��邾�����Ȃ��A���Ƃ̕s�����Ȃ��i�������ƁA�����̐E�Ƃ������ƁA�͎����̐������ێ����Ă����Ƃ����Ӗ��ł͋`���I�c�݂ł͂��邪�A���ʁA�������Ƃ͎��ȕ\���⎩�Ȏ����̏d�v�Ȏ�i�Ȃ̂ŁA����͌������Ƃ�������B������ɂ��掸�Ǝ҂��J�Ɉ���Љ�́A�s�������`�̊ϓ_����͍Œ�̎Љ�B�j�A���@�Ƃ͂����Ȃ����C�����悢�����̏Z���������A�����̋��琧�x�����B���A�ǂ�Ȏq���ɂł������Ɏ����̉\�����Ђ炭�`�����X���^�����A�����̌���\�͂��\���������āA�ꐶ���I������Љ���������邱�Ƃł���B
�@�ړI�́u���Y�W�𒆐S�Ƃ���A����̎Љ�o�ϑ̐��̎����v�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�������i�Ƃ��Đ^�Ɂu�s�������`�I�ȎЉ�v���������邱�Ƃɂ���B�܂��Ƃ��������������]�����悤�ɁA�u�����L�ł��낤�������L�ł��낤���A�l��߂��Ă���L���ǂ��L�v�Ȃ̂��B
�@�u�^�Ɏs�������`�Љ���������鎑�{��`�̐��v�́u�^�Ɏs�������`�Љ���������Ȃ��Љ��`�̐��v�����D��Ă���B
�@���������{��`�̐��͂��̍����ɁA�u�^�̎s�������`�Љ���������Ȃ��v�f�v�����Ă���B�Љ�̕x�̌���ł���u���Y��i�̎��L���v���B���̎Љ�ɛƂ߂Ă����A�u����Ɛ��v�A�������Ɛ�ƏW�����i�����ł́u���Ǝ��L���v�ł���u�ǐ�E�Ɛ��Ǝ��L���v�ł���B����͎��{��`�̐��̋��݂ł�������ł͂��邪�A���̎d�g�݂��u�^�̎s�������`�Љ�v������j�ލ��{�v�f�ƂȂ��Ă���B���̍\���I���̂䂦�Ɏ��͎d�g�݂Ƃ��āu�Љ��`�̐��Љ�v���D��Ă���Ƃ����킯�����B
�@�u���Y��i�̎��L���v�A���Ȃ킿�u����Ɛ��v�ɂ͐�ΊѓO���Ȃ���Ȃ�Ȃ��@��������B�u����ƌ̗��v�Nj��v���B�����X�̊�Ƃ����̖@�����ѓO�ł��Ȃ�������ǂ��Ȃ邩�H�m�ꂽ���Ƃ��B����ƂƂ��ẮA���{��`�Љ��̑ޏ�𖽂�����B������u���{��`�Љ�v�̃C�f�I���M�[���炷��A�u����ƌ̗��v�Nj��v�́u��ΑP�v�Ȃ̂��B
�@�Ƃ��낪�u���{��`�Љ�v�ɂ�����u��ΑP�v�́A�u�^�̎s�������`�Љ�v�̃C�f�I���M�[���猩��ƁA�K�������u��ΑP�v�ł͂Ȃ��B���ɂ��A����́u�^�̎s����`�Љ�����ꂩ��˂�������Q�v�Ƃ��ė�������邱�Ƃ�����B
| �i |
�O�W�N�X������ˑR���E���P�����w�V���R�o�ώ�`�I���{��`�̐��̕��x�Ƃ��̍s�����Ă�����ɂ��A���ɂ��̊���[������B���{��`�͗��j�I�ɁA���̎��X�̌o�ϐ����Љ���哱����̐��Ƃ��Ă͏I�����}���Ă���̂����m��Ȃ��B�j |
�@�u������`�v���琏�������Ɉ�ꂽ���A���̎��̒����l���́A��`��̐��Ȃlj��ł��ǂ������B�����ƉƑ��́u���a�ň��S�����v������Č���A�z�Ɋ����ē������Ƃ�]�����Ă���鐭�����͂ł��������x�������B
| �i |
�����炭���ł��������낤�B�O�W�N�P�P�������֍s���Ă��镪�͉ƂƘb�����Ă������A�w�����l���͐���������Č���Ă��邩�璆�����Y�}���x�����Ă���B���������łȂ���A�����͋��Y�}�����ĂЂ�����Ԃ��܂���B�x�Ƃ����̂������Ƃ�����B�j |
|
|
 |
|
�@�������A�Ӊ�͂����ł͂Ȃ������B�ނ́u������`�v�Ɍł܂��Ă����̂ł���B������`�̂��߂Ȃ牽�ł�������B���ۂ����ƌ�̂��ƂɂȂ邪�A�P�X�S�T�N�W���P�T���A�����R�Ɠ��{�R�̊ԂŒ�틦�肪�������A������������̍�������ɂ͂��������A���Y�}�R�Ɛ키���߂Ȃ�A�Ӊ�͋����{�R�Ǝ�����̂ł���B
�@���̎��A�Ӊ�ɂ́A���]�����Ƃ���ɘA�Ȃ锃�َ��{�ƁA�n��A�������{�ƁA�Ȃǂ̊��҂��W�܂�A���{�̃o�b�N�A�b�v������V�R���ƂȂ���������q���������X�A�Ӊ�̖{���n�E�쏹��������Ă������B
�@��C���ƊE�̋����A���i�����������j���A�쏹��K��A�Ӊ�ɂU�O�O�O�����̎�����\���o���ƌ����Ă���B�i�O�f�u�����ߌ���j�v�o�P�P�V�j
�@���̋��́A��C���]�����̋����̈�l�ŁA��C�o�ϊE�̑���Ƃ�����C���H��̉�������B
�@���c�@�l�a�V�h��L�O���c�́A�O�O�ɏa��h��̓`�L���������W�E�������Ă���B���̑�T�T���̑�U���u���؎��Ƌ���v�̍������Ă݂�ƁA���̋��̂��Ƃ��o�Ă���B������ƈ��p���Ă݂悤�B
�@�吳�P�T�N�i�P�X�Q�U�N�j�U���T���̍��ł���B�����Ӊ�ɌR����������\���o���A���炭�V�|�W�����O�ł��낤�B
| �w |
��������A��C�����������c���g�X�����ؖ������ƒc�����m��A���A�܌��\�l���y�r��\�l���A���������J�L�A�����ҕ��j�c�L���c�X�B�h��A�\���]���o�ȃX�B
�����A������y�r���؍��b��m������Ãj�����A�R�@�j���e�A�E��s���}�ߎ`��J�J���B�h��A��Î҃���\�V�e���}�m�����q�u�B������A������s��y���j���e�A��������g���ƒc��\�҃g�m���k��J�J���A�h��o�ȃX�B
���C�f�����A�h��A�������R�@�j���L�e�ߎ`��ÃV�A���������ʌ������g���j�A�����e�P����j�փV�A�ӌ��m�������i�X�B�x |
�@�����Łu������v�Ƃ����Ă���̂͏a����Ƃ߂Ă������؎��Ƌ���̂��Ƃł���B�a��͋璆���̐�����̂��Ƃ��A���낢��P������������Ƃ��낤�B�u�����e�P����j�փV�A�ӌ��m�������i�X�B�v
�ihttp://www.shibusawa.or.jp/SH/denki/55.html�j
�@�a��Ɍ��炸�A���{�̍����E�o�ϊE�͒����̏�ɑ傫�ȊS���������B��������R�ł���B���{�̑ΊO�����̂R�^�S�͒����ɐU��������Ă����̂�����B���ڂ̗��Q�W�҂ƌ����ׂ����낤�B�u���{�̌R����`�̒����N���v�Ƃ������ۓI�Șg�g�݂ł͂Ȃ��A�������������ւ̌o�ϐN���i�����ꂪ�����l���Ƃ̌b�����ɂ��ƂÂ��o�ϐi�o�E�Β������Ȃ�A�������Ɋ��}���ꂽ���Ƃł��낤�B���}�����i�o�ɂ͌R���I�����͂���Ȃ��B�j�A�Ƃ������̊�w�ɂ���o�ϊW���猩�Ă����ƁA������肪���{�i�����E�o�ϊE�j�ɂƂ��Ď�����������ۑ肾�������Ƃ�������B���̓`�L�����ł͑Β�����b���������ߓ��{���{�W�҂Əa���낢�닦�c�������Ƃ������Ă���B
�@
�@�������ďӉ�́A�����o�ϊE�i���̑����́A���̂悤�ɊO�����{�A�鍑��`�Ƌ������т��Ă����̂����j�̊�]�̐��ƂȂ����B�������Ӊ�́A�����v���R���i�߂Ƃ��Ē��ڌR���͂������Ă���B�O�f���u�����ߌ���j�v�ɂ��ƁA���̎��Ӊ���������Ă����R���͂́A�Q�O���������Ƃ����B�i�O�f���P�P�V�o�j
�@��������ɐ��{���ڂ����������{�i�����}���h�Ƌ��Y�}�������S���́j�́A���̓����́A�R���͂��قƂ�ǎ����Ă��Ȃ������B�Ӊ�̋���ȌR���͂�}�����悤�Ƃ͂������A�قƂ�ǎ����������Ȃ������B
�@��ɂ������悤�ɁA���������w�������J���҂̃[�l�X�g�E�I�N���P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�̂R���ɐ��N���Ă���B���Ɏ������w���́u��C�I�N�v�́A�R������|��������łȂ��A��C�Վ��v�����{���������Ă���B�������R���싞�ł͖k�����ɗ�̓싞�������������Ă���B
�@����͎��̑S���̑z�������A���̂����C�́u�Љ��`�v���O��v�̂悤�ȁA�J���҂��V�g�������͋C�ł͂Ȃ��������H�t�ɟ��]������鍑��`�͂��ꂾ����@�����点���Ƃ������悤�B
�@�Ƃ���ŁA���{�̈ꕔ�̋��ȏ��I���j���́A���̂�����̘J���҂̃[�l�X�g�A�I�N���A�u�������O�̖\���v�Ƃ��ĕ`���Ă���B�m���ɟ��]������鍑��`�ɂƂ��āA���������l���̔��U�́u�\���v�Ƃ����f��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�����������l���̗���ɗ��ĂA����́u�\���v�ł͂Ȃ��A�u���鍑��`�����v���B
�@����������`���o���̂ɉ��́A�������Ⴄ�`�ʂɂȂ�̂��ƌ����A�������u�N�̗���ɂ���Ē��߂邩�v�Ƃ������_���Ⴄ���炾�낤�B������u�\���v�Ƒ�����̂͗鍑��`�̗���ɗ����Ē��߂Ă��邩�炾���A������u���鍑��`�������B�v�Ƒ�����̂́A�����l�������`�̗���ɗ����Ē��߂Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�����炱�������u�����l���̐킢�v���u�\���v�Ƃ��ĕ`�ʂ��Ă��錻�݂̓��{�̈ꕔ�̋��ȏ��I���j���́A���ꂩ��W�O�N�o�������A�����́u�鍑��`�v�̎��_�ŗ��j�߂Ă���킯���B |
|
 |
|
�@����Ɋւ��āA�����ǂ�Ŕ��ɋ����[�����k������V���̎�Âœ����s���Ă���B�b��͂Q�V�N�R���́u��C�I�N�v�ł͂Ȃ��A�Q�T�N�T���ɔ��������u�T�E�R�O�v�^���ł���B���̎����̂��������́A��C�ɐi�o���Ă������{���{�E���O�Ȃ̍H��ŁA���{�l�ē������l�J���҂��ˎE�����o�����������B�����̉̂��Ƃ������S�y���A�u���鍑��`�����v���g�������B
�@���̍��k��́A�u��ꎟ���E���v�Ƃ������O�̂v�����T�C�g�ihttp://ww1.m78.com/index.html�j�Ɍf�ڂ���Ă���B�悭�������W�����Ă��ċɂ߂ĎQ�l�ɂȂ�T�C�g���B���̒��ɓ����̑�㖈���V�������p����Ă���B
�ihttp://ww1.m78.com/sinojapanesewar/530.html�j
�@�o�Ȏ҂͓����Γ��ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�����Γ�j�A���m���ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/���m��j���ʈꑢ�i�������m�ȉԐꖱ�j�A
���������i�������O�Ǔ���B���O�Ȃ͗��j�I�ȂT�E�R�O�^���̖��_����Ό�)�A�����[���Y(�������m�a���В�)�A�������g(����{�a�d���j��B������������ɍH��������Ă�����Ƃ��B
�@�����Γ�͐l���m��A���{���\���铌�m�j�w�҂��B���m��́A�u�����ߌ���j�v�̐��Ƃ��B�����u�����l���v���j�_�v�Ȃǂ̒��삪����B
�@�W�ӏ������p���Ă������B
| �w |
������ |
�d�E���̒������ۂ��ꂴ��͊e���̑���������ʂ��߂���B�e���݂Ȏ��������悢�q�ɂȂ낤�Ƃ��邩�炶��B�݂��܂��č��̔@���͎x�߂ɉ��̎d���������Ă���ʁB���ꂪ���{��p���Ɩ{���ɋ�y�����ɂ��Ă����킯�͂Ȃ��B��������{�l�͂悭�l���Ȃ���Ȃ�� |
|
���ʈꑢ
�i���m�ȉԐꖱ�j |
������������܂��A���{�����{�����ʼn����^���ł��J�n����ƁA�����r��������������č��� |
|
���� |
����͓��{�̐��{���������炶��A�O���ȓ��ɂ�����ʃn�C�J���_�������Ė{���̑Ύx�O���Ƃ������̂����ʂ��炶��B�����ɖ����ƉƏ��N�������A���N���O���Ȃ̘A����ڝ�����ʂ��炢���܂��� |
|
���m�� |
�d�E����H��n�т��r�炳���͕̂������炻�ꑊ���̖h�������Ă��Ȃ�����ł͂���܂��� |
|
��������
�i���O�Ǔ���) |
���������Ȃ̂ł��B�������邱�Ƃ́A���������h������ԈႢ�ł��N��Ƃ������{�l��������Ɠ��{�l�ɓ�Ȃ�������A���ۓ��{�l����Ԕn�����݂Ă���̂ł� |
|
�����[���Y
(���m�a�����j |
���{�͖a�т����ł��~����̎��{���x�߂ɉ��낵�Ă���B���ꂱ�̂܂܈��g����킯�ɂ͂����ʁB�����獡�x�����͓O��I�ɉ������Ă��炢�����Ɖ�X�͎v���Ă���B����Ȃ��Ƃ��x�X������悤�ł͎��ۓ��{�̑Ύx�f�Ղ��������`�����`���ł������ |
|
���� |
�������������傫���Ȃ��ĐÂ܂�Ό����\�N�ʂ͓�x�ƋN������͂Ȃ��B�V�͗��j���ؖ����Ă���B�����Ď��̑z���ł͂Ȃ����珔�N�͂��̂���ŃO���O���d����i�߂Ă䂯��낵���B���N�͂�������Ɛ��{�𗊂�ɂ��邪�A���{�̊O���ȂɃ\���ȋ��d�ȍ���������̂ł��� |
|
���� |
����ł͍����̎x�ߊw����������{�̈ېV�����̂悤�Ȏu�m�͏o�ė��ʂł��傤�� |
|
���� |
�o�܂����̂��B�o�����Ă��ꂽ���̂ł� |
|
�������g
(����{�a�d���j |
�����x�߂������Ȃ�������{�͂ǂ��Ȃ�܂��� |
|
���� |
�x�߂̐V�v�z�͋����Ȃ�Ƃ������Ƃ���ɂ��Ă��܂���B������������V�������œ����ɉ�X���l���Ă݂Ȃ���Ȃ�ʓ_�ł� |
|
���� |
���{�����Ɏx�߂֍s���Ƃ��āA���x�e�P���ǂ��������ׂ��ł��傤�� |
|
���� |
�ʖڂł��B�e�P���v����ɒ��x�̖��ŁA�����������̎x�߂̐V�v�z�Ƃ����Ɛ^�̒�g�Ȃǂł�����̂ł͂���܂��� |
|
���� |
���{�̎G�����Љ��`�̂��Ƃ������˂Ύx�߂͂����������� |
|
��� |
�����ł��B���m�̎G�����Љ��`�̂��Ƃ������˂Γ��{�͂����������܂���i����j�x |
�@�w�����Γ�ɂ͋C�̓łȂ悤�ȍ��k��ł͂��邪�A���ꂪ�����̓��{�̒m���l�̃��x���ł���B���ɓ����́A������d�Y�ɑ��鋭��ȓ��Ă����������Ă���B���������u�m���l�v���u���Ɛl�v�ƈꏏ�ɂȂ��āA���ʂ��Ȃ��u�t�@�V�Y���鍑��`�̘_���v����{�̍����ɐU��܂����̂ł���B�܂��A���̂��e���ȔF���͂ǂ����B���ꂪ�u�����ߌ���j�v����Ƃ��鋞�s�鍑��w�̋������B�����ЂƂB�����V���ł���B���̓������疈���Ɍ��炸�A�����A���O���ƐV���i���̓��{�o�ϐV���j�ȂǑ��}�X�R�~�́A�R���̒��������A�u�t�@�V�Y���鍑��`�v�̎v�z����{���ɂ�܂��Ă������B
�@�܂�́A�������{�̑����̐l�����́A�w�^���鍑��`�ҁx���͂��߂Ƃ��āA�u�鍑��`�ҁv�̗���Œ����Ɠ��{�̊W�����Ă����̂ł���B���̎��_�̒��ɂ́u�����l���̔��鍑��`�����̗���v�Ƃ��̐������Ȃlj]�����_�͑S���������Ă���B���́A�u�^���鍑��`�҂̎��_�v�ł͂Ȃ��A���{�̑�����ʑ�O�̎��_�ł���B�P�X�S�T�N�W�������Ƃ��āA�{���ɂ��̎��_�͈�ς����̂��Ƃ������ł�����B
| �i |
���̍��������Ă��邤���ɖ邪�����Ă��܂��Ē��ɂȂ����B�V�������ɍs���Ċg���ċ������B�w�R���A���K�U�U���x�̃^�C�g���̂��ƂɁA�w�q���V�l�]���x�w���҂R�P�T�l�Ɂx�̃T�u�^�C�g�����x���Ă���B���G���T�����Q�X�������d�B���J�쌒�i�̏�������B�G���T�����ɂ��ĉ�����������̂��B��
��������w�ǂ��Ă��閳�����[���E�}�K�W���s�������[���E�}�K�W�����w�ǂ���A�Ƃ����̂����{��ɂȂ��Ă��Ȃ��A�c��_�a���`�������̂����m��Ȃ��t�w�h�����������@�s���������x�̓w�b�h���C���Łw�C�X���G���̑�K�̓K�U�U���A�Q�O�O�l�ȏ�̃e�����X�g���E�Q�x��Over
200 terrorists killed in massive Israeli assault on Gaza���ƕA�e���푈�̈�ł��邱�Ƃ��������Ă���B
���������A����̂b�m�m�j���[�Y�Ńu�b�V�������̍��������A�R���h���[�T�E���C�X�̋L�҉�̖͗l���f���o����āA���C�X���u�܂��n�}�X���e���s�ׂ����߂�̂��挈���B�v�Ɖ]���Ă����B
��������A�����O���w�́w�����j���[�X�x�̓G�W�v�g�w�A���E�A�n���[���x���̂P�Q���Q�W���t���d�q�ł̃g�b�v�L���Ƃ��āu�C�X���G�����K�U���A����200���ȏ�̑�S���Ɂv�̌��o���ŁA�U�����q���̓o���Z���Əd�Ȃ������߁A���ꂪ����ɐ��S�ȏ�ԂɂȂ������Ƃ�`���Ă���B
http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/src/read.php?ID=15437�@
���҂R�P�T�l�͖����ꒃ�ł���B�C�X���G���̓i�`�X���l�̖����r�Ŏ�`�҂ɂȂ����悤���B�㐢���j�Ƃ́w�Q�O�O�W�K�U��s�E�����x�ƌĂԂ��낤�B�j |
|
|
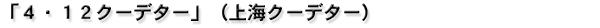 |
|
�@���ďӉ�ł���B�������������̋@��𐧂��邩�̂悤�ɂ��āA�Ӊ�̍����}���h�E�y�ы��Y�}���ɑ���U�����n�܂����B
�@�P�X�Q�V�N�S���A�u�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�i��C�N�[�f�^�[�j�ƌĂ��u��C�J���҂̑�s�E�����v���N����B�Ӊ�ɂ��u�����U���v�̖{�i�I���g�ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@�ŏ��ɓ��{��v�����������������u��C�N�[�f�^�[�v�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/��C�N�[�f�^�[�j�̋L�q�����Ă������B
�@
| �w |
�P�X�Q�V�N�i�����a�Q�N�j�S���Q���A�Ӊ�͗��@�m�A�����U�A�������A���ϐ[�A���Í]�A���t��A���Α\���������A��C�Œ��������}�����Ď@�ψ����c�����W���A��c�̒��Łu���Y�}�������}�����ŋ��Y�}���ƘA�����āA�d������؋�������v���ƂŌ�������Ă��o���A�L�B���������Ȃ̗��ϐ[�͂��̈ӌ��Ɏ^�������B�����ĉ�c�Łu���}�����v�y�сu���}�ψ���v���߁A�������}�����H�삪�i�s�����B�x |
�@���}�j�A�b�N�����m��Ȃ����A���@�m�i�肻������j
�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/���@�m�j�͌R�l�Ō�ɒ��ؖ��������㗝�ɂȂ��Ă���B�����}���{��p�E�o�̍ۂɂ́A�Ӊ�ƍs�������ɂ����A���`�ɒE�o�����B��ɒ��ؐl�����a�����{�Ɍ}�����k���Ŏ��������B�����U�i�͂��������j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�����U�j���R�l�ł����ꂽ�헪�ƂƂ��Ēm����B�Ō�܂ŏӉ�ƍs�������ɂ����B�������i�������傤�����j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/���ЃR�E�j���R�l�����A�Ӊ�́u�鍑��`�Ɠ��������������Y���͟r�ł�D�悷�鐭��v�ɔ����A�Ō�܂Œ����Ɏc���Ē��ؐl�����a�������ɎQ�������B������v���̎��Ɂu�E�h�v�Ƃ��Ĕᔻ����A���E���Ă���B���݂͖��_����Ă���B���ϐ[�i�肳������j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/���ϐ[�j���R�l�B�������Ɠ��l�A�Ӊ�̕��j�ɔ������Ԃ��킩���A���ؐl�����a�������ɎQ�������B���Í]�i���傤���������j�ihttp://sweb.u-shizuoka-ken.ac.jp/~saga/yowa17.html�j�́A�����������I�Ɏx��������C�̍����o�g�炵���B���t��i�������j�A���Α\�i�肹�������j�͋��Ɋw�ҏo�g�ŁA�����œ|�i�K�̊v����`�ҁB�Ӊ�ƂƂ��ɋ���ȁu������`�ҁv�ɂȂ��Ă���B
�@�v�����������������̋L�q�𑱂��悤�B
| �w |
�i���P�X�Q�V�N�j�S���U���A�Ӊ�͌R�y����h�����A�u�����Ő퓬�ɔ����悤�i���������j�v�Ƃ����т̊����f���A��C���H��H�l���@���ɑ���A���f���������A�����ɏӉ�͐�A�^��̓��ڂł��鉩���h�A�����сA�m��♓��̂Ƃ���Ɋ���o���A�E�h�c�́u���؋��i��v�Ɓu��C�H�E�A����v��g�D���A��C���H��ɑR�����B�x |
�@��C���H��͐�ɂ������悤�ɁA���Y�}���w�������C�̘J���g���A����g�D�B�Ⴋ���̎��������w�������B��i����ς�j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/��j�́A��C�Í��X������Ƃ��鋐��\�͔ƍߑg�D�ł���B���ɃA�w���̖����ő傫�Ȏ����ƌ��͂�z�����B�^��i��������j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�^��j�͐��������ɋN�������u���������v������Ƃ��鐭���I�閧���Ђ��������A�u�Z��m�`�v���d��\�͒c�g�D�ł��������炵���B
| �w |
�S���X���A�Ӊ�͟�����i�ߕ��̐����𖽗߂��A�����U�ɁA���P��i�߂ɂ���悤�C�������A���킹�Đ펞�������12����Еz�����B�����A�����Ď@�ψ�������@�A���t�P�A�������A���Í]�A�ʕv���ƘA���Łw��}�~���ʓd�x�\���A�����������{�̗e�����������B�S���P�Q���A�Ӊ�͊e�ȂɁu��v���Đ��}�����s����v�Ɩ��߂��o�����B������m��♂͏�C���H��������U���o���Đ������߂ɂ����B�@�x |
�@�m��♁i�Ƃ����傤�j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�m��♁j�͐�̎�̂ŁA���łɓ`���I�ȑ��݂������B��C���H�������i�������ォ�j�ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�����j�̉��t�̉��ł��������炵���A���Ƃ��l�I�ɐe���������B����ş����m��♂ɊȒP�ɂ��т��o���ꂽ���̂ƌ�����B
| �w |
�S���P�Q���閾���A�Ӊ�̎w�������u���؋��i��v�Ɓu��C�H�E�A����v�͏�C�̑d�E����o�����A��C���H��@���̒��Ԃ���A�}�k�A��s�A�Y���A�������U�������B���̌�A�Ӊ�͟�����i�ߕ��ɍ����v���R��26�R�ɏ�������悤���߂������A�u�J���҂����ւ��߂��Ă���v�Ƃ������Ƃ������ɍH�l���@���ɑ��ĕ������������s���A300�l�]���E�������B�x
|
| �w |
���S���P�R���A��C���H��͘J���ґ����J�Â��A�Ӊ�Γ��������������B���̌��10���l�]�̘J���҂�w������R�H�ɍs���A�����}��26�R���t�c�̎��P��ɐ��肵�����A�R���͌Q�O�ɑ|�˂��A���̏��100�l�]�肪���ɕ����҂͐��m��Ȃ������B�����āA�Ӊ�͏�C���ʎs�Վ����{�A��C���H��y�ы��Y�}�̑g�D��ؑS�Ẳ��U�𖽗߂��A���Y�}���y�т��̎x���҂�{�����A1000�l�]��ߕ߂��A��v�ȃ����o�[�͏��Y���ꂽ�B�P�T���ɂ́A300�l�]���E����A500�l�]���ߕ߂���A5000�l�]�����H�����B�����ȋ��Y�}���̟����A���N�A�␢���炪�Q�����B�x |
�@�v����Ɂu�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�͓T�^�I�ȁu�����E���N�[�f�^�[�v�������̂ł���B���̎������u�N�[�f�^�[�v�ƌĂ��̂́A�Ӊ�����̎��������������ɂ��āA�������{���獶�h�y�ы��Y�}��ǂ��o���A���̎������������A�u�Ӊ�Γƍّ̐��v�����߂Ă�������ł���B�u�����E���\�́v�͍��̓��{�ł��A��O�̓��{�ł��A�P�X�U�T�N�̃C���h�l�V�A�����N�[�f�^�[�ł��A�P�X�V�R�N�̃`���E�����N�[�f�^�[�ł��K���\�͔ƍߑg�D�ƘA�g����B���́u�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�͂��������u�����E���\�́v�̐�삯�Ƃ��Ă��L�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
|
 |
|
�@���́u�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�Ɍĉ����邩�̂悤�ɂ��āA�S���P�T���ɂ͍L�B�ł����āA�Ӊ�̎x�z����n��ł́A���Y�}���E�J���҂ւ̑ߕ߁E�s�E���s��ꂽ�B���̒��O�̂��ƂɂȂ邪�A�S���U���ɂ́A�k���ŁA���{���x�z���钣�����R���̌R�����\�A��g�ق��P�����A�B��Ă������Y�}����ߕ߁E���Y�����B���̎��A�������Y�}�n�݈ȗ��̎�v�����o�[�A���������E���ꂽ�B
�@���̎����̌�A�������Y�}�́A���l���Ă݂Ă��A�N���l���Ă݂Ă��s�v�c�ȗ���s�\�ȍs�����Ƃ�B
�@���̎��̐�����傴���ςɊT�ς��Ă������B
�@�u�T�E�S�^���v�u�T�E�R�O�v�^����ʂ��āA�����l���́A�����Ƃ����������������I�ۑ肪�u���鍑��`�����v�Ɓu�ߑ�I�����`�̎����v�ł��邱�ƂɋC�������B����R�~���e�����������ɂ�����ۑ肪�u�Љ��`�v���v�ł͂Ȃ��A�u���鍑��`�����v�ł���A�u�����Ɨ������v�ł��邱�ƂɋC�����āA�P�X�Q�O�N�i�吳�X�N�j�A�u�����E�A���n���e�[�[�v���̑����A�����́u����E�����Ɨ������v��ϋɓI�Ɏx�����邱�Ƃɂ����B�����Ă��̒��S�ɑ����̒��������}�������āA���������������������������B�������A�P�X�Q�R�N�i�吳�P�Q�N�j�A�u�A�\�e���v�����q�Ƃ���u�����E���b�t�F�錾�v���āA���̊��҂ɉ������B
�@�������������������ɑ傫��������ݏo�����̂ł���B�P�X�Q�S�N�i�吳�P�R�N�j�A���������}�͑�P��S�������J���āA���Y�}�������Y�}���̐g���͂��̂܂܂ō����}�ɎQ������B���Ȃ킿��������������������A�����ɑ�ꎟ�������삪��������B���ʂ̖ڕW�́u�鍑��`�̘��S�ł���A�������I�ȗ}�������ł���R���œ|�v�Ƃ������j���f���A�k�����J�n�����B�傫�Ȍ�Z�͑������������邱�Ƃł���B
�@�R���I��p�ҏӉ�͂��̖k���̒��S�ɍ���̂����A�R�~���e�����⒆�����Y�}�������뜜���Ă����Ƃ���A�k����ʂ��ďӉ�́A�R���I���͂̏W���Ə����ɐ�������B�������ďӉ�́A�u������`�ҁv�̖{�����ނ��o���ɂ��āA������厑�{�E�n��K���i���̔w��ɂ͗鍑��`������j�̗v�����A�ˑR���̖�������Y�}����J���ҊK���Ɍ����ċs�E���J�n����B���ꂪ�u�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�̖{���ł��낤�B���̃N�[�f�^�[��ʂ��ďӉ�́A�R���ʂ����Ȃ������}�S�̂̌��͂��������Ă��܂��B
�@���ꂪ�����̐����̗��ꂾ�낤�B�������𗠐����̂͏Ӊ�ł���A���Y�}�͑����̓}�����E���ꂽ����łȂ��A�D�G�Ő퓬�I�ȑ����̘J���҂��������B
�@�Ƃ��낪�������Y�}�́A�P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�S���Q�V���A�{���n�ł��镐���ŊJ���ꂽ��T�����Y�}�S�����ŁA�������c�_�̖��ł͂��������A�u��������ێ��v�����肵�Ă��܂��̂ł���B
�@�u�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�قǏӉ�̖��m�Ȉӎv�\���͂Ȃ��B�ɂ��ւ�炸�A���̎��̋��Y�}�́A�����}�ň�ɂ܂Ƃ܂�A�u��������v�����̕��j��ς��Ȃ������B���̌���̔w��ɂ̓R�~���e�����́u��������ێ��v�u�������ɂ����鍑���}�̎哱�����F�v�Ƃ�����{���j�Ǝw�����������B
�@�܂蓖���̒ƏG�𒆐S�Ƃ��鋤�Y�}�����́A���̃R�~�e�����̎w���𐳂������̂Ƃ��āA�S������ɂ͉���Ȃ����j���@�B�I�Ɍ��肵�Ă��܂����̂��B
|
|
 |
|
�@���R�̂��ƂȂ��炱�̕��j�͏Ӊ���疳�����ꂽ�B����Ε@��ł���������B�������{�̒��ł����ۂ��͂��܂����B�������{�P���̎�ȌR�l�����i�Ƃ����Ă����̂قƂ�ǂ͂��ƌR���ł��邪�j�����炩�ȁu�����v�ɓ]�����̂ł���B�����}���h���u�����v��N���ɂ��Ă������B�]���Ȃɒ��Ԃ��Ă������h�n�R�l��|���i������Ƃ��j�����Y�}���̏ȓ�����̑ދ���v�������B
�@�ȉ��͎�|���������ɓ]�������Ƃ�`�����㒩���V���̋L�����B���t�͂P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�U���X���ƂȂ��Ă���B
�ihttp://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/ContentViewServlet?METAID
=00789458&TYPE=HTML_FILE&POS=1&LANG=JA�@�j
| �w |
��|�������싞�h�ɖ��� ���Y�h���ɒ��肷
�y�������d�ܓ����z�]���͍ŋߌΓ�Ɏ����ŋ��Y�h�̉��\�r�������ɒ[�Ȃ鋰�|�������Ƃ�̂œ�����蕐���h�ɂ��݂��Ă�����|�������ߓ��̒ʓd�ŗ��@�m���Ɩk����g�ɂ��ĉ���Ĉȗ��ԓx��ς��싞�h�ɉ��������Y�}�r�˂ɒ��肵���̂œ쏹����э]���e�n��苤�Y�}�n���������͑��X���n�ɓ���ė����A��|�����̕����͎O�t�ł��邪���̒��������̈�t�͋��Y�n�Ŏ�|���R�ɑR���Ă���A�Ȃ���������������𗦂�ʎR���ɂ��������鎁�Ƒō��������ʈ�v���č]���̋��Y�h�����邱�ƂƂȂ����A�������{�͂��̌`���ɑ傢�ɘT�����Ă��邪�抸���鎁��ƐE���ĉ��������O�R���ɔC�������x |
�@���̋L���Łu�싞�h�v�Ƃ����̂͏Ӊ�����}���{�̂��Ƃł���B�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�Ŏ��������������Ӊ�́A�{���n��쏹����싞�ɑJ���Ă����B
�@����������̒��ŁA�u�n�����ρv�ƌĂ�鎖�����N����B�P�X�Q�V�N�T���Q�P���A�����v���R��W�R�������q�i�Ƃ��������B���ƌΓ�̌R���j�̕��������ˁi���傱�����傤�j�̘A���������ŏȑ��H��i�J���g���j�A�_������A���Y�}���@�ւ��P���P�T�Ԃɂ킽���ď��Y���J��Ԃ��������ł���B
�@�ёI�W�i�O���o�ŎЁ@�P�X�U�W�N�R���R�P���@���Łj��P���u�䉪�R�̓����v�̍��̒��ɁA
| �w |
�Γ�Ȃ̕��]���A�g�z����тł́A�P�X�Q�V�N�t�ɂ́A�����L�͂Ȕ_�������g�D������Ă����B�T���Q�P���A�����˂������Ŕ��v�������i�܂�u�n�����ρv�j���������A�v���I��O���s�E�����B�T���R�P���A���]���A�g�z����т̔_���R�́A�����Ɍ������Ă����݁A���v�����͂ɔ����������悤�Ƃ������A���a����`�̒ƏG�ɑj�~����ēP�ނ����x�i�o�P�R�O�j |
�Ƃ���B
�@�܂艽��Ȃ����ׂ��Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B
�@�����}���h�̟����q�i�������j�������ɓ]�����B�J���ҋ��@���̊����͐�����y�n�v���͌��ւƂȂ����B�����q���������{��������̋��Y�}���r���ɓ������B
�@�Q�V�N�i���a�Q�N�j�V���P�R���A���Y�}�͕������{����P�ނ��A�P�T�������}�́u�e������̔j���v��錾�A�����ɂP�X�Q�S�N�i�吳�P�S�N�j�P���ȗ��́u��ꎟ��������v�͖����Ƃ��ɕ����̂ł���B
�@���S�����ƂȂ����Ӊ�́A�P�X�Q�V�N�X�������Ɠ싞�̗����{�ꂵ�A���̎w�����������Ă����E�E�E�B
�@�����܂ł��A��ꎟ�����������܂ł̑傫�ȗ���ł���B |
|
 |
|
�@�����ł̑傫�ȋ^��́A�u�S�E�P�Q�N�[�f�^�[�v�̌�����̃R�~���e�����́A�u��������ێ��v�u�����}�哱�̓������v�ȂǂƂ������悻���I�Ȏw�����j���Ƃ�A���̕��j�̂��߂ɂނ��ނ������̋��Y�}����J���ҁE�_�����E������悤�Ȍ���Ƃ����̂��Ƃ����_�Ɖ��̒ƏG���͂��߂Ƃ��鋤�Y�}�����́A���悻���̔n�������w�����j�ɖӖړI�ɏ]�����̂��ƌ����_�ł���B
�@���̋^��ɑO�f���u�����ߌ���j�v�i��g�V���j�͂o�P�P�X�\�o�P�Q�O�̒��Ŏ��̂悤�ɓ����Ă���B
| �w |
���[�j���̎���\�A�ł͓}�̎w�������߂����ăX�^�[�����A�u�n�[������ƃg���c�L�[�A�W�m���B�G�t�炪�������Η����Ă���A���̑Η��̓R�~���e�����̒������̂܂������܂ꂽ�B�g���c�L�[����������A���������������}�ւ̒ǐ������߂ċ��Y�}�Ǝ��̘J�_�^����W�J����Ǝ咣���Ă����̂ɑ��āA�X�^�[�����͍�������̈ێ��ɌŎ����A�Ӊ���邢�͟����q�Ƃ̌�����ɗ͔����悤�Ƃ����B
���ꂪ��C�̂S�E�P�Q�N�[�f�^�[�Ⓑ���̔n�����ς̂悤�Ȕ��F�e���ɑ��ėL���Ȕ����������邱�Ƃ��ł����A�v����s�k�ɓ�������ƂȂ������Ƃ͖����ł���B�������a���킸���U�N�̒������Y�}�����_�I�ɂ����H�I�ɂ������n�ł��������Ƃ��A�v���s�k�̑傫�ȗv���ł������B
�X�^�[�����͔s�k�̑S�ӔC�����Ƃ��U���P���P�߂̂悤�Ȋv���I����̎������T�{�^�[�W�������ƏG�̉E�����a����`�ɋA���Ă��邪�A�͂ނ��뒉���ɃX�^�[�����̘H��������Ă����Ƃ����]����̂ł���B�x |
�@�����łU���P���P�߂Ƃ����̂́A�P�X�Q�V�N�U���P���R�~���e�������������w�߂Łu�y�n�v���̎��s�v�u�V�����R���̑n�o�v�u�����}�����ψ���̉����v�u�����I�ȏ��Z�̒Ǖ��v�Ȃǂ��悻�A�����}�̘g���ɂ��Ă͎��s�ł������ɂ��Ȃ����I�������ɖ����������P�߂ł������B�ƏG�͂��܂��߂ɂ����̓��e�ŁA�������{�̍��h�����q�ɂ��������A�ɂׂ��Ȃ����₳��Ă���B
�@��������w�̕��c�D���͘_���u�R�~���e������V����_�v�̒��ŁA
| �u |
�E�E�E�R�~���e�����Ɋւ�����j�I�E�_���I�Ȍ����́A�O���ł����{�ł��A�ŋ߂ɂȂ��Ă悤�₭�{�i�����Ă����Ƃ����Ă����悤�ł���B�E�E�E�R�~���e�����̗��j�ɂ́A�ɂ߂ĐϋɓI�ȑ��ʂƓ����ɁA�����A�\�Ɍ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ے�I�ȏ��ɓI���ʂ��܂܂�Ă����B�v�i�o�P�U�P�j
|
| �u |
�E�E�E��V������i���P�X�R�T�N�����a�P�O�N�j�܂ŁA�R�~���e�����̂Ƃ��Ă����헪�E��p�ɂ́A�X�^�[������`�̖���Ɋ�b��u���A����I�Ȍ��ׂ��B����Ă����B�����A���[�j����`�̎���ƃX�^�[������`�̎���Ƃł́A�R�~���e�����̗��j�]���̏�ŁA�傫�ȋ��ܖʂ��w�E���邱�Ƃ��ł���B���[�j���̃R�~���e�����ɑ���\���I�Ȋ֗^�Ɋr�ׁA�X�^�[�����̓R�~���e�����̊����̕\����ɂ͈�x���o�ꂹ���A�]���āA�w���ڂɐӔC����x���Ȃ������x�i�g���A�b�e�B�j�ɂ�������炸�A�R�~���e�����̏����c�⏔�w�߂��ĕ]������ꍇ�ɂ́A�ނ̉e�̊֗^�̐Z�����𐳂����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�i�o�P�U�R�j |
�@�Əq�ׂĂ���B���c�����̘_�����������̂̓\�A����O�����A��͍��ł��ς���Ă��Ȃ��B
�@���[�j���̎����i���[�j������������̂͂P�X�Q�S�N�\�吳�P�R�N�P���ł���B�����͂��̂P�S������A�P�X�Q�T�N�R���Ɏ�������B�j�́A�R�~���e�����́A���E���Y��`�^���̒��S�������B�X�^�[�����̎���ɂ́A�R�~���e�����͂���h�q�̓���Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ����Ƃ�����������������ƌ����߂��ł��낤���H�u�\�A�̎Љ��`�v�������ł������悤�ɁA�R�~���e�������܂��u�X�^�[������`�v�̓o��ɂ���đ傫���ώ������̂ł���B
�@�ё炪�������Y�}�̎w�������m������̂́A�R�~���e�����̉e����E����̂́A�̂��Ɍ���悤�ɁA�P�X�S�Q�N�i���a�P�V�N�j�̂��Ƃ����A����܂Ŗё�̓R�~���e�����̌�������j�̂��߂ɉ��x���ς��������܂����B�ё�́A���{�̒鍑��`�Ɠ������ʁA�X�^�[������`�̃R�~���e�����Ƃ���킴������Ȃ������Ƃ����]����̂ł���B
|
|
 |
|
�@�u�c��_�_���v�̒��́A�u�Ӊ�̓R�~���e�����ɓ�������Ă����B�v�u�ё̓R�~���e�����̎�悾�����B�v�Ƃ����P���c�t�ȋL�q�������邽�߂ɂ����܂ŗ��Ă��܂����B
| �i |
�܂����x���J��Ԃ��ɂȂ邪�A����ȒP���c�t�Ȓj���Ȃ��q�����ɂȂ����̂��H�j |
�@�u�c��_�_���v���т����j�ς́A�܂����{�̎����}�̑����̐����Ƃ̗��j�ςł���A�Ƃ������Ƃ͔ނ���x������w�҂�}�X�R�~�A�W���[�i���X�g�A�����𐳂����ƐM���鏭�Ȃ���ʓ��{�̎s���̗��j�ς̂��Ƃł����邪�A���̐푈���w�N���푈�ł��������Ȃ��������x�Ƃ����c�_�̑O�ɁA�w��̓��{�R�͒N�Ɛ�����̂��x�ƌ������ɐ^���ɓ����Ă݂�K�v������B
�@�c��_���g�́A���̖��A���Ȃ킿�����{�R�͈�̒N�Ɛ�����̂��Ƃ��������A���܂�[���͍l���Ă��Ȃ��B���镔���ł́u�Ӊ�����}�R�v�Ɛ�����A�ƍl���Ă���ӏ������邵�A�u�R�~���e�����̎��̖ёv�Ƃ��������ł́A���邢�͒������Y�}�Ɛ�����Ƃ��l���Ă���悤�ɂ�������B�u���͏Ӊ�̓R�~���e�����ɓ�������Ă����B�v�ƌ����Ă��镔���ł́A�R�~���e�����A���Ȃ킿���ۋ��Y��`�Ɛ�����A�ƍl���Ă���悤�ɂ�������B����́A�������A�c��_�����ł͂Ȃ��B
�@���̐푈�́u�N���푈�ł͂Ȃ������B���{�̖h�q�푈�������B�v�Ǝ咣���鐭���ƁA�w�ҁA�}�X�R�~�A�����l�i�H�j�A�W���[�i���X�g�A�s���̒N�ɕ����Č��Ă������B�u�N�Ɛ�����̂��H�v
�@������͉̂��b�Ȋ炷�邩���m��Ȃ��B�u�ǂ����Ă���Ȕn���Ȏ��������̂��H�킩�肫���Ă��邶��Ȃ����H�v������̂́u�Ӊ�v�u�ёv�u���Y��`���́v�u�R�~���e�����v�u�\�A�̉A�d�ɂ����̂����ꂽ���́v�E�E�E�B
�@�ݐM��́w�ݐM���z�^�x�i���a�T�W�N�\�P�X�W�R�N�@�A�ϓ��o�Ł@�P�P���W�����Łj�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
| �w |
�@���A�����ŁA�푈�ٔ��̓��ۂɂ��ďڍׂɘ_�������͂Ȃ����A�푈�ٔ��i���ɓ��R���ٔ��̂��Ɓj��ʂ��ē��{�����̒��ɁA�u���{�͐N���푈�������A�������Ƃ������v�Ƃ����~�ߕ����A���O�\�N�����������ł��������c���Ă���悤�Ɏv����B�͂Ȃ͂������Ɏ����Ă͖����J���ȗ��A���{�̂��Ă������Ƃ͂��ׂĐN���ł��舫�ł���A�ƌ�������A���炪�����ɕ����������Ă���悤�ȏ�Ԃ�������̂ŁA�����ňꌾ�q�ׂĂ݂����B�x�i�����o�P�V�|�o�P�W�j |
�@�������߁A���Ȃǂ͂����ł��낤�B�u�����N���͖��������̍��ƈӎu�������B�v�ƌ����Ă���̂�����B�������͂����������������A����������炱�̌��_���̂ł͂Ȃ��B��s���Ƃ��āu���j�v�A���Ɂu�����ߌ���j�v���w��ōs���ߒ��œ���ꂽ�A�N�̂��̂ł��Ȃ��A���̌��_���B
�݂𑱂��悤�B
| �w |
�E�E�E�푈�ɂ͎��q�ƐN���̋�ʂ��\�Ȃ̂��Ƃ��������_��w���ɐV���Ɋ�^����Ƃ�����i���ɓ��R���ٔ��́j�Ȃ������̂ł���B
�č��𒆐S�Ƃ����A�����̏����̑Γ���̐���̊�{�́A�푈�̐ӔC�����ׂē��{�����ɕ��킹�i���݂̘b�̓r�������A�����́A�݂͎���Ⴂ�����Ă���B�|�c�_���錾��ɓ��R���ٔ��̋L�^�A��̌R�̑Γ����������Ȃǂ�ǂތ���A�푈�̐ӔC�́A���{�̍����ɕ��킹�Ă͂��Ȃ��B�V�c���t�@�V�Y���ƌR����`�҂ɕ��킹�Ă���B���炩�ɂ��̗��҂���ʂ��Ă���B�c��_�ƈႢ�A�����Ȋ݂̂��ƂŁA�������ԈႦ��͂��͂Ȃ��B������Ӑ}�I�Ȋ��Ⴂ�Ƃ����ׂ����낤�B�j�A���{�����������Ă��鍢�����J�͂��ׂĎ��Ǝ����ł���Ǝv�����܂���_�ɂ���A���̈Ӗ��œ����ٔ�����Ό��͂�p�����g�V���[�h�������̂ł���B�����̔�p�Ɛl���̑����Ō��������������ٔ����A���̌�̐��E���a�̐i�W�ɂǂ�قǂ̉��l�������Ă��邩�́A�����܂ł̍��ۏ�̕ϑJ������Ζ��炩�ł��낤�B�����m�푈���̍ő�̖����ʎE�l�ł���A�L���E����ɓ������ꂽ���q���e�ɑ���ӔC�́A�����ٔ��ł͑S���s��ɕt����ꂽ���A���̂��Ƃ����ɂ����Ă�����Ȋj��͋������o�������A�l�ޑS�̂����Ĕj�ł��������̏d��ǖʂɗ������߂Ă���̂ł���B�x�i�����P�X�o�j |
�@�b�͈Ⴄ���A�݂͍L���E����ւ̌��������̖{�����悭��ÁE�I�m�Ɍ��Ă���Ƃ����ׂ��ł��낤�B |
|
 |
|
�@���̕��͂̒��ŁA�݂������Ă��邱�Ƃ́A�ɓ��R���ٔ��̕s�����̑��ɂ́A���̂Q�_�ɂ��悤�B
�@�@�P�D���̐푈�͐N���푈�ł͂Ȃ������B
�@�@�Q�D���{�̓A�����J�ɕ������B
�@����ł́A�݂͂��̐푈���ǂ����Ă����̂��Ƃ����ƁA���{�̎��q�푈�������A�ƌ����Ă���킯�����A����͘_���I�ɂ��������B
�@�푈�����{�̍��y�Ő��ꂽ�̂Ȃ��i���Ƃ��x�g�i���푈�ɂ�����x�g�i���l���̂悤�Ɂj�A����͎��q�푈�����A���Ƃ��ƒ����嗤�ł̐킢���A�����m�푈�ɔ��W���Ă������킯�ŕ����ʂ�̎��q�푈�������킯�ł͂Ȃ��B�������݂̔F���̒��ł́A���q�푈�������B�݂�����Ȕ�_���I�Ȏv�l������͂����Ȃ��B������A�݂�����Ă��Ȃ����Ƃ����Ă��Ȃ���A�݂̘_�����͈�т��Ȃ��E�E�E�B
�@�u���̐푈�ŁA���{�̓V�c���t�@�V�Y���E�R����`�͈�̒N�Ɛ킢�A�N�ɔs�ꂽ�̂��H�v�E�E�E���ꂪ���̃e�[�}�ł���B�c��_�Ƙb�����Ă��Ă��A�炿�������Ȃ��̂ŁA�����E��䏊�A�ݐM��ɓo�ꂵ�Ė�����킯�����A���݂̊��̐S�ȓ_�͌�������ł���B
�@�������l����q���g�͏\���ɒ��Ă���Ă���B
�@�݂͂��̐푈�͐N���푈�ł͂Ȃ������A�ƍl���Ă���B���q�푈�������ƍl���Ă���B�ł͐��������͒N���������Ƃ����ƃA�����J�ł���B�݂ɂ͒����l���Ɛ�����ƌ����ӎ��͋ɂ߂Ċł���B�����ăA�����J�ɂ͕������A�ƍl���Ă���B�ɓ��R���ٔ��͌��Ǐ������A�����J�����������{���ق������̂ł���A���j�I�ɂ��A�@�I�ɂ��������͂Ȃ��ƍl���Ă���B���̍l�����́A�݂̒��삷�ׂĂ��т��ނ̎咣�ł�����B |
|
 |
|
�@�����ŋ����I�ɂ��̐푈���l���Ă݂悤�B�����̒��Ɏ��_��u���Ă݂�ƁA���������A�A�w���푈�ȗ��A�����͈���I�ɐN�����Ă������j���������Ƃ͂���܂ŁA���̃V���[�Y�Ō��Ă����Ƃ��肾�B
�@���������x�͎��_���A�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�A���V�A�A�A�����J�A���{�ȂǁA�̗���Ɉڂ��A���̒鍑��`�I�ϓ_���璭�߂Ă݂悤�B����́u�����s�ꑈ�D�j�v�������B
�@���̐A���n���̂悤�ɒ������P�ꍑ�̐A���n�ɂȂ�Ȃ������̂́A�������]��ɂ��K�͂��傫���A��������S�ȐA���n�ɂ��邾���̗͂��������鍑��`�������݂��Ȃ������ƌ����ɂ����Ȃ��B
�@�܂��A�P�X���I���E�ɒ鍑��`�I�e�����m�������C�M���X�������ɑ����z�����B�n���I�ɋ߂����V�A�����ɓ쉺���Ă����B�ߑ㉻��i�߂����{���j���[�t�F�[�X�Ƃ��ċ}���ɓo�ꂵ�Ă����B�t�����X�A�h�C�c�Ȃǂ����ꂼ��̒鍑��`���Ƃ��Ă̗͗ʂɉ����āA�������\�H�����B�t�B���b�s���̐A���n�����I�����A�����J�鍑��`������Ă����B
�@�������Ē����̗������߂����āA���ɂ�ݍ����A��������̍��Ǝ��D�����߂Ă������B
�@��ꎟ���E���̖u���Ƃ��̌����́A�������߂���̐��͐}����ς������B�܂����V�A���E�������B�������A����͊ϓ_��ς��Ă݂�ƒE�������̂ł͂Ȃ��A�鍑��`�I���l�̌n�Ƃ͑S���قȂ鉿�l�̌n���������Ƃ��ĕϐg�����̂ł��邪�A�鍑��`�I���l�̌n�����������Ƃ��ẮA�Ƃɂ������E�������B
�@�s�퍑�A�h�C�c���S���E�������B���ō��͂����Ղ����t�����X�́A��������傫����ނ��A�x�g�i���A���n�o�c�ɐ�O����p���ɕϊ������B�C�M���X�͍ő�̒鍑��`������A���セ�̎�����A�����J�ɖ����n������Ȃ������B����������ˑR�傫�ȉe���͂�ۂ����A�鍑��`���Ƃ��Ă͌�ނ����B
|
|
 |
|
�@�������Ďc�����̂��A�u�Ύ���D�_�v�I�ɉe���͂𑝂������{�鍑��`�Ƒ�ꎟ���E���ő傫���͂𑝂����A�����J�鍑��`�������B�L��ŋɂ߂Ė��͂ɕx�ޒ����̎x�z�����߂����ē��{�鍑��`�ƃA�����J�鍑��`���ɂݍ����i�D�ƂȂ����B
�@�������āA�ݐM��̔F���ł́A�����x�z�����߂���ŏI�킪�A���Đ푈�i�����m�푈�j�������̂ł���A�鍑��`���{�ɂƂ��āu�����v�͎c���ꂽ�ő�́u���v�E�����E�s��v�ł���A����������̂́A�鍑��`���{�̎��E�s�ׂɓ������A��������̂́u���q�s�ׂ��v�ƌ������ƂɂȂ�B
�@�v���o���ė~�����̂��A���ĊJ��̂ЂƂ̂��������ƂȂ����u�n���E�m�[�g�v�̂��Ƃ��B�ȒP�ɂ����āu�n���E�m�[�g�v�Ō����Ă��邱�Ƃ͈�ł���B�u���{�͒����嗤���炻�̌R���͂�P�ނ���B�v�Ƃ������Ƃ��B��������Ȃ���A��v�Ȍo�ϊW�����ׂĒf�₷��A�ƌ������Ƃł�����B
�@����܂Ō��Ă����Ƃ���A�鍑��`�ɂƂ��ČR���͂̓Z�b�g�ł���B�R���I�\�͂�w�i�ɂ��Ȃ���A�鍑��`�I�o�ϗ����͎��Ȃ����A�g���ł��Ȃ��B�R���͂̓P�ނ́A�鍑��`���{����������S�ʓP�ނ��邱�Ƃ��Ӗ�����B
�@������ݐM��ɂƂ��āA���Đ푈�i�����m�푈�j�́u���q�̐푈�v�������̂ł���B���������ł��݂́u�Ӑ}�I���Ⴂ�v�����Ă���B�u���q�̐푈�v�͂��̒ʂ肾�Ƃ��Ă��A����́u���{�̎s����ʁv�ɂƂ��Ắu���q�̐푈�v�������̂ł͂Ȃ��A�u���{�̒鍑��`�v�ɂƂ��Ắu���q�̐푈�v�������̂ł���B
�@�݂��u���̐푈�͐N���푈�ł͂Ȃ��A���q�̐푈�������B�v�Ǝ咣���鎞�A�ނ����S�ɒ鍑��`�҂̘_�����g���āA�鍑��`�҂̗���ɗ����Ď咣���Ă��邱�Ƃ𗝉����Ă����˂A���̘_���͎����т��Ȃ��B |
|
 |
|
�@�����m�푈���A��{�I�ɂ͒����̔e�����߂���u�鍑��`�Ԑ푈�v�������Ƃ����݂̔F���́A���̒ʂ萳�����Ƃ��Ă��A�݂̔F������́u�����Ƃ̐푈�v�͉��������̂��A�ƌ������_�͂����ۂ蔲�������Ă���B
�@���_���u�����ߌ���j�v�ɗ���ɖ߂��Ă݂悤�B
�@�A�w���푈�ȗ��̒����̗��j�́A�ꌾ�ʼn]���A����̗��s�s�ȐN���i�鍑��`�̐N���͗�O�Ȃ����s�s�ł���B�j�������A����Ɛ키���j�������B�i�������Q����̂́A�����l�������̗���̐N���ɒ������ԑf��Ő�������Ƃ������B�j
�@���̒������j�̍ŏI�ǖʂœo�ꂵ���鍑��`�����{�鍑��`�������B���̎��A�����J�͎���̂��߂̒鍑��`�̗��v�Ǝ��{��`�������`�i������u���W���A�����`�Ƃ����Ă������x���Ȃ����낤�B�j�̂Q�̈قȂ闧�ꂩ��A�������x�������B�����m�푈�ɂ́u�t�@�V�Y���Ɩ����`�̐킢�v�Ƃ������ʂ����������Ƃ͕�����Ȃ������������B
�@���ǁA�����Ɛl�������������́A���{�̒鍑��`�������̂ł���B����������͋��\�������t�@�V�Y���鍑��`�������B
�@���̐푈�́u�鍑��`�Ԑ푈�v�ł͂Ȃ��B�����l���̑����猩��A�u���鍑��`�푈�v�ł���A�u�����Ɨ��푈�v�������B�����l�����猾���A�푈�́u���{�̒鍑��`�E�R����`�E�V�c���t�@�V�Y���v�Ƃ̐킢�ł���A�����āA����ɏ��������̂ł���B�u���q�̐푈�v�Ƃ����Ȃ炱��قǂ́u���q�̐푈�v���Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�݂̒��ł́A�u�����l���Ɛ���Ă���ɔs�ꂽ�B�v�Ƃ����F���͂Ȃ��B
�@�����u���Č���v�i�����m�푈�j�ɁA���{�i�Ƃ����Ă��鍑��`���{�ł��邪�B�j�ɕ����Ȃ���A��������P�ނ���K�v�͂Ȃ������ƍl���Ă��邱�Ƃ��낤�B
�@����݂͊���т��āA�鍑��`�҂̘_�����g���āA�鍑��`�҂̗���ŗ��j�����A���E�����Ă��邩�炾�B�鍑��`�҂̘_���ȊO�͓��荞�ތ��Ԃ��Ȃ��B
�@�������A�����݂̔F�������̒ʂ�Ȃ�A�݂͂܂��������j�F��������Ă���Ɖ]�킴��Ȃ��B�u�鍑��`���{�v�́u�鍑��`�A�����J�v�ɔs�ꂽ���A�����l���ɂ��s�ꂽ�̂ł���B�J��Ԃ����݂����̔F���ɒB�����Ȃ��̂́A�ނ��鍑��`�҂̘_�������������A���ʂ̓G�u�����l���v�������Ă��炸�A�]���Ĕނ��鍑��`�ɏ|�˂��u�\�k�v�A���Y��`�ɐ�������Ă���u�\���v�Ƃ������Ȃ��������炾�B
�@�c��_�̎咣�́A���݂̘̊_����c�t�ɂ��ǂ��ǂ����Ȃ����Ă���ɉ߂��Ȃ��B |
|
 |
|
�@�����u�c��_�_���v�ł����Ƃ����Ɗ������̂͂��̓_�ł���B�b�́A�c��_�ł��Ȃ��A�݂ł��Ȃ��A���q���ł��Ȃ��A�����������ł��Ȃ��A�E�������Ƃł��Ȃ��A�E�������l�ł��Ȃ��A�E���}�X�R�~�E�W���[�i���Y���ł��Ȃ��B���Ȃ�ʂ�����ʎs���́u���j�F���v�̖�肾�B
�@�^���鍑��`�҂ł���ݐM��₻�̎O���z�ł���c��_���A�鍑��`�҂̘_�����g���Ă��̗��j�ς�ł����āA���̗��ꂩ�琢�̒������Ă���̂́A����Ӗ����R���낤�B�i�����A�݂���㎩�����w�^���鍑��`�ҁx�ł���{�����B���A�w�����`�ҁx�ł��邩�̂悤�ɐU�镑���̂̓t�F�A�ł͂Ȃ��B�j
�@�������{�̈�ʎs�����A�Ȃ��u�鍑��`�ҁv�̘_���Ɨ���ŗ��j�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H
�@�����������{�̈�ʎs�����A�u�^�������`�ҁv�ł���Ȃ�A�����`�̘_���Ɨ���ŗ��j�߁A���̗��ꂩ�猻�݂̐����ɔ��f�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�Q�P���I�ɐ�����A�����u���{�̎s���v�ɂ́A���̈�l��l�ɂ��̐ӔC������B
�@�u�c��_�_���v����N�������́A�]���āu���j�F���v�́A����������匠�҂�����{�̈�ʎs���́u���j�F���v�̖��Ȃ̂��B |
|
| �i�ȉ�����j |
 |
 |