 |
 |
| No.23-6(抜き書き) |
平成21年1月1日 |
 |
| ※ |
本シリーズ「その6」は思いもかけず長文になってしまった。そのため「その6」最終部分を、別途に抜き書きしておく。
|
|
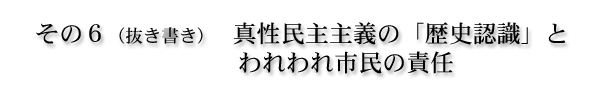
|
 |
|
「田母神論文」の中の、「蒋介石はコミンテルンに動かされていた。」「毛沢東はコミンテルンの手先だった。」という単純幼稚な記述を検証するためにここまで来てしまった。
| ( |
また何度も繰り返しになるが、こんな単純幼稚な男がなぜ航空幕僚長になったのか?) |
「田母神論文」を貫く歴史観は、また日本の自民党の多くの政治家の歴史観であり、ということは彼らを支持する学者やマスコミ、ジャーナリスト、それらを正しいと信じる少なからぬ日本の市民の歴史観のことでもあるが、あの戦争を『侵略戦争であったかなかったか』という議論の前に、『一体日本軍は誰と戦ったのか』と言う問題に真剣に答えてみる必要がある。
田母神自身は、この問題、すなわち旧日本軍は一体誰と戦ったのかという問題を、あまり深くは考えていない。ある部分では「蒋介石国民党軍」と戦った、と考えている箇所もあるし、「コミンテルンの手先の毛沢東」という部分では、あるいは中国共産党と戦ったとも考えているようにも見える。「実は蒋介石はコミンテルンに動かされていた。」と言っている部分では、コミンテルン、すなわち国際共産主義と戦った、と考えているようにも見える。これは、しかし、田母神だけではない。
あの戦争は「侵略戦争ではなかった。日本の防衛戦争だった。」と主張する政治家、学者、マスコミ、文化人(?)、ジャーナリスト、市民の誰に聞いて見てもいい。「誰と戦ったのか?」
あるものは怪訝な顔するかも知れない。「どうしてそんな馬鹿な質問をするのか?わかりきっているじゃないか?」あるものは「蒋介石」「毛沢東」「共産主義勢力」「コミンテルン」「ソ連の陰謀にそそのかされた勢力」・・・。
岸信介は『岸信介回想録』(昭和58年―1983年 廣済堂出版 11月8日初版)で次のように書いている。
| 『 |
今、ここで、戦争裁判の当否について詳細に論ずるつもりはないが、戦争裁判(*極東軍事裁判のこと)を通じて日本国民の中に、「日本は侵略戦争をした、悪いことをした」という受け止め方が、戦後三十年たった今日でも根強く残っているように思われる。はなはだしきに至っては明治開国以来、日本のしてきたことはすべて侵略であり悪である、と言う解説、教育が未だに幅をきかせているような状態も見られるので、ここで一言述べてみたい。』(同書P17−P18) |
さしずめ、私などはそうであろう。「中国侵略は明治政権の国家意志だった。」と言っているのだから。ただ私はそう言う解説を受けたり、教育を受けたからこの結論を得たのではない。一市民として「歴史」、特に「中国近現代史」を学んで行く過程で得られた、誰のものでもない、私の結論だ。
岸を続けよう。
| 『 |
・・・戦争には自衛と侵略の区別が可能なのかといった理論や学説に新たに寄与するところは(*極東軍事裁判は)なかったのである。
米国を中心とした連合国の初期の対日占領政策の基本は、戦争の責任をすべて日本国民に負わせ(*岸の話の途中だが、ここは、岸は若干勘違いをしている。ポツダム宣言や極東軍事裁判の記録、占領軍の対日政策文書などを読む限り、戦争の責任は、日本の国民に負わせてはいない。天皇制ファシズムと軍国主義者に負わせている。明らかにこの両者を区別している。田母神と違い、聡明な岸のことで、ここを間違えるはずはない。だから意図的な勘違いというべきだろう。)、日本国民が今日受けている困苦や屈辱はすべて自業自得であると思いこませる点にあり、その意味で東京裁判も絶対権力を用いた“ショー”だったのである。多くの費用と人命の損失で結末を見た東京裁判が、その後の世界平和の進展にどれほどの価値をもっているかは、今日までの国際情勢の変遷を見れば明らかであろう。太平洋戦争中の最大の無差別殺人である、広島・長崎に投下された原子爆弾に対する責任は、東京裁判では全く不問に付せられたが、そのことが戦後においても激烈な核戦力競争を出現させ、人類全体をして破滅か存続かの重大局面に立たしめているのである。』(同書19P) |
話は違うが、岸は広島・長崎への原爆投下の本質をよく冷静・的確に見ているというべきであろう。 |
|
 |
|
この文章の中で、岸が言っていることは、極東軍事裁判の不当性の他には、次の2点につきよう。
1.あの戦争は侵略戦争ではなかった。
2.日本はアメリカに負けた。
それでは、岸はあの戦争をどう見ていたのかというと、日本の自衛戦争だった、と言っているわけだが、これは論理的におかしい。
戦争が日本の国土で戦われたのなら(たとえばベトナム戦争におけるベトナム人民のように)、これは自衛戦争だが、もともと中国大陸での戦いが、太平洋戦争に発展していったわけで文字通りの自衛戦争だったわけではない。しかし岸の認識の中では、自衛戦争だった。岸がこんな非論理的な思考をするはずがない。だから、岸が語っていないことを補ってやらなければ、岸の論理性は一貫しない・・・。
「あの戦争で、日本の天皇制ファシズム・軍国主義は一体誰と戦い、誰に敗れたのか?」・・・これが今のテーマである。田母神と話をしていても、らちがあかないので、黒幕・大御所、岸信介に登場して貰ったわけだが、その岸も肝心な点は口をつぐんでいる。
しかし考えるヒントは十分に提供してくれている。
岸はあの戦争は侵略戦争ではなかった、と考えている。自衛戦争だったと考えている。では戦った相手は誰だったかというとアメリカである。岸には中国人民と戦ったと言う意識は極めて希薄である。そしてアメリカには負けた、と考えている。極東軍事裁判は結局勝ったアメリカが負けた日本を裁いたものであり、歴史的にも、法的にも正当性はないと考えている。この考え方は、岸の著作すべてを貫く彼の主張でもある。 |
|
 |
|
ここで巨視的にあの戦争を考えてみよう。中国の中に視点を置いてみると、清朝末期、アヘン戦争以来、中国は一方的に侵略を受けてきた歴史だったことはこれまで、このシリーズで見てきたとおりだ。
しかし今度は視点を、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、アメリカ、日本など、列強の立場に移し、その帝国主義的観点から眺めてみよう。それは「中国市場争奪史」だった。
他の植民地国のように中国が単一国の植民地にならなかったのは、中国が余りにも規模が大きく、これを完全な植民地にするだけの力をもった帝国主義国が存在しなかったと言うにすぎない。
まず、19世紀世界に帝国主義的覇権を確立したイギリスが中国に足場を築いた。地理的に近いロシアが次に南下してきた。近代化を進めた日本がニューフェースとして急速に登場してきた。フランス、ドイツなどもそれぞれの帝国主義国としての力量に応じて、中国を蚕食した。フィリッピンの植民地化を終えたアメリカ帝国主義もやってきた。
こうして中国の利権をめぐって、列強がにらみ合いつつ、中国からの搾取と収奪を強めていった。
第一次世界大戦の勃発とその結末は、中国をめぐる列強の勢力図を一変させた。まずロシアが脱落した。しかし、これは観点を変えてみると脱落したのではなく、帝国主義的価値体系とは全く異なる価値体系もった国として変身したのであるが、帝国主義的価値体系をもった国としては、とにかくも脱落した。
敗戦国、ドイツが全く脱落した。大戦で国力を消耗したフランスは、中国から大きく後退し、ベトナム植民地経営に専念する姿勢に変換した。イギリスは最大の帝国主義国から、大戦後その首座をアメリカに明け渡さざるを得なかった。中国からも依然大きな影響力を保ちつつも、列強帝国主義国としては後退した。
|
|
 |
|
こうして残ったのが、「火事場泥棒」的に影響力を増した日本帝国主義と第一次世界大戦で大きく力を増したアメリカ帝国主義だった。広大で極めて魅力に富む中国の支配権をめぐって日本帝国主義とアメリカ帝国主義が睨み合う格好となった。
こうして、岸信介の認識では、中国支配権をめぐる最終戦が、日米戦争(太平洋戦争)だったのであり、帝国主義日本にとって「中国」は残された最大の「権益・利権・市場」であり、これを失うのは、帝国主義日本の自殺行為に等しい、これを守るのは「自衛行為だ」と言うことになる。
思い出して欲しいのが、日米開戦のひとつのきっかけとなった「ハル・ノート」のことだ。簡単にいって「ハル・ノート」で言っていることは一つである。「日本は中国大陸からその軍事力を撤退せよ。」ということだ。それをしなければ、主要な経済関係をすべて断絶する、と言うことでもある。
これまで見てきたとおり、帝国主義にとって軍事力はセットである。軍事的暴力を背景にしなければ、帝国主義的経済利権は守れないし、拡張できない。軍事力の撤退は、帝国主義日本が中国から全面撤退することを意味する。
だから岸信介にとって、日米戦争(太平洋戦争)は「自衛の戦争」だったのである。ただここでも岸は「意図的勘違い」をしている。「自衛の戦争」はその通りだとしても、それは「日本の市民一般」にとっての「自衛の戦争」だったのではなく、「日本の帝国主義」にとっての「自衛の戦争」だったのである。
岸が「あの戦争は侵略戦争ではなく、自衛の戦争だった。」と主張する時、彼が完全に帝国主義者の論理を使って、帝国主義者の立場に立って主張していることを理解しておかねば、その論理は首尾一貫しない。 |
|
 |
|
太平洋戦争が、基本的には中国の覇権をめぐる「帝国主義間戦争」だったという岸の認識は、その通り正しいとしても、岸の認識からは「中国との戦争」は何だったのか、と言う視点はすっぽり抜け落ちている。
視点を「中国近現代史」に立場に戻してみよう。
アヘン戦争以来の中国の歴史は、一言で云えば、列強からの理不尽な侵略(帝国主義の侵略は例外なく理不尽である。)を受け続け、これと戦う歴史だった。(私が驚嘆するのは、中国人民がこの列強からの侵略に長い期間素手で戦ったことだった。)
その長い歴史の最終局面で登場した帝国主義が日本帝国主義だった。この時アメリカは自らのための帝国主義の利益と資本主義内民主主義(それをブルジュア民主主義といっても差し支えないだろう。)の2つの異なる立場から、中国を支援した。太平洋戦争には「ファシズムと民主主義の戦い」という側面もあったことは紛れもない事実だった。
結局、中国と人民が戦った相手は、日本の帝国主義だったのである。しかもそれは凶暴化したファシズム帝国主義だった。
この戦争は「帝国主義間戦争」ではない。中国人民の側から見れば、「反帝国主義戦争」であり、「民族独立戦争」だった。中国人民から言えば、戦争は「日本の帝国主義・軍国主義・天皇制ファシズム」との戦いであり、そして、これに勝利したのである。「自衛の戦争」というならこれほどの「自衛の戦争」もない。
ところが岸の中では、「中国人民と戦ってこれに敗れた。」という認識はない。
もし「日米決戦」(太平洋戦争)に、日本(といっても帝国主義日本であるが。)に負けなければ、中国から撤退する必要はなかったと考えていることだろう。
それは岸が一貫して、帝国主義者の論理を使って、帝国主義者の立場で歴史を見、世界を見ているからだ。帝国主義者の論理以外は入り込む隙間がない。
しかし、もし岸の認識がこの通りなら、岸はまったく歴史認識を誤っていると云わざるを得ない。「帝国主義日本」は「帝国主義アメリカ」に敗れたが、中国人民にも敗れたのである。繰り返すが岸がこの認識に達し得ないのは、彼が帝国主義者の論理しか持たず、正面の敵「中国人民」が見えておらず、従って彼らを帝国主義に楯突く「暴徒」、共産主義に煽動されている「暴民」としか見なかったからだ。
田母神の主張は、この岸の論理を幼稚にたどたどしくなぞっているに過ぎない。 |
|
 |
|
私が「田母神論文」でもっとも問題と感じたのはこの点である。話は、田母神でもなく、岸でもなく、自衛隊でもなく、文民統制問題でもなく、右翼政治家でもなく、右翼文化人でもなく、右翼マスコミ・ジャーナリズムでもない。他ならぬわれわれ一般市民の「歴史認識」の問題だ。
真性帝国主義者である岸信介やその三下奴である田母神が、帝国主義者の論理を使ってその歴史観を打ち立て、その立場から世の中を見ているのは、ある意味当然だろう。(ただ、岸が戦後自分が『真性帝国主義者』である本質を隠し、『民主主義者』であるかのように振る舞うのはフェアではない。)
われわれ日本の一般市民が、なぜ「帝国主義者」の論理と立場で歴史を眺めなければならないのか?
もしわれわれ日本の一般市民が、「真性民主主義者」であるなら、民主主義の論理と立場で歴史を眺め、その立場から現在の政治状況に判断を下していかねばならない。21世紀に生きる、われわれ「日本の市民」には、その一人一人にその責任がある。
「田母神論文」が提起した問題は、従って「歴史認識」の、それもわれわれ主権者たる日本の一般市民の「歴史認識」の問題なのだ。 |
|
| (以下次回) |
 |
 |