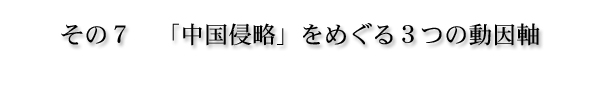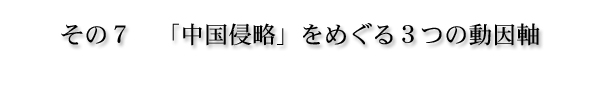|
 |
| No.23-7 |
平成21年1月10日 |
 |
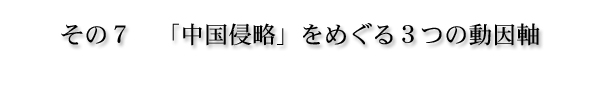 |
 |
|
前回見たように岸信介は自分なりに帝国主義者の論理をたて、あの戦争を「侵略戦争ではなく自衛の戦争だった。」と言っているわけだが、田母神にいたっては、その度胸も、帝国主義者としての確信も信念も、自分なりの論理を構築する脳ミソもない。
こういう人物が、すぐ飛びつくのは「・・・と言われているが実はそうではない。」という言い方である。説得力はないが、イメージだけを残す効果はある。余り考える力のない人たちには、それなりに有効ではあるが、社会全体を力強いイデオロギーでぐいぐい牽引していく力には、当然ながら成り得ない。
次の文章など典型であろう。
| 『 |
1928年の張作霖列車爆破事件も関東軍の仕業であると長い間言われてきたが、近年ではソ連情報機関の資料が発掘され、すくなくとも日本軍がやったとは断定できなくなった。「マオ(誰も知らなかった毛沢東)(ユアン・チアン、講談社)」、「黄文雄の大東亜肯定論(黄文雄、ワック出版)」および「日本よ、「歴史力」を磨け(櫻井よしこ編、文藝春秋)」などによると、最近ではコミンテルンの仕業という説が極めて有力になってきている。』(文中カッコの使い方はママ) |
新説を提出するのは構わない。しかしルールがある。新説には必ずそれに対応する通説がある。新説は通説を論破することが必要である。論破するだけなく、そこに説得力のある新たな解釈を加えるから新説に値するのである。通説を迂回する新説は、実は新説ではなく珍説であり、異説ですらない。
田母神は自分の論理とそれに基づく歴史観を示すことができない。だからこうした珍説に飛びつくわけだが、張作霖列車爆破事件が「ソ連の情報機関」の仕業だとして、これまでの歴史解釈にどのような影響があるのか?これが「日本が侵略国家でなかった。」ことをどう立証しているのか、田母神はなにも示していない。 |
|
 |
|
「張作霖列車爆破事件」とは一体どんな事件だったのかを振り返ってみよう。
「張作霖爆殺事件」については、その直接の実行者河本大作(当時大佐)の手記「私が張作霖を殺した」が昭和29年(1954年)12月号の文藝春秋に掲載されている。しかし、これは河本大作が直接書いたものではない。私が直接使ったテキストは、1988年(昭和63年)4月5日第8刷、『「文藝春秋」にみる昭和史』第一巻で、同書の宣伝惹句には『「文藝春秋」誌上を飾った時代の一級証言から精選・再編集』とあり、河本大作の手記も「河本大作」の筆者名で書かれているばかりでなく、簡単な著者紹介すら付いている。にも関わらずこれは河本が直接書いたものではない。
河本大作(http://ja.wikipedia.org/wiki/河本大作)は、1928年(昭和3年)張作霖を爆殺した後、軍法会議にはかけられず、翌1929年(昭和4年)に予備役に編入されている。その後1932年(昭和7年)満州鉄道の理事、1934年(昭和9年)には満州炭坑の理事長に就任している。今考えてみれば、「張作霖爆殺事件」の首謀者として、その責任を一身に背負った論功行賞と見ることができる。
| ( |
同様に田母神俊雄に今後どのようなポストが用意されているかは十分に注目しておく必要がある。) |
1942年(昭和17年)には、満州鉄道同様の国策会社山西産業の社長に就任している。山西産業は太原市(山西省の省都)に今でもある山西針績廠の前身のようである。日本軍が創立した紡績工場ではなく、軍閥(閻錫山)が撤収するとき日本軍が接収し、国策会社としたようだ。次のサイトにすぐれた記述がある。(http://shanxi.nekoyamada.com/archives/000116.html)日本の敗戦後、この山西産業は、中華民国政府(蒋介石政権)に接収されたが、河本は最高顧問として新会社に残る。その後国共内戦で、国民党軍(直接には閻錫山軍)側について共産党軍と戦ったが、1949年、共産党軍は太原を制圧。河本は戦犯として太原収容所に収監された。1955年(昭和30年)この収容所で病死した。享年72才。
従って文藝春秋の手記が出たときは、国共内戦に決着がつき、河本大作は太原収容所に収監されたばかりのころだと思う。中華人民共和国成立が宣言されるのは1949年(昭和29年)10月1日である。 |
|
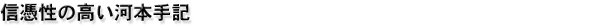 |
|
それではこの手記には信憑性がないのかと言うとそうでもない。河本大作の義弟平野零児が河本から聞き取りをしてまとめたものだという。(http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/koumotodaisaku.html )
それでは、文藝春秋には平野が持ち込んだのかというとこれまたそうでもないらしい。平野は「河本手記」が文藝春秋に掲載されていることを知ったのは、日本に帰国した後のことだという。実際には平野が河本の家族に送っていた写しを、平野の友人が文藝春秋に提供したもののようだ。井星英によれば、この友人というのは阿部真之助であり、この事実を井星英は、1980年(昭和55年)11月15日、電話で文藝春秋の小林米紀に電話で確認をとっているという。実際この手記の内容は、別途に森克己が直接河本から聞いた話と大筋一致しており、信憑性は高いものだと考えざるを得ないし(http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/koumotodaisaku2.html )、なにより、河本の話は現在残されている記録文書と一致している。ここでの問題は文藝春秋社の不誠実な態度だ。河本大作が自分で書いたことにすれば、インパクトもあり雑誌の売れ行きも良くなるのであろうが、事実に反する。何よりの罪作りは、折角の河本の話をその信憑性から疑わせてしまったことだ。この雑誌の創立当初からの方針であり、商売上手といえばそれまでのことだが、ジャーナリズムとしては限度があろう。限度を越えれば、イエロー・ジャーナリズムと言われても仕方がない。(もし文藝春秋がジャーナリズムとするならの話だが。)
ざっと日本語Wikipedia(http://ja.wikipedia.org/wiki/満州某重大事件)からこの事件のあらましを見ておこう。
| 『 |
1928年(昭和3年)6月4日、蒋介石の率いる北伐軍との決戦を断念して満洲へ引き上げる途上にいた張作霖の乗る特別列車が、奉天(瀋陽)近郊、皇姑屯(こうことん)の京奉線(けいほうせん)と満鉄線の立体交差地点を通過中、上方を通る満鉄線の橋脚に仕掛けられていた黄色火薬が爆発した。張作霖は胸部に重傷を負い、数時間後奉天市内の病院で死亡。また警備、側近ら17名が死亡した。
関東軍司令部では、国民党の犯行に見せ掛けて張作霖を暗殺し、それを口実に関東軍が満洲全土を軍事占領しようという謀略を、河本大作大佐が中心になり計画。河本からの指示に基づき、6月4日早朝、爆薬の準備は、朝鮮軍から関東軍に派遣されていた桐原貞寿工兵中尉の指揮する工兵隊が行った。実際の爆破の指揮は、現場付近の鉄道警備を担当する独立守備隊の東宮鉄男大尉がとった。2人は張作霖が乗っていると思われる列車の前から8両目付近を狙って、付近の小屋から爆薬に点火した。
河本らは、予め用意しておいた中国人労働者を殺害し、現場近くにその中国人2人の遺体を放置して、「犯行は蒋介石軍の便衣隊(ゲリラ)によるものである」と発表。この事件が国民党の工作隊によるものであるとの偽装工作を行っていた。 』 |
今ここでの関心事とテーマはこの事件を微に入り細を穿つことではない。
河本大作の手記の内容をたどることによって、当時の日本の帝国主義がいかに中国をめぐる状況を理解できていなかったことを確認し、あわせて中国近現代史を日本の帝国主義の立場から眺めてみようと言うところにある。
| ( |
以下『』は、すべて前掲「『文藝春秋』に見る昭和史」第1巻 P44からP52からの引用である。) |
|
|
 |
|
河本は、もともと中国とのつきあいは長い。日露戦争に従軍し、戦争が終了した後も、満州守備隊を志願して満州に滞在した。1914(大正3年)、第一次世界大戦勃発の年に、陸軍大学校を卒業すると、駐支那派遣隊司令部付きとして漢口に駐在、陸軍参謀本部支那課、1921年(大正10年)には駐北京日本大使館付き武官となって1923年(大正12年)まで北京に止まった。その後、陸軍参謀本部付きとなって帰国している。
この河本の経歴と日本の中国侵略史は、日本の帝国主義が、日露戦争で橋頭堡を作り、第一次世界大戦で「火事場泥棒的」に帝国主義列強の中で中国に対する利権・権益を獲得していった時代とほぼ重ねあっていることがわかる。
「21ヶ条の要求」を突きつけ、1919年には「5・4運動」が起こって、中国人民の反帝国主義運動の矛先が、ロシアやイギリスから日本へと向かった。河本が北京に駐在した1921年から23年は、ちょうど日本の帝国主義が、「東三省」(すなわち満州)に傀儡政権をたてて、中国本部(中国本土という意味であるが、いつこういう言い方がでてきたのか私は知らない)からの満州の切り離しを行うことによって、日露戦争以来獲得してきた権益を確保しようとした時であり、この傀儡政権には、奉天軍閥の張作霖を想定していたころである。
一方列強はワシントン会議(ワシントン体制)で、満州においては日本の特殊権益は認めるが、中国本部は「機会均等」、いわば「斬り取り勝手」という体制を築いた。日本の帝国主義もこの体制を認めざるを得なかった。
中国人民は労働者階級を中心にして全土で激しい階級闘争を展開し始めた。この時期最も重要なことは、一般民衆レベルで「反帝国主義闘争による民族独立」「反封建闘争による近代民主主義の確立」がもっとも重要な政治課題であることをはっきり認識し始めた、と言う点である。
河本が中国からいったん引き揚げ、日本で参謀本部勤めをしていた時期はちょうどこうした動きが具体的な政治的「かたち」を形成し始め、その標的が日本の帝国主義に合わされていった時期に当たる。
1926年(大正15年)3月、河本は関東軍高級参謀として再び中国に赴任する。 |
|
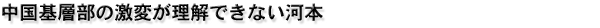 |
|
河本が中国を不在にしていた間に、反帝国主義・反封建主義闘争は一つの展開期を迎えている。すなわち孫文国民党を中軸とした第一次国共合作の成立であり、反封建主義闘争としての「北伐」の開始である。
| 『 |
そこで、久しぶりに満州に来てみるといまさらのごとく一驚した。
張作霖が威を張ると同時に、一方日支21ヶ条問題(*21ヶ条の要求のこと)をめぐって排日は到る処に行われ、全満に蔓(はびこ)っている。日本人の居住、商租権などの既得権すら有名無実に等しい。
(*商租権とは借地権のこと。)
在満邦人20万人の生命、財産は危殆に瀕している。満鉄に対しては幾多の競争線を計画してこれを圧迫せんとする。日清、日露の役で将兵の血で購われた満州が、いまや奉天軍閥の許に一切を蹂躙されんとしているのであった。』 |
河本は悲憤慷慨するが、まずこの時期の反帝国主義闘争は、別に対日21ヶ条の要求を基本としているわけではない。すでに「5・4運動」「5・30運動」を通じて、「反帝国主義運動」は大きく成長していた。特に「5・30運動」ではすでに労働者階級が運動の主体になっており、中国でも労働者階級が反帝国主義運動の中核を担うようになっていたことはすでに本シリーズで見てきたとおりだ。もし河本が中国の基層部における激変をしっかり把握していれば、「一驚する」こともなかったはずだ。河本は誰を相手に中国で戦いを展開しようとしているのかをまったく見ていないと言うべきであろう。
「満鉄の競争線」と言っているのは、張作霖軍閥が欧米資本の支援を受けて、南満州鉄道に並行する鉄道を敷設し、南満州鉄道と競合していたことを指す。特にもうすでに世界的な不況がはじまっており、貨物輸送などがこの競合線に奪われ、南満州鉄道は大打撃を受けていた。
張作霖は、第一次世界大戦が始まるころには、軍長クラスの軍閥だった。ご記憶であろうか、大隈内閣の後を受けた寺内正毅内閣の基本政策は、北京の段祺祥政権に経済援助を与え、西原借款に代表されるように、強圧的な軍事力のかわりに、金で中国の利権を買うといった体のソフトな「侵略政策」に軌道修正していた。この段政権支援政策は、結局満州の一小軍閥だった張作霖を中央政界の大立て者の一人に成長させることになる。
だから、河本の印象では、張作霖などは顎で使える軍閥というイメージだったが、関東軍の高級参謀で満州に戻って来たときには張作霖は押しも押されもせぬ大立て者に変身していたのである。
従って河本の認識では、張作霖を使って満州を事実上日本の支配下に置こうとしたのに、その張作霖は日本の言うことを聞かない存在になってしまった、という理解があるはずだ。
しかし実際には、中国全体には大きな、「反帝国主義運動」という政治的地殻変動が起こっており、張作霖といえどもその地殻変動の中で、生き残りを図ろうとしている軍閥にすぎないという認識は全く見られない。これは、関東軍全体の、従って日本軍部全体の、従って日本の支配者層全体の共通認識だったはずである。 |
|
 |
|
こうして河本は、「満州における邦人の地位が下落したこと」や、「東寧(*今の黒龍江省牡丹江市)では邦人が満人から鞭打たれるのを目撃し」、「チチハルでは日本人の娘子群が満人から極端に侮辱されているのを視る」ことでなど、日本の満州支配に危機感を募らせる。つまりかつて河本が知っている満州とはわずかの間に様変わりしていたわけだ。
| 『 |
・・・しかもこの圧迫は独りそうした暴虐に留まらない。経済的にも、満鉄線に対する包囲態勢、関税問題、英米資本の導入など、ことごとくが日本の経済施設、大陸資源開発に対しての邪魔立てである。撫順で出炭する石炭に対しては不買を強いている。これでは、日本の大陸経営はいっさい骨抜きとされている。
郭松齢事件で、もしも日本からの、弾薬補給から、作戦的指導に到るまで、少なからぬ援助がなかったら、奉天軍(*張作霖軍)の今日の武威はなかったのである。いわば大恩返しとして、商租権のごときは奉天軍が進んで提供した権益である。』 |
郭松齢事件というのは張作霖の、有力軍長だった郭松齢(かくしょうれい)が張作霖に対して反乱を企てた事件である。第二次奉直戦争に勝利した張作霖は北京に進出して、北京政府の実権を掌握しようとする。張作霖の背後に日本軍と日本の帝国主義の後ろ盾があることに不信感を抱いていた郭松齢は、軍閥内部の勢力争いもあって、1925年(大正14年)11月、突然張作霖に叛旗を翻す。全く準備のなかった張作霖軍はなすすべを知らず、山海関、錦州(遼寧省の主要都市)が攻略され、張作霖は一時下野も考えたほどの劣勢だった。
関東軍はすでに張作霖擁立を決定していたころで、南満州鉄道附属地20里以内の軍事侵攻を許さないなどの援助をし、その間に張作霖軍は態勢を立て直し、反撃に出て郭松齢軍を殲滅した事件である。
1925年11月といえば、河本が関東軍に赴任する3−4ヶ月前の事件であるが、弾薬補給や作戦指導までしていたとは知らなかった。南では第一次国共合作がすでに成立しており、孫文なきあとの汪精衛国民政府が成立していた。
上記の河本の文章は、そこまでして面倒を見てやっているのに、最近の日本に対する仕打ちは何事であるか、と言う文章である。
河本の文章から感じられることは、一言で云えば「独善」である。「帝国主義的侵略」をしているのだから競争相手もあるだろう、張作霖は張作霖なりの立場や都合があるだろう、第一自分たちが支配しようとしている満州や中国人民の立場や生活、思いもあるだろう。これらを分析研究し、相互の力関係を冷静に計量し、しかる後に政策化し実行するのが、優秀な「帝国主義者」というものだろう。ところが河本はすべて自分の都合で情勢を分析し、自分の立場や視点からのみものごとを見ている。何故日本に対する反感がこれほど高まっているのか、中国人民の間に本質的にどんな変化が起きているのかといった、視点を変えてものごとを見る科学的思考の訓練の基礎が全くできていない。要するに独善主義である。
話は先走るようであるが、この「独善主義」なにも河本ひとりに限ったことではない。戦前軍部全体を覆う基本的性格であった。「独善主義」は必然的に「ご都合主義」を誘発する。そして科学的思考を離れるから「精神主義」に陥らざるを得ない。こうして1945年の敗戦までこの「独善主義」は日本全体を覆っていくことになるのである。
|
|
 |
|
| 『 |
翌けて(*ママ)昭和2年(*1927年)2月7日であった。
田中義一は総理大臣兼外務大臣として台閣にあったが、自ら主張して、いわゆる「東方会議」を開かんことを提唱した。外務政務次官に森恪がいた。
当時関東軍司令官は、白川大将去って、武藤信義中将が、大正15年(*1924)年7月に代わって赴任していた。
武藤中将は、露西亜通で、かつて参謀本部第二部長も勤めて支那にも明るかった。・・・・・
やがて東方会議が開かれることになった。武藤将軍もそれに出席されることになり、自分もそれに随従して上京することになった。
会議では、当然満州における対策が討議されねばならなかったが、満鉄線に対する奉天軍閥がとった、包囲態勢に関しては、もはや外交的な抗議等では及ばないことを自分は力説し、武藤将軍は、この会議に置いて武力解決を強調された。田中首相もこれを諒とし、武力解決を是とすることに大体の方針が決せられた。
そこで、自分は具体案として左の情勢を利することを献策した。そのころ、支那南方に起こった蒋介石が、孫逸仙(*孫文)と共に北伐を開始し、奉天派はこれに対して、その先端は、浙江方面上海にまですすみ、張学良と楊宇霆(よううてい)を首将としてあたらしめていた。
蒋介石のかねて軍官学校で養った新鋭の兵は、奉天旧軍閥の兵とは、雲泥の相違で、軍紀等でもまるで違っている。ことに揚子江以南には元来、南方派の勢力が根強く張っている。張作霖は勢いに乗じて上海までも手を伸ばしているが、やがて蒋介石らの北伐が開始されれば、たちまちにして奉天軍はまたまた奥の手の関内へ逃げ込みの一手をもちうる二相違ない。・・・・張作霖が敗退して関内に帰ればまたまた安泰である。
北京にでて大元帥を誇号(*ママ)している張作霖は、三十万の大兵を擁して今は関外にある。この三十万の兵がゾロゾロ敗れて関内に流れ込んだら、またまたどんな乱暴をやるか分からない。といってこれを助けたところで一生恩にきるような節義はない。それは郭松齢事件で試験済みである。
その次に南北相戦って、東支や山東の地を戦禍の中に曝すのもまた幾多の権益を持つ日本をはじめ列国にとっても、また無辜の支那民衆のためにも看過すべからざることである。北伐も北支では阻止しなければならない。
同時に敗退した場合の張作霖の兵三十万は、よろしく山海関でことごとく武装解除してのみ入れるべきである。そして武力のない、秩序、軍紀のない、自制のない、暴虐な手兵をもたぬ張作霖を対手に、失われつつある一切の、我が幾千件にわたる権益問題を一気に解決すべきである。
右の方策は会議の容れるところとなり、ことに森恪は、この献策に非常な共鳴をした。そしてこれは東方会議の議決となった。』 |
幣原外交に替わって登場した田中義一内閣(1927年=昭和2年4月から1929年=昭和4年7月まで)で行われた「東方会議」(1927年6月27日から7月7日)に関する記述である。日本語Wikiepdia、「東方会議(1927年)」の項<http://ja.wikipedia.org/wiki/東方会議_(1927年)>を読んでもまるきり何のことか分からないが、この河本の記述を読むと、東方会議のポイントがよく分かる。
要は満州問題の最終解決、すなわち軍事的解決の方策策定にあったのだ。
|
|
 |
|
ここで蒋介石の立場に場面転換して、状況を眺めてみよう。
前回見たように蒋介石は1927年、4・12クーデター(上海クーデター)を起こして、国民党内の共産党員を一掃すると共に、戦闘的な労働者階級を弾圧、虐殺して反共の旗印を鮮明にする。コミンテルンの誤った、ある意味スターリンの手前勝手な指示に翻弄された中国共産党も、いったんもたついた後、国民党と絶縁して、ここに第一次国共合作は名実ともに崩壊する。
1927年(昭和2年)7月のことである。つまり「東方会議」はこの第一次国共合作崩壊劇のまっただ中で開かれたことになる。
この時点で蒋介石の南京政府は、表面から見れば、河本が言っているように「支那南方に起こった蒋介石」であり、一地方軍閥に過ぎないと見える。しかし蒋介石の南京政府は、他の軍閥とは決定的な違いがあった。それは孫文革命の政治的正統性をしっかり受け継いでいたと言うことだ。別な表現でいえば、蒋介石の背後には民族独立を願う中国人民の「ナショナリズム」が厳然と存在していたということだ。
この後は何度も引用している「中国近現代史」(前掲、岩波新書)から、小島晋治と丸山松幸共同執筆の文章を引用しよう。
| 《 |
しかし蒋介石を支えたもう一つの要素は、国民革命以来「独立と統一」を求めてきた巨大なナショナリズムの潮流であった。国民革命の指導者として、蒋介石は他の軍閥や政客が得ることのできない大きな資産を受け継ぐことができたのである。彼の「統一」政権はあの強大な民衆の革命運動がなければ不可能だった。この資産を背景にして蒋介石は「近代国家」の樹立に進み始めた。
本来近代ナショナリズムには「被抑圧人民の解放」(*人民民主主義革命)と「近代国家の創出」という2つの側面がないまぜになっている。この2つは対立するものではないが、また直接むすびつくものでもない。蒋介石はむしろ「人民の解放」を切り捨てることによって「近代国家」を実現しようとしたのである。それは明治日本が歩んだ道であった。》 |
「人民の解放」(*人民民主主義革命)の側面を切り捨てる具体的政策が「反共主義」ということであった。
「近代国家の創出」の側面では、関税自主権の回収、領事裁判権の廃止を含む不平等条約の撤廃努力であり、度量衡の統一、学校教育制度の整備などがあげられる。このうち関税自主権の回収については、イギリス・アメリカに対しては1928年(昭和3年)に回収に成功し、日本については1930年(昭和5年)に成功している。ただし肝心の関税収入は、対外借款の償還の担保として押さえられていたままだった。西原借款も当然この中に含まれている。形式的には、自主権を回復したかのように見えるが、実質上は首根っこを押さえられたままだった。
蒋介石はこの後1928年1月から第二次北伐を開始して、北京政府を牛耳る軍閥割拠の状態を解消し、国民党の統一政権を樹立しようとするわけだが、これは「東方会議」の半年後のこととなる。
河本はさすがに、この状態をよく見通しており、張作霖軍閥はまけるだろうと予測している。 |
|
 |
|
日本の帝国主義にとっての問題は、もし張作霖が負ければ、蒋介石軍が満州にやってくる、満州が戦場になるだろう、これを防ぐには日本軍が介入せざるを得ないということだが、それまでのいきさつから考えれば、外交交渉によって満州の権益を守るという迂遠な方法よりも、中国本土から満州を切り離して独立させ、政治的に満州を独立させればよい、ということになる。このための軍事行動をためらわずに進めて行こう、これが「東方会議」の結論だった、と言うことになる。
果たして再び北伐(第二次北伐)が開始され、予想通り張作霖軍はひとたまりもなく、敗れ去り、満州に逃げ帰ろうとする。
続けて河本はこう書いている。
| 『 |
・・・初め蒋介石は、山東、北支の戦禍に巻き込まれるのを避けよと言う提案を容れていたにかかわらず、勝ちに酔って、ついに斉南城内を通過せず、ここに入城して約を違えたので、昭和3年(*1928年)の斉南事変が勃発し、我が出兵となった。一方奉天軍(*張作霖軍)は、予想通り敗走して、山海関へ雪崩を打って殺到した。』 |
張作霖軍の敗走は河本の予想通りとして、「約を違えて」「斉南事変が勃発」
とはどういうことか? |
|
 |
|
話をまた蒋介石に戻す。前述の通り蒋介石は28年(昭和3年)1月、再び北伐を開始する。これがいわゆる第二次北伐である。孫文北上宣言から開始された第一次北伐とこの第二次北伐は、名前は同じでも内容は似て非なるものだった。
第一次北伐は、中国民族統一戦線の「反帝国主義運動」、その一環としての「軍閥打倒」の中国革命運動として意義づけることができる。しかし第一次国共合作崩壊後の第二次北伐は、精々意義付けを行ったとしても「中国近代化」「資本主義内民主主義実現のための国内統一運動」としか評価できない。しかもその後の蒋介石国民党の「ファシズム化」の実情を見てみると、上記評価すら怪しくなってくる。
実際、この時の北伐軍は四軍編成だったが、第一軍総司令蒋介石は納得できるとしても、第二軍総司令・馮玉祥(もと直隷派軍閥)、第三軍総司令・閻錫山(山西軍閥)、第四軍総司令・李宗仁(広西軍閥)となると、まるで軍閥総出演である。この北伐軍が奉天派の張作霖と戦うのだから、これは軍閥の内戦と言った方が近い。
実際のところ、奉天軍には戦意はなく、河本の予想したとおりの展開になった。半年後の28年(昭和3年)6月3日、張作霖は北京を脱出、6月8日北伐軍はほとんど戦わず北京に入城した。
こうして蒋介石国民党は、中国を統一、首都を南京に置いた。この時点で袁世凱以来の「北洋軍閥」は名実ともに消滅したのである。この時「北京」は改称され「北平」と改まった。「北平」という呼び方は、1949年10月1日、中華人民共和国が成立し、首都を「北京」に置くまで約20年間続くのである。
|
|
 |
|
河本の言う「斉南事変」はこの第二次北伐の過程で発生している。
北伐軍が山東省に入ると、田中義一内閣は「居留民保護」を名目に山東出兵を決定、28年(昭和3年)4月20日、第六師団を山東省の省都、斉南に向かわせた。この山東出兵は「居留民保護」とはいうものの、明らかに「北伐」に対して軍事干渉を狙ったものだった。
| ( |
なお、この時の山東出兵は『第二次山東出兵』と呼ばれている。『第一次山東出兵』はその1年前、27年<昭和2年>5−7月、同じく田中義一内閣の時に行われている。今振り返ってみても、田中義一内閣の山東出兵は、なんら法的根拠がない。関東軍は南満州鉄道守備兵として駐屯しているわけだし、駐支派遣軍は北京付近、精々天津までが派遣可能な範囲である。山東省は満州でもなければ、北京近郊でもない。そして当時だれもこの山東出兵の法的根拠を日本国内で問題にした形跡がないのだ。田中義一内閣も後のアリバイづくりとして、北京政府=張作霖政権と名目的な条約とか約款を締結した痕跡もない。それとも大隈内閣の時の「21ヶ条の要求」時に法的根拠が求められるのであろうか?それとも私が知らないだけだろうか?
もうこの時田中義一内閣は、歴史的アリバイ作りですら忘れてしまっているかのようだ。あたかも華北以北は自分の庭ぐらいにしか思っていない。帝国主義日本の中国侵略は、意識の上でもこの時そこまで進んでいたと見なければならない。この時までには、日本の支配階級ばかりでなく、知識階級、一般民衆まで、自国軍隊を華北で自由に展開している様を怪しまない、骨の髄までの『侵略国家』になっていたようだ。
ただわれわれ日本人の名誉のために付け加えておけば、当時日本の労働農民党だけが「対支非干渉全国同盟」を結成し、山東出兵に強く抗議し、反対していた。しかし、この運動も田中義一内閣によって叩き潰された。
この事件から、80年以上経た今、われわれ日本市民は、「田中義一内閣」の精神を引き継ぐのか、あるいはこの「労働農民党」の精神を引き継ぐのか、一体どちらなのか、これが今われわれに突きつけられている問題だ。) |
斉南事変は、この時出兵した日本軍と斉南に入城した北伐軍が大規模な市街戦を展開し、北伐軍2000人、日本軍230人日本人居留民16人の死者を出した事件である。
確かに河本の言うとおり、日本側と蒋介石側には直接戦闘をしないという約束があったようだ。それが何かのきっかけで大規模な戦闘に発展したようだ。日本語Wikiepdiaを見ても(http://ja.wikipedia.org/wiki/済南事件)、未だに事件の発端ははっきりしていない。
しかし大局的に見れば、戦闘に発展するかも知れない地域に軍隊を送れば、起こりうることだし、本当に日本人居留民保護を言うのなら、そんな危ない地域からは避難しておくべきだろう。
ただいきさつからすれば、先に日本軍が斉南に入城していたのであり、北伐軍はその後からやってきた。河本は「昭和3年(*1928年)の斉南事変が勃発し、我が出兵となった。」としているが、これは順序が逆であろう。記憶違いか意図的な書き損じである。 |
|
 |
|
田中義一内閣は、戦争が満州に及ぶのを恐れた。というよりもこの事件を機に、本格的に満州の中国本部切り離し=満州の独立を企てていたというべきであろうか。
斉南事変の直後、1928年(昭和3年)5月18日、日本政府は、
| < |
戦乱京津(*北京と天津のこと)地方に進展し、その禍乱満州に及ばんとする場合は、帝国政府としては満州治安維持のため、適当にして有効なる措置をとらざるを得ざることあるべし。> |
とする声明を発し、北伐軍・北京政府軍に通告したのである。これは内戦に軍事介入しますよ、ということを内外に宣言したのに等しい。
また事実上中国東三省(満州)の治安維持は、日本が担当すると言うに等しい。これも首をひねりたくなるような声明だ。法的には満州は中国の主権下にある。日本は満州には権益を持つものの、日本にとっては、満州は主権の及ばない地のはずであるが、この時すでに日本の帝国主義は、満州を自国の支配下に置いていることを隠そうともしなかった。
古屋哲夫は、この時の政治的状況について極めて鋭い見解を「日中戦争」という本(岩波新書。テキストに使ったのは1985年6月5日第2刷。)の中で述べている。
| ( |
この古屋の見解が専門歴史学者の中では定説になっているのかどうか、私は知らない。が、とにかく鋭い見解である。) |
ともかくも引用してみよう。(引用は<>である。) |
|
 |
|
| < |
(*山東出兵に関して)・・・それは当時「現地保護」(日本人が居住している現地まで日本軍を送り込んで保護する)と呼ばれたやり方であり、それまでの幣原外交とちがう田中外交(*田中は外務大臣を兼任)の特色を示すものとうけとられた。つまり、直接には幣原喜重郎が外相だったら、軍隊を現地へ送るより、在留日本人の方を安全な場所まで引き揚げさせたに違いないと考えられたのである。しかし両者の違いは、単に居留民保護の方法と言うだけの問題ではなく、国民革命(*古屋は蒋介石の中国統一・独立運動という意味でこの国民革命と言う言葉を使っている。必ずしも中国国内の人民民主主義革命を意味しない。)全体にどう対応するのかという問題にまで及ぶものであった。
すなわち幣原外交の場合には、国民革命によって中国が統一されることは、動かし難い勢いであるとみて、むしろその統一の勢いを支持しながら、その性格を日本にとって(*ここの日本は、帝国主義日本という意味である。)望ましい方向に導くことを主眼として政策が進められていた。具体的には、蒋介石の反共政策を支持して国共を分裂させ、国民革命を反共派が主導するものとすれば、そこでは日本の満蒙権益を認めさせることも可能になる、というのが幣原の構想であったように思われるのである。
・・・しかし田中外交の場合には、その反共派が主導権を握ったにしても国民革命軍という軍隊によって、満蒙が外から占領されることを拒否する、と言う点に政策の最重点を置くものであった。組閣直後のすばやい山東出兵(*第一次)は、このような軍事的発想を物語るものといえよう。
・・・この出兵(*第一次)の間に、田中内閣は、朝鮮・中国駐在の外交官・軍人などを招集して東方会議を開き、対中国政策についての意見を求めて、新しい構想を打ち出そうとしていた。
ここで注目されるのは、この会議を前にして、すでに関東軍司令部が「東三省(熱河特別区域=*河北省・遼寧省・内モンゴルの境界地域一帯を指す。満州帝国時代には満州帝国に含まれていた。現在は内モンゴル自治区に編入されている。=を含む)に一長官を置き自治を宣布せしむ」との方針を決定していたことである。6月1日付け(*1927年=昭和2年)のこの文書を見ると、この自治長官の下に財政・軍事顧問を置き、新しい鉄道協約を結び、土地の開墾、鉱山の採掘、牧畜および諸工業などを「日支共存共栄を趣旨」として実現していくといった構想が述べられている。それは、満蒙を国民革命(*蒋介石の中国統一)から切り離して、日本の特殊利益地域にしていくことを企てるものものであった。>(以上同書P40−P41) |
| < |
そしてさらに注目すべきことは、これらの要求を中国の中央政府に対してではなく、張作霖に対して要求し、張作霖がこれに応じないならば、張を倒し、「帝国(日本)の認むる適任者を推挙して東三省長官として本要求を遂行せしむ」としている点であろう。それは中国中央政府を無視して、満蒙に傀儡政権を立てて切り離してしまおうとするとするものであり、中国に対して戦争を仕掛けるのと同じ意味をもつものというほかはない。まさに関東軍は、侵略政策の尖兵の地位にたちあらわれてきたのであった。>(同書P42) |
上記の記述は古屋哲夫が、本来南満州鉄道の現地守備隊にすぎなかった「関東軍」が、なぜ、大陸侵略の尖兵として重きをなすに至ったかを論証する過程の記述である。
重要なことは、日本の帝国主義が、すでに満州事変以前に満州の中国本部切り離し=傀儡独立国家樹立を企図しており、張作霖が不適切なら、適切な人物を擁立することを考えていたということだ。 |
|
 |
|
また幣原外交との関連で言えば、「幣原外交」を「ソフトな侵略政策」と呼ぶならば、「田中外交」は「ハードな侵略政策」と呼ぶことができ、第一次大戦後のワシントン体制で、アメリカの帝国主義と協調して中国を侵略することをいったん容認したかに見える日本の帝国主義が、実は一枚岩ではなく「ハードな侵略政策」を採用することによって、ワシントン体制を破壊しようとした点も重要である。
すなわち、このことは次の「満州傀儡帝国」成立の重要な伏線であると同時に、中国大陸の覇権をめぐる「帝国主義間戦争」たる「太平洋戦争」の伏線ともなっていることを意味する。つまり「満州傀儡帝国成立」は決して苦し紛れに出てきたアイディアだったのではなく、大陸侵略の一方法として帝国主義日本が準備してきた一つの帰結だったのである。
「張作霖爆殺事件」はこうして準備されたといえるだろう。河本が言うように、張作霖は満州に専念しようとはしなかった。北京に出て北京政権を掌握したがった。しかしこれは張作霖の立場に立ってみれば当然のことだったろう。
張作霖は、北京の段祺瑞政権の元でその権威と勢力を大きくしたのであり、満州における権威も北京政府の「東三省巡察使」としての権威だった。彼が独自に満州に自治政権を作ったわけではない。その北京政府に空白が生まれれば、当然有力軍閥としてその空白を埋めなければならない。それに彼の軍隊30万は満州には過大であった。30万の軍隊を養うには北京中央政府を掌握する必要があった。
こうして日本政府にとって満州に専念して唯々諾々と日本の帝国主義のいいなりにならない張作霖は邪魔者になったのである。 |
|
 |
|
河本はこう書いている。
| 『 |
かかる奉天軍の排日は、もっぱら張作霖の意図に出たところで、真に民衆が日本を敵とする底(*ママ)のものではない。(*これは河本の希望的思いこみだろう。)・・・一人の張作霖が倒れれば、あとの奉天派諸将といわれるものはバラバラになる。今日までは、張作霖一個によって、満州に君臨させれば、治安が保たれると信じたのが間違いである。・・・
巨頭を斃す。これ以外に満州問題解決の鍵はないと観じた。一個の張作霖を抹殺すれば足るのである。』 |
河本が言っていることは随分飛躍があるように見えるが、先ほどの古屋哲夫が引用した1927年(昭和2年)6月1日付け文書の趣旨を下敷きにおいてみれば、「張作霖抹殺」は関東軍や河本一人の考え方ではなく、「東方会議」を直前にした田中義一内閣の基本方針だったことが分かる。
問題はいかに「張作霖」抹殺を行うかである。
河本は書いている。
| 『 |
・・・では張作霖を抹殺するには、なにも在満の我が兵力を持ってする必要はない。これを謀略によって行えば、さほど困難なことではない。
当の張作霖は、まだ北支でウロウロして、逃げ支度をしている。我が支那派遣軍の手で、これを簡単に抹殺せしむれば足るーと考えられた。
竹下参謀(*おそらく陸軍大学校第33期卒の竹下義晴―最終階級は中将―だろうと思われる。なお河本は第26期卒)が、その内命を受けて、密使として、北支へ赴くことになった。
それを察したので、自分は竹下参謀に、
| 「 |
つまらぬ事は止したが好い。万一仕損じた場合はどうする。北支方面にこうした大胆な謀略を敢行出来得ると信ずべき人が、果たしてあるかどうか、はなはだ心もとない。万一の場合、軍、国家に責任を持たしめず、一個人だけの責任ですませるようにしなければ、それこそ虎視眈々の列強が得たりといかに突っ込んでくるかわからない。俺がやろう。それより外はない。」 |
と言った。』 |
つまり河本は、軍また恐らく内閣黙認の上で、張作霖爆殺を実行したものと考えられる。河本を軍法会議にかけられなかったばかりか、あとの面倒もみたわけである。
このあとの河本の手記は、爆殺の実行の模様を描いているわけであるが、これには何の興味もない。
張作霖の後をついで奉天軍閥の総帥となった長男の張学良は、河本の見通しとは逆に奉天軍閥を良くまとめ、翌1928年(昭和3年)12月には、蒋介石国民政府に忠誠を誓い、東三省全体を蒋介石国民党政府に合流させた。こうして、蒋介石は全国統一を成し遂げたのである。
このいきさつを河本は手記の中でどう書いているか。
| 『 |
・・・しかし当時すでに学良周囲の若い要人達は、欧米に心酔して、自由主義的立場にあって、学良もまたこれらのものをブレインとして重く用いていたので学良の恐日は漸々排日に変移し、ついには侮日とまで進んでいった。
こんな次第で、梟雄張作霖が亡んで学良と変わっても、なんら満州の対日関係は好転せず、かえって反対の傾向をたどり、学良政権を再び武力によって倒壊しなければ、ついに満州問題を永遠に解決する道はないことが瞭然となった。』 |
しかし河本はこの短い同じ文章の前に、「張作霖一個を斃せば満州問題が解決できる。」といい、恐らく「東方会議」でもそう主張したことだろう。見込み違いを起こしても、自分の分析の誤りを素直に自己批判せず、常に他に責任転嫁するという旧日本陸軍の体質を河本もまた色濃く受けついでいる。 |
|
 |
|
これら一連の出来事は、私に大きな疑問を起こさせる。というのは、これまで私は、教科書的歴史書で、
| 「 |
軍部の暴走が中国との戦争を泥沼化させ、日本の政治はこれに引きずられて中国との戦争の深みに入った。アメリカを中心とする民主主義勢力がこれに牽制をかけようとして経済制裁を行い、この経済制裁で追い詰められた日本が、一か八かの賭けに踏み切り太平洋戦争が勃発した。」 |
と教えられてきた。
まったく間違いではないものの、中国との戦争は、軍部の暴走のために、突発的に発生したのではない。こうして見てくると、明治以降日本帝国主義国家の意志として進めてきた中国侵略が、第一次世界大戦、世界的経済恐慌を経て極めて暴力的な形で噴出した、それが一連の中国との戦争だったことが了解される。
河本の手記はもうこれくらいでいいだろう。
ここまでで確認できることは、「張作霖爆殺事件」は、決して河本ら一部跳ね上がり軍人の突発的事件などではなく、軍部そして恐らく田中内閣の暗黙の了解のもと実施された事件だったこと、その狙いは張作霖を抹殺することによって、満州を中国本部から切り離し、傀儡政権を満州に作り上げる点に狙いがあったこと、そしてそれは日露戦争以来の帝国主義日本の、大陸侵略のひとつの完成型であったこと、などであろう。
歴史の事実は、張作霖一個を抹殺しても、日本の帝国主義にとって満州の情勢はいかんともし難く、さらに遠回りを、さらに暴力的にならざるを得なかった。日本の帝国主義の、この見込み違いは決して偶然の産物などだったのではなく、根本的に、戦っている相手を見誤ったために起こった見込み違いなのであって、この意味では必然の見込み違いであった。
すなわち、日本の帝国主義は、反帝国主義を果敢に戦う中国人民を相手に戦っていたのであって、蒋介石やまして軍閥張作霖を相手に戦っていたのではなかった。張作霖の後継者張学良といえども、この中国人民の鉄壁の決意を無視することは出来なかった、というべきであろう。
田母神らの「ソ連情報機関謀略説」など、「珍説」はおろかたわごとである。 |
|
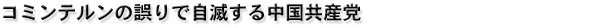 |
|
ここで再び視点を「中国近現代史」に立場に移そう。
第一次国共合作崩壊(1927年=昭和2年7月)後、混乱を極めた中国共産党はいったいどうなったのか?田中義一内閣が、居留民保護を名目として第一次山東出兵を行ったころである。
スターリン主義のコミンテルンはなおも中国共産党に対して誤った指令を出し続ける。「都市武装蜂起」の指令である。
コミンテルンは「ロシア革命型」の都市プロレタリアートが社会主義革命を達成するという方法論が、唯一絶対の社会主義革命のパターンだと思いこんでいた節がある。クリストファー・ヒルの指摘を待つまでもなく、ロシア革命は、ロシアの極めて後進的なツアーリ制度、農奴制度の中に急速に工業化した都市の中にプロレタリアートが創出され、近代的資本主義の、今日風にいえばセーフティネットが全く存在しないままに、苛酷な収奪と搾取にさらされ、生存基盤がおびやかされたために蜂起して達成された革命だった。
そのロシア方式をそのまま機械的に中国に当てはめようとしたのが、この時期のコミンテルンの指令だった。中国における課題は、「民族独立」であり、「人民民主主義革命」であり、社会主義革命ではなかった。
このコミンテルンの「都市武装蜂起」の方針に従って、1927年(昭和2年)8月1日、
賀竜(がりゅう)(http://homepage2.nifty.com/ryurinsya/1helong.htm)(http://ja.wikipedia.org/wiki/中国人民解放軍)、葉挺(ようてい)(http://ja.wikipedia.org/wiki/葉挺)らの部隊、朱徳(しゅとく)(http://ja.wikipedia.org/wiki/朱徳)の将校教育連隊約2万が南昌(広西省。http://ja.wikipedia.org/wiki/南昌市)に結集して武装蜂起した。いわゆる南昌蜂起である。
南昌蜂起は結論から言って、全く誤りであった。軍事的には、蒋介石国民党軍に較べて圧倒的に劣勢だった、というより自前の軍隊を持たなかった中国共産党軍が、頼りにすべきは労働者・農民であった。しかし労働者・農民は動かなかった。蜂起部隊はわずか3日で敗退し、南昌を放棄した。
8月7日(1927年。昭和2年)、中国共産党中央は漢口で緊急会議を開き、陳独秀らの妥協路線を厳しく批判した。
陳独秀の妥協路線というのは、国共合作維持路線のことである。国共合作を維持するため、土地没収は大中地主に限定し、小地主からの没収は禁止していたばかりでなく、労農権力(ソビエト権力)の樹立も禁止していた。これを実施すると、国内小ブルジュワジーの支持も失い、国民党の支持基盤を失い、国共合作維持をさらに困難にするからである。しかしこの政策のもとで、大多数をしめていた農民や労働者の支持をどうやって獲得せよ、というのか。
私自身は確認していないが、南昌蜂起で労働者、農民が全く動かなかった理由も容易に想像できるというものである。
国共合作を維持しつつ、都市武装蜂起などとは全くあり得ない幻想である。
しかし、この国共合作維持路線は、陳独秀ら中国共産党中央独自の方針ではない。スターリン主義に染まったコミンテルンからの指示だった。 |
|
 |
|
岩波新書「中国近現代史」はP128の註に次のように書いている。
| 『 |
労農ソビエト樹立の必要性を早くから強調していたのは、トロツキーで、スターリンは国共合作に固執してこれに反対していた。ソビエト建設の方針が出されるのは11月(*1927年)そのころにはもうほとんどその可能性は残されていなかった。しかも党中央は「革命情勢は不断に昂揚しつつある」として無謀な都市蜂起の続行を指示し、長沙攻撃を中止した毛沢東らを規律違反で処分した。』 |
つまりこの時のコミンテルンの指示は、労働者・農民を支持基盤に取り込まないまま、都市武装蜂起をせよ、というまるで自殺しろ、といわんばかりの指示だった。軍事的には圧倒的に蒋介石国民党軍が優勢であり、共産党軍が勝つ見込みは全くない。
この時期のコミンテルンの指示がどうしてこんな矛盾に満ちたものであったか、私にはまるでわからない。「スターリン主義の誤り」といって片付けるには、しかし、中国共産党にとってあまりにも犠牲が大きかったのである。
8月7日(1927年)の共産党中央の緊急会議では、陳独秀らの方針を批判しながら、労農武装を進め、秋の収穫期に湖北、湖南、江西、広東の四省で武装蜂起する方針を決定すると共に、総書記に瞿秋白(くしゅうはく)(http://homepage2.nifty.com/ryurinsya/1quqiubai.htm)の指導部を選出したが、矛盾したコミンテルンの指示のもとの方針が成功するはずもなく、ことごとく失敗した。
ただ南昌蜂起で結集した蜂起軍は、三軍に編成され、これが中国共産党がはじめて持った自前の軍隊となった。それまでは国民政府の国民革命軍の軍隊として編成されていたのである。
南昌蜂起の1927年8月1日は、従って現在、人民解放軍の建軍記念日となっている。 |
|
 |
|
この誤った方針のために、最大の打撃を被ったのは、27年12月の「広州コミューン」事件だろう。
インターネットで「広州コミューン」を検索すると、次のサイトが見つかる。
(http://www.tabiken.com/history/doc/G/G094L100.HTM)短いので全文引用すると、
| 『 |
広東コミューンともいう。1927年(民国16)12月中国共産党の指導下に武装蜂起した兵士と労働者が3日間にわたって広州市を占拠した事件。彭湃が海豊・陸豊にソヴィエト政権を樹立していたとき,国民党系の張発奎の支配する広州市内で張太雷・葉挺・葉剣英・聶栄臻(じょうえいしん)らの率いる兵士と労働者が蜂起した。12月11日に決起して当日中にほとんど全市域を占拠。3万余名の大衆集会を開き蘇兆徴を主席とするソヴィエト政権樹立を宣言し,軍閥と国民党の打倒、8時間労働制・土地国有・大資本家の財産没収などの綱領を採択した。だが,決起後の行動計画が不十分で,武装労働者も少なく,農民軍の来援も実現しなかった。12日にはイギリス・アメリカ・日本・フランスの軍艦に支援された国民軍や保安隊などの反撃が開始され、形勢不利となった決起隊主力の教導団は,13日海陸豊に撤退したが,張太雷を初め蜂起軍兵士や労働者ら5700名が犠牲となった。この敗北は瞿秋白(くしゅうはく)左傾路線の誤りによるものといわれている。』 |
ほぼ正確な記事だと思われるが、これは瞿秋白らの誤りというより、コミンテルンの方針に忠実に従った結果といったほうがより正確だろう。注目されるのは、こうした人民蜂起に蒋介石国民党軍だけなく、英米日仏といった列強も一致して攻撃にあたったことだ。
中国をめぐる情勢の中で、帝国主義列強間の争いと妥協、中国国内人民民主主義闘争、中国人民の反帝国主義闘争・民族独立闘争という3つの対立闘争軸がもっとも端的に示された事件ともいいうる。
この惨劇から逃れ出ることができたのは、葉剣英などほんの一部の人間だけで、人民革命側はほぼ全滅だった。この中には、朝鮮義勇軍の約150人の青年も含まれ、間接的に朝鮮の対日反帝国主義闘争にも打撃をあたえたのである。
こうして1927年(昭和2年)末までには、中国から共産主義勢力は、都市でも農村でもほぼ一掃されたといってよい状況になった。蒋介石国民党軍の圧倒的勝利である。
ただ毛沢東を中心とする小部隊は、山岳地方に立てこもり一部残存した・・・。が、もう問題にするに足らない勢力となったのである・・・。 |
|
 |
|
しばらく、張作霖爆殺事件(1928年=昭和3年6月)まで、共産党勢力がどうなったかを追ってみたい。というのは誰が見ても、これで中国における共産党勢力がその命脈を絶たれ、歴史の表舞台から完全に姿を消すと思われたのにもかかわらず、そうならなかったからである。しかし、それにしても、この時点で、17年後の1945年からはじまる国共内戦で、共産党側が勝利するなどと予測したものは、中国共産党員も含めて一人もいなかったはずである。
一連の都市武装蜂起で、毛沢東は湖南を担当したが、毛沢東は早々と長沙(*湖南省都)攻撃を蜂起、山岳地帯に撤退する。毛沢東は責任を問われて、共産党中央の要職を解かれる。
毛が湖南蜂起の残存部隊約1000を率いて立てこもったのは、湖南・広西の省境に横たわる羅霄(らしょう)山脈の中だった。そのほぼ中央に位置する井岡山(せいこうざん)地域に、毛沢東の部隊は立てこもった。1927年9月末のことらしい。
毛沢東が1929年(昭和4年)11月25日付けで送った中国共産党中央に送った報告書(「井岡山の闘争」という表題が毛沢東選集ではつけられている)から引用すると、
| 『 |
軍事根拠地――第一の根拠地は井岡山であり、・・・の四県の県境にまたがっている。北麓は・・・、南麓は・・・であり(*いずれも地名)で両地の間は90華里ある。(*メートル法採用までは1中国里は約650mだったので、90華里はおよそ60km足らずではないか。)東麓は・・・、西麓は・・・(*いずれも地名)で両地の間は80華里(*同。およそ50Km)ある。周囲は・・・(*いずれも地名の羅列)で合計550華里(*同。およそ360Km足らず)である。・・・の各地には(*いずれも井岡山の部落名)みな水田と村落があり、もともと匪賊や敗残兵の巣窟となってところであるが、いまでは、われわれの根拠地となっている。しかし人口は二千にも満たず、もみの生産は1万担たらずで(*1担は約60Kg)で、軍の糧秣は・・・の3県(*いずれも麓の県名)からの輸送に依存している。』
(外文出版社「毛沢東選集」第1巻 P108−P109 1968年3月31日初版) |
というからとんでもない僻地に引きこもったわけである。
|
|
 |
|
毛沢東は、地元の武装農民と残存兵に対して政治的教育を実施して次第に革命軍兵士に変えていった。
やや長い引用になるかも知れないが、人民革命だの、土地革命だの、政治的教育だの抽象的な話より、この毛沢東の報告書(「井岡山の闘争」)から引用してしまった方がよほど具体的でわかりやすい。またこの理解は、その後の「抗日戦争」や「国共内戦」全体を貫く、いわゆる「毛沢東思想」の根幹部分にもかかわるものであり、理解しておくのに無駄はあるまい。
なお、この井岡山で「紅軍」が誕生した事になっているが、毛自身は「赤軍」と呼んでいる。
| 『 |
赤軍兵士の大部分はやとい兵部隊からきているが、赤軍にはいるとすぐ質が変わる。まず第一に。赤軍がやとい兵制度を廃止したことは、兵士に、他人のために戦争するのではなくて自分のため人民のために戦争をするのだと感じさせている。赤軍には今でも(*この報告書が党中央に送られたのは1929年11月)正規の給与制というものはなく、食糧と食油、食塩、たきぎ、野菜などの費用、それにわずかばかりのこづかい銭を支給するだけである。赤軍将兵のうち、他の地方の出身者にまで土地を分配することはかなり困難であるが、この省境地区(*すなわち井岡山周辺のこと)にはそれぞれ土地が分配されている。
政治教育を通じて、赤軍兵士はみな階級的自覚をもち、みな土地の分配、政権の樹立、および労働者・農民の武装化などの常識を身につけるようになり、自分のため、また労農階級のために戦うのだということを知るようになった。だから、かれらは苦しい闘争の中でも不平をいわない。』(前掲書、P101−P102) |
| 『 |
湖南省委員会(*これは共産党湖南省委員会のこと。よくわからないが、この時毛沢東の部隊は湖南省委員会の指導下にあったらしい)は、兵士の物質生活をすくなくとも一般の労働者、農民の生活よりはいくらかよくすることに気を配るよう、われわれにいってきている。だが、現在はその反対で、主食のほかは、食油、食塩、たきぎ、野菜などの費用としても、毎月1万元以上の銀貨が必要であり、それはすべて土豪からの徴発で支給している。(*この時まだ徴税権を確立できていなかったものと見える)現在、全軍五千人の冬服についていうと、綿はあるが綿布がない。こんなに寒いのに、多くの兵士はまだ夏服を二枚重ね着しているだけである。さいわいに苦しい生活にはなれている。しかも、その苦しさは誰もがおなじで、軍長から炊事兵にいたるまで、主食以外は一律に五分ぶんの食事しかとっていない。こづかい銭を支給するにも二角(チャオ)なら一律に二角にし、四角なら一律に四角にしている。(*1元=10角=100分)兵士はだれも不平をいわない。』(同書 P103) |
| 『 |
戦闘のあるたびに負傷兵がでる。栄養不足や寒さやその他の原因で、病気する将兵が多い。』(P104) |
|
|
 |
|
| 『 |
赤軍の物質生活がこのように粗末であり、戦闘がこのように頻繁にやられているにもかかわらず、赤軍として依然として崩れず維持できているのは、党の果たしている役割のほかに、軍隊内で民主主義が実行されているからである。上官は兵士を殴らず、将兵は平等に待遇されており、兵士には会議を開き意見を述べる自由があり、煩わしい儀礼は廃止され、会計は公開されている。兵士はまかないを管理し、毎日五分の食油、食塩、たきぎ、野菜などの費用の中から少しばかり節約してこづかい銭にあてている。これを「食費の余り」と呼んで、一人当たり毎日六、七十文(ウェン)もらっている。こうしたやり方に、兵士は満足している。特に新しく入ってきた捕虜の兵士は、国民党の軍隊とわれわれの軍隊都では全く違った世界であることを感じている。かれらは、赤軍の物質生活が白軍(*毛沢東は国民党軍のことをこう呼んでいる。)より劣ってはいても、精神的には解放されたと感じている。おなじ兵士で、昨日は敵軍内で勇敢でなかったものが、今日は赤軍内で非常に勇敢になるのは、民主主義の影響である。赤軍はるつぼのようなもので、捕虜の兵士が入ってくると、たちまちとかしてしまう。中国では人民が民主主義を必要としているばかりではなく、軍隊もまた民主主義を必要としている。軍隊内の民主主義制度は、封建的なやとい兵部隊を打ち壊す重要な武器となるであろう。』(P104−P105) |
| 『 |
敵軍に対する宣伝で、最も効果的な方法は、捕虜を釈放したり、負傷兵を治療してやったりすることである。敵軍の兵士や大隊長、中隊長がわが軍の捕虜になれば、すぐ彼らに宣伝を行い、残りたいものと帰りたいものとにわけ、帰りたいものには旅費を与えて釈放する。このようにすれば、「共産匪は手当たり次第人を殺す」といった敵の欺瞞は、たちどころに打ち破られてしまう。楊池生(ヤンチーション)の<九師団旬刊>は、われわれのこのようなやり方について「悪辣なるかな」と驚嘆している。赤軍兵士達は、捕らえられてきた捕虜に対して非常に親切にいたわったり温かく見送ったりするので、「新しい兄弟の歓送集会」があるたびに、捕虜達はその演説で、われわれに心からの感謝をもってこたえている。敵の負傷兵を治療してやることも、大きな効果がある。李文彬(リーウェンピン)のような利口な敵は、近頃、われわれのやり方を見習い、捕虜を殺さず、捕虜となった負傷兵を治療している。・・・』(P107−P108) |
付け加えることはあまりないだろう。中国の戦いは、中国人民の心をいかに捉えるかの戦いになっていたのである。 |
|
 |
|
ただ、この報告書は1929年11月の時点であり、毛沢東が井岡山に立てこもった1927年9月時点では、さらに酷い状況であったことは想像に難くない。
1928年5月には、南昌蜂起から逃れて各地を転戦した朱徳の部隊が合流、さらに湖南省南部の農民軍も合流し、兵力1万の労農紅軍第四軍が編成された。
軍長には朱徳、党代表には毛沢東、政治部主任には陳毅(http://ja.wikipedia.org/wiki/陳毅)が任命された。28年夏には、軍閥軍の攻撃を退けて、根拠地を拡大し周辺にじわじわ浸透していった。
同時に土地改革をすすめた。28年12月、「井岡山土地法」は、すべての土地を没収して、家族数に応じて分配することを定めたものであり、農民を主体とする中国人民の心を捉えていったのである。
先の毛沢東の報告書は、当然この土地改革にも触れている。
| 『 |
省鏡地区の土地状況―大まかにいえば、土地の60パーセント以上が地主ににぎられ、農民の手にあるものは40パーセント以下である。江西省方面では、土地がもっとも集中しているのは遂川県で、約80パーセントが地主のものである。永新県がそれにつぎ、約70パーセントが地主のものである。万安県、寧岡県、蓮花県では自作農が比較的多いが、やはり地主の土地が多くて、約60パーセントをしめ、農民の土地は40パーセントしかない。湖南省方面では、茶陵、?県の両県とも約70パーセントの土地が地主の手中にある。』(P109) |
| 『 |
中間階級の問題―さきにのべたような土地状況のもとでは、すべての土地を没収して再分配することが、大多数の人々の支持を受ける。しかし、農村のなかは大体三つの階級、すなわち大・中地主階級、小地主・富農の中間階級、中農・貧農階級にわかれている。富農はたいてい小地主と利害が結びついている。富農の土地は、総土地面積のうちでは少ない方であるが、小地主の土地とあわせると、かなり多いものになる。このような状態は、おそらく全国的にみても大差ないであろう。省鏡地区では、土地を全部没収し、徹底的に分配する政策をとっている』(P109−110) |
同書P132−133の原註には次のように記述されている。
| 『 |
・・・あとになって、毛沢東同志は、地主の土地だけを没収するのではなくすべての土地を没収するのは誤りであり、この誤りは、当時、土地闘争の経験に欠けていたことからきたものである、と指摘した。1929年4月に出された興国県の土地法では、「すべての土地を没収する」を「公有地と地主階級の土地を没収する」にあらためている。』 |
とある。 |
|
 |
|
毛沢東の報告書を続けよう。
| 『 |
白色テロ下の中間階級の寝返りー中間階級は革命の高揚期に打撃を受けたので、白色テロがひとたびやってくると、たちまち寝返りをうつ。反動軍隊を手引きして永新県、寧岡県の革命的な農家の家をさかんに焼き払ったのは、この両県の小地主と富農であった。かれらは反動派の指示にしたがって、家を焼き払い、人をつかまえたりして、なかなか勇ましかった。赤軍が二度目に寧岡、新城、古城(クーチョン)、龍市(ロンシー:龍は龍かんむりの下に石と書く)一帯にやってきたとき、数千の農民は、共産党がかれらを殺すという反動派の宣伝を真にうけて、反動派について永新に逃げていった。われわれが「寝返りをうった農民を殺さない」、「寝返りをうった農民が刈り入れに帰ってくるのを歓迎する」と宣伝したので、やっと一部の農民がそろそろ帰ってきた。』(P111) |
| 『 |
もし、中国で豪紳・軍閥の分裂と戦争がつづけられていず、また全国的革命情勢が発展していないとすれば、小地区での赤色割拠は、経済的にきわめて大きな圧迫をうけ、割拠の長期的な存在は問題になってくるであろう。なぜなら、このような経済的圧迫には、中間階級がたえられないばかりでなく、労働者、貧農および赤軍もたえられなくなるときがくるかもしれないからである。永新、寧岡両県では塩がなくなり、綿布、薬は完全にこなくなり、その他のものはいうまでもない。現在、塩は買えるようになったが、値段はひどく高い。綿布、薬は依然として無い。寧岡県、永新県の西部、遂川県の北部(以上はいずれも今の割拠地)の最大の産物である木材や茶や油類は、依然として運び出せないでいる。)』(P112) |
| 『 |
土地分配の基準―郷を土地分配の単位としている。山が多く、農地が少ない地方、たとえば永新県の小江区(シァオチァン)では、三つか四つの郷を一つの単位として分配したところもあるが、そういうところは極めて少ない。農村では老若男女の別なくすべてに、均等に分配された。現在は党中央の規定に従い、労働力を基準とすることにあらため、労働できるものには労働できないものの二倍分を分配するようにした。』(P112−113) |
| 『 |
土地税―寧岡県では20パーセント徴収しており、党中央の規定より5パーセント多いが、いま徴収中なので変更するわけにもいかず、明年あらためて引き下げることにする。このほか、遂川、雨県(雨は雨かんむりに口が三つ下につく)に、永新各県の一部は割拠地域内にあるが、いずれも山地で農民はあまりにも貧しいので徴税するわけにはいかない。政府や赤衛隊の経費は、白色地域の土豪からの徴発に依存している。赤軍の給養については、米はいまのところ、寧岡県の土地税のうちからとっているが、現金は全部土豪からの徴発に依存している。十月には遂川県を遊撃して。一万余元を調達した。これで一時は間にあうので、つかってしまったときにまた方法を考えよう。』(P114) |
|
|
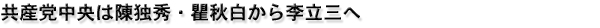 |
|
土地改革問題は共産党にとって根幹にかかわる問題だったが、それぞれに事情があり、簡単には行かなかったことが窺える。
話は若干さかのぼって28年2月のことになる。コミンテルンはそれまでの指示をあらため、ソビエト化された「農民地域」では土地改革と紅軍の建設に全力をあげるべきであるとした。この指示に基づいて28年6−7月モスクワで開かれた中国共産党第6回全国大会も内容を新たな方針として採択した。
見方をかえていえば、これはコミンテルンの指示に忠実でなかった「毛沢東路線」を、コミンテルン、共産党中央が追認したものと言えよう。なおこの時、「長沙退却」の責任をとらされていた毛沢東は中央委員に復帰している。またこの時、中国共産党の実権は、瞿秋白から李立三に移った。李立三といえば、1925年(大正14年)、中国革命運動の一大転機を作った「5・30運動」の指導者である。陳独秀、瞿秋白とコミンテルン路線(*スターリン路線)に忠実な指導者は、大きな犠牲を払った上に、その失敗の責任をとらされる格好で失脚をするのであるが、「5・30運動」の英雄、李立三までその運命が待ち構えているとはこの時予想した人は少なかったのではないだろうか? |
|
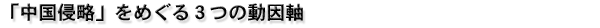 |
|
1928年(昭和3年)末までの「日本帝国主義の中国侵略」をめぐる直接の動因軸を、中国共産党、蒋介石国民党政府、日本の帝国主義、という3つだと仮定してみると、中国共産党は主としてコミンテルンの相次ぐ誤った指令を忠実に実行しようとしたためにほぼ、自滅壊滅状態に陥ったといえるだろう。
日本の帝国主義は、河本らの張作霖爆殺事件に代表されるように、真の敵を見誤ったために、これも自滅的に足踏み、迂回することになる。
こうしてみるとこの3つの軸のうち蒋介石国民党が「日本帝国主義の中国侵略」をめぐる抗争の中で着実に前進、その足場を固めていったかのように見える。
しかし、蒋介石国民党もその内部に、致命的弱点を抱えていた。それは、その政権の性格が、先にも見たように半封建的な性格を色濃く残した軍閥の連合体だったことだ。これでは近代的資本主義内統一国家樹立はおぼつかない。もし蒋介石政権が、資本主義内民主主義に立脚する近代国家創出に成功していれば、アメリカやソビエトなどの支援をうけ、日本のファシズム的に凶暴化した帝国主義を完全に追い出し、中国に国民党政権を確固として築き上げ、中華人民共和国の成立はなかったものと思われる。
しかし歴史の現実はそうではなかった。蒋介石政権は、孫文の国民革命の正統性を表面受け継ぎながらも、その後、自らもファシズム反動政治の道を歩み、中国人民の期待を裏切っていくのである。
田母神論文を良く読んでみると、田母神には、まずこの3つの動因軸、すなわち「民族独立と人民革命」をめざす中国共産党、本来近代統一国家のもとに健全な資本主義体制を構築すべきであったが、ついにそれが成し遂げられなかった蒋介石国民党、次第に凶暴化していく日本の帝国主義という3つの動因軸が全く見えていない。
ということは田母神を支持する自民党勢力、それを支持する学者・文化人、マスコミ、市民にも見えていない。戦後60年以上経ってもまだ見えていない。
この人達は、あの戦争を岸信介が観じたように、アメリカと日本の帝国主義戦争としか見ていない。彼らの歴史観はそのまま、現在の日本を取り巻く国際情勢認識にまで持ち込まれているかのようだ。それは彼らの安全保障をめぐる世界認識に端的に表れているようだ・・・。 |
|
| (以下次回) |
 |
 |