| No.18-2 | 平成19年2月17日 |
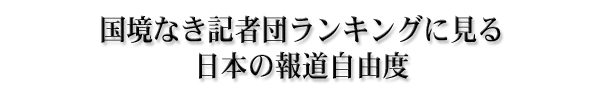 |
|
| No.18-2 | 平成19年2月17日 |
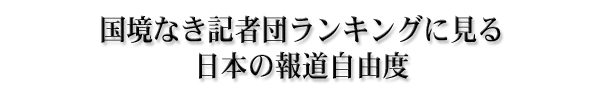 |
|
 |
|||
ざっと2006年度報道の自由度ランキングを概観したが、「国境なき記者団」がいかなる基準で順位を決定していったかを見てみたい。方法は50の質問項目を設定し、それから得られた回答を集計して点数を積み上げ、順位を決定している。 従って50の質問項目そのものが、「報道の自由度」を決定する基準と言うことになる。 その基準は、ある意味、ランキングそのものより重要である。 (質問項目の原文はhttp://www.rsf.org/article.php3?id_article=19390 翻訳は「世界報道の自由度インデックス2006準拠用質問項目」) ざっと概観してすぐ気がつくことは、国境なき記者団は、「報道の自由」を国家権力の介入の観点と共に、その社会がいかに言論の自由を尊重しているかの両方の観点から見ていることだ。 国家権力が直接介入していないから報道の自由がある、と思うのはとんだ錯覚だ。その社会が、「言論の自由」「報道の自由」を尊重することが、民主主義的な社会形成の基本条件だということを骨身に浸みてわかっているかどうかがもっと重要なのだ。その意味では、言論の自由に富む社会は、構成員一人一人の政治的教養が高い社会だともいえる。 報道の自由は国家権力によっても抑圧できるし、社会そのものが放棄することもありうる。われわれはともすれば、国家権力による抑圧の方ばかりに注意が行き勝ちだが、まったく同様に報道の自由を尊重し、それを守るために戦う社会でなければならない、ということをこの質問項目は教えてくれる。 たとえば、質問項目の1番目は、2005年9月1日から2006年9月1日までの1年間の間、と区切った上で、何人のジャーナリストが「殺害されたか?」と尋ねている。2番目は「国家の関与によって殺害されたか?」と尋ね、国家の関与と社会による殺害とを区別している。 |
|||
これに関してすぐに思い出すのは「赤報隊」事件だ。1987年5月3日の憲法記念日、「赤報隊」を名乗る右翼が、朝日新聞阪神支局を襲撃した。その場にいた小尻知博記者が散弾銃で射殺、犬飼兵衛記者も銃撃され3ヶ月の重傷を負った。極右テロによる殺害である。もちろん官憲による殺害ではない。しかしこの事件は官憲による殺害と同様、あるいはそれ以上に重要な事件である。なぜなら、日本の社会が許した殺害だからである。優秀な日本の警察もこの事件ばかりはお手上げのようで、犯人は今に至るも分からない。 (なおこの事件は時効を迎えた。) 重要なのは、日本の社会はジャーナリストの殺害を許す社会だ、ということを再確認することだ。少なくとも上位20位に入っている国はそれを許さない社会を育てている。 |
|||
さすがに日本の国家権力も、戦前と違って逮捕や投獄など、あからさまな抑圧はしなくなった。従って、国境なき記者団の質問、3.逮捕されたかまたは監獄に送られましたか?、や4メディア関連の事件で、現在留置されていますか? あるいは重い判決を(1年以上)を受けていますか?、に関する事件はなくなった。しかしいざとなれば牙をむく。外務省機密漏洩事件がそれを証明している。 1972年佐藤内閣の時に沖縄返還交渉が行われたが、この時日本政府とアメリカの間に国民の目からは隠しておきたい密約があった。その密約文書を手に入れたのが、毎日新聞の西山太吉記者だった。西山記者は外務省の女性事務官から入手したのだが、二人は愛人関係にあった。 ここから政府の検察を使った猛烈な巻き返しが始まる。女性事務官は国家公務員法100条(秘密を守る義務)違反で逮捕され、西山記者も111条(秘密漏洩をそそのかす)違反で逮捕された。 検察は問題の本質をすり替えた。取材の自由よりも、国家機密漏洩罪が優先する、としたのだ。しかもこのやり口が汚い。機密文書を入手するために、女性事務官に近づき色仕掛けで落としたというシナリオで起訴に持ち込んだ。 有名な起訴状の文句を引用すれば、「女性事務官をホテルに誘ってひそかに情を通じ、これを利用して」である。この薄汚い文章を書いたのは、当時東京地検検事で現民主党参議院議員の佐藤道夫であるといわれる。 世論はこの検察の「論点のすり替え」にまんまとはまった。問題の本質、つまり機密があったかなかったかという国民の知る権利から、西山太吉記者の取材方法に焦点がそれていった。起訴状の「ひそかに情を通じ」という扇情的な一言が、国民の感情を見事に煽ったのである。(「情を通じ」という検察語は、戦前特高警察の大好きな常套語だった。) 確かに西山記者にも、致命的な誤りがあった。愛人関係で文書を手に入れた、と言う点ではない。この文書を当時の野党社会党に渡したことだ。政争の道具になると分かっていて渡した。「報道の自由」の立場からすると自ら墓穴を掘った、というべきであろう。 |
|||
マスコミ、特に週刊「新潮」やその他のマスコミは二人の不倫関係を中心にあおりに煽った。取材方法が人倫にもとると言うわけだ。世間の批判は、西山太吉記者と毎日新聞社に集中した。他のマスコミも誰もこれを擁護しなかった。 マスコミと世論は、つまり日本の社会は、言論の自由の立場からすると自殺行為に走ったのである。 毎日新聞社は孤立無援の状態になり、西山太吉記者を停職処分とした。ジャーナリスト生命は完全に断たれた。 裁判は最高裁に持ち込まれ、最高裁は「その方法が刑罰法令に触れる行為や、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。」として西山太吉記者に対して有罪判決を行う。 今この判決を読んで、我々はキチッと批判が出来るだろうか? 「国民の知る権利」は近代民主主義が勝ちとった貴重な思想的財産である。この裁判官のいう「法秩序全体」の中心に座るべき項目の一つである。この裁判官は「国民の知る権利」よりも「社会観念上是認することの出来ない態様のもの」が優先すると考えたのだ。 こうして西山記者はジャーナリストとしての生命を断たれ、「沖縄返還密約」はうやむやとなった。 政府の完全勝利である。多くのマスコミはそれとは気づかず大敗北を喫した。 それから30年後、つい最近アメリカの公文書の秘密保持期限が切れて公開となった。当然沖縄返還交渉関連の文書も公開され、密約があったことが確認された。知らぬ存ぜぬを決め込んで、国会や裁判で偽証した政治家や高級官僚は、断罪されていない。 |
|||
さて国境なき記者団の「報道の自由度」基準項目を続けてみよう。 5.脅迫は受けていますか?これは日本の社会では日常茶飯事である。右翼の脅迫はまだわかりやすい。最近は下火になったが、ひところの創価学会の脅迫は手が込んでいた。何人もの人間を動員して「嫌がらせ」とも脅迫ともつかない脅しをかけるのである。創価学会の脅迫行為が最近下火になってきた理由はまた後ほど見てみる機会があるとして、ここでは創価学会の起こした言論弾圧事件をみてみよう。 1969年にジャーナリスト藤原弘達(当時明治大学教授)が「創価学会を斬る」を出版しようとして起こった事件である。 Wikipediaの記事で関係部分を丸ごと引用しよう。 (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AB%96%E5%87%BA%E7%89%88%E5%A6%A8%E5%A E%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6)
短い文章だが、とんでもない事実が凝縮されている。竹入義勝は政治政党「公明党」の委員長であり、衆議院議員である。日蓮正宗という一宗教一派の信者団体である創価学会の会長(=当時)であった池田大作の要請(事実上は指示)で、出版差し止めを企画する。竹入は、政権党の幹事長で実力者の田中角栄に出版差し止め出来ないか、と相談を持ちかける。池田、竹入、田中とここまで登場した人物の頭の中に、「言論の自由」という言葉はあってもそれはお題目で肉化していなかったことは間違いない。少なくとも重大な犯罪を犯しているという認識はなかったはずだ。 次は出版社、取次店に対する圧力だ。この時大量動員された創価学会・公明党の人たちが、出版社・取次店・書店に一斉に嫌がらせ、脅迫を行った。この人たちの頭の中に「言論の自由」「報道の自由」という言葉はなかったに違いない。 次は取次店・書店の人たちだ。ボイコットや嫌がらせを受けては、商売に差し支えるから、一時は創価学会・公明党の圧力に屈した。これを今考えてみると「みんな商売でメシを食って行かなくてはならないので当然だ。」という考え方もあるだろう。しかし「言論の自由」「報道の自由」はその社会が戦い取るものだ。 次に田中角栄だ。この人物は後に自民党総裁、日本国総理大臣になっている。この時多くのジャーナリズムは「今太閤」として大いにもてはやした。彼が言論の自由や出版・報道の自由についてどのような考え方をもっているかは十分に認識した上でだ。 Wikipediaの記事では、池田は藤原に謝罪したことになっているが、実は真から謝罪した訳ではなかった。 |
|||
それは続いて盗聴事件を引き起こすことでも証明される。 当時公明党・創価学会批判の急先鋒に立っていたのが、日本共産党だったが、何を思ったか創価学会は共産党委員長宮本顕二(=当時)の自宅に電話盗聴装置を仕掛けるのである。偶然にこの盗聴装置を発見した宮本は(正確には宮本の秘書だそうだが)、犯人不明のまま刑事告発を行う。一番疑われたのは公安である。組織的にこんなことを共産党委員長の自宅に仕掛けるのは公安以外にはない。 真相は10年後に明らかになる。週刊誌(週刊ポスト)がこの事実を暴露したのである。 (このへんの詳しい事情は段勲が書いている。http://www.toride.org/tap/tap1.htm) 国境なき記者団の50の基準の中の18番目に、ジャーナリストの監視(盗聴・尾行)が上げられている。 宮本はジャーナリストではない。しかし共産党機関紙「赤旗」の事実上の親分だった。公明党・創価学会に対する批判の急先鋒だったのが「赤旗」だったことを考えるとこの18番目の基準に該当する。 今ここでの問題は公明党・創価学会が基本的に「言論の自由」「報道の自由」に対してもっている考え方が変わっていないということだ。それは「出版妨害事件」「宮本宅盗聴事件」を未だに事実を明らかにした上で清算していないことでも分かる。 さらに問題なのは、この公明党は今や政権与党に居ると言うことだ。田中角栄に頼まなくても、自ら田中角栄になっている。 そうしてもっとも問題なのは、それをこの社会が許していると言うことだ。 その上まだ問題なのは、この問題が過去の問題になっていないということだ。 「報道の自由」「言論の自由」はその社会がたたかいとって守るものだ。 |
|||
日本における「言論の自由」「報道の自由」は戦い取られたものではない。戦後占領政策で与えられたものだ。それだけにひ弱だ。お隣の韓国のように、独裁政権を打倒して勝ちとってはいない。だから、機密漏洩事件のように、ちょっと応用問題の形で出題されると途端に落第点になってしまう。その体質は今に至るも変わっていない。それどころか国境なき記者団のランキングの通り、ますます悪化の一途をたどっている。 国境なき記者団の50の基準の8.違法に投獄される、9.拷問を受ける、10.誘拐される、又は人質を取られる、11.ジャーナリストの失踪、12.武装民兵や秘密組織がジャーナリストを標的としましたか?になってくるとさすがに日本では表面見あたらない。 報道の自由に対する抑圧は、もっと巧妙になっているからだ。我々の気がつかないところで進んでいる。 だが、12.ジャーナリストやメディア企業に対してテロリストの行動がありましたか?、となってくるとこれはイエスだ。日本でこの種の事件を引き起こすのは、粗雑なままで洗練されていない右翼暴力団か、あるいは宗教の仮面をかぶった金儲け組織や権力亡者組織だ。 これに関してすぐに思い浮かぶのが、フリージャーナリスト溝口敦だ。溝口は幅広い分野をカバーするが、特に暴力団、創価学会問題に詳しい。また食肉業界の内幕を描いた「食肉の帝王」では2002年日本ジャーナリスト会議賞を受賞した。 1990年、溝口は暴力団関係者に背中を刺され重傷を負った。「溝口の口をふさげ」ということだろう。犯人は未だに捕まっていない。日本の警察は優秀なのだそうだが、朝日新聞阪神支局事件の犯人が捕まっていないなど、「言論の自由」や「出版の自由」関連の事件になると途端に無能になる。警察全体は優秀なのだが、無能な人間をたまたま配置しているということかも知れない。そうだとすれば、特に優秀な警察官を配置する必要がある。(もしいればの話だが) 溝口にはとって、もっと酷い事態が訪れる。2006年1月、もう独立して立派に社会人となっている自分の息子が、暴力団に襲われたのだ。幸い命に別状はなかったが、溝口にとっては十分な警告になったはずだ。溝口自身は、山口組という日本最大の組織暴力団を向こうに回して戦うのだから、はなから自分の命はないものと決めてかかっているだろう。 しかし家族は別だ。特に子供は別だ。息子を殺されることは恐らく自分が殺されるより溝口には応えることだろう。襲った暴力団を形容するに当たって、卑劣・卑怯者という以外言葉が見つからない。 国境なき記者団の50の基準の17番目に、「ジャーナリストの友人、同僚、家族に対して襲撃または脅迫がありましたか?」という項目があるが、これを地でいくような事件である。 国境なき記者団の50の項目は、すべてレポーターたちが体で経験した項目だ、というのが実感だ。よく読んでみると机の上でたてた基準ではなく、レポーターたちがひとつひとつ体験した基準であることが分かる。 溝口が経験したような、あるいはもっと悲惨な事態を経験したレポーターが、恐らく数多くいるのだろう。 |
|||
さすがに、国家権力が直接介入するような事例はなくなった。26.外国語新聞の没収や29.すべてのメディアの中身を事前に検閲できるような公的存在などはない。 しかし30.民間設立メディアの自主検閲が状態化しているか? 31.タブーとなっているテーマがあるか?(軍、政府内での衝突、宗教、対立的見解、分離独立要求、人権問題など)、といった項目になると、おやと思わせる。 実際今、日本のジャーナリズムが直面している大きな問題は、「報道の自己規制」ではないだろうか? 「旧日本軍による従軍慰安婦制度」を非難する決議案が2006年9月13日米下院国際関係委員会を通過した。この問題は同委員会の担当だから、この委員会を通過すると、下院本会議に上程されることになる。朝日新聞はこれをほとんど無視同然の扱いをした。 (逆にこの問題を比較的大きく扱ったのは、サンケイ新聞や読売新聞である。しかしニュースを報道するというより、このような不当な決議案を通してしまっては日本の言い分が国際社会に反映されない、従軍慰安婦の問題はすでに決着がついている、と言う立場からの論評だった。それもすぐ尻すぼみになる。結果このニュースを知っている日本人は極めて少ない。) 私はこのニュースをニューヨーカー・マガジンの電子版で知った。ニューヨーカー・マガジンの切り口はこのニュースそのものではない。日本政府が、この法案を潰すために「毎月6万ドルの報酬で大物ロビイストを雇っている。ブッシュ政権もこの法案には消極的で、米下院議長を駐日大使のポストと引き替えに説得し、結果今回本会議上程はなさそうだ。」という記事だ。この記事は知っている限り日本の主要なマスコミは報じなかった。 (詳細は「潰された米下院従軍慰安婦非難決議http://www.inaco.co.jp/isaac/back/014/014.htm) 一般国民に影響力の大きい日本のテレビも報じなかった。 この非難決議は、中間選挙が終わった後、再び米下院で取り上げられ、2007年1月31日に米下院にいよいよ上程された。06年10月は国際関係委員会を通っただけなので、無視同然な扱いを受けたと言う解釈も成り立つ。07年1月は本会議上程だからどうだろうか、と思っていたらこれも無視同然な扱いだった。テレビも報じていない。 一部には「すでに解決済みの問題で、日本バッシングをするアメリカの議会には徹底的に反論し、日本の立場を国際社会に訴えなければならない。」とする論調の記事が出ていた。しかしこれは、この非難決議の本質をすり替えた議論である。日本国民にはなにも伝わらない。 |
|||
朝日新聞もこれはまずいと思ったのか、2月16になって、ニューヨーク特派員電で、この問題を比較的大きく取り上げた。内容を読んでみると、「従軍慰安婦問題は、すでに決着済みの話。謝罪も終わっている。今更謝罪を要求する米下院は不当。日本政府としてはこの不当な決議案を撤回させるために全力をあげる。」といった内容の駐米日本大使のコメントを中心に記事が作ってある。 この朝日の特派員は下院の決議案を読んでいないか、読んでも故意に要旨を無視したかのどちらかだ。 この決議案は、原文は「THOMAS[Library of Congress]」とサーチエンジンで検索し、検索(search)のボックスに「H.RES.121」と打ち込むと入手できる。訳文は2007年1月31日米下院に上程された旧日本軍従軍慰安婦制度非難決議案 に掲げておいた。 一読してわかるようにこの決議案は、確かに日本に謝罪を要求してはいるが、そこに力点があるのではない。力点は「従軍慰安婦」に代表されるような性奴隷制度や戦争における女性に対する性暴力や迫害が二度と起こらないように、その犯罪性を今の世代や次世代に良く教育しろ、また国際的にもそうした教育を推進する原動力に、日本はなれ、と言っているのだ。謝罪もそのためのけじめなのだ。 日本とアメリカの駆け引きといった小さい話ではなく、もっと国際的な女性に対する性暴力の再発を防ぐ、と言った観点からこの決議案は書かれている。 それにしてもトーンダウンしたものだ。昨年米下院の国際関係委員会を通過した決議案と較べてみよ。(この決議案の原文は先ほどの要領で今度はH.RES.759と打ち込むと入手できる。訳文は2006年4月4日に上程され、9月13日に国際関係委員会を全会一致で通過した、米議会下院旧日本軍性奴隷制度非難決議案。) ハーパーズ・マガジンのケン・シルバーマンは、「中間選挙が終わって1月の議会で最上程されるだろうが、かなり後退したものになるはずだ。」と書いていたが、その通りになった。まるで米下院と日本の外務省の妥協の産物のような内容だ。 恐らくは日本政府とアメリカの議会はこの内容で合意したのだろう。日本政府や外務省は、「決議案阻止に向けて全力をあげる。」と息巻いているが、それは日本の国内向けデモンストレーションだろう。そのデモンストレーションのお先棒をかついでいるのが、日本の大手ジャーナリズムだ。ここは全く私の推測である。 私は「従軍慰安婦問題」については、政府からの無言の圧力を受けて、主要なジャーナリズムの中に、自主規制が存在しているのではないか、と感じている。海外の日本に関する論調には極めて敏感な日本のジャーナリズムなのに、この問題は大きく取り上げない。または正しく伝えない。 |
|||
直接証拠ではないが、状況証拠はある。ことの発端は、慰安婦問題を扱ったNHKの番組「ETV2001―問われる戦時性暴力」(2001年1月30日放映)が番組直前になって改変が行われた事件である。 取材に全面的に協力したバウネットジャパン(「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク=共同代表 西野瑠美子氏・東海林路得子氏)が、このNHKの改変に対して損害賠償を求めて提訴した。2004年の1審では、番組改変についてはNHKに責任はない、として番組制作会社にのみ責任が帰せられた。 ところがその後新事実が出てきたのである。番組担当のNHKのデスクが、「政治介入があった、そしてNHKの理事が番組を説明するため、当時の安部晋三官房副長官に会い、その後急遽番組が大幅に作り替えられた。」と証言したのである。 07年1月に出た東京高等裁判所の控訴審判決は、 1. NHKの理事は、政権党の政治家に会い、その気持ちを忖度して番組を作り替えた。 2. 政治家(安部晋三官房副長官ら=当時)は、番組改変に圧力をかけたとは認められない。 3. NHKは原告の期待権を裏切った。 として200万円の損害賠償を命じたのである。NHKはすぐさま上告したからこの問題は恐らく延々と続くのだろう。しかしもう私には十分である。 今や首相となった安倍は、テレビのインタビューでこの判決に関する感想を語り、「これで私が圧力をかけていないことが証明された。会いたいと言うので会って意見を求められたので、あくまで公平・中立に、と申し上げただけです。」と若干胸を張っていた。 NHKの理事を安倍が呼びつけていない、というのは恐らく本当であろう。安倍とNHKの理事の間にどのような会話がなされたのか、これはどちらかが真実を言わない限り藪の中だ。 今ここで問題としたいのは、NHKの首脳部は「ETV2001―問われる戦時性暴力」の内容を把握し、直感的にこれはお伺いを立てないといけない、と判断したことだ。そしてすぐさま安倍官房副長官に面会を申し入れた。安倍も忙しい中これは重要と判断して理事にあって内容を聞いて、感想を述べている。 明らかに従軍慰安婦問題は、報道要チェック事項であり安倍もNHKの理事も事前にこのことを了解していたということだ。安倍は「公平・中立に」と言うだけで良かった。どこをどう直せばいいのかは、言わなくても分かる・・・。 この事件は、「従軍慰安婦問題」に関して、NHKの中に経営レベルでの自主規制が存在していることをはしなくも暴露してしまった。 それとも、「政治的圧力ではありません。私が進んで会いに行って意見を聞いたのですから。でもこれは自主規制ではありません。」とでも、このNHKの理事は言うつもりなのだろうか? |
|||
さらに想像を逞しくすれば、従軍慰安婦問題だけではなく報道要チェック事項が他にもあり、自主規制という名前の報道統制が全国に張り巡らされているのではないか、という疑いが頭をもたげてくる。 私が毎日目を通し続けている日刊新聞は、朝日新聞一紙だけだが、その朝日新聞で見る限り、経営トップレベルの報道要チェック事項ではないかと疑えるのは、イラク戦争における戦争犯罪性、イラン核疑惑問題における核兵器と核の平和利用の意図的混同、北朝鮮拉致問題、国民年金財源不足の真の原因追及、学校教育問題、共産党は出来るだけニュースにしない、天皇及び天皇家報道、創価学会問題、憲法問題、地方財政破綻の真の原因追及などである。私が誇大妄想狂であれば幸いである。 大手ジャーナリズムやテレビ局が、何故またいかようにして政治権力の御用ジャーナリズムになっていったかは、極めておもしろいテーマだが、大きすぎてここでは扱えない。日本の「報道の自由」が戦い取られたものではない、という事実のツケが今徐々に肥大化してきている、というだけだ。 (しかしこれは何も言っていないに等しい。) 国境なき記者団が、日本の報道の自由問題で特にふれているポイントが2つある。 「アメリカ、フランス、日本における報道の自由はこのところ引き続き腐り続けている。・・・(日本は)国粋主義の勃興や閉鎖的な『記者クラブ』が日本における民主主義的な言論の自由にとって脅威となっている。日本経済新聞社は火焔瓶を投げつけられたし、幾人かのジャーナリストが極右行動主義者(uyoku)によって身体的に攻撃を受けた。」 日本経済新聞社に火焔瓶が投げつけられたのは06年7月21日のことである。日本経済新聞は20日付で「昭和天皇は靖国神社が第2次世界大戦のA級戦犯を合祀したことに不満だった」という記事を掲載していたという。ジャーナリストではないが、元自民党幹事長加藤紘一の自宅兼事務所が放火される事件が発生している。 こうした右翼の動きは、次のような主張に要約されよう。
有門の主張は戦前の井上日召を思い出させる。ポイントは政財界人に対する威嚇にある。戦前大正デモクラシーから昭和初期になだれ込んだ日本は急速に右傾化を強めていった。それは中国大陸侵略と完全に軌を一にしていた。右翼の暴力を露払いのようにして、軍部テロリズムが頭をもたげる。全国に張り巡らされた特高警察を足腰に、まず左翼関係者の弾圧が始まった。次に左翼ではないが当時としてはリベラルな知識人・ジャーナリストへの弾圧が始まった。そうして国家暴力・国家テロの前に、みな沈黙したのである。天皇制イデオロギーと相容れない宗教団体も弾圧された。 何かが始まるときに、右翼はまず著名な政財界人を狙う。脅しがききやすいからだ。もたざるものには脅しは利かないが、もつもの対する脅しは実に有効だ。 (そうか。もたざるものも命だけはもっているか。) 今の右翼の台頭は、一体何の露払いなのだろうか? いいようのない胸騒ぎを感じているのは私だけだろうか? |
|||
国境なき記者団が指摘する「記者クラブ」制度についてみてみよう。 記者クラブとは、特定のメディア企業に所属するジャーナリストだけが、もっとも主要な情報源(政府、国会などなど。)において、取材を許されるという仕組みで、現在この制度を取っている国は事実上日本だけになった。 (詳しくはWikipedia「記者クラブ」を参照のこと。おずおずと賛否両論が併記されている。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E8%80%85%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96 ) 日本だけになった、というのは、つい先頃まで韓国でも似たような制度が取られていたからだ。ノ・テウ政権はあっさりこれを廃止してしまった。韓国が似たような制度をもっていたのは、戦前の日本占領時代の名残である。 記者クラブに加盟している各社は特権階級で、主要な情報をまず最初に独占できる。取材される側は相手が見えているから情実も利きやすい。「これは書かないでね。」といわれれば、いうことを聞かざるを得ない。 つっこみも甘くなる。もしオフレコネタを書いたらどうなるか、記者クラブ加盟他社から村八分にあって、わびを入れることになる。 これを取材される側、特に権力を持った側(その権力とは本来国民から付託されたものだが)から見ると 極めて重宝な代物だろう。書いて欲しいこと、書いて欲しくないことを指示出来るのだから。ジャーナリストは本来民衆のための番犬(Watch dog)だ。ところが記者クラブ制度の下では、番犬ではなく飼犬である。 要するに記者クラブとは、権力を持った側と大手ジャーナリズムの官製談合組織だと思えばまず外れていない。 もともと大手ジャーナリズムの報道の自主規制は偶発的なものではなく、記者クラブ制度に代表される日本の大手ジャーナリズムの体質なのだ。 それではこの体質はいつ頃形成されたものだろうか? 現在の日刊新聞の体制のはじまりは、1941年(昭和16年)12月の新聞事業令(勅令)だといっても過言ではないだろう。 言論統制を徐々に強めていった旧帝国政府はついに新聞事業令を発布し、全国の新聞の統廃合に踏み切る。 いうまでもなく、言論統制のためには新聞は少ない方がいい。 静岡県立大学前坂俊之教授の研究によれば、1939年当時(昭和14年)、全国に7670紙(うち月刊以下の頻度の新聞が4300)あったという。 全国紙は朝日、毎日、読売の3紙、ほか「東京、大阪は4,5社、名古屋・福岡は2社、あとの各県は一県一社に整理統合して、報道は同盟通信に一本化する」(同教授 2005年 「マス・コミュニケーション研究 No.66」より。なお同教授のサイトはhttp://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/~maesaka/ 同論文はこのサイトの「戦争報道」のコラムにはいると全文読むことが出来る。) 政策を軍部が中心となって進めたという、紆余曲折はあったものの、この政策は実現し、現在の全国紙、ブロック紙、県紙のヒエラルキーと構造がほぼできあがった。 新聞業界は、この軍部の露骨な言論統制に体を張って抵抗したかというと、必ずしもそうでもない。内心賛成した経営者も多かった。というのは当時の新聞業界は、大手と中小、中央紙と地方紙がお互いの利益をめぐって三つ巴ならぬ、多層にわたる競争を続けており、経営体質は弱っていたからだ。こうして整理統合されてみれば、生き残った新聞社にとっては、独占による利益(それは中央だろうが地方だろうがかわらない。)によって一息つけたからである。新聞の再販売価格制度もそのまま現在に維持している。 Webジャーナリスト木村愛二(同氏のサイトはhttp://www.jca.apc.org/~altmedka/)の引用している記事(『別冊東洋経済新報』(52・3)所収記事「日本の内幕」)によれば、この時読売新聞のオーナーだった、 正力松太郎は「新聞ほどもうかる事業は、世の中に二つとない、戦争中といえども、公定価格でもうかったのは、新聞だけであった」と語ったという。 (この記事は上記サイトの「電網木村書店」から読むことが出来る。) |
|||
日本の敗戦後、軍部による言論統制が崩壊し、また新聞紙が全国に乱立したかというと、そうはならなかった。つまり基本的に東条英機内閣の時にできあがった「国家総動員体制」の枠組みの中の言論統制システムがそのまま戦後も継続されたのである。 なぜ戦前のように百花繚乱のような新聞制度が復活しなかったか、これも興味あるテーマだが、これも私が扱うにはあまりにも準備不足である。 ただ、戦後もの不足の時に、GHQと政府は「紙」の統制で新聞の乱立を押さえることができた、ということと、「トウジョー」が作った言論統制の仕組みがアメリカ占領軍にも都合がよかったので、壊さなかったのだろう、という推測が成立するだけだ。 しかし、これは私の単なるあてずっぽうでもない。第一次読売争議の結末が上記推測のリトマス試験紙になっていると思うからだ。 |
|||
| (以下その③) | |||
 |
|||