| (2012.5.18) | ||||||||||||||||
| 【参考資料】ヒロシマ・ナガサキ・フクシマ | ||||||||||||||||
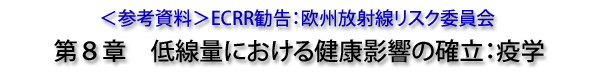 誤謬だらけの「ICRP疫学体系」 |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
| あたかも法則の如く扱われる「仮説」 | ||||||||||||||||
第7章ではECRRは、その対象とする電離放射線の健康影響を、ICRPのそれとは根本的に全く違う観点から眺めていることを見た。一言でいうならICRPは低線量分野での健康影響は「致死性がん」のみ(白血病もがんの一種である)とするのに対して、ECRRは、死産・流産を含んで「幅広い健康損傷」にあると主張する。 しかしECRRはそれをいかなる科学的方法論で立証していくのであろうか? ICRPの採用する方法論では、こうしたことは問題にならない。乱暴にいってしまえば、自説の正しさを立証する基本的な科学的方法論などは必要がない。ICRPは、電離放射線の人体に対する影響を「法則」から導き出しているからだ。だから生起した現象はその法則に照らしてあれこれ解釈すればこと足りる。 ICRPの「法則」は、『電離放射線は一時に大量(1シーベルト以上。状況によっては100ミリシーベルト以上と解釈できる時もある)に浴びない限り人体に対してさほど大きな影響はない』というものだ。実際には彼らの主張は「生涯累積線量100ミリシーベルト以下の世界では、放射線が人体に損傷を与える、という科学的証拠はない」と言い方になっている。 もちろんICRPはこの言説を「仮説」だと言っている。しかしその「仮説」を彼らはあたかも「科学的法則」のように取り扱っている。こうした言説をもつ科学者にとって、現実に100ミリシーベルト以下の低レベル放射線被曝によって人体にどんな影響が起きているかはさして大きな問題とはならない。「法則」に照らし合わせてみれば、自明のことだからだ。ICRPの学問体系は「電離放射線に関する科学」なのではなく「電離放射線に関する解釈学」とならざるを得ない。 もちろんICRPにも仮説を導き出す「現実」があった。その現実を調査・分析して「仮説」を導き出し、それを「法則」として扱っている。その現実とは、今から60年以上もまえの広島・長崎における原爆被爆者生存者調査(Life Span Study-LSS)である。つまりICRPはLSSを根拠にした法則を金科玉条としている限り、自らの正しさを立証する方法論などは必要がない。現実に起こっている出来事も、自らの法則に合致した事実関係だけをすくい上げればこと足りる。自らの法則に合致しない事実関係が数多く出てきては困るので、彼らの特徴は「調査をしないこと」だ。 調査さえしなければ、事実は出てこない。この特徴は、古くはイギリスのウィンズケール事故(セラフィールド事故)でも、アメリカで多発した原発事故や放射性物質漏洩事件でもチェルノブイリ事故でも貫かれている。そして今また「フクシマ危機」でも貫かれようとしている。しかしこれは科学ではない。 |
||||||||||||||||
| 疫学的アプローチの重要性 | ||||||||||||||||
一方、ECRRの学問体系では、それ自体「法則」などと云うものはない。様々な仮説はあってもそれを法則化することはできない。ECRR2010年勧告の第3章では、ECRRは自らの方法論を「帰納法的」とし、原理・原則から出発するICRPの方法論を「演繹的」と名付けそれに対置させた。 簡単に言って演繹とは原理・原則から出発する一つの推論方法である。たとえば有名な三段論法は代表的な演繹法推論である。 「人は皆死ぬ」という普遍的原則から出発して、「哲野イサクは人である。」従って「哲野イサクは死ぬであろう。」という間違いのない結論を引き出す。この場合「人は死ぬ」という絶対間違いのない「真理」から正しい推論を導き出している。 これに対して帰納法は個別事実から出発して普遍的真理や原則を導きだすアプローチである。「ソクラテスという人は死んだ。」「プラトンも死んだ。」「アリストテレスも死んだ。」だから「人は皆死ぬのである。」という普遍的真理を導き出す。 ECRRの方法論(アプローチ)は徹底的に帰納法である、とECRRは主張している。従って個々の事実を見つけ出すことが最重要になる。個々の事実関係を発見する事に失敗すれば、それは当然その結果として普遍的真理や事実の発見などということはできなくなる。 そうした帰納法というアプローチを採るECRRにとっての最大の武器の一つは「疫学」である。もちろん実験も大きな武器になるが、低線量内部被曝はその性質からして実験室の実験には限界がある。一つには対象がヒト集団であること、次には20年、30年という長期にわたる夥しい数の実験対象が必要であるからだ。 (ICRPのアプローチが演繹的であることは認めるにしても、ICRPが演繹法を採用しているという主張は私には認めがたい。というのは厳密に言ってそれは演繹法ではないからだ。演繹法を採るなら、絶対真理や原則から出発しなければならない。ところが広島や長崎の生存者調査(LSS)から導き出した原理・原則、すなわち「電離放射線は一時に大量に浴びない限り人体に大きな健康損傷はない」はいまだに仮説である。まだ普遍的な原理にはなっていない。もし真面目な演繹論者であれば自らの仮説が普遍的真理であることの証明に全力をあげるであろう。ところが、ICRPはこの仮説が真理であることを全力をあげて証明しようとしていない。ばかりか、その仮説が真理でないことを傍証するかもしれない事実関係に目をつぶっている。ICRPの方法論は演繹的だ、というのは褒めすぎだろう。) ECRRにとって疫学的アプローチが決定的に重要になる。実はICRPもこれまで取ってきた方法論は徹底的に疫学である。前出のABCC=放射能影響研究所(放影研)の永年の研究、「LSS」自体も「疫学」の産物である。同じ「疫学」を使って、同じテーマ、すなわち「電離放射線の低線量被曝」を扱ってなぜこうも違う結論がでてくるのであろうか? |
||||||||||||||||
| 政治的・経済的バイアスのかかりやすい疫学 | ||||||||||||||||
それは恐らくはECRRとICRPは同じ「疫学」を手法として使ってもその扱い方が違うからであろう、ICRPの使ってきた「疫学」は恣意的であり科学的でない、というのが、第8章「低線量における健康影響の確立:疫学」の主要テーマの一つであり、ECRRからのICRP批判の論点である。 それではそもそも疫学とはどんな学問なのであろうか?日本語ウィキペディア『疫学』は次のように言う。『えきがく(Epidemiology)は、個人ではなく、集団を対象とした、疾病の秩序ある研究である。疫学は、病気と怪我の頻度、そしてその分布に影響する因子を対象とする。ただし、「集団を対象にする秩序ある研究」という部分以外については諸説あり、国際的な合意は得られていない。医学部、教育学部や経済学部等の幅広い学生に勉強されている。手法として統計学を多用する。』 ごく簡単に言って「疫学」とは「統計学」の医療分野への応用なのだ。しかし前出日本語ウィキは『疫学は疫の字に病垂(疒)が付くため医学であると誤解されているが、英語ではEpidemiology(epi; upon広範な -demos; people人間の -logos; study学問)と書き、人間集団に対するあらゆる因果関係の確認に用いられる学問である。』とも述べ、対象分野は医学とは限らないとしている。しかしここでの「疫学」の理解は、「電離放射線の人体への影響」という分野に限定して差し支えない。 ECRRは疫学を次のように定義している。 『疫学とは、ヒトの集団における疾病の分布と要因とに関する学問である。疫学の重要な側面は、実験的であるよりも観察的であるので、データから導かれる推論にバイアス(bias)や混乱が起こる可能性のある領域で仕事をしなければならないということである。』(第8章第8.1節「証拠と推論」:ブラッドフォード・ヒルの規範 -日本語テキストp74。ページ表示は以下同じ) ECRRのいうように疫学は実験に依存するよりも観察に依存するので、その解釈は場合によれば幅広く多様である。そこに疫学的アプローチの難しさがある。 ともあれ疫学的アプローチは、統計学的手法を採用するということと哲学や社会学など幅広い学問分野の支援を必要としているということを理解しておこう。またこの第8章の文脈から言えば、 『研究に選択的なバイアスがかけられ、または、ある結論を見出すかあるいは見出さないかを方向づけられさえするかも知れない分野である。加えて、全ての研究は、文化や雇用、あるいは政治的な圧力を含む理由によって反対の意見を持つグループからの、少なからぬ批判の対象になることもあるだろう。本委員会は、公表論文や論説記事の中に、これら3つすべてバイアスの機構についての証拠を見出してきている。』(p74) ことへの理解も重要であろう。 そして、 『放射線と健康とについての全ての疫学研究から結論を導くに際して、本委員会はその研究の出所と、特に、その研究に資金を提供している団体や研究者にあると見込まれる方向性のバイアスを、非常に注意深く考慮している。』(p74) つまり疫学研究においては、純粋医科学的というよりも、哲学・社会学・政治・経済など様々な立場から、利害関係も絡みながら、バイアスがかかりやすいということだ。 これは、わかりやすく言えば原子力利益共同体を支持・発展させるための研究には金が出るが、そうではない研究たとえば「低線量内部被曝は危険」であるとか、低線量被曝による健康影響などの調査や研究には金が出ないなどの世界的な風潮をさしている。 |
||||||||||||||||
| ブラッドフォード・ヒルの規範 | ||||||||||||||||
さてこうした純粋医科学以外のバイアスを排除するためには、疫学研究には、手堅いプロセスが必要であるが、オースティン・ブラッドフォード・ヒル(Sir Austin Bradford Hill)が示した手順がとりわけ価値がある、ECRR勧告はいう。 この手順は「ブラッドフォードの規範」と呼ばれるものである。 ここでブラッドフォード・ヒルに深く立ち入るつもりはないが、英語Wikipedia「Sir Austin Bradford Hill」によると、
その規範の第一は「統計学的有意」である。簡単にいってしまえば、その結果が「偶然」ではなく、統計学的にみて必然の結果であることの保証である。
一般論で言えば、科学的に見て有意といわれる水準は過誤発生の確率は5%未満(p<0.05)である。しかし―。
ところで、疫学的(統計学的)結論が、「有意」であるかないかを検証する手続きは、「仮説検定」(hypothesis testing)と呼ばれている。 若干煩雑だが、「仮説検定」について理解を深めておきたい。先にも述べたように疫学(その手法は統計学である)は常に誤りを含む危険性がある。 この誤り(過誤=error)は大きく分けて2種類になる。すなわち―。
第8章はこの「第2種の過誤」に対して、『放射線被曝の潜在的に危険な結果を出すという意味で特に重要となる』と注釈を入れている。 というのは低線量放射線被曝による健康損傷は、有意を示すのに十分な数(試料数)を確保できないことが多い。こうした場合「第2種の過誤」を犯しやすい。ヒルはこうした「統計的に有意でない」場合、「第2種の過誤」をできるだけ避けるために、「無罪(not guilty)」(イングランド法)とするよりも、「証拠不十分(non-proven)」(スコットランド法)と考えるべきだ、と主張しているという。 このことが重要なのは、「低レベルの放射線被曝が健康に危険がある、という証拠はない」という言い方がいつのまにか「低レベル放射線被曝は健康に危険はない」という言い方にすり替わっているからだ。 |
||||||||||||||||
| 新しきい値論と食品安全委員会での議論 | ||||||||||||||||
ICRP派学者は、冒頭に紹介したように、「実効線量100ミリシーベルト以下では健康に害があるという科学的証拠はない」という主張をしているわけだが、それがいつの間にか「実効線量100ミリシーベルト以下の被曝は健康に害がない」という主張にすり替わっている。これは生涯実効線量100ミリシーベルトを「しきい値」とする「新しきい値論」に他ならない。 ここで指摘されていることは、決して抽象的な医科学論争なのではない。「フクシマ放射能危機」に直面して、内部被曝発生の最大の危険は放射能汚染食品摂取にあると考えている現在の日本の汚染食品規制に関する議論の中でも堂々と出てくるのだ。 「3.11」発生を受けて日本の厚生労働省はただちに放射能汚染食品の介入限度値(厚労省の言葉では暫定規制値)を設定する。しかし「暫定」の言葉が示すように日本の法体制に則った決め方ではなかった。放射能汚染食品の規制は内閣府の食品安全委員会のリスク評価を受けて、厚労大臣の諮問機関である薬事・食品衛生審議会に諮問しその答申を得てリスク管理機関である厚労省が放射能汚染食品の介入上限値(規制値あるいは基準値)を決定しなければならなかった。しかし2011年3月17日厚労省が発表した暫定規制値はこうした手続きをすっ飛ばしたものだった。(「放射能汚染された食品の取り扱いについて」厚労省<http://www.inaco.co.jp/isaac/kanren/24.html>参照のこと)厳密には違法状態である。 この違法状態を解消しようと厚労省は、内閣府の食品安全委員会に放射能汚染食品に関するリスク評価を依頼する。食品安全委員会は「放射性物質に関する緊急とりまとめ」を2011年3月29日に急きょ発表し、「暫定規制値」の違法性を緩和しようとした。(<http://www.inaco.co.jp/isaac/kanren/24.html>)しかし、「緊急とりまとめ」も正式な審議を経たものではないので違法性は根本からは解消されない。そこで食品安全委員会は、「放射性物質の食品健康評価に関するワーキンググループ」をスタートさせ、4月21日から会合を重ねた。会合は終始厚労省の官僚が描いたシナリオ通り進んで、9回まで重ねた。第9回会合では「評価書(案)食品中に含まれる放射性物質」も準備されており、ここで幕引きの意図がありありだった。(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/fukushima/foods/20110726_sfc9_hyouka.pdf>) 勢い第9回会合は、この「評価案」を承認する儀式の様相を呈した。この評価案は生涯被曝線量100ミリシーベルト以下では健康損傷に関する科学的データは見当たらないとし、食品による被曝を年間1ミリシーベルト以下に抑えるべきだとしている。そして次のように述べる。
この文言に対しておずおずと異議を唱えたのは、国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究部長の津金昌一郎(専門委員)である。津金は言う。
これに対して座長で、東北大学大学院薬学科教授の山添康は「なにをいまさら」という感じで次のように言う。
なおも津金は食い下がる。
と述べる。要するに津金の言うところは、100ミリシーベルト以下で健康損傷を示す科学的データはない、という言い方が100ミリシーベルト以下は安全である、リスクはない、という言い方に変わる恐れがある。100ミリシーベルトが「しきい値」のように受け取られる恐れがある、ちゃんと「放射線被曝はゼロでなければ健康リスクはゼロにならない、その上で、100ミリシーベルトを基準とした、と明記すべきだ、と言う点にある。ICRP学説を信奉する科学者も含め、誰しも異論のないまっとうな議論だろう。 |
||||||||||||||||
| 農林省通知の悪のり | ||||||||||||||||
ところがリスク管理機関であるはずの厚労省にとってこの表現は甚だ都合が悪い。というのはいったん決めた介入値(基準値ないしは規制値)は「危険の下限値」であって、それ以下は安全値である、という印象を強く残したい。 「風評被害」という言い方もここから生まれる。暫定規制値は「食品1kgあたり500Bq」だった。これは本来これ以上は危険だという介入値である。決して危険の下限値ではない。ところが、リスク管理機関であるはずの厚労省や農林省はこれを下限値だと思わせたい。つまりこれ以下は安全だと思わせたい。彼ら自身は口が裂けてもこれが安全値だといわないが、そう思うようにし向けている。だから規制値以下の食品は本来安全だが、危険とみなされて売れない、すなわち風評被害だ、という言い方が生まれることになる。これを大手マスコミを使って大々的に全国に宣伝をする。ついには「福島産品を積極的に食べて復興を応援しよう」などというキャンペーンが生まれてくる始末だ。津金の言うように「放射線被曝はゼロでなければ、健康リスクはゼロにならない。介入値は危険の下限値ではなく、これ以上は目に見える危険が生ずる介入値だ」と一言明記し、このことを全国に周知徹底することが本当の「放射線防護教育」である。 この食品安全委員会の「評価」を早速盾にとって、全国の食品関連業者に圧力をかけたのが農水省である。放射能汚染食品の「新基準値」が実施されたのは2012年4月1日である。農水省は、実施後の4月20日「食品中の放射性物質に係わる自主検査における信頼できる分析等について」(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/fukushima/foods/20120420_maff.pdf>)という通知を全国の食品関連業者に農林水産省食料産業局長で出し、独自基準による食品検査をおこなわないようにとする極めて悪質な介入をおこなった。中で次のように言う。
ここでいう基準値は実際にはこれ以上は目に見えて危険とする介入値なのだが、農林省は食品安全委員会の「評価書」を盾にとって、これは安全値であると強弁している。そしてこれを下回る基準をもつ自主基準は「過剰な規制」と断じている。 ECRRがその勧告第8章で指摘する「第2種の過誤」は疫学につきものの過誤であるが、ICRP派の学者はこの「第2種の過誤」を意図的に利用しているという好例だし、これは決して単なる学問上の論争なのではなく、実際に私たちの実生活に直接影響を及ぼしている、意図的・悪質な「過誤」なのである。 |
||||||||||||||||
| 過誤防止の2つの決定 | ||||||||||||||||
こうした「過誤」を防止するために、ECRRは次の2つの決定をおこなった。 第1は「予防措置のアプローチ」である。わかりやすく言えば、仮にそれが過剰なリスク評価であっても、その過剰なリスク評価によって人類に直接害を及ぼすことにはならず、「第2種の過誤」も防止しうる。 第2の決定は、そのリスク評価の信頼性の精緻化(向上)のために「ベイズ理論(Bayesian Approach)を導入するということだ。ベイズ理論(ないしはベイズ主義)は統計学の頻度主義に対抗する考え方だ。日本語ウィキペディア「ベイズ確率」は、
という説明をおこない、また次のような例題も引いている。
頻度主義を取る統計学では、100万年前に火星に生命が存在したかどうかは仮説として棄却せざるを得ない。しかしベイズ主義ではこれは十分にありそうな仮説として扱う。そしてその確率を計算することができる。 低線量被曝については、それが細胞損傷であり、細胞そのものの研究が現在急ピッチで進められていることを考えればわかっていないことが余りにも多い。この場合頻度主義では「損傷がある」とすることは仮説にもならないが、ベイズ主義では十分仮説として成立することになる。私は、予防という観点から見てこの分野の疫学の基礎にベイズ主義を導入することは妥当以上のものがあると思える。 疫学的アプローチに関して、第8章は「リスク因子と疾病の間には強い関連性(因果関係)があるべき」、その「関連性(因果関係)は異なる状況においても繰り返し観察されるべきである」、またその関連性は「特異的(specific)であるべき」、その特異性は「可逆性と結びついているべきである」と主張している。特異的であることが可逆性と結びついているべきと言う主張は、たとえばその原因の特異性が除かれれば、疾病は発生しなくなる(可逆的)などいうことを意味している。どれもこれも疫学研究は必須の条件とは思えるが、現実的には「低レベル放射線障害」の世界においては、明確にこれら特徴が現れることは少ないと思える。「低レベル放射線障害」の世界では、すでに疫学的アプローチは限界に達しているのではないか。この世界で特に有効性を発揮するのは、分子生物学的(細胞学的)アプローチや、ベラルーシのバンダジェフスキーが試みたような病理学的アプローチではないかと思える。 |
||||||||||||||||
| 奇形も流産すれば「奇形」とカウントされない | ||||||||||||||||
次に興味深いのは第8章2.6節で「生物学的勾配(biological gradient)」を取り上げていることだ。
たとえば、ICRPの仮説「直線しきい値なし理論(LNT)」は全くそのような理論である。被曝線量100mSv以上の世界で当てはまった科学的知見を、線量が小さくなれば、応答(たとえば“がん”の発生)も小さくなるはずだとしてそのまま100mSv以下の世界へ直線的に延長した仮説だ。この仮説が正しいのかどうか、一度も検証されていない。従って仮説は仮説のままとどまっている。分子生物学的なアプローチで、そうではないという事実が出ても、それは放射線被曝との直接の因果関係が証明されていないとしてその事実そのものを認めていない。従って「LNT仮説」は仮説のまま止まっている。 しかしこれは(LNT)は必ずしも真実ではない、と第8章はいう。その例として出生時奇形(birth malformation)をあげる。
つまり流産することになる。ベラルーシのバンダジェフスキーは、2003年スイス・メディカル・ウィークリーに発表した論文『子どもたちの臓器におけるセシウム137の慢性的蓄積』の中で次のように述べている。
こうして、胎児は奇形の危機にさらされる。バンダジェフスキーは病理学的研究の結果、胎盤が食い止められるセシウム137の限度を胎盤1kgあたり100Bqと述べている。これらセシウム137は母体中の血液から胎盤に蓄積されたものだ。 実際には何が起こるかというと、出産前に奇形が判明するのでバンダジェフスキーがいうように妊娠中絶するのである。話は変わるようだが、ICRP派の学者はこうした、奇形や妊娠中絶をチェルノブイリ事故による放射線影響と全く認めていない。 例えば、2012年5月17日、広島で開かれた「第66回 日本口腔科学会学術集会」に関連して開催された「市民公開講座 放射線災害復興の道―広島、長崎から福島へ-」の中でシンポジストとして講演した長瀧重信は次のように述べた。
長瀧は国連科学委員会、WHO、IAEAがそれぞれ独立した調査をおこなった機関のように描いているが、実際には同じ報告がぐるぐると回っているだけだ。長瀧自身ICRP派の大物の一人で、放射線影響研究所(放影研)の理事長、これも核利益共同体の牙城、日本アイソトープ協会の常務理事をそれぞれ長く務めている。 ICRP派の学者は、たとえばこのバンダジェフスキーの病理学的研究は「誤謬」として歯牙にもかけていない。といって正面切った科学的批判をするわけでもない。 話を第8章に戻す。 放射線の影響で奇形となった胎児はさらに増大する放射線の毒でついに死に至る。(現実には多くのケースで人工流産または妊娠中絶がおこなわれた)この線量では、従って奇形の数は上がらない。単に出生率(birth rate)が低下するだけだ。ウクライナ、ベラルーシでは少なくとも妊娠中絶と共に生児出生が激減した。 (<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/genpatsu/ukraine1.html><http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/genpatsu/ukraine2.html>を参照のこと)
従って線量応答関係は決して直線には現れない。さらに放射線に傷ついた細胞が示す放射線に対する「二元的感度(dual sensitivity)」や「2相的(biphasic)な」応答反応を考慮すれば、少なくとも低線量で応答が直線的に現れる、などということは厳密に見て考えられそうにない。
ここで「誘導細胞」といっているが、これはなんのことか私にはわからない。普通誘導細胞(induced cell)というと、ES細胞やその他の幹細胞から分化させた細胞のことを指すと思われるが、この場合そうではないだろう。恐らくはバイスタンダー効果で見られるように、放射線攻撃を受けた近辺で異常を起こした細胞のことを指すのではないか?そう理解すると文意は通じるが・・・。 |
||||||||||||||||
| 生物学的妥当性 | ||||||||||||||||
第8章2.7節は、疫学的研究において「生物学的妥当性」の必要性を論じている。勧告はブラッドフォード・ヒルの次の言葉を引用して、このことの必要性を論じている。
例えば「フクシマ放射能危機」に遭遇して鼻血を出す人が非常に多く出ている。私の身の回りにも多い。鼻血を出すことと低線量放射線影響の直接の因果関係はなかなか科学的には論証できない。鼻血を出す理由は数十通りの理由が考えられるからだ。しかし多くの人が「フクシマ放射能危機」との関係を疑っている。いわば経験的な状況証拠があるからだ。こうした場合、もし妥当性があると考えられれば、この可能性を捨て去るべきではない。
すなわち今は「鼻血」と「フクシマ放射能危機」との因果関係について、科学的に論証できないのは、まだ分子生物学(細胞学)が未発達だからだと考える事もできる。
ICRPの仮定する直線的応答関係(LNT理論)はどちらにせよ、特に低線量内部被曝においてはいかにも成り立ちそうにない。分子生物学(細胞学)においてはゲノムの不安定性(genetic instability)やバイスンダー効果(bystander effect)など徐々にではあるが、細胞の世界が判明しつつある現代においては、これら細胞の複雑で、動的な様々の応答関係をうまく説明できない。20世紀ならいざ知らず、21世紀の今は非科学的と言わざるをえない。 |
||||||||||||||||
| 怪しい1mSvのリスクと動物実験 | ||||||||||||||||
そして話は疫学の放射線学への応用(放射線疫学-radiation epidemiology)へと移っていく。
ICRPは1Svについて5×10-2のがんによる過剰死を想定している。すなわち、平均1Svの被曝を受けた100人の集団のうち5人はがんで死ぬ、という計算だ。したがって平均1mSvの被曝では、その1/1000、すなわち10万人のうち5人はがんで死ぬという計算になる。これは預託線量で計算すると、1mSvに被曝した2万人が70年間の寿命期間で、1人だけがんで過剰死することを意味している。 この考え方に従えば、異常に高率となったがんの発生や核施設の付近に住んでいる人たちの間で発生するがん、あるいはICRPが計算する「低レベル放射性物質」に被曝させられた人の間で発生するがん、こうした健康損傷は、放射線の影響ではない、何か他の原因だとして、放射線被曝の結果とみなされない。 疫学というのは常に誤りを含んでいるものである。その誤りは、冒頭示したように、第1種の過誤と第2種の過誤に分類される。こうした過誤を防止するため、さまざまな無謬検定がおこなわれるのであるが、ICRPは「1mSvで5×10-5の致死がんリスクを予想」するという疫学上の結論を検定する努力は一切なされていない、とECRR勧告第8章は指摘している。 低レベル放射線被曝の健康影響を調査研究する際に、最も有効な手段の一つは「動物実験」である。ここでも一定程度疫学的アプローチを使わざるを得ない。しかし動物実験の結果がただちに人間のケースに当てはめられる(外挿)ものではないことは明らかだろう。 ECRRは、動物実験をヒトに外挿するに際して、3つの留保条件を設定している。
動物実験はある意味ICRP派学者・研究者のお家芸である。夥しい動物実験の研究報告がある。たとえば、放射能汚染食品のリスク評価を行うため、2011年4月から7月まで9回にわたって開かれた内閣府食品安全委員会の「放射性物質の食品健康評価に関するワーキンググループ」で厚労省の官僚が用意した資料の中にも数多く動物実験の結果が「リスク評価資料」として提出された。第4回会合で提出された「放射性セシウム知見とりまとめ(案)」(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/fukushima/foods/20110525_sfc4_Cs.pdf>)をみても「溶解性の137Cs(塩化セシウムとして)を単回経口投与されたモルモットで、セシウムの速やかな吸収と広汎な分布が報告された。(Stara 1965)。137Cs及び他の放射性元素を含む極めて不溶性の使用済燃料粒子(平均直径0.93 μm)を単回経口投与されたラットでは、137Csの吸収は10%未満であった(Talbot et al. 1993)」、「セシウムは動物の胎盤も通過する。また、乳汁でも認められる。放射性標識した塩化セシウムを妊娠動物へ経口投与後、ヒツジの新生児では母動物より組織中134Csレベルが低いことを示した(Vandecasteele et al. 1989)。哺乳中の児動物の134Cs濃度は最終的に母動物を超えた。」、「放射性セシウムに急性経口曝露した動物の死亡に関する研究は見つからなかったが、8 64~147 MBq/kg(1.7~4.0 mCi/kg)の有害な初期体内負荷量となる量の137CsClを単回静脈内投与された若い成体ビーグル犬で、生存率の低下が観察された(Nikula et al. 1995, 1996)」など夥しい数の動物実験の研究が盛り込まれている。しかし、ヒトへの影響で、解剖病理学的な知見は一切報告されていない。
要するに、信頼できる疫学データを示すにはあまりにもサンプル数が少なく、また研究機関も短い、という批判である。
ヒトに関する低線量被曝のデータが数多くあるにもかかわらず、ICRP派の学者・研究者は動物実験に依存し、自分に都合の良いデータを報告し、安易にヒトに外挿する傾向にある。この「動物実験」と題する節はそうした傾向に対する警告と読めないこともない。 |
||||||||||||||||
| 『間違った線量』と『間違った参照集団』 | ||||||||||||||||
この章の最後は、チェルノブイリ原発事故で多くの胎児が「胎内被曝」に遭遇し、それによって6カ国で、小児白血病が増加したこと、これらは低レベル放射線被曝の結果であること、従ってICRPのリスクモデルは信頼できないこと、またこうした疫学研究が間違いであることはあり得ないことを主張し、ICRPによって公表された疫学研究が陥っている過誤を種別ごとに分類し一覧表にしている。煩雑かも知れないがそれをやや丁寧に見ておくことにしておきたい。というのはここをしっかり理解しておけば、ICRP派学者の科学的外観に隠れたトリックは容易に見破れるだろうからだ。 表8.1 「公表された放射線リスクの疫学研究にある過誤」 1番目のカテゴリーは『間違った線量』。『研究は一貫して測定あるいはモデル化された外部線量を共変原因として用いており内部線量をそれに包含させている。もしも後者(内部線量)がより危険なものであればその結果から確かな結論は導けない。』<“Studies invariably use measured or modelled external dose as the cause covariate and subsume internal dose within it. If the latter is more hazardous no safe conclusions can be drawn from the results.”> 外部被曝と外部被曝について特にその区別をつけないのがICRP学説の大きな特徴である。外部・内部合わせた総線量を問題にし、その総線量で健康損傷をおしはかる。ここで問題としているケースで私などがすぐ思いつくのは、ICRP派の代表的な疫学研究、「広島。長崎の原爆生存者寿命調査(LSS)」であろう。LSSでは、放射線被曝の損傷は「ガンマ線と中性子線」で生じたとする。そして線量推計体系(DS86やDS02など)を元にして、原爆被爆者の被曝線量を特定していく。爆心地付近ならともかく、爆心地から半径2km以遠で、中性子線やガンマ線による重篤な放射線障害が発生するというのは考えにくい。従って爆心地から同心円状に放射線障害はその重篤度を薄めていくはずである。ところが実際にはそうならなかった。残留放射能やフォールアウト(いわゆる黒い雨)で内部被曝した被爆者の中には、爆心地から5km離れていても2km圏内にいた被爆者より重篤な症状を示したものも多かった。LSSは「間違った線量」の代表例である。 2番目のカテゴリーは『間違った参照集団』。疫学では研究対象集団と参照集団を調査し、比べることで有意味な結論を引き出そうとする。ある被曝集団の健康影響を調査する時、当然その参照集団は全く被曝していなければならない。ところがしばしば、参照集団も被曝している。これでは精確な疫学的結論は出てこない。第8章では3つの例を挙げている。
「2.」の例で予想されまた懸念されるのは、「フクシマ放射能危機」でもまた同じ手口が使われるであろうことだ。放射能汚染がきれいに同心円状に広がっていくなどと言うことはおよそ現実的ではない。福島のある研究集団の参照集団を同じ福島や近辺のやはり放射能汚染をしている地域から選んではならない。
|
||||||||||||||||
| 間違った仮定 | ||||||||||||||||
次のカテゴリーは『間違った試料』。2つの事例をあげている。
このケースについては私は不勉強で何も知らない。NRPBは英国放射線防護局(National Radiological Protection Board -NPRB)。1970年の「放射線防護法」( the Radiological Protection Act)によって設立された。この時は電離放射線関する研究・調査を行い、その防護について政府関係機関に対する意見具申を行うというものだった。アメリカにおけるNCRP(アメリカ放射線防護審議会)とほぼ同様な役割を担っている。
第4のカテゴリーが『間違った仮定』。
これまで論じてきた中でも最大の誤謬の一つ。放射線に対する感受性の違いやさまざまな細胞間応答によって、特に低線量域では直線比例的な影響がでるはずがない。結局、現実をこのLNT仮説に無理に押しはめることによって、放射線影響を過少評価することになる。
誘導放射線抵抗性、または「放射線抵抗性の誘導」とは低線量の放射線を細胞に照射すると、あるいは前照射すると、高線量照射をおこなっても染色体異常の発生頻度が低下する現象をいう。LNT仮説では全く説明のつかない現象である。この現象は動物実験ではすでに確認され定説となっているが、ヒトには適用されていない。このことはLNT仮説が「間違った仮定」であることを強く示唆している。ICRP派の学者や研究者は、LNT仮説と整合性をとろうとしているが、成功しているとはいえない。
これもICRP学派のおかしな仮定である。「100mSv以上の致死性がんが発生するリスクが高まるが、それ以下だとがんが発生するという科学的根拠はない」。いわば「100mSv新しきい値論」である。「がん」とは、細胞の老化現象である。従ってがんになる要因はさまざまであるし、その機序(がん発生の筋道)も一様ではない。細胞が「がん化」するに際して、電離放射線の影響は、「がん化」をスタートさせるきっかけとなっているかも知れないし、「がん化」の最終的なだめ押しになっているのかも知れない。少なくとも「100mSv以上や以下」が、「がん化」の何か目安になっているとは思えない。近年の「がん」に関する研究は、「新しきい値論」のような古くさい概念に基づく仮説を完全に打ち破っている。 |
||||||||||||||||
| 間違ったエンド・ポイント | ||||||||||||||||
第5のカテゴリーは『間違った方法論』。2つ事例を挙げている。
これはなんのことか全く私はわからない。
平滑化(smoothing)とは統計学においてなされる手法らしい。「連続的なデータ処理において、他のデータよりも大きく乖離しているデータを平均化、あるいは除去することにより、合理性を保つこと。」と説明されている。前出のごとく、ECRRはその疫学にベイス主義(ベイス理論)を取り入れることを決定している。ベイス主義とは未知の情報が存在するとした推論体系でもある。それを「平滑化」してしまっては、有意なデータは出てこないだろう。 第6のカテゴリーは『間違ったエンド・ポイント』である。『ICRP はエンド・ポイントとしてガンに強く焦点を当ててきている。小児死亡や分娩前後の死亡を含む、多くの他の疾病や症状については排除され続けている』 ICRPは低線量放射線被曝の健康損傷として、「がん」、「白血病」、「知能低下」しか認めていない。しかもこれは未だに仮説にとどまっている。これは低線量放射線被曝の驚くべき過少評価をもたらしている。実際チェルノブイリ事故で健康損傷を起こし死亡に至る最大の疾病は「がん」ではない。心臓病だ。それに呼吸器系障害や循環器系障害が続いている。エンド・ポイントを「がん」だとすることによって、もっと深刻な疾病を無罪放免してやっている。 第7のカテゴリーは当然のことながら『間違った結論』。『(研究論文の)結論や概要においては影響はないと主張しながら、(その論文の)表の結論や本文を綿密に検討すると、そこでは影響がるという明確な証拠を示しているような研究論文が、そこではありふれて存在している。』と第8章は述べている。 第8のカテゴリーは間違った結論や間違った仮定を支える『間違ったデータ』である。
この『間違ったデータ』については、枚挙にいとまがない。これを一つ一つ数えていくとキリがない。しかしこれは『間違ったデータ』というべきだろうか、チェルノブイリ事故後の旧ソ連政府の対応や、事故直後のIAEAの対応、アメリカ・ワシントン州ハンフォード・プルトニウム工場の工場労働者の健康に関する公衆衛生調査や疫学調査をもみ消そうとした動きを見ると『間違ったデータ』などという生やさしいものではない。明らかに『改竄』であり『ウソ』という表現が似つかわしい。 こうしてみてくると、ICRPの採用する疫学は、言葉の正しい意味での疫学ではなく、自らの信仰に合致するように意図的に歪められた疫学、というべきだろう。 |
||||||||||||||||
| (第9章へ続く) |
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||