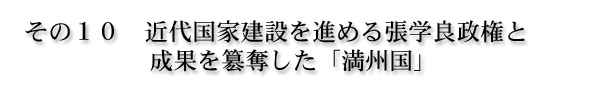|
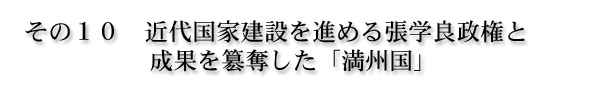 |
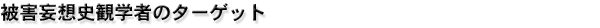 |
|
�@�O��܂łŌ������Ă������Ƃ̒��ł��������킩���Ă������Ƃ̈�́A�u�c��_�_���v�Ȃ�G���́A�c��_�����g�Ō������Ă������ʂƂ��������A�c��_���N���ɋ������܂ꂱ�Ƃ��A�e�G�ɏ����U�炵�����̂��Ƃ������Ƃ��B
�@����ł͒N���c��_�ɂ��������u�������I�ȗ��j�v���������̂��Ƃ����A�������Ă���̂́A�u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�ҁE�����҃O���[�v���낤�Ƃ������Ƃ��B���������w�ҁE�����҂́A�}�X�R�~�̈ꕔ��o�ŊE�̈ꕔ���g���āA�u���̐푈�͐����������B�v�u���{�͔�Q�҂������B�v�Ƃ����C�f�I���M�[���Љ�ɗ�������ł͂Ȃ��A���{��v�����������������Ȃǂ��ϋɓI�ɗ��p���āA�ӊO�ƍL���Љ�ɐZ�����͂��߂Ă���B
�@�Ƃ��낪�w�p�I�ɂ͔ނ�̎d���͖w�nj�������Ȃ��B���Ƃ��A�������w�������̊w�p�_���f�[�^�o���N�g�b���m�����h�i�T�C�j�C�j��http://ci.nii.ac.jp/���Ō����������Ă��ނ�̎d���͗]�茩�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��Ƃ��ȗ��j�w�҂͂킸���ɁA�`��F���炢���B
�@�܂�ނ炪�^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���̂́A���j�w���w�p�����O���[�v�ł͂Ȃ��B�G����V���ł͉X�����_����W�J���Ă���ނ�́A�w�p�����O���[�v�̊Ԃł͒��ق�����Ă���̂��B
| �i |
��ɂ͊w�p�����O���[�v��ɓw�͂��₵�Ă����ɂȂ�Ȃ��A�L���ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����_������̂��낤�B��������肵���A�����B�j |
�@�ނ�͕����Ȋw�Ȃ�h�q�ȂȂǂƂȂ����Ďd�������邱�Ƃɂ���ď\�����V���H���Ă�����B�L���ɂł��Ȃ낤���̂Ȃ�A�G������̎��M�˗��A�u���˗��Ŏ��������҂ł���B
�@���������ނ炪�A�����ƃ^�[�Q�b�g�ɂ��Ă����̂́A��̉����������Ƃ����Ɓu���{�̑�O�v�ł���B��O���オ����Ɍ����Ă����Љ�\���̒��ŁA�u�푈�v��u���\�ȓV�c���t�@�V�Y���v�ڑ̌��Ƃ��ċL�����Ă��鐢��͏��Ȃ��Ȃ��Ă����B����ł͂��������u��O�v�̋L����������ꂪ�������p�����Ă��邩�Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B
�@
�@�����������ǂ܂�Ă����㐢��̐l������A�����̒��w�E���Z������v���o���Ă݂�Ƃ����B�w�Z�ŗ��j�͏K�������A���{�j�Ō����u���a�j�v�͂قƂ�Nj삯���������B���̗��j�ɂȂ�Ƌ��t���̂��y�э��łقƂ�ǂȂɂ�����Ă��Ȃ��B����ɓs���悭�u�̎O�w���v�ɂԂ�������A�����������������������B���Z���w�ł́A���{�̌���j�͏o�肳��Ȃ��Ƃ������������B
�@������ʂ̓��{�s���́A���{�̌���j�Ɋւ���f�{�͂Ȃ��̂��B�]���Ă����́A�u���{�̌���j�v�ɂ��Ă͖��m�ł���B
�@�u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�҂������^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���̂́A�����������{�̌���j�ɂ��Ă͊�b���{�̂Ȃ��A�u���{�̈�ʎs���v�ł���B
�@�������Č����Ƃ��A���́u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�҂����ɂƂ��ēc��_�͋ɂ߂ēs���̂������݂��B�ނ��u�����q�����v������ł���A�c��_�Ƃ����L�����N�^�[�Ɣނ̒P���c�t���������A�u����ǂv�Ƃ��������ɂ҂����肾��������ł���B
�@�l���Ă����ė~�����B�ނ������́u�q�����v�łȂ���A���̎G��������قǎЉ�̘b��ɂȂ�͂��Ȃ������낤�B�A�p�O���[�v�͍ŏ�����u�c��_�_���v���g���ȁh�ɑI�Ԃ��肾�����̂��A�Ƃ��������͋��炭�Ԉ���Ă͂��Ȃ����낤�B
�@�Q�^�₪����B�c��_�̔w��̂��������w�҃O���[�v�̂��̂܂��w��ɂ́A�ǂ�Ȑ��͂�����̂��H�����Ĕނ�̑_���͈�̉��Ȃ̂��H�E�E�E�E�B
|
|
 |
|
�@�c��_�͎��̂悤�ɏ����Ă���B
| �w |
�@���Ԃ͑k�邪�A�����͂P�X�O�O�N�̋`�a�c�����̎��㏈���𔗂��P�X�O�P�N�ɉ䂪�����܂ނP�P�J���Ƃ̊Ԃŋ`�a�c�ŏI�c�菑����������B���̌��ʂƂ��ĉ䂪���͒��������l���������Q�U�O�O���̕����������u�b�a���̌����i�`��F�A������w�o�ʼn�j�v�B�܂��P�X�P�T�N�ɂ��͐��M���{�Ƃ̂S�����ɂ킽����̖��A�����̌�����������āA������ΉQ�P�ӏ��̗v���ɂ��č��ӂ����B�������{�̒����N���̎n�܂�Ƃ������l�����邪�A���̗v�����A�̐A���n�x�z����ʓI�ȓ����̍��ۏ펯�ɏƂ炵�āA����قǂ������Ȃ��̂Ƃ͎v��Ȃ��B��������x�͊��S�ɏ�������y�����B�������S�N��̂P�X�P�X�N�A�p���u�a��c�ɗ�Ȃ������ꂽ�������A�A�����J�̌㉟���őΉQ�P�����̗v���ɑ���s�����q�ׂ邱�ƂɂȂ�B����ł��C�M���X��t�����X�ȂǂȂǂ͓��{�̌��������x�����Ă��ꂽ�̂ł���B�u���{�j���猩�����{�l�E���a�ҁi�n������A�˓`�Ёj�v�B�x |
�i����Ǔ_�A�J�b�R�̎g�����Ȃǂ͂o�c�e�����̃}�}�B�j
�@��̉���_���悤�Ƃ��Ă���̂��s���ȕ��͂ł��邪�A������c��_���������܂ꂽ���Ƃ𖢏����̂܂������������낤�B
�@��ɂ���Ă������ԈႢ������B
�@�c��_�́A�u�`�a�c�����v�̌��ʂƂ��Ă̖k���c�菑�i�c��_�͋`�a�c�ŏI�c�菑�A�Ə����Ă��邪�P�X�O�P�N�X���̋c�菑�͖k���c�菑�ł���B�j�Ɋ�Â��ē��{�͒��������̂�����A����́u�N���v�ł͂Ȃ��A�Ƃ��������̂�������Ȃ��B
�@�w���ɂ�钓���͐N���ł͂Ȃ��x
�@����͂��̃V���[�Y�̖`���ł��������u�k�فv�ł���B
�@�`�a�c�^���i�`�a�c�����j�́A�A�w���푈�ȗ��N���������Ă��������l�́A���A���n�^���������B���̔��A���n�^�����̌R���͂̑O�ɋ����������A�����ꂽ��u�k���c�菑�v�������B�u�k���c�菑�v���̂��̂��A�N���̌��ʂȂ̂��B������A���̋c�菑�̓��e�������ɂƂ��Ă͋��J�I�ȓ��e�������B��ȍ��ڂ����o���Ă݂Ă��A���̂��Ƃ��ł���B
| �E |
�������v�X���W�O�O�O�����̔������B
�i����͓����������{�̔N�ԍΓ��̂P�O�{�ȏ�ɂ�����B�j |
| �E |
�ŁE���łȂǍ��Ǝ匠�ɑ�����ېŌ��E���Ō��̎�����̔��D�B |
| �E |
�O�������ʋ��ݒ肵�āA���O�@���n���ݒ�B |
| �E |
�������̊l���B |
�@������u�k���c�菑�v�����邩��N���ł͂Ȃ��A�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�k���c�菑�̓��e���̂��u�N���v���������Ƃ𗧏��Ă���B |
|
 |
|
�@�u�Q�P�ӏ��̗v���v�Ɏ����Ă͂����Ɣ����e���B
�@�@����œc��_�͉������������̂��Ƃ����ƁA�u�Q�P�����̗v���v�́A���鍑��`�I�N�����s���Ă��������Ƃ��Ă͂��قǖ����ȗv���ł͂Ȃ������A�����Ƃ��b�������̖����ӂ����A�����N���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@�c��_�����g�Łu�Q�P�����̗v���v�ɂ��Č��������Ƃ͎v���Ȃ����A���炭�N���ɋ������܂ꂽ���Ƃ𒆓r���[�ɏ������̂��낤�B��̓c��_���g�́u�Q�P�����̗v���v���̂�ǂ��Ƃ��Ȃ����낤�B
�@�܂�ނ͂��̎����{�������ɑ��ĂȂɂ�v�����A���̌��ʂ��ǂ��Ȃ��������S���킩���Ă��Ȃ��B����͍\��Ȃ��B���͓c��_�����E�h�E�X�s�[�J�[����Ɏg���A�c��_���g���������Ă��Ȃ��u���j�F���v���A���̑_���Ƌ��ɓ��{�̎Љ�ɂ�܂���A���ꂪ�b�̂悤�ɒ��a���Ă������Ƃ��B
�@�C���^�[�l�b�g�œ��{��S���̓ǂ߂�T�C�g�͍��̂Ƃ���Ȃ��B���{��v�����������������ł��u�ΉQ�P����v���v�̍��ihttp://ja.wikipedia.org/wiki/�Ή�21����v���j�͔��ɂ킩��ɂ������e�ƂȂ��Ă���B
�@�p��v�����������������ł͓��{��Wikipedia�����͂邩�ɉȊw�I�ȋL�q���Ȃ���Ă���B���ږ��́uTwenty-One Demands�v(http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-One_Demands )�@�܂��uFirst World War.com �v�Ƃ����T�C�g�ł͉p���������̂Q�P�����̗v�����̂��̂��p���S���e�L�X�g�œǂ߂�B�ihttp://www.firstworldwar.com/source/21demands.htm�j
�@���́A���x�����p���Ă����g�V���u�����ߌ���j�v�̂o�V�U�\�o�V�V������p���邱�Ƃɂ���B�u�Q�P�����̗v���v�́A�T�̃O���[�v�ɕ�����Ă���B
| �w |
��ꍆ |
�R�����v�B�R���Ȃɂ����錠�v�Ɋւ��ē��{�ƃh�C�c����������ꍇ�������{�͂��ׂď��F���邱�ƁB |
|
��� |
�얞�B�E�������Âɂ�������{�̗D�挠�B�����E��A�y�ѓ얞�B�S���̑d�،������̉����A���{�l�̋��Z�E�c�Ƃ̎��R�A�s���Y�擾���A�z�R�̌@����F�߂邱�ƁB |
|
��O�� |
�����ʌ��i�̍��فA�����i���������������̍��قƂ��邱�ƁB���̎��Y�y�э̌@����ۑS���邱�ƁB�x |
�@��L�̂����R���Ȃ̌��v�́A��ꎟ���E��킪�u������Ƃ����ɁA�h�C�c�ɑ��Đ���z�����A�����n�߁A�鍑��`���{���h�C�c����D�悵�����̂ł���B�܂����B�E�����������S���̌��v�́A���I�푈�̌��ʃ��V�A���瓾�����̂Ƃ��̌ネ�V�A�Ƃ̖���ŗ����ԂŔF�ߍ��������̂ł���B
�@����ɑ��đ�O���́u�����ʌ��i�v�i�����Ђ傤�������j�Ƃ͈�̉��Ȃ̂��B�R�������ł��Ȃ��A���B�E�����������S���ł��Ȃ��A�����ʌ��i���Ȃ������ŏo�Ă���̂��H
�@�����ʌ��i�͌��݂̌Ζk�ȕ����s�E���z�ɂ��鐻�S��Ђł���B�������Ζk�Ȃ̑�聃�����⁄�̓S�z�A�]���Ȃ��ʋ����ւ����傤���̐ΒY�����ꂼ�ꌴ���Ƃ�����̓S�|�R���r�i�[�g���B�u�����ʁv�̖��O�́u���z�v�u���v�u�ʋ��v�̂R�̒n�����Ƃ��Ă���ꂽ���̂��������B��http://www.tabiken.com/history/doc/E/E108L100.HTM���B
���̐��S��Ђ́A�����ɁA�����̋ߑ㉻���Ƃ̈�Ƃ��Đݗ����ꂽ�B���{�������ʌ��i�Ɗւ������悤�ɂȂ����̂́A�h��v���̎��A�j�ꂽ���Ђ���{�̎؊��ŕ������������ł���B�܂���{�͂��̊����ʌ��i�ɕ���������݂��������̊W���B��������͎����̎P���Ɏ��߂悤�Ƃ����Ӑ}���������킯�����A���̈Ӑ}���u�Q�P�����̗v���v�̒��̑�O���Ƃ��Đ��荞�܂��Ă������Ƃ����킯���B
�@�@�w�@��l���@�̓y�s�����B�@�������݂̍`�p�𑼍��ɏ��n�E�ݗ^���Ȃ����ƁB�x
���̍��ڂ��R�������E�u���ցv�Ɍ���b�ł͂Ȃ��B�����S�̂ɋy�Ԙb���B�����܂ňꍆ����l���܂ł����{���{�̌��t�����u�v���v�����ŁA���̑�܍��́A���{���{�́u�v���v�ł͂Ȃ��u��]�v���Ə̂����B��قǂ́uFirst World War.com �v�̉p��\���ł́A�u�v���v�́udemand�v�A�u��]�v�́urequest�v�ƖĂ���B���ƂŌ�����{���{�̍Ō�ʒ��ł������悤�Ɂu�v���v�Ƃ́A�F�߂��Ȃ���u�푈�ɑi����v�Ƃ����Ӗ��ł���A�u��]�v�Ƃ́u�푈�܂ł͂��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł������B |
|
![�����̕ی썑����_���u��]�����v](04.jpg) |
|
�@����ł͂ǂ�ȍ��ڂ��u��]�v�������̂��H�U���ڂ���B
| �w |
�@ |
�������{�͓��{�l�̐����E�����E�R���ږ���ق����ƁB |
|
�A |
�K�v�Ȓn���̌x�@����������Ƃ��邩�A�x�@�ɓ��{�l���ق����ƁB |
|
�B |
����͓��{�ɋ����������A�������ق̕���H������邱�ƁB |
|
�C |
�ؒ��E�ؓ�ɂ����{�̓S���~����F�߂邱�ƁB |
|
�D |
�����Ȃ̉^�A�{�݂ɑ�����{���{�̗D�挠�B |
|
�E |
���{�l�̕z���������F���邱�ƁB�x |
�@�����ŕ����Ȃ����˂ɏo�Ă���悤�Ɍ����邪�A����͒n�}���v���`���Ă݂�Ƃ킩��₷���B���{�������푈�Ő�����D������p�̂��傤�ǑΊ݂������Ȃ��B�܂��p�𑫂�����ɂ��Ă��嗤�ɐi�o���悤�Ƃ����I���Ȃ܂ł̐N���Ӑ}�ł���B
�@���Ɍ܍��u��]�����v�́A�������̂܂ܘb���ʂ�A�����㒆���͓��{�̕ی썑�ƂȂ�ɓ������B����ȁu��]�v����������͂����Ȃ��B
�@�܂������鍑��`�N�����ł���u�v���炵�Ă��A���I�푈�ł���Ɠ얞�B�̈ꕔ���v������ŁA��ꎟ��풆�̂ǂ������ɎR���������U�����������̓��{���A���ꂾ���̗v�����o���͍̂s���߂����Ɗ������B
�@��ł�����悤�ɑ�ꎟ���E����A�����푈���n�܂�܂ŁA�A�����J�鍑��`�哱�́u���V���g���̐��v�́A���B�ɂ�������{�̓��ꌠ�v�͏��F���邪�A���̑��́u�����s��v�́u��ˊJ���v�u�@��ϓ��v�A���Ȃ킿�ǂ������ʂȍ��̓��ꌠ�v�݂͂Ƃ߂܂����A�Ƃ������Ƃ������B
�c��_�́A
| �w |
���̗v�����A�̐A���n�x�z����ʓI�ȓ����̍��ۏ펯�ɏƂ炵�āA����قǂ������Ȃ��̂Ƃ͎v��Ȃ��B�x |
�Ə����Ă��邪�A���ꂪ���������Ǝv���A�v��Ȃ��͓c��_�₻�̔w��ɂ���u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�҃O���[�v�̏���Ȃ̂ł����āA�w�̐A���n�x�z����ʓI�ȓ����̍��ۏ펯�ɏƂ炵�āx�������̗v���͉ߑ�ŁA�u�������������v�̂ł���B�܂���߂��������̂ł���B
| �i�� |
�C���^�[�l�b�g�œǂ�ł���ƁA���X�u���O�̒��ɁA�w���̂T�������́A�������ɔ閧�����ɂ��ė~�����Ƃ����v�]�����Ă����̂ɁA������͐��M�͗ɖ\�I����Ƃ������A�s�����ȑԓx���Ƃ����B�x�ƕ��S���Ă���L�q�ɂ��ڂɂ�����B����͓������{�̎嗬�̌����F�������A���̓����̌����F�����������肻�̂܂܁A���݂̎����̗��j�F���ɂ��Ă���B
�������A�悭�l���ė~�����B����͖\�͒c���e�����X�g�̎�������ț������ł͂Ȃ����H
�@�w�@�x�@�␢�Ԃɂ͖ق��Ă���A�Ƃ������̂ɂ��O�̓o�������B���̗��Ƃ��O�͂��Ă�邼�B�x�j |
�@���ɑ�܍��́A�鍑��`�ɂƂ��Ă��d����ł���B���̂܂܂ł͒����S�̂����{�̕ی썑�ɂȂ��Ă��܂��E�E�E�B
�@�]���Č܍��u��]�v�����̖͗Ҕ��ɂ������B�]���ē��{����艺������Ȃ������B
�@�c��_�́w�����̌�����������āx�Ə����Ă���̂͋��炭���̂��Ƃ��낤�B�Ƃ����ēc��_�������܂ŗ������ď����Ă���Ƃ͓���v���Ȃ��B�u�������̌����������ꂽ�v�Ƃ����N���̎��肩�A���ɍ��荞�܂ꂽ���Ƃ������s�ǂ̗����̂܂����Ă���̂��Ǝv���B |
|
 |
|
�@�Ƃ����̂́A�c��_�̕��͑S�̂ɂ������ȁu�g�[���v�����邩�炾�B���Ƃ��A�w�͐��M���{�Ƃ̂S�����ɂ킽����̖��A�����̌�����������āA������ΉQ�P�ӏ��̗v���ɂ��č��ӂ����B�x�Ƃ����ӏ��ł���B
�@�u�ΉQ�P�ӏ��̗v���ɂ��č��Ӂv�Ƃ́A�]�肨�ڂɂ�����Ȃ��\���ł���B�u�����͂Q�P�����̈ꕔ��v�������ꂽ�B�v�Ƃ��A�u�Q�P�����̗v���Ɋ�Â��āg�u�R���ȂɊւ�����v�h�Ȃǂ��������ꂽ�B�v�Ƃ������͂��ł���B
�@�P�X�P�T�N�P����G�d�M���t�́u�Q�P�����̗v���v����T���̍Ō�ʒ��A���ꂩ��A�����ċN����A��A�̏������Ɨ������������A�܂ł����ǂ����l�ԂȂ�A�u�ΉQ�P�ӏ��̗v���ɂ��č��Ӂv�Ƃ����\���ɂ͈٘a�����o����Ǝv���B
�@����͎��̑S���̐��������A�c��_�́u�Q�P�����̗v���v�����ꂼ�ꕔ���I�Ɏ蒼������āA�ŏI�I�ɒ����Ɓu���Ӂv�����Ǝv������ł���̂ł͂Ȃ����B
�@�����łȂ���A��L�̕\���͐��܂�Ȃ��Ǝv���B
�@�m�F���Ă��������́A�����̑�܍��u��]�v�����ɖҔ��������̂́A�����Ē����⒆���l���̂��߂������̂ł͂Ȃ����Ƃ��B�����܂ł��ꂼ��̒鍑��`��������N������ɂ������āA���̑�܍��u��]�v�������傫�ȏ�Q�ɂȂ邩��ł���B
�@���{�̑�G���{�ƒ������͐��M���{�̌��͂Q�T��ɂ��y�Ƃ����B�i���֘A�������Q�P�����̗v���ɑ�����{���{�̍Ō�ʒ����Q�Ƃ̂��ƁB�j
�@
�@���̊ԗ����{�����݂��ɏ������������̂��Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B�͐��M���{�͂����Ȃ��Ƃ��A�����J�ȂǂƂ̗Ƃ��̖��𑊒k���������߂����邵�A���҂̑Ë��_�Ƃ����A��܍��u��]�v��������艺����Ƃ����_�����������B������݂�A�͐��M���{�͉��Ē鍑��`��w�i�ɂ��āA�鍑��`���{�ƌ������Ă����킯���B
�@��ɂ��́u�Q�P�����̗v���v����̏d��ȕ����Ƃ��āA�w�T�E�S�^���x�Ƃ�����喯����`�^�����N����킯�����A�w�T�E�S�^���x�ɂ����钆���l���̓{�肪�A���ڈ����������Ă���鍑��`���{�Ɍ������Ă���Ɠ����ɁA���̒鍑��`���{�Ɏ㍘�������͐��M���{�ɂ���������B���̒����l���̓{������������ڂ������͂��Ă݂�ƁA�͐��M���{�ɑ���{��́A���ė���𗊂�ɂ���p���ɑ��āA�Ȃ������ƒ����l���Ɉˋ����A����ɂ��Ȃ������̂��Ƃ����{��ł��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���Ƃ��ƒ鐭��焂�_���͐��M�����ł����Ă݂�A�͐��M�����ɐl���Ɉˋ�����p�������߂邱�Ƃ͖����ȑ��k�ł͂��������A�͐��M���{���A�Q�P�����̗v��������Œ鍑��`���{�ɑΌ�����ہA�����l���̗͂��ߏ��]�������_�́A�鍑��`���{���S�����l�ł������B
�@�鍑��`���{�́A���̌���A�P�X�S�T�N�̔s��܂ł̂ǂ̎����ɒu���Ă��A���j�����͂Ƃ��Ắu�����l���̗́v�𐳓��ɕ]���������Ƃ͈�x���Ȃ������B���ꂪ�ނ�̈�т����u����F���v�ł������B
���̑S���s���ȁu����F���v���A�ނ�鍑��`���{���S�߂Ȕs�k�ɓ����Ă����d�v�ȗv�f�ɂȂ�킯�����A���U�O�N�ȏ���o���Ă��鍡������݂�A���́u����F���v�́A�����c��_�₻�̔w��ɉB��Ă���w�ҁE�����ҕ{���[�v�́A���݂ɂ�����u���j�F���v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�u�c��_�_���v���т��������́A���́u���j�F���v���A�Ⴆ���́u�Q�P�����̗v���v�̎��́A��G���{�A���Ȃ킿�����̒鍑��`���{�́u����F���v�Ƃ������肤���ł���ƌ����_���B���Ȃ킿�u���j���������́v�Ƃ��Ă̒����l���̗͂�S�������Ƃ��Ă���B
�@���ǁA���̎����͐��M���{���A��G�d�M���{���A�Њ�Œ鍑��`�̓������ɂ݂Ȃ���A�܂������l���̗͂�S�������Ƃ��A�u���v���P����Ԃɂ͂������B |
|
 |
|
�@��ɂ��ꂽ�̂͒鍑��`���{�ł���B�鍑��`���{���A���Ƃ��Ɨv�����Ă��钆���ɂ����錠�v���A��ꎟ���E���̂ǂ������������ď��߂Ċl���ł��鐫���̂��̂ł���B���[���b�p�̐헐�����܂��Ă��܂��u�Ύ���D�_�v�ł��Ȃ��Ȃ�B�t���͐��M���{�ɂƂ��ẮA�u���v���������Β������قǗL���A�Ƃ������Ƃł�����B
�@�������āA�P�X�P�T�N�T���V���̍Ō�ʒ��ƂȂ�킯�ł���B�c��_�������Ă���悤�ɁA�u�����̌�����������āA������ΉQ�P�ӏ��̗v���ɂ��č��ӂ����B�v�Ƃ�������s���ł͂Ȃ������̂ł���B
�@���̒鍑��`���{�̏ł�Ԃ�́A�T���V���̍Ō�ʒ��̕��ʂ̒��ɂ悭�\��Ă���B
�@�Ō�ʒ��i���֘A�������Q�P�����̗v���ɑ�����{���{�̍Ō�ʒ����Q�Ƃ̂��ƁB�j�́A
| �w |
�{�N�P�����Ă��x�ߐ��{�ɐ\����Ă��ȗ��A�����Ɏ���܂ŋ��݂�₫�x�ߐ��{�Ɖ�c���邱�Ǝ��ɓ�\�L�܉���d�˂���B�x |
�@�ƁA�ꌩ���������������Ȃ��b�������Ă������̂悤�Ȉ�ۂ�^���A
| �w |
�鍑���{�̏C���Ăɑ��A�T���P�����ȂĎx�ߐ��{�̋��ւ���͑S�R�鍑���{�̘����ɔ�������̂ɂ��āA�`�i�����j�ɊY�Ăɑ����ӂ��錤������������̍�����������݂̂Ȃ炸�A�P�B�p�ҕ��Ɋւ���鍑���{�̋ꈣ�ƍD�ӂƂɑ��Ă͖w�Lj�ڂ̘J�������ւ�����̂Ȃ�B�x |
�@���͐��M���{�ɑ��ĕs�����q�ׂ�B���Ƀh�C�c����D�������v�A�u�P�B�p�v�u�R�������v�Ɋւ��Ă͑S�����݊��Ȃ������B��̂��������猩�āA�����͐��M���{�̎p���ɂ́A���R�̎x�����������ƌ��邱�Ƃ��ł��A���ꂪ�͐��M���{�ɋ��d�p������点���ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@�����œ��{���{�������Ă��邱�Ƃ́A�u�h�C�c����D�������v�ɂ��Ă��A�K���ȂƂ��ɁA�����ɕԊ҂���A�Ƃ����Ƃ���܂ŏ������Ă�����̂ɁA���̍D�ӂ��S���]�����Ă��Ȃ��B�v�Ƃ������Ƃ��B
�@�������͐��M���{�����̎�ɂ͏��Ȃ��B����������グ�����̂����~���{���₷�₷�ƕԊ҂���킯�͂Ȃ��B�����瓖�R�˂��ς˂�B
�@
�@����ɑ���A���{���{�̌������͍��݂��܂�����ɁA���������܂����B
| �w |
�����P�B�p�̒n���鏤�Ə�R������ɓ����ɉ������v�n�ɂ��āA�V���l�����邩�ׂɓ��{�鍑�̔���錌�ƍ��Ƃ̐����Ȃ炴�邱�Ƃ͌���ւ�����Ȃ�B�����Ċ��Ɉ�x�V�����Ɏ��߂���ȏ�͊��Ďx�߂Ɋҕ�����̋`���|���V�Ȃ�����炷�A�i�ĔV���ҕ����ނƂ���͐��ɏ����ɉ�����鍑�����̐e�P���v�ւ͂Ȃ�R��Ɏx�ߐ��{�̋�S��ȂƂ�����͎��ɒ鍑���{�̈⊶�ւ���\�͂��鏊�Ȃ�B�x |
�@�u�P�B�p�͎��ɏd�v�Ȓn�ł���B��������{�鍑�͎����̌��Ɣ�p�Ŋl�������̂ł����āA�{�������ɕԂ��`���͑S���Ȃ��B�����e�ɏ����Ԃ��A�Ƃ܂ł����Ă���Ă���̂ɁA���̐e�ؐS���킩��Ȃ��̂��B�v�Ƃ���������ł���B
�@�ǂ�ł��邱����̓������������Ȃ肻���ȕ��ʂł���B�Ȃɂ��u�P�B�p�v�͒����̊O�ɂ����āA���N���ǂ����ɂ����āA������h�C�c������߂��Ă�����̂��A�Ɗ��Ⴂ�������ȕ��ʂ��B
| �i |
��������G���{�̒N������ȕ��͂��������̂��낤���H�p���炵�������Ƃ���ł���B�i������Ƃ������͂Ȃ��B�j |
|
|
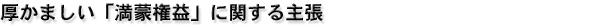 |
|
| �w |
�|���Ē鍑���{�̏C�����A���̏����ɑ���x�ߐ��{�̉ɏA�čl�ӂ���A�f�Ɠ얞�B�y�������Â̒n����n���㐭����A�������H�Ƃ̗��Q��A�鍑�̓���W��L����n�悽��́A���O�̔F�ނ鏊�ɂ��āA���W�͎��ɒ鍑���O��Q��̐�����o����ɂ��āA���ɐ[����v��������̂Ƃ��B�x |
�@�����͓얞�F�y�ѓ������Ái�������S���j�̌��v�Ɋւ��邭����ł���B
�@�얞�B�Ɠ������S���œ��{������Ȍ��v�������Ă��邱�Ƃ́A�����������łɔF�߂Ă���A�Ǝ咣���Ă���ӏ��ł���B
�@�������A���̎��_�ŁA�鍑��`���{���A���ւ̌��v�Ɋւ��āu�鍑�̓���W��L����n�悽��́A���O�̔F�ނ鏊�ɂ��āv�Ƃ����̂́A�����ɉ��ł������܂����Ȃ����H
�@�Ƃ����̂́A���̎����I�푈�ŔF�߂������̂͂���Ɠ얞�B�S���̌o�c���₻�̕����n�̑d�،��A���邢�͗����E��A�ȂǗɓ������ɂ�����d�،��ł����āA����֑S�̂Ɋg�債�A���̌��v��A�����ɔF�߂����悤�Ƃ����̂��A���I������̉ۑ�ł������������A���̈Ӗ��ŗ��������܂��A���ւт�������{�̓��ꌠ�v�͔F�߂Ă��Ȃ����������B
�@�����炱���A����𑁂��@�I�ɔF�߂����悤�Ƃ����̂��A����̂Q�P����v���̊�{���q�ł���B������A�u���O�̔F�ނ鏊�v�Ƃ����̂͌����߂��ł���B�������炷��u��Y����v�Ȍ������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�������鍑��`���{�͈ꍏ�������A���̌���ЂÂ����������B�����玟�̂悤�ȕ��͂ɂȂ�̂ł���B
| �w |
�鍑���{�͍������ɑΎx�ߐ��{��藈��T���X���ߌ�U�����ɖ����Ȃ�ɐڂ��ނ��Ƃ����҂��B�E�������ɖ����Ȃ����̂�����Ƃ��͒鍑���{�͑f�̕K�v�ƔF�ނ��i������ׂ����Ƃ���䢂��ߖ����B�x |
�@���ꂪ�Ō�ʒ��̌��тł���B�v����ɂ���ȏ㎞�Ԃ��������Ȃ��B�T���X���ߌ�U���܂łɍŏI��Ăɑ��ē��ӂ̉���z���A���������łȂ���A�w�鍑���{�͑f�̕K�v�ƔF�ނ��i������ׂ����Ƃ���䢂��ߖ����B�x�ƕ��͂ɑi���Ăł��A�F�߂����邼�A�Ɛ��ނ̂ł���B
�@���̒鍑��`���{�̋��C�A���d�p���Ǝ�鎖���ł��邪�A���͂����ł͂Ȃ��B�A�ꍏ�������������������Ƃ���A�ł�ł���B
�@�͐��M���{�́A���͂ɑi�����Ă͏����ڂ͂Ȃ��A���[���b�p����ŖZ�����鍑��`�������܂ł͌����ꂵ�Ă���Ȃ��A�����x���őS�ʓI�ɓ��{���̍ŏI�I�Ȍ������ɋ�������̂ł���B
�@�������A�u�Q�P�����̗v���v�Œ鍑��`���{���A�ŏI�I�Ɏ�ɓ��ꂽ���ʂ́A�u�鍑��`�I���ʁv�Ƃ��Ă��A�����ɂ����肪���������B
�@�����l���́u���鍑��`�����v�̖���́A����܂Ŏ�Ƃ��āA�����Ƃ����炵���I���ȐN�����J��Ԃ��Ă����C�M���X�Ɍ������Ă����B�Ƃ��낪�A���̂Q�P�����̗v��������ŁA�p���u�a��c�����S�ɃE�B���\���̂P�S�����̌����𗠐�ƁA�����l���́u���鍑��`�����v�̖���́A�͂�����C�M���X�������{�ւƌ������̂ł���B
�@����͓��{�l���̗���ł݂Ă��A�鍑��`���{�̗���Ō��Ă��A�͂���m��Ȃ������ł������B
�@�������A�����l���̗͂��ߏ��]�����Ă����鍑��`���{�́A�����l����G�ɉ��Ƃ��u�v��m��Ȃ������v�ł��邱�Ƃ𐋂ɔF�����Ȃ������B�����Ă��̔F���͂P�X�S�T�N�̔s��܂ő����̂ł���B
�@�]�k�Ƃ͂Ȃ邪�A�s��̌���A�c��_�ݏo�������{�̎x�z�w�́A�����l���̗��j�����͂𐳓��ɕ]�����Ă������Ƃ����ƁA�����͌�����B����́A�����Β�������̐��X�̌��̌����ƂȂ�A���݂������Ă���B
| �i |
�c��_�́A�w�܂��P�X�P�T�N�ɂ��͐��M���{�Ƃ̂S�����ɂ킽����̖��A�����̌�����������āA������ΉQ�P�ӏ��̗v���ɂ��č��ӂ����B�������{�̒����N���̎n�܂�Ƃ������l�����邪�A�x�Ə����Ă������Ƃ����L���̂��Ƃ��낤�B
�ŏ��A���͓c��_�����������Ă���̂�������Ȃ������B�u�Q�P����v���v�������N���̎n�܂肾�A�ƌ����Ă���l�͂܂Ƃ��ȗ��j�w�҂ł���A�܂����Ȃ����낤�B�����푈�ő�p��D�������A���邢�͓��I�푈�Ń��V�A���璆���ɂ����錠�v�����������N���̎n�܂肷��̂��A�펯�I�ȂƂ��낾�B
�������A�c��_�̒m����F�����N���ɋ������܂ꂽ���Ƃ��A�����s�ǂɔނ��������Ă���A�Ƃ������Ƃ������������A�Ȃ��ނ��������������������ł���B
�܂�A�u�Q�P�����̗v���v��A�鍑��`���{�́A�����l���̔��鍑��`�^���̖�ʂɗ��B���̌㒆���l���ɂƂ��āu����v�Ƃ́u�����v�u�R���v�Ɠ��`�ɂȂ�B�c��_�͂��̘b�������œǂނ��A�N���ɕ��������āA�����ȗ����������A����Łu����𒆍��N���̎n�܂�Ƃ������l������v�Ƃ����L�q�ɂȂ����̂��B�c��_�͓��{���u�����N�����͂��߂����Ɓv�Ɓu�����l���̖�ʂɗ��������Ɓv���������Ă���̂��B�j |
|
|
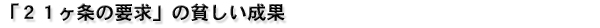 |
|
�@�Ƃ������A�u�Q�P�����̗v���v�u�Ō�ʒ��v���o�ē��{�̒鍑��`����ɓ��ꂽ�u���ʁv�̒��g�����Ă݂悤�B
�@�P�X�P�T�N�i�吳�S�N�j�T���V���̍Ō�ʍ�����A�����ȈČ��Ɋւ��ē����ԂŁA�����ɂ�鍇�ӂ��A�x���Ƃ��U���̏��{�܂łɂ͂ł��������Ă����B
| �i�� |
�Ȃ����B�͖{���u���F�v�Ə����ׂ��ł���B���F�͖{���n���ł͂Ȃ��B���F�͖��F���Ȃ薞�F�l�Ȃ�{�������O���[�v���w�����t���B���������͊��p�I�Ɂu���B�v�ƕ\�L���Ă���A���̌���������Ă���B) |
�@�����ʂɌ���Ǝ��̂P�R�{�ł���B�i�����͊O���Ȃ̌��J�������B�ԍ��͎����X�̂��߂ɂ����B�ڍׂ����֘A�������@�Q�P�������@�P�X�P�T�N�T�����Q�Ƃ̂��ƁB�j
| �P�D |
�u�R���ȂɊւ�����v |
| �Q�D |
�u�R���Ȃɉ�����s�s�J���Ɋւ�����������v |
| �R�D |
�u�얞�F�y�������ÂɊւ�����v |
| �S�D |
�u������A�̑d�؊������ɓ얞�F�S���y����S���̊����Ɋւ�����������v |
| �T�D |
�u�������Âɉ�����s�s�J���Ɋւ�����������v |
| �U�D |
�u�얞�F�ɂ�����z�R�̌@�����Ɋւ�����������v |
| �V�D |
�u�얞�F�y�������Âɉ�����S�����͊e��ʼnۂɑ���؊��Ɋւ�����������v |
| �W�D |
�u�얞�F�ɉ�����O���ږ⋳���Ɋւ�����������v |
| �X�D |
�u�얞�F�y�������ÂɊւ���������ɋK�肷�鏤�d�̉��߂Ɋւ�����������v |
| �P�O�D |
�u�얞�F�y�������ÂɊւ��������ɋK�肷����{���b���̕��]���ׂ��@�@�ߋy�ʼnۂ̌���Ɋւ�����������v |
| �P�P�D |
�u�����ʌ��i�Ɋւ�����������v |
| �P�Q�D |
�u�P�F�p�d�ؒn�Ɋւ�����������v |
| �P�R�D |
�u�����ȂɊւ�����������v |
�@�ȏ�̂P�R�{�̒��ŁA�鍑��`���{�ɂƂ��Ă����Ƃ��ً}���d�v�������̂��w�R�D�u�얞�F�y�������ÂɊւ�����v�x�������B
�@�Ō�ʒ��̒��ŁA�u���ւɂ�������{�̌��v�͒N�����F�߂�Ƃ���v�ƍ��ꂵ����G���{���������A���̖��ւɂ�����������v�����͔Րł͂Ȃ������B
�@�얞�B�S���̌o�c���ɂ��Ă��A�����E��A�̑d�،��ɂ��Ă��A���V�A�Ɛ����̏��������p�������̂ŁA���̃��V�A�̑d�؊����͂Q�T�J�N�ł���A���{�̂��̑d�؊������ƈ����p���ł�������A��L�́u���ꌠ�v�v�̊��������͂Q�T�N�������B�����炻�̂܂܂ق��Ă����Ƒd�؊������܂��Ȃ���āA�얞�B�S���◷���E��A�������ɕԂ��Ȃ��ĂȂ�Ȃ��Ȃ�B������鍑��`���{�͂��̑d�؊��������̋@��������Ƃ��������Ă����̂ł���B
|
|
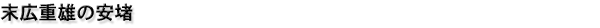 |
|
�@���̖����A���s�鍑��w�����E���L�d�Y�́A�P�X�P�T�N�i�吳�S�N�j�T���P�S���E�P�T���t���̑�㒩���V���ŁA�u�얞�F�y�������ÂɊւ�����v����������̂����͂���悤�ɂ��āA���̂悤�Ɍ���Ă���B��Ⓑ���Ȃ邩���m��Ȃ����A���p����B
�@
| �w |
�@���I�푈�̌��ʓ얞�F�͉䂪���͔͈͂ƂȂ������A�]�������������鎖�̏�Q�ƂȂ������̂���������B
�@����͓얞�F�ɉ��ėL����䂪�d��Ȍ����A���͔͈͂̍��тƂ��Ȃ�������̔���Ȃ鎖�ł������B�֓��B�i������͗ɓ������̑d�̂��Ɓj�͓��I�u�a������Ɉ˂��āA�I�����d�،����������̂ł���B�I���͍��n���E�E�E����̓�����\�ܔN�������Ƃ��āA�d���ċ������̂ł����āA�䂪���͘I���̌����𑴘ԁA�p�������̂ł��邩��A���S��\�O�N�i���P�X�Q�R�N�j�����吳�\��N�ɑd�؊��Ԃ������ƂȂ锤�ł������B
�@�얞�F�ɉ�����䂪�ő�̗��v����A�얞�F�S���y�Y�S���ɑ����A���͑����v�ׂ̈Ɍo�c�������̒Y�z�́A���I�u�a����Z���Ɉ˂��ĘI�����������̂ŁA�E�E�E�Y�S���͉^�]�J�n�̓����A�E�E�E�A�O�\�Z�N�̌�x�ߐ��{���A������x�����ĔV���������̌���������A���\�N��ɂ͑�����x��������v�������āA�x�߂̗L�ɋA���鎖�ƂȂ��ċ����B�E�E�E��������͋^�Ȃ������ċ������B
�@�X�ɓ��I�푈���䂪�����A�R����̖ړI�̈������i�����݂̒O���j��V�Ԃɕ~�݂������O�S���i��������j�́A�E�E�E�͍H�������̓����N�Z���ď\�ܔN�A�����吳�\�ܔN�i���P�X�Q�S�N�j�Ɏx�ߐ��{�ɔ��n���ׂ����̂ł������B
�@�ȏ��������Ƃ���Ɉ˂��Ė����Ȃ�@���A�֓��B�̑d�؊��Ԃ͗]���Ƃ���͂ɔ��N�A����S���͏\��N�A�얞�F�S���͓�\�l�N��Ɋ���������̂ł���B�@
�@�����֓��B�ƔV�ɕ��т��ē�̓S���̊����́A������v�����炸���ē������邱�ƂɂȂ��ċ�������A�얞�F�ɉ�����䂪���̒n�ʂ͐r���s���̂��̂ł������B
�@�E�E�E���I�푈�Ƃ�����푈���ׂ��A��]���������đQ���l�������錠�����A�ނ��ނ��Ԃ����Ƃ͍����̔E�Ԕ\�킴��Ƃ���A�D�@��ɏ悶�đd�،p���̌����ׂ��ׂ����́A�֓��B�Ĉȗ��䂪���ǎ҂����������ӂ�ӂ�Ȃ������Ƃ���ł���B
�@�֓��B����ł͂Ȃ��B�������푈�̊l���ł���얞�F�S���y����S���������Ă͂Ȃ�ʁB���ꖒ���l�����ԉ����̕K�v�������ċ����̂ł���B
�@�\�N�ڂɂ��đ҂��\�����@��͓��������B�͍��▢�\�L�̑�푈�ׁ̈A����ɓ����ڂ݂�̉ɂ��Ȃ��A�Ⴕ���̑�푈�N�炴�肹�A���͉䂪���͊֓��B�d�؊��Ԗ����̎����ɁA���̍D�@��Ȃ���������m��ʁA���ɉ䂪���͓V�C�Ȃ�Ɖ]��˂Ȃ�ʁB
�@�E�E�E���ɉ��ĉ䂪���̓얞�F�ɉ�����n�ʂ́A�ɂ߂��ł̂��̂ƂȂ����B�얞�F�ɑ���䂪�����̕s�����Ȃ��A�����W�ɑ����Q�͏������ꂽ�B�x |
�@�Ȃ�Ƃ��鍑��`�I�N���C�f�I���M�[�ނ��o���̋c�_�ł��邪�A�c��_�I�u��Q�ϑz�j�ρv�w�ҁE�����҂́A�u�������ƌ�������߂�v�悤�ȁA�k�٘_�@�����A�����Ȃ����ɂ܂��܂��Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@���L�̂��̒k�b�́A�얞�B�̌��v�����Ƃ����ꂽ���ƂɃz�b�Ƃ��Ă��铖���́A�鍑��`���{�̕��͋C���悭��\���Ă���B
�@�m���ɌR���͂Ŝ������Ė�������������̏��i�u�얞�F�y�������ÂɊւ�����v�j�ł͎��̂悤��搂��Ă���B
| �w |
���� |
���������͗�����A�̑d�؊������얞�B�S���y����S���Ɋւ��������������X�X�ӔN�ɉ������ׂ����Ƃ�B |
|
���� |
���{���b���͓얞�B�ɉ����Ċe�폤�H�Ə�̌��������݂���ז��͔_�Ƃ��o�c����וK�v�Ȃ�y�n�����d���邱�ƂB
| �i�� |
�����̌��t�Ŏؒn���̂��Ƃ����d���Ƃ��������A���{�l���y�n����A���̒n�ʼnc�ƍs�ׂ�_�Ƃ��c�ނ��Ƃ́A�₪�Ď��O�@���A�x�@���A�s�����̊l���ɂȂ���A���d���l���͏d�v�ȑ����ł������B�j |
|
|
��O�� |
���{���b���͓얞�B�ɉ����Ď��R�ɋ��Z�������e��̏��H�Ƃ��̑��̋Ɩ��ɏ]�����邱�ƂB |
|
��l�� |
���{���b�����������Âɉ����Ďx�ߍ������ƍ�燂Ɉ˂�_�Ƌy�����H�Ƃ̌o�c���ׂ��ނƂ���Ƃ��͎x�ߍ����{�V�����F���ׂ��B |
|
�掵�� |
�@�x�ߍ����{�͏]���x�ߍ��Ɗe�O�����{�ƂƂ̊Ԃɒ���������S���؊��_��K�莖����W���ƈׂ��A���ɋg���S���Ɋւ��鏔������_��̍��{�I�������s���ׂ����Ƃ�B
|
|
|
�����x�ߍ����{�ɉ����ēS���؊������Ɋւ��O�����{�ɕ����A���݂̊e�S���؊��_��ɔ䂵�L���Ȃ������������Ƃ��͓��{���̊�]�ɂ��X�ɑO�L�g���S���؊��_��̉������s�ӂׂ��B�x |
�@�܂��ɂ�����߂ŁA�O���̐��͂���ؓ����Ă����Ȃ��悤�ȋK���݂����̂ł���B |
|
 |
|
�@�����A�����̑d�،������́A��قǐS�z�������ƌ����ĕʓr�Ɍ��������i�u������A�̑d�؊������ɓ얞�F�S���y����S���̊����Ɋւ�����������v�j�����킵�A���߂̗]�n�������Ȃ��`�ŔO���������Ă���B
�@���̌��������ł͎��̂悤�Ɍ����B
| �w |
������A�d�؊����̉����͖����W�U�N������P�X�X�V�N�Ɏ��薞���ƂȂ�A�얞�B�S���ҕ������͖����X�P�N������Q�O�O�Q�N�Ɏ��薞���Ɖ����B�����̏���P�Q���ɋL�ڂ���^�A�J�n�̓����R�U�N�̌�x�ߍ����{�ɉ����Ĕ��߂���̈�ӂ͔V���Ƃ��ׂ�������S���̊����͖����X�U�N������Q�O�O�V�N�Ɏ��薞���Ɖ�����B�x |
�@��̏������łX�X�J�N�̉����A�Ƃ��������ł͕s���ł��̌��������ŁA���������̊m�F�����s���Ă���B�Ȃ�Ƃ������܂�������ł���B
�@���̎��A���ꂽ����͌��������͍��v�P�R�{�������B���v��ޕʂɂ���ƁA�u���B�y�ѓ������S���֘A�W�{�v�u�R���Ȋ֘A�R�{�v�u���̑��Q�{�v�ƂȂ�B
�@�u���̑��Q�{�v�̂����A�����ʌ��i�Ɋւ�����������́A�u���������I�ɁA�����ʌ��i�����{�̎��{�ƂƂ̍��َ��ƂɂȂ鎞�ɂ͂�������F���邱�ƁB�v�Ɓu���{�ȊO�̊O�����{�Ƃ̍��قɂ��Ȃ����ƁB�v���������e�ł���B
�@�����ʌ��i�͌��݂̌Ζk�ȕ����s�E���z�ɂ��鐻�S��ЁB�������Ζk�Ȃ̑�聃�����⁄�̓S�z�A�]���Ȃ��ʋ����ւ����傤���̐ΒY�����ꂼ�ꌴ���Ƃ���B�u�����ʁv�̖��O�́u���z�v�u���v�u�ʋ��v�̂R�̒n�����Ƃ��Ă����Ă���B
�@
�ꏊ�����B�ł͂Ȃ��A�Ζk�Ȃ�����g�ؒ��h�Ƃ������ׂ��ŁA���̂Q�P�����̗v���̒��ɂłĂ���̂͐������˂Ȋ���������B�t�ɂ��ꂾ���鍑��`���{�̎�������������������B |
|
 |
|
�@�������A��㒩���V���̂P�X�P�U�N�i�吳�T�N�j�P���P�U���E�P�V���t���u�А��v�L���i���֘A�������@�����ʌ��i�ɂ��ā@��㒩���V���А��@�P�X�P�U�N�j��ǂނƁA���̎������킩��悤�ȋC������B
�@�����ʌ��i�̖��͂͑��̓S�z�ɂ���B�قƂ�ǖ��s���Ƃ��v���閄���ʂɉ����āA���̓S�z�̏��x�̍����͂U�T���ƌ���ꂽ�B�X�G�[�f�����U�O���A�A�����J�ł��T�T���A�h�C�c�łT�O���A�C�M���X�łS�O���A���E�̕��ς��R�T���ƌ����Ă������ł́u���x�U�T���v�ł���B
�@���̑��z�R�ɍŏ��ɖڂ������̂��h�C�c�A���̌�x���M�[�̎��{�A�A�����J�̎��{�ȂǗ����̍z�R�ɗZ���������������B���������������킯��悤�ɂ��ē��{���Z���ɐ��������̂��A�h��v����ł���B
�@���̋L���������ꂽ�吳�T�N�i�P�X�P�U�N�j�����A���Ƌ�s�A���l������s�A�O�䍇�����킹�āA�R�O�O�O���~�ɏ��A�������V���ɂP�T�O�O���~�̐V�K�؊������s���悤�ƌ����Ƃ��낾�����B�������N���U������W���Ƃ����D�����ł���B
�@���ꂾ���ł͂Ȃ��B���̓S�z�́A�吳�S�N�i�P�X�P�T�N�j�A���{�̔������S���ɂQ�T���g���A�k�C���̖k�C�������|���ɂT���g���A�v�R�O���g�����A�o����Ă����B��肩�犿�z�̐��S���ւ̏o�ׂ��N�ԂR�O���g������������A���{�������ɑ��Ɉˑ����Ă��������킩��B
�@��̑�㒩���V���̎А��́A�u�N���I��i��M���āA�����Ƃ̌o�ϊW�����ׂΕK�������l���̔�������̂ʼn���ł���B�����ʌ��i�ւ̐i�o�́A����܂ő��b�Ɋ�Â��Ď��{���Ă����B��������{�ւ̔����͏��Ȃ��B����͉ؖk�▞�B�Ɋr�ׂ�Ƌ����قǂł���B���������i�o�𐋂���A�K�����Ē鍑��`��r�����āA���{�������ʌ��i�̏d�v�ȃp�[�g�i�[�ɂȂ�ł��낤�B�����ʌ��i�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�Ǝ��ɂ܂��Ƃ��Ȏ咣��W�J���Ă���B
�@�������A�u�Q�P�����̗v���v�ŋ����I�Ɂu�����ʌ��i�v�̔r���I�������咣����悤�ł́A���b�Ɋ�Â��Γ��Ȍo�ϊW�͎����ł���͂����Ȃ��B���̌�̓W�J�́A���Ǔ��{���{�́A�����ʌ��i�̏d�v�ȃp�[�g�i�[�ɂȂ邱�Ƃ͂ł����A��ɌR����i�߂ċ��D���邱�ƂɂȂ�̂ł���B |
|
 |
|
�@�����P�{�̌��������͎��Ɋ��V��ł���B�Z���̂ň��p���悤�B
| �w |
�������ɂ��Ύx�ߍ����{�͕����ȉ��ݒn���ɉ����ĊO���ɑ��D���R�p���Y���C�R�����n���̑���̌R����̎{�݂��ׂ����Ƃ��������x�ߎ���O�����ؓ���O�L�e�{�݂��s�͂ނƂ��邩�@���ӎu�����Ȃ邩�x�ߍ����{�ɉ����Ă͉ʂ��Ďz����ӎu��L�������ۂ��x�x |
�@�v����ɁA
| �u |
�������{�́A�����ȉ��݂ŁA���{�ȊO�̊O���̌R���̌R����n��ݒu���邱�Ƃ������ƕ����Ă���B�܂����������{�ȊO�̊O�����������Ē������g�̊C�R�R����n��ݒu����Ƃ������Ă���B����͎������ǂ����m�F�������B�v |
�@�Ƃ����̂��A���̌��������̓��e���B
�@���͂������O���̐��Ƃł͂Ȃ�����A����ȊO������ʓI�Ȃ̂��ǂ����͂킩��Ȃ��B���A�u�����������������ƕ��������{�����H�v�Ƃ������e�̊O���͂����ɂ���ł���B
�@���̓��e�́u�Q�P����v���v�̑�܍��A�������]�����̈ꕔ�A���Ȃ킿�u�D�����Ȃ̉^�A�{�݂ɑ�����{���{�̗D�挠�B�v�̏��F�̗v���Əd�Ȃ��Ă���B��܍������͍��ڂ��ƁA�����ς�������߂��͂������A���͂��������`�Ō��������Ɏc�����킯�ł���B
�@���́u����v�ɑ��Ē������́u���������v�Ɖ�Ԃ��Ă��邪�A��G���{�Ƃ��ẮA�����ȉ��݂ɓ��{�ȊO�̊O���̌R����n��ݒu���Ȃ��A�Ƃ����������Ƃ����Ƃ����Ƃ��낾�낤�B���������܂���͂͂Ȃ��������B����̎��_�ł̎����m�F�������̂ɑ��āA�u���̎��_�v�ł́u���������v�Ɖ��Ă��邾���ŁA���̌�b���������A�Ƃ���������ł����R��������ł���B
�@��G���{�Ƃ��ẮA�u�����O���̊C�R��n��O������؊������Ă̒����C�R��n��ݒu���Ȃ��B�v�Ƃ������e�ɂ����������̂��낤���A����ł͕����Ȃɂ�������{�̗D�挠��F�߂邱�ƂɂȂ�A�܍������P��̎�|�ɔ����A��ʼn��Ē鍑��`�̔����������B����͔��������A���������炩�̌����͂Ƃ��Ēu�������A�Ƃ������ƂŐ�̂悤�Ȋ��V��Ȍ��������ƂȂ������̂Ǝv����B |
|
 |
|
�@�������Č��Ă����ƁA���֊W�ȊO�ŗL�����̂�����e�������Ă�����́u�R���ȂɊւ�����v�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̏��̍��q�́A�R���ȂŃh�C�c�������Ă������v�͂��̂܂ܓ��{�����������A�����͂�������F���邱�ƁA�ƌ����_�ɂ���B
�@�������A���̎R���Ȃɂ�����鍑��`���{�̌��v���A���̌�̃��V���g���̐��̒��ł�������Ђ����肩�������B
�@���Ȃ킿�P�X�Q�Q�N�i�吳�P�P�N�j�Q���́u�R���Ȍ��ĉ����Ɋւ�����v�ł���B����͓��{���{�ƒ��ؖ������{�������������ŁA���N�U���ɔ��������B���̏��œ��{�͎R���Ȃɂ�����h�C�c����D�������v�A�y�тQ���ł����S�����v�𒆍����ɕԊ҂�����Ȃ������B���̓��{��v��������������������r�I���m�ȋL�q�����Ă���B
��http://ja.wikipedia.org/wiki/�R�����ĉ����Ɋւ�����
�@����͒������A���{�ƓƎ��ɒ����������ł͂��邪�A�w��ɂ͓��R�鍑��`�̋����ӌ��������Ă����B�Ƃ��������O�N�P�X�Q�P�N�i�吳�P�O�N�j�P�P�����V���g����c�Ō��肳�ꂽ�u��ꎟ���E����̐��E�̘g�g�݁v�\�z�ɉ���������ł���A�u�R�������ҕt���v�������Ƃ������Ƃ��ł���ł��낤�B
�@���V���g����c�ł́A�܂��d�v�Ȃ��Ƃ́A���ꂪ��㐢�E�̎哱�����������A�����J�鍑��`�哱�̉�c�ł���A�鍑��`�Ԃ̐��̐��̐����I�g�g�݁E�R���I�g�g�݂����肳�ꂽ�Ƃ������Ƃ��B
�@�c��_�́u�x���T�C����c�v�Ɍ��y���āA
| �w |
�������i���Q�P�����̗v������j�S�N��̂P�X�P�X�N�A�p���u�a��c�ɗ�Ȃ������ꂽ�������A�A�����J�̌㉟���őΉQ�P�����̗v���ɑ���s�����q�ׂ邱�ƂɂȂ�B�x |
�Ə����Ă��邪�A�x���T�C����c�̖{���́A�I���Ȃ܂ł́u�ΓƔ�����c�v�ł���B���̘g�g�݂̂��Ƃ͂قƂ�lj������܂��Ă��Ȃ��B���̎��������q�ׂ����Ƃ́A�u�Q�P�����̗v���v�����ɂƂǂ܂炸�A�����̖����������̎咣���B�����������������̎咣�������̂͒��������ł͂Ȃ��B�����鍑��`�̐A���n�N����`�ɋꂵ�ފe�����݂Ȏ咣�����̂ł���B�������͂܂���������Ɏ���݂��Ȃ������B�����u�E�C���\���̂P�S�����̌����v�����ɑ傢�ɗ�܂��ꂽ�A���n�E���A���n�����́A���̃x���T�C����c�̌���Ɍ��������]�����B���������Ē������u�x���T�C�����v�ɒ��Ă��Ȃ������B�]���ăA�����J�������̌㉟���������A�Ƃ����c��_�̔F���͍��ꂩ��Ԉ���Ă���B |
|
 |
|
�@�A�����J�鍑��`�哱�̐��̐��́A�P�X�Q�P�N�i�吳�P�O�N�j�P�P���̃��V���g����c�ł悤�₭���肷��B���̎���c�ł́A�C�R�R�k���Ŏ�͕͊ĉp�����T�F�T�F�R�̔䗦�����܂����B���������̂��Ƃ��������Əd�v�Ȍ���́A�u�l�J�����̒����������m���ׂɊւ���̓y���̑��d�A���ĉp���̋����v�A�u���p�����̏I���v�A�u�����ŏ�ꗥ�]���T���ŁA�t���łQ�D�T�|�T����F�߂�B�v�A�u�X�J�����̒������A�����J�́w��ˊJ���x�̎咣�ɉ����Ē����̎匠���d�A�̓y�ۑS�A�̋@��ϓ��v�����肳�ꂽ���Ƃł���B
�@�X�J���͓��{�A�A�����J�A�C�M���X�A�t�����X�A�C�^���A�A�x���M�[�A�I�����_�A�|���g�K���A�����ł��邪�A���̏��̎�|�́A����܂ŁA�C�M���X�E���{�̓Ɛ��ԂɂȂ肩���Ă��������s����A����܂ł̊������v�d���A�S�̓I�ɂ́w��ˊJ���x�����悤�Ƃ������Ƃ������B
�@����ŗL���ɂȂ�ɂ́A�����ɂ͏o�x��Ă����鍑��`�A�����J�ł���B
�@���{�ɂ��Č����A���ւɂ����錠�v�͔F�߂邪�A����ȊO�̒����ł́A�鍑��`�e���̋@��ϓ������肳�ꂽ�B�R�������̌��v�́u���{�̊������v�Ƃ͔F�߂��Ȃ������̂ł���B���̂��Ƃ�������̂��A���V���g����c����킸���S������A�P�X�Q�Q�N�Q���ɒ������ꂽ�u�R���Ȍ��ĉ����Ɋւ�����v�������̂ł���B
�@�u�A�����J�Ɍ㉟�����ꂽ�����v���́u���{�̌��������x�����Ă��ꂽ�C�M���X�A�t�����X�v���̂́A�c��_�I�u��Q�ϑz�j�ρv�w�҂̖��m�E���������炷��u���킲�Ɓv�ł���B
�@�����R���Ȃ̌��v��Ԋ҂������Ȃ�������A���Ȃ��Ƃ��鍑��`���{�́A��ꎟ���E����̒鍑��`�̐��E�x�z�̐��̘g�g�݁A���Ȃ킿���V���g���̐������яo�����Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�������吳����̒鍑��`���{�ɂ́A�܂����ꂾ���̓x���͂Ȃ������B����������A�鍑��`���Ƃ��Ďv�����ʂ͂����Ă����Ƃ������Ƃ�������B
�@���������ꂾ���ɁA�鍑��`���{�̓��ʂł́A�u��Q�҈ӎ��v�͋��܂��Ă��������̂Ǝv����B
�@���݂̓c��_�I�u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�҂⌤���҃O���[�v�ɂ͂��́u��Q�҈ӎ��v�����L���̂悤�Ɉ�`���Ă���̂��Ƃ����悤�B |
|
 |
|
�@�����ł�����x�A�P�X�P�T�N�i�吳�S�N�j�́u�Q�P�����̗v���v��U��Ԃ��Ă݂悤�B
�@�鍑��`���{�́A�����l���̔����ƓG�ӁA�鍑��`���̌x���S���Ȃ���A�����ȁu�Q�P�����̗v���v�𒆍��ɓ˂������B���̌��ʓ������͉̂����H
�@�������Č��Ă݂�Ɠ얞�B�ɂ����錠�v�����������̂ł���B
�@���̌��ʎ��������͉̂����H�����l���̐M���ƗF��ł���B���܂��ɗ鍑��`�e���̐M�p���������B���p�����́A���V���g���̐��Ƌ��ɏI�����A���ꂩ�珙�X�ɁA�鍑��`�A�����J�Ƃ͓G�ΊW�ɓ����Ă����B
�@�鍑��`���Ƃ��Ă݂Ă��A���{�ɂƂ��ẮA���ɍ���Ȃ��������肾�Ƃ����邾�낤�B���̎��̒鍑��`���{�͗]��ɂ��������Ǝv����̂ł���B
�@�u�Q�P�����̗v���v�́A�鍑��`���Ƃ��Ă����܂�ɋ�����A�Ƃ������z�͉����������̊��z�ł͂Ȃ��B
�@���̎����i�P�X�P�T�N���吳�S�N�j����P�Q�N��Ƃ����A���傤�Ǒ吳���珺�a�ւ̋��ڂɂȂ�B���̊ԁA�鍑��`���{�̒����N���́A�u���V���g���̐��v�̘g�g�݂̒��ŁA������߂ɂȂ�v���������u����邱�Ƃ��ł��Ȃ��āA�����␂�ԂɂȂ�B
�@
�@��������ł́A�����}�Ƌ��Y�}�Ƃ̊Ԃɑ�ꎟ�������삪�������A�����́u�����Ɨ����ꍑ�ƌ��݁v�Ɍ������āA�傫�Ȉ���ݏo�������A�܂��P�X�P�V�N���������A�܂��u���S�ȃ\�r�G�g�E���V�A�v�́A���̋ߑ㍑�ƒ�����S�ʓI�Ɂu����������`�v�̗��ꂩ�狭�͂Ɍ㉟������B
�@���̊ԓ��{�́A�u��ꎟ���v�̍D�i�C�������ԂɏI���A���E���Q�ɓ���O�ɂ��łɏ��a���Q�ɓ˓����Ă����B
�@���̎����A���a�Q�N�i���P�X�Q�V�N�B���a�Q�N�Ƃ����Ă��A���a���N�͔N���̂P�T�Ԃ����Ȃ������̂�����A���傤�Ǒ吳���珺�a�ւ̑ւ��ڂɂȂ�j�A�����ɃG�R�m�~�X�g�����T�g�́A�u�����v�R�����Ɏ��̂悤�Ȉꕶ�i�Q�l�����F�u�R�k��c�̌o�ϓI���߂Ɠ��{�̗���@�����T�g�v���Q�Ƃ̂��ƁB�j���Ă���B�����͓����̃A�����J�哝�̃N�[���b�W�́w�⏕�͌��������Ɋւ���R�k���Ɋւ����āx�Ɋւ���L�q���B�Ȃ����́u�⏕�͌����������v�͌�ɁA�t�[�o�[�����Łu�����h���R�k���v�Ƃ��Ď�������B
| �w |
�@���������A���̌̂ɑR��A���{�͍��̍یR�k���̂��̂ɔ����ׂ����Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��B��́A�����̐��̒��ɉ����āA�����̓��{�̎��͂��ȂāA�p�ĕ��̔@���Ƌ������āA�̓y�́u�g���v����}���邱�Ƃ��S�R�Ԉ���Ă���B���̂��Ƃ͑Ύx�Q�P�����̋��v�A�V�x���A�o���̑厸�s���ɂ���āA�߂Ɏ����ς݂̂��Ƃł���B�x |
�@���̘_���̒��ō����́A���̂��Ƃ��咣���Ă���B
| �P�D |
���E�̒鍑��`�́A�h�Պ��ł͂Ȃ��m�����ł���B |
| �Q�D |
�m�����ɂ����āA���{�̂悤�Ȓx��Ă������{��`�����R���ŗ̓y�g�������ׂ��ł͂Ȃ��B����͕K�����s������B |
| �R�D |
���{�͒鍑��`���z�����V�������l��Ɛ��E�����m���ɍv�����ׂ��ŁA���̂��ߒ��N�A��p�A�얞�B�̌��v��������ׂ��ł���B |
| �S�D |
���a���Q�ɑ�\�������{�̌o�ϓI�s���l�܂��ŊJ����ɂ͂��̕��@�����Ȃ��B |
�@���̘_���̒��ŁA����ł͍����T�g�́A�鍑��`�I���E�����ɕς�邠�炽�ȁu���l�̌n�v�Ƃ͂Ȃɂ��ɂ��Ė������Ă��Ȃ��B�Ƃ������܂��o���Ă��Ȃ������ƌ����ׂ��ł��낤�B�܂����̍����̎咣�́A���悤�ɂ���Ắu�哌�����h���v�𗝘_�I�ɏ����������̂ƍl���邱�Ƃ��o����B�������A���炭�͂����ł͂Ȃ��ł��낤�B����́A�u�R����`�ɂ��Ȃ����E�����v�̊m�����咣���Ă��邱�ƁA���̂��߂ɂ́A���N�A��p�A�얞�B�̌��v�̕������咣���Ă��邱�Ƃł��킩��B
| �i�� |
���ۂɂ͍����T�g�́A���̌�o�ϐ���ƂƂ��āA�R����`���{�̍��Ƒ������̐��̒��Ɏ����g�ݍ���ł������ƂɂȂ�̂����E�E�E�B�j |
|
|
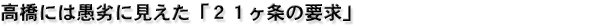 |
|
�@���̍������猩��ƁA��G�����́u�Q�P�����̋��v�v�i�����͂��̘_���̒��Łu�Q�P�����̗v���v�ł͂Ȃ��u���v�v�Ə����Ă���j��V�x���A�o���Ȃǂ́A���̉���Ƃ��������Ȃ������B
�@�����Ŏ��͂ӂƁu���s�j�ρv�Ƃ������t���v���o�����B���Ȃǂ͂��́u���s�j�ς��̂��́v�Ƃ������ƂɂȂ邩���m��Ȃ��B
�@�Ƃ��낪���͎����őS�R�u���s�v���Ǝv���Ă��Ȃ��B�u���s�v�Ƃ͎����Ŏ������s�߁A�Ղނ��Ƃ��B�����܂ōl���Ă���Ǝ����ŋC�������B���́u�鍑��`���{�v�������̂��ƂƂ͑S�R�l���Ă��Ȃ��̂��B
�@���͓��{�l�ł��邵�A���{�l�ł��邱�ƂɌւ�����������Ǝv���B���̎����炵�āu�鍑����`���{�v�́A�������{�Ƃ������t���g���Ă��Ȃ���A���Ƃ͉����䂩����Ȃ����̂ƍl���Ă���B�܂�u�鍑��`���{�v�́A���ɂƂ��āu�����v�̔��e�ɑS������Ȃ��T�O�Ȃ̂��B
�@�܂莄�ɂƂ��āA�������{�Ƃ������t���g���Ă��Ȃ���A�u�鍑��`���{�v�ƐM���ƗF�����{�Ƃ���u���a��`���{�v�Ƃ͑S���ʕ��A���邢�͑Η��T�O�Ƃ��čl���Ă��邱�ƂɎ����ŋC�������B
�@������́u���a��`���{�v�̈���ł��邱�Ƃ����F���A���̈���ł��邱�ƂɌւ�������Ă���B���̎��ɂƂ��āu�鍑��`���{�v�́A�����̂��Ƃǂ��납�A�O��I�ɔᔻ������ׂ��u���ʂ̓G�v�Ȃ̂��B������鍑��`���{��ᔻ���邱�Ƃ͎��ɂƂ��Ắu���s�v�ǂ��납�A�u���ʂ̓G�ɑ���U���v�Ȃ̂��B�u���s�j�ρv�ǂ��납�u�鍑��`���{�T�f�B�Y���j�ρv�ƌĂ�ł�����Ă������B
�@����u���s�j�ρv�Ƃ������t���g���l�����̂��Ƃ��l���Ă݂悤�B�ނ�́A�u�鍑��`���{�v��ᔻ���邱�Ƃ����́u���s�v���Ɗ�����̂��H���������܂ł��Ȃ����낤�B
�@�ނ�́u�鍑��`���{�v�̂��Ƃ��A�u�����̖����v�ł���A�u�����͂��̐w�c�ɑ����Ă���v�Ƃ����A���ӎ�������B�����炱���ᔻ���邱�Ƃ́u�����Ŏ������s�߁A�Ղށv���Ƃ��Ɗ�����̂��낤�B
�@�Ƃ��낪�u�鍑��`���{�v�͎��ɂƂ��Ắu���E����ׂ��G�v�Ȃ̂��B
�@�ނ�Ǝ��̊Ԃɂ́A��Ήz���������[���[���a������悤���B |
|
 |
|
�@���ēc��_�͖`���Ɉ��p�������͂ɑ����Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
| �w |
�܂��䂪���͏Ӊ�����}�Ƃ̊ԂƂ̊Ԃł����ӂ����ČR��i�߂����Ƃ͂Ȃ��B�P�X�O�P�N����u����邱�ƂɂȂ����k���̓��{�R�́A�R�U�N����b�a�������̎��ł����T�U�O�O���ɂ����Ȃ��Ă��Ȃ��B�u�b�a�������̌����i�`��F�@������w�o�ʼn�j�v�B���̂Ƃ��k�����ӂɂ͐��\���̍����}�R���W�J���Ă���A�`�̏�ł��N���ɂ͂قlj����B������d�Y�O����b�ɏے������Β��Z�a�O���������䂪���̊�{���j�ł���A����͍����̂��ς��Ȃ��B�x�i�����J�b�R�A��Ǔ_�̓}�}�j |
�@��L���͂œc��_�������Ă��邱�Ƃ́A�v����Ɂu�嗤�i�o�͐N���ł͂Ȃ������B��ɑΒ��Z�a�O���������v�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@���낢����_���܂��͂����A�Β��Z�a�O���̏Ƃ��āu�����O���v�܂Ŕ�яo���Ă���̂ɂ͋������B���̒j�̈�m�����Ƃ����\���̂��悤���Ȃ��B
�@�����O���̖{���́A�鍑��`�Ɛ��ʏՓ˂�����A�����嗤��Ƌ��ɐN�����Ă䂱���Ƃ����������B�ꎞ�I�����A�ނ̌����͗鍑��`���哱���čs�����A�Ƃ����ǖʂ��猩�Ď���̂ł���B
�@�ʂȌ�����������A�����O���Ƃ́A�����ɂ����錠�v�����Ē鍑��`�Ƌ��L���A���̈Ӗ��ł́A���{�̒鍑��`�𐢊E�̒鍑��`�̐��̒��ɂ����ۂ�Ƒg�ݓ���A���̈��S�ۏ�̐��̒��ŁA��胊�X�N�̏������N���̓���������Ƃ������̂ł������B
�@�������A�勰�Q�̑O����[���ȕs���Ɋׂ��Ă������{�̎��{��`�́A�\�͓I�ɑ嗤�ɂ͂����������鑼�͂Ȃ������B�������āu�����O���v���u���O���v�Ƃ��Ĕے肷��̂ł���B�����ėƑΌ����Ă܂Łu�����N���v�𐄂��i�߂悤�Ƃ��鋥�\�ȓV�c���t�@�V�Y���R����`���䓪����B����͈ꕔ�R���̓Ƒ��ł͂Ȃ��B�ǂ��l�߂�ꂽ���{�̎��{��`�̋��ɂ̑I���������̂ł���B
�@�����猾���A�䂪�c��_�N���͖��炩�Ɂu���\�ȓV�c���t�@�V�Y���R����`�v�ɑ����Ă���B���̓c��_�N�����A���g�̐������̍����Ƃ��āA�����̘_�G�������u�������O���v�������o���Ă��邩������̂ł���B
| �i |
�W�F���g���}���̕����͌����Ď��̂悤�ɓc��_��l������͂��Ȃ��B�������A���̐��Łu�c��_�N�A���͌N�Ƃ͑����l����������Ă���Ǝv���̂����ˁB�ł���Ύ��������o���Ȃ��ŗ~�����ˁB�v�Ƃ͂����Ă��邾�낤�B�j |
�@�����Ƃ��c��_�́A���g�̈�`�q���ǂ��ɗR�����Ă��邩�𗝉����邱�Ƃ��A����ɕK�v�Ȓm�����������킹�Ă͂��Ȃ��B���ɍ��荞�܂ꂽ���Ƃ𖬗��Ȃ����ׂĂ���ɉ߂��Ȃ�����A���ɂ��������Ă��ڂ��p�`�N�����邾�����낤�B |
|
 |
|
�@�w�܂��䂪���͏Ӊ�����}�Ƃ̊Ԃł����ӂ����ČR��i�߂����Ƃ͂Ȃ��B�x�̋L�q�ɂ܂Ƃ��ɂƂ荇������͂Ȃ��B�����A�����ɗc�t�ȕ��͂ł��낤���A�̐S�ȕ����ł͘_�|����т����ė~�����Ƃ͎v���B
�@�Ƃ����̂́A�c��_�͑O���́A���镔���Łw���{�̋߉q�������t�́A�u�x�ߌR�̖\�߂��^�����Ȃ��ē싞���{�̔��Ȃ𑣂����߁A����f������[�u���Ƃ�v�Ƃ��������\�����B�䂪���͏Ӊ�ɂ������푈�ɂЂ����荞�܂ꂽ��Q�҂Ȃ̂ł���B�x�Ə����Ă��邩�炾�B
�@���́u�����푈�ɂЂ����荞�܂ꂽ�B�v���́A���R�R��i�߂��낤�B�R��i�߂����ɂ́A���̓s�x�u�Ӊ�����}�Ƃ̊Ԃł����ӂv���̂��H
�@����ȃo�J�Șb�͂���܂��B�푈�̓��̑���ɌR�̔z�u�ɂ��āu���ӂv��Ȃǂƌ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B
�@
�@�������������������ƂX�Ə�������A�݂�ȂɃo�J�ɂ����̂��B�u��Q�ϑz�j�ρv�̘A���ɂ��炾���āA�o�J�ɂ���Ă���B
�@�c��_�N���́A���͍u����̈˗��ŖZ�����悤�����A���N�̍����܂łɂ͕K���u�������́v�̑㖼���ɂȂ�B
|
|
 |
|
| �w |
�P�X�O�P�N����u����邱�ƂɂȂ����k���̓��{�R�́A�R�U�N����b�a�������̎��ł����T�U�O�O���ɂ����Ȃ��Ă��Ȃ��B�u�b�a�������̌����i�`��F�@������w�o�ʼn�j�v�B���̂Ƃ��k�����ӂɂ͐��\���̍����}�R���W�J���Ă���A�`�̏�ł��N���ɂ͂قlj����B�x |
�@���̂܂�ł킯�̂킩��Ȃ��L�q�́A���͓c��_�̔w��ɉB��Ă���u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�҃O���[�v�⌤���҃O���[�v�̃��b�Z�[�W�ł�����B�킯���킩��Ȃ��L�q�ɂȂ��Ă��܂����̂́A�ЂƂ��ɓc��_�̗���͕s���A�ނ̓��̈����̌��ʂł����āA���ꂾ���ɂ��̋L�q�ɑ��āA���j�I�����Ɋ�Â��Ĕ��������Ă����̂́A���̐܂��d�����B
�@���̖ړI�̂��߂ɂ́A��x�u�鍑��`���{�v�̒����N���̗��j�Ƃ��̐N���ɑ��钆���l���̐킢�ɖ߂��Č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@����ɂ͂P�X�Q�W�N�i���a�R�N�j�̒��������E������̒����ɂ��ǂ��Ă݂�̂��K���Ǝv����B
�@���j�̐��I�����҂ł͂Ȃ����ɂ͂��܂������̂��Ȃ����ۂȂ̂����A���ɂƂ��Ắu�Q�P�����̗v���v��������̐ߖڂƍl���A�܂����̐ߖڂ��u���������E�����v�ɒu���������A���̌�́u�鍑��`���{�v�̒����N���̗��j�Ƃ��̐N���ɑ��钆���l���̐킢���X���[�X�ɗ������ł��A���������̂ł���B
�@���̃V���[�Y�Ō����悤�ɒ��������E�����́A�鍑��`���{�̈�̑傫�ȕ�����ڂł������B�i��http://www.inaco.co.jp/isaac/back/023-7/023-7.htm���Q�Ƃ̂��ƁB�j
�@���������E�������̂��̂͋����I�ɂ݂�A�������Ԃ��������A���̎������N���钼�O�A�鍑��`���{���A���̍ő�̌��āu���֖��̉����v�ɑ��āA��蓾�����ɂ́A�傫���R�̕������������悤�Ɏv���B
| 1�D |
���֒��ړ����@���{�����N�E��p���l�A���ւړ������ɂ��������ł���B���̏ꍇ�́A�����鍑��`�̍��ےk���̐��ł���u���V���g���̐��v�i���邢�͍��ۘA���j�̘g���яo���A�鍑��`�ƒ��ڂ̑Η��W���o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂������鍑��`���{�̎x�z�w�͂��قǏd�v�����Ȃ��������̂́A�����l���̖����Ɨ������Ƃ̒��ڑΌ����������Ȃ������B�܂��{���I�ɂ́A��v�_�E�Ë��_�����������Ӊ�����}�Ƃ��Ό����邱�ƂɂȂ����͂��ł���B |
| �Q�D |
���֘��S�����@���ւɘ��S�������������A���S������ʂ��Ďx�z���A���D��������ł���B�x�z�Ǝ��D�̋����́A�N����S�Ƃ��A�܂��ǂ�Ș��S�̐��ɂ��邩�ɂ��B�]���Ē鍑��`�Ƃ̑Ό��A�Ӊ�����}�Ƃ̑Ό��̒��x�́A�N����S�Ƃ��邩�ɂ���Č��܂�B������N����S�Ƃ��邩�͌���I�ɏd�v�Ȗ�肾�����B |
| �R�D |
�������x�z�@�̎x���Ǝx���̉��ɖ��ւ����������x�z���Ă������B���̏ꍇ������`�̘g���Ɏ~�܂邱�Ƃ͕ۏႳ��邵�A�Ӊ�Γ싞���{�Ƃ��a瀂��̈��͂ʼn��������ނ��Ƃ��ł����ł��낤�B�����Ƃ����X�N�̏��������ł͂��������A�ő�̌��_�́A���ւɂ�����鍑��`���{�̍ő嗘�v���ۏႳ��Ȃ����Ƃ��낤�B |
�@���炭�u�����O���v�͂Q�ƂR�̊Ԃ̂ǂ����ɂ������̂��낤���A�u�c���O���v�͂P�ƂQ�̊Ԃɂ������B�u�Ό��Ύ��v�͂P�ƂQ�̊ԂŁA���炭�u�c���O���v���P���ɂ������̂��낤�B
�@�]���Ăǂ̈Ăɂ��Ă��A�N����S�Ƃ��邩�͑傫�Ȗ�肾�����B���̘��S�����̑�P���͒������������B
�@���̒��������֓��R�͔��E���Ă��܂��̂ł���B��Ɉ��p�����u�͖{��L�v�i���Y�t�H�@���a�Q�X�N�P�Q�����j��M����A���������E�͒P�ɉ͖{���̓ƒf�Ƃ͂������A���Ȃ��Ƃ��֓��R�S�̂̈ӎu�������A�ƌ��邱�Ƃ��ł��邵�A���Ȃ��Ƃ����̌�͖̉{�̏������l����A���R�Q�d�{�����ٔF���Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�@�܂肱�̎��_�ŁA�u���������S��Θ_�v����߂��c���`����t�̕��j����A����i��Łu�������s�v�_�v�ɂȂ����킯���B
�@�m���ɒ鍑��`���{�ɂƂ��āA�����܂Ŗk���ɐi�o���S�����ɍ��߂������悤�Ƃ��钣�����̕��j�́A���̎����ɂ߂Ċ댯�ɂ܂�Ȃ����̂Ɖf�����B
�@�u�Q�P�����̗v���v�����ŋɂ߂Ă͂����肵���悤�ɁA�鍑��`���鍑��`���{�ɔF�߂����ꌠ�v�n��́A�얞�B�E�������Âł���B�鐭���V�A���|��A�Љ��`�\�A���������������Ƃ��Ă��A���X���B�S�̂ł���B
�@������A�u���藣���_�v���䓪����B���Ȃ킿�A�鍑��`���{�ɂƂ��āA�u���ۗЉ�v�ɑ��Č��v�m�Ɏ咣�ł��Ȃ��u�����{���v�Ɓu���ցv��藣���A���v�m�Ɏ咣�ł���u���ցv�ɂ�����x�z�̐����܂��m�����悤�Ƃ����̂���{�헪���B
�@���̒鍑��`���{�̊�{�헪�ƑS�����ɔe���𗧂Ă悤�Ƃ��钣�����̕��j�Ƃ͍��{�I�ɑ��e��Ȃ��B����������S�̓���Ƃ��Ă��܂ł��l���Ă���ƁA
�u���藣���v�������ł��Ȃ����肩�A��b�ł߂��̐S�Ȗ��B�i�܂莡���ێ����j�ɂ܂Ő헐���y�т��˂Ȃ��B
�@�������āA�u��������̂Đ���v���̗p���A���킹�Ă��̍����ɏ悶�Ĉꋓ�ɌR���N�U���s�����Ƃ����̂��u���������E�v��v�������B���̎��̊֓��R�̐헪�͖��B�̘��S�͒N�ł������A�Ȃ���Ȃ��Ă������Ƃ����ɂ߂ė��\�ȕ��j�ŁA���̈Ӗ��ł͐�قǂ̕����i�I�����j�̒��́A�u�P�D���B���ړ����v�Ɍ���Ȃ��߂����̂������Ƃ����悤�B |
|
 |
|
�@�Ƃ��낪�A�u���������E�v�͎v���������ʕ����֎��Ԃ��ꋓ�ɐi�߂Ă��܂��̂ł���B�u�v���������ʕ����v�Ƃ͕\���������A����͂����܂Łu�֓��R�v�Ȃ�A���{�̌R���ɂƂ��Ắu�v���������ʕ����v�Ȃ̂ł����āA�����܂Ŕނ�̎�ϓI�v�����݁A����������u�ƑP�v�������ɋ����������̏؋��ł�����B
�@�É��N�v�́u�����푈�v�Ƃ����{�i��g�V���@�W�T�N�U���T���@��Q���j�̒��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
| �w |
�͖{�i�����B���������E�����̒��ڐӔC�ҁj�͔��E�����ɂÂ����̋�̍��p�ӂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��A�E�E�E���̎����́A���֓Ɨ������̎����Ƃ����֓��R�̖ڕW�ɂƂ��āA���ڂɂ̓}�C�i�X�̌��ʂ������炵�����͊m���ł������B�����v���i������͏Ӊ�����}�̒������ꐭ��̂��Ƃ��낤�B�j���疞�ւ�藣�����Ƃ���_�ł͊֓��R�Ƌ��ʂ̗���ɗ����Ă����c���O���i���c���`��̂��ƁB�c���͊O�������C���Ă����̂ŌÉ��͂����������B�j�A������A�������̑��q�̒��w�ǂɑ��āA�������{�ƑË����Ȃ��悤�Ɉ��͂����������A��������w�ǂ̑ԓx����𐔃��������������Ƃ��o���������ł������B�x |
�@�É��������Ă��邱�Ƃ́A�ȉ��̂��Ƃł���B
| �P�D |
�͖{�ɂȂɂ����̎肪�����āA�������E�����킯�ł͂Ȃ��B |
| �Q�D |
�c���`�����@�̎�̈Ⴂ��������̂́A�������̑��݂͎ז��ɂȂ��Ă���A�u���ւ̐藣������v�Ƃ����_�ł́A�͖{��֓��R�ƈ�v���Ă����B |
| �R�D |
�������̌�̘��S�́A�N�ł��悩�������A�Ƃ肠�����c���`���֓��R�́A�������̑��q�̒��w�ǂ�z�肵�Ă����B |
| �S�D |
���̒��w�ǂɈ��������������A���w�ǂ͌��ǁA�������{�̑��ɂ����B |
�@�ǂ����Ă���Ȏ��ԂɂȂ����̂��H
�@�͖{��֓��R�́u���������E�����v���N�����āA�ǂ����悤�Ƃ��Ă����̂��H |
|
 |
|
�@�͖{�͎S�߂Ȏ��s�ɏI��������̖d���̈Ӑ}�₻�̌�̌v��ɂ��đ��������Ȃ��B
�@���p�́u��L�v�ł͂킸���Ɏ��̂悤�Ɍ���Ă��邾���ł���B
| �w |
�����Ė���A��V�R�i���������̌R���j�������N�����A���i�b������ɓ������āA��V�Ɨ��̌R���N�����āA���̌�̖��B���ς���C�ɋN����蔤���������̂����A��V�h�ɂ͌����ȑ����B�������āA����������V�R�̍s����j�~���A���{�R�Ƃ̏Փ˂𖢑R�ɖh���ŏI������B�x |
�����̒��i�b�́A���Ƃ��Ɛ����̕����o�g�҂ŁA�h��v�����N������͐��M���{�ɎQ�����A���̌㒣�����̟����ɓ���A��V�R���̏d���̈�l�ɂȂ�B�̂��ɖ��B���ς�������u���B���v����������ƁA�֓��R�ɉ����āu���B���v�ɎQ�����A�u���B��������b�v�ɏA�C����B
��http://ja.wikipedia.org/wiki/���i�b���@
�@���i�b�̂��̌�̋O�ՂƂ��͖̉{�̋L�q�Ƃ��d�ˍ��킹��A���������E�����̒��ォ�炷�łɊ֓��R�ɏ�芷���Ă����A�Ƃ��������͏\�����藧�B
�@�����B�́A��͂��V�R���̏d�v�l���ŁA���̎���V�Ȓ��ł���A�������E�̒��ڍō��ӔC�҂������B
�@�����ŁA�͖{�́u���̌�̖��B���ς���C�ɋN����蔤���������v�Ə����A�܂������������ɂ��܂��Ȃ���u���{�R�Ƃ̏Փ˂𖢑R�ɖh���ŏI������B�v�Ƃ��Ă���ʂ�A���������E�ŕ�V�R���R���s�����N�����A���̌R���s���������Ɋ֓��R��������A��C�ɖ��B���ςɔ��W������v�悾�����B�܂肱�̎����̂R�N��ɋN����u�����Ύ����v�̃��n�[�T���̂悤�Ȏ����������B
�@�͖{�́u����������V�R�̍s����j�~���v�Ə����Ă��邪�u���������v�͉͖̂{��֓��R�̕��ł����āA��V�R�͏������������Ă͂��Ȃ������B
�@�u���E�v�̌���ɕ�V�R�𗦂��ċ삯�����̂́A��V�x���i�߉��珫�R�������B
�@���̌�́u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�i�p�앶�Ɂj�Ƃ����{�ɏ]���āA���Ă݂悤�B
| �w |
��V�x���i�߉��珫�R�͎��͓��{�l�ł������B�ނ͓��{�����r�،ܘY�Ƃ����A���Ƃ��Ƃ͗��m�Q�V�����̌R�l�ł��������A�嗤�ւ̗Y����Ē������̌R���ږ�ɂȂ����̂ł���B�E�E�E�r�ɂ́A���̎��������{�R�̉A�d�ł���Ƃ����ɕ��������B�����ŁA�u��V�Ȃł͉��l�Ƃ����ǂ���킵�߂Ă͂����Ȃ��B���{�R�͂����炭�@����˂���Ă���v�ƁA��V�R�ɔ��C���ւ����Ƃ����B
�����A�͖{�̌v��ł́A�삯������V�R�Ƃ̊Ԃŕ��͏Փ˂������N�����A��C�ɓ얞�B�̐�̂�d���͂��ł������B�x |
�@�����Ŏ��̓��͎�����Ɋׂ�B�r�،ܘY�́A�͖{�́u��L�v�ɂ��o�Ă���̂ł���B
| �w |
�@�E�E�E��������A���̔��j��������̌v��ƒm���āA���ł����������ė����ꍇ�́A�䂪���͂Ɉ˂炸�A�����h�����߂ɁA�r�،ܘY�̑g�D���Ă���A��V�R���́u�͔͑��v���r���w�����Ă���ɂ����邱�ƂƂ��A��������߂����A�֓��R�i�ߕ��̂���������O�̒����L��͌R�̎�͂��x�����Ă����B�x�@ |
�@�͖{�́u��L�v�ɂ���r�،ܘY�Ɓu���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�ŏo�Ă��鉩�珫�R�r�،ܘY�͓���l���Ȃ̂��H���炭�����l������܂��B
| �i |
�܂���������̋ǖʂŁA�܂���������̃e�[�}�œ��������̐l�����o�ꂷ�邱�Ƃ͂���B�P�X�S�T�N�W���̌��������O��A�����j���[���[�N�E�^�C���X�́A�����Ȋw���̋L�҂œ�l�̃E�C���A���E���[�����X�L�҂������B��l�͌�����^�Ńs���[���b�c�A�܂��Ƃ����E�C���A���E�k�E���[�����X�L�҂ŁA������l�͌���������̍L���ɓ���A���e���悤�Ƃ��ă}�b�J�[�T�[�i�ߕ��̌��{�Ɉ���������A���e�ł��Ȃ������E�C���A���E�g�E���[�����X�L�҂ł���B���͒������Ƃ��̓�l�̐l����l���Ǝv������ł����̂ŁA���e�̖����̂��߂ɑ卬���Ɋׂ��Ă����A�����ĕʐl���ł��邱�Ƃ��������ɂ́A��l�ŁA�����A���O���ƊJ���A���ꂩ�����������B���ꂩ�炱�̓�l���u�P�ʃ��[�����X�v�A�u���ʃ��[�����X�v�Ƌ�ʂ��邱�Ƃɂ����B�����炱�̍r�،ܘY���x���S�������ē��R�ł���B�������ԈႢ�Ȃ�����l���ł���B
��http://d.hatena.ne.jp/maroon_lance/20080408/1207663825���j
|
�@�����u�͖{��L�v�Ɓu�w�Ǐ،��v�̋L�q���Ȃ��������悤�Ƃ���A���ʂ���̐��������܂�悤���A����͎}�t���߂��낤�B�v�́u��V�R�ł́A�r���܂ޗ�ÂŌ����l�������w�����Ă���A�~�G�~�G�̊֓��R�̒����s�ׂɏ��Ȃ������B�v���Ƃ��m�F���Ă����Ώ\�����낤�B |
|
 |
|
�@�@�����ŁA�����푈�j�S�̂�ʂ��čł����͓I�ȃL�����N�^�[�A�ё����A���̎������������͓I�ȃL�����N�^�[�A���w�ǂ����߂ēo�ꂷ��B
�@���j�ł́A�e����e���ɂ��ꂼ�ꖣ�͓I�ȃL�����N�^�[���A�܂�Ő_�l�̈��Y�̂悤�ɁA���R�Ƃ������B�����ĒN�ɂ��o���Ȃ���d�������āA�����Ə�����B���傤�ǖ����̍�{���n�̂悤�ȁA�k���������قǖ��͓I�ȃL�����N�^�[���B���w�ǂ͂��傤�ǂ��������L�����N�^�[���B���w�ǂɓ��ꍞ�ނƑ�E���������Ȃ̂ŁA�b��O�ɐi�߂悤�B
| �i |
���w�ǂ́A�P�X�O�P�N�������̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�Ⴂ������R�l�Ƃ��Ă̍˔\�͒N�����F�߂�Ƃ��낾�����B���������E�����̎��ɂ͂܂��Q�V�������炾�������ƂɂȂ�B���̌�P�X�R�U�N�̐��������̎��ɁA��i�ł��葸�h���Ă����Ӊ���ċւ��Ă܂ō�������𔗂�A���N��������삪�����A��������R��������ł�������B�w�ǎ��g�́A���������̒���A����i��ŏӉ�ɓ��s�����̂܂ܗ��j�̕\���䂩��p�������B�Ӊ�͗⍓���S�ɓ��E��G���E�����j�����A���w�ǂ͎E���Ȃ������B�E���Ȃ������B�w�ǂ͂��̌ジ���Ɠ�֏�Ԃɒu�����B�Ӊ�͑�p���S�̍ۂɂ��w�ǂ�A��čs���A��p�œ�ւ���B��ւ��������̂͂P�X�X�O�N�A�w�ǂ̂X�O�̒a���������������Ƃ������������B���̎��w�ǂ́A���{�̂m�g�j�̎�ޔǂ̋��߂ɉ����āA�C���^�r���[�ɉ�����B���̎��̊w�ǂ̌��t�́w���{�̎Ⴂ�l�Ƙb�������������B�x�������B���̌�w�ǂ̓n���C�ɍs���A�����łP�O�O�̐��U�����B���{��v���������������͔�r�I��Âȕ`�ʂ����Ă���B��http://ja.wikipedia.org/wiki/���w�ǁ��j |
�@���w�ǂ́A���E���ɖk���ɂ����B���g�̒a�����̃p�[�e�B�ɏo�Ă������ɁA�����̑�������炳���B�������A�����͍��������łɎ��S���Ă����Ƃ͒m��Ȃ������B
�@�u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�ɂ��ƁA
| �w |
���͕��������Ƃ��P�T�Ԃقǒm��܂���ł����B�������B���ċ����Ă���Ȃ������̂ł��B���̎��͂����A����������������Ƃ�m���Ă��邾���ł����B�ł����玄�͖k������͖k�Ȃ�?�B�i����イ�j�ɍs���A�R����P�ނ�����C���𐋍s���܂����B���̔C�������������Ƃ��ɁA����������ƕ��������Ƃ������Ă��ꂽ�̂ł��B�x
|
| �w |
�������֓��R�̎d�Ƃ��Ƃ������Ƃ͒N�ł��m���Ă��܂����B����͌��R�̔閧�ł����B�����얞�B�S���ɂ͓��{�̌R�l�̑��ɁA��̒N���߂Â����Ƃ��ł����ł��傤���B�ł����玄�͓��{�̌R�l�͌����Ȃ̂ł��B���̎������d�g�ނ��߂ɁA���{�͎��O�ɓ얞�B�S�����ꎞ�~�߂��̂ł��B���ɒN���D�Ԃ��Ƃ߂���ł��傤���B�x |
�@�ƒ��w�ǂ͌�����B
�@�������̎���m�����w�ǂ́A�ˑR�p���������B�Ȍ��V�ɖ߂�܂ł̒��w�ǂ̍s���́A�����ԓ�Ƃ���Ă����B
| �w |
�R�C�ւ��߂�����i���ؖk�𗣂ꖞ�B�̒n�ɓ���Ɓj�A���{���ł����ς����Ƃ������Ƃ͕������Ă��܂����B���{���Ɍ�����ΎE����邩���m��Ȃ��Ǝv���܂����B�����Ŏ��͐������ɕϑ����ċD�Ԃɏ���V�ɖ߂�܂����B�x |
�@�w�ǂ̘b�̓r�������A�u�͖{��L�v�ł́A�͖{�͂����̂Ƃ�������̂悤�Ɍ����Ă���B�i��ł��o�Ă���B�j
| �w |
�`�A����̗��҂���A���w�ǂɑ����瑼�ӂ̂Ȃ����Ƃ������āA���݂₩�ɒ��i���w�ǁj�A�k���l�̋A�邱�Ƃ�ϜȂ����̂ŁA�悤�₭�w�ǂ����S���āA�邩�ɋ�́i���[��[�j�ɕϑ����ĕ�V�ɋA���Ă����̂ł������B�x |
�@�͖{�́A�N�ɂ�������Ȃ��Ǝv���Ď����̎咣�ɓs���̂����b���ł����グ���̂��낤�B�w�ǂ̘b�ɖ߂낤�B
| �w |
�@�N�������ƋC�t���܂���ł����B��V�ɋA���Ē����{�Ɏ����p�������Ă��A�����ł������ƐM���܂���ł����B�E�E�E���������͕��̎�����������܂˂ď������Ƃ��ł��܂������A���̈�ӂ��c���Ă��܂����̂ŁA���̖��Ŏ��X�Ɩ��߂������܂����B�����č����]���V�̌��Ď��������ׂĉ������Ă���A���̎��\�����̂ł��B�x |
�u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�ł́A���w�ǂ̑��߂��������L�тւ̃C���^�r���[���ĎO���p����Ă���B���̈��L�т͎��̂悤�Ɍ����Ă���B
| �w |
��X�́A���������{�̊֓��R�ɂ���Ďd�g�܂�Ă������Ƃ�m���Ă��܂����̂ŁA�������̎��\�����ɉB�����Ƃɂ��܂����B��X�͊֓��R�����������{���Ɏ����Ƃ�������A���̋@��ɏ悶�ĕ����V�ɐi�߂�̂ł͂Ȃ����Ƌ��ꂽ�̂ł��B��X���B�������Ƃɂ��A���{�R�͍Ō�܂Œ����������̂��ۂ��A�͂����肵�������ނ��Ƃ͂ł��܂���ł����B�x |
| �w |
�������Ď��͂��܂��^�т܂����B���w�ǂ��֓����疳���߂邱�Ƃɂ��A���̓�ǂ����ꂽ�̂ł��B���k�̘V���������́A���w�ǂ��Ⴂ�w���҂Ƃ��ė��h�Ɉ�ďグ�Ă����̂ł��ˁB���w�ǂ͂����̈АM������A�ނ̋A�Ҍ�͕�V�R�����������Ɉ��肵�܂����B�������ē��{�̓`�����X��������ꂸ�A���������Ƃ͂ł��܂���ł����B�x |
�@�����ł�͂���ɂȂ�̂́A�������̌�p�ґI�тł���B�鍑��`���{�ɂƂ��ẮA���B�̘��S�̓��I�тƌ������Ƃł�����B
���x�����p���Ă���͖{��L�i���|�t�H�@���a�Q�X�N�P�Q�����j�ł́A�����̎���͂��ڂ����B
| �w |
�E�E�E���{���ł͍���̓��O���i�����B�j�̎�]�҂ɂ́A�N��I�Ԃׂ����ɂ��Ď�X�̈ӌ����s���A��V�R�̌R���ږ�ł��������䎵�v������h�͗k�F��i���悤���Ă��j�𐄂��A������V�����@�ւɂ������`�^�������̈�h�͒��w�ǂ𐄂��A���̊ԂɎ�X�Ó����������B�x |
�@�k�F軂́A�������̒��N�̕����ł���A�������Ȃ����ƒ��w�ǂƕ���ŁA��V�R��������������l���ł������B���w�ǂƊr�ׂ�ƁA�����ɂ������^�C�v�̌R���R�l�ŁA�����̕�V�R�����̐l�]�͒��w�ǂɏW�܂��Ă����B�܂���V�R���ɓ��{�̌R���ږ₪�����A�Ƃ����ƂȂɂ���قɊ������邩���m��Ȃ����A��́u�Q�P�������v�̒��́u�얞�B�ɉ�����O���ږ⋳���Ɋւ�����������v�Ɂu�x�ߍ����{�͏����얞�B�ɉ����Đ��������R���x�@�Ɋւ���O���ږ⋳����b�ق��ނƂ���Ƃ��͍Ő�ɓ��{�l��b�ق��ׂ��B�v�Ƃ���̂����{����Ă����̂ł���B
�@�܂��A�����@�ւ́A���{��vi���������������ł́u��ɌR���܂��͏��R���g�D�ɂ��������R���g�D�������A����E�镏�H��E�Δ������Ȃǂ��̒n��A�����͍��n��ōs���g�D�ł���B�L�`�ɂ͂����ɗނ������C���𐋍s����g�D���܂܂��B�v�i�����@����http://ja.wikipedia.org/wiki/�����@�����j�Ɖ��̂��Ƃ��킩��Ȃ����������Ă��邪�A�v����ɌR���H��@�ցE�R������@�ւł���B���̎����鍑��`���{���A�A�w�������A�U���A�E�l�A�����Ȃǂ��܂ޕ\�����ɏo���Ȃ��悤�ȉ����d�������Ɉ������B���B�ɂ������V�����@�ցA�ؖk�ɂ�����V�Ó����@�ւ��L���ł���B�i�����@�ւ͖{���L���ɂȂ��Ă͂����Ȃ��͂������A����͂ǂ��Ȃ낤���H���ɂ͂킩��Ȃ��B�j
�@���ĉ͖{�𑱂��悤�B
| �w |
�E�E�E���̂܂ܕ�V����ɂ����i�����w�ǂ��A�k�F軂����{�R���x�����ĕ�V�ɂ͖߂�Ȃ������j�A�匠�҂Ȃ��Œu�����Ƃ́A������ʔ����Ȃ��̂ŁA�`�A����̗��҂���A���w�ǂɑ����瑼�ӂ̂Ȃ����Ƃ��������i���͖{���̉����������A�e�����ÎE���Ă����āA���瑼�ӂ͂Ȃ��A���Ȃ����̂��B�j�A���݂₩�ɒ��A�k���l�̋A�邱�Ƃ�ϜȂ����̂ŁA�悤�₭�w�ǂ����S���āA�邩�ɋ���i���[��[�j�ɕϑ����ĕ�V�ɋA���Ă����̂ł������B�i���܂��Ղ��Đ\����Ȃ��B�͖{�̂��̂������悭�킩��Ȃ��B���S�����l�Ԃ���͂ɕϑ����ĕ�V�ɋA���Ă�����̂��B�\���x����������A���w�ǂ͂��������̂��B�͖{�͎������킩���Ă��Ȃ����Ƃ��A���X�Ƃ��ĉ�����Ă���B���������l���͖₢�ɗ����Ȃ��Ō��ɗ�������̂��B�j
���傤�ǂ��̍��̂��Ƃł������B�O�x�ߑ�g�ь���������V�֗��āA�܂����ƂȂ����������ʋC�����ł��钣�w�ǂɈ������B�x |
�@�@�@ |
|
 |
|
�@�͖{�͉��̂��������������������̂��B�����͒��ڂ̎��M�҂ł��镽��뎙�������ԈႦ���̂��B�ь����́A�������g�A�x�ߒ����g���C�������������Ƃł���A�Ȃɂ�蒣�����E���w�ǐe�q�Ƌɂ߂Đe���ȊW�ɂ������B
�@�Ƃɂ����A���w�ǂ��������{�̑��ɒǂ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl�����c���`��́A�ь�����I��ŁA�����S����g�ɔC�����A�������̑��V�ɏo�Ȃ�����ƂƂ��ɁA���w�ǂ̐����ɓ����点���̂ł������B�O���Ȃ̊O�������قɂ́A���̎��c�����тɗ^�����w�����u�ё�g�m���w�ǃj�\�����x�L��|�v�Ƃ����������ۑ�����Ă���B�i�������B���͒��ړǂ�ł��Ȃ��B�j
�@�ȉ��́A�u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�i�p�앶�Ɂ@�����V�N���P�X�X�T�N�T���Q�T�����Łj����̈��p�ł���B
| �w |
�u���B�n���{�̊O�s�i���[�v�Ƃ��������o������n�܂邱�̕����̒��œc���́A�������Ƃ̊Ԃő��������{�Ƃ̗F�D�W�������������w�ǂƂ̊ԂɈێ����A���͂��Ė��B���u�x�ߑS�y���Ń����B�V�^�y�n�j�V�^�C�v�|�͐����Ă���B�������A���̎��́A��͂荑�����{�Ƃ̑Ë��ɒ��w�ǂ�����ʂ悤�ނ������~�߂邱�Ƃł������B�u�O����`�A�V�������i���������{�̍����j�m�̗p���i���f���i�C�g�]�t���m�K�A���K�A�����i���c���`��̂��Ɓj�n�R������t���`�e�m���f�ʖڃf�A���g�l�փ��B������̓m�N���i��������͓͂싞�Ɏ�s��u���������{�̂��Ɓj�O�N�������P�l�o���{�m�ӎu�n�B���Z�k�g�m�M�X���B�v�x |
�@�@
�@�����ɂ��A�ь����́A�P�X�Q�W�N�i���a�R�N�j�̂W���W���A�X���A�P�Q���ƎO��ɂ킽���Ē��w�ǂƉ�k�����B�����Ď��̂悤�ȍ��ӂɒB�����B
| �w |
��k�Ë��j�փV�e�n�[�e�j�p�O�����Ԍ`���ϖ]���׃X�R�g�j����V�^�x |
�@�����͎��̂悤�ɉ������B
| �w |
���Ȃ킿���w�ǂ́A�������{�Ƃ̑Ë����O���������҂Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���B�E�E�E����͈ꉞ�A�ѓ��g�̃����c�𗧂Ă��Ƃ������邪�A�t�Ɍ����ΎO������ɂ͍������{�̎P���ɓ��邱�Ƃ����肤�邱�Ƃ���{���ɔF�߂������ɓ����������B�E�E�E���������{���́A���̂Ƃ����w�ǂ��A���łɍ����}�̎P���ɓ��蒆���̓���Ƃ������������̓���������ƌ��ӂ��Ă������Ƃ܂ł͎v������Ȃ������̂ł���B�x�i�o�T�X�j |
�@���ĉ͖{�͂��̌o�܂��ǂ��������Ă��邩�H
| �w |
�ь����͊w�ǂɁA���{�O�j���̊փ������̖L�b�A����̊W�̈�߂�����āA�ÂɊw�ǂ��G���ɁA�k�F軂��ƍN�ɋ[���āA�傢�Ɋw�ǂ����サ���B�x |
�@�͖{���͚o���ׂ��ł���B |
|
 |
|
�@�u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�Ƃ����{�́A���w�ǂ̃C���^�r���[���܂�ł���B�Ƃ������A�X�O�̒a�������@��ɑ�p�ł̓�֏�Ԃ���������������w�ǂɁA�m�g�j���C���^�r���[���e���r�ԑg�����̂����Ƃ��Ƃ̖ړI�ł������B���̃e���r�ԑg�͂m�g�j�X�y�V�����w�u���w�ǂ͂��܌��v�\�����푈�ւ̓��\�x�Ƒ肳��ĂP�X�X�P�N�ɕ��f���ꂽ�B���̂Ƃ��̎�ލޗ��Ƃ���ɔ��������ޗ����܂Ƃ܂��Ă��̖{���ł����̂�����A���w�ǂ̃C���^�r���[�����̖{�̒��Ɋ܂܂�Ă��ē��R�ł���B
�@���̖{�͒��ڒ��w�ǂɃC���^�r���[�������j�w�҂̉P�䏟���Ɠ����̂m�g�j�̓��ʎ劲�������鑺�Ƃ����l�����\�ɏo�Ă��邪�A���ۂ̎��M�҂͓����̔ԑg�f�B���N�^�[�������A������Ɖ��c���ł���B�����A���̒�����ł���B���������D�G�Ȑl�����A�m�g�j�̒��S���牓�������A�m�g�j���u�̐��v���o�K���_�v�W���[�i���Y���ɂȂ��Ă����̂́A�c�O�ł���B
�@�Ƃ��������̃C���^�r���[�Œ��w�ǂ́A�ь����Ƃ̉���ǂ��������Ă���̂���������Ă݂悤�B
| �w |
�ь�������͍ĎO�ɂ킽���āA���ɍ������{�ƍ��삵�Ȃ��悤�ɓ��������Ă��܂����B���͍Ō�܂Ŗ��m�ȕԓ������܂���ł����B�����Ă����̂ł��B���́A�ނ��A�鎞�H���ɏ��҂��A���������݂܂����B
���̎��A�т���͂��������܂����B�u���Ȃ��̂�������ƁA���Ƃ͌Â�����̗F�l�ł��B�������A���͐��{�̖����Ă��Ȃ��̂��Ƃ�K�ꂽ�̂ł��B����ɂ�������炸�A���Ȃ��͏I�n���m�ȉ����܂���ł����ˁv
�����Ŏ��͂����������̂ł��B�u�ѐ搶�B���Ȃ������̑���ɂȂ��čl���Ă������������Ƃ́A�����g���l��������A�����Ƃ��炵�����̂ł����v
����Ɣނ͂ƂĂ���т܂����B
�u�ł��A�ЂƂ����l���Ă���������Ȃ��������Ƃ�����܂��v�Ǝ��������ƁA�ނ͉��b�Ȋ�����āA�u������������͂Ȃ�ł����H�v�Ɛq�˂��̂ŁA���͓����܂����B�u����͎��������l���Ƃ������Ƃł��v�x |
�@���w�ǂ��싞���{�Ƃ̍������l���Ă����̂́A�Ȃɂ����{�R�ɕ����������E���ꂽ�Ƃ������R����ł͂Ȃ��悤���B
�@��ꎟ�������삪�������āA�싞���{���k�����J�n����B�����ČR���E�k�����{�̑œ|��ڎw���ē{���̔@���k�サ�Ă���B
�i���̂U�u�^�������`�Ɖ�X�s���̐ӔC�v
��http://www.inaco.co.jp/isaac/back/023-6/023-6.htm���Q�Ƃ̂��Ɓj
�������͂��̖k���ɉ�����A�싞���{�ɑΌ��p���������悤�ɂȂ�B�܂����̂��Ƃ��A���֕�������𐄐i���A�������ɂ͖��B�ɕ��������ĉ��a�������S�ł��ė~���������鍑��`���{���A��������������v���ɂ��Ȃ����̂����A���w�ǂ́A�鍑��`���{�Ƃ͑S�����̗��ꂩ��Y��ł����B
| �w |
�������͕��̂��ƂŔY��ł��܂����B���͕����s���Ă������ɔ�����������ł��B�ł����玄�͕��ɁA�u������������Ă��邱�̐푈�ɁA�ǂ̂悤�ȈӖ�������̂ł����H�Ȃ��������́A����Ȑ킢�����Ă���̂ł����H�v�Ƌl�ߊ��܂����B���͉͓�ȂŘH���ɖ��������̐l�����āA�ƂĂ��������Ɏv���܂����B���͗܂𗬂��Ȃ��狩�т܂����B�u����͈�̂ǂ��������ƂȂ�ł��H��̉��̂��߂ɁH�v���̎��A���̂悤�ɐl�X���ꂵ��ł����̂́A���ׂē���̂����������̂ł��B�x�i�u���w�ǂ̏،��v�O�f���j |
�@���w�ǂ̂��̌��t�ɑS���E�\���������Ă��Ȃ��������Ƃ́A��ɋN����u���������v�ŗ��h�ɏؖ������E�E�E�B
| �i |
���w�ǂɓ��ꍞ�܂Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ��Ă���B���ꍞ�ނƒ����Ȃ�B����Ȓ������́A��̒N���ǂ�ł����H�E�E�E�������A�����A�ǂ��Ƃ��Ȃ�I����͎������g�̂��߂ɏ����Ă���̂��B�j |
|
|
 |
|
�@�������āA�P�X�Q�W�N(���a�R�N)�P�Q���A���w�ǂ͗тƂ̖�������`�ŁA�V�������B�Ɍf���A�싞�������{�ɍ������邱�Ƃ�\�����A�����ɓ싞�������{�̖k���͏I�����A�S������͊�������̂ł���B
�@�u�V�������B�Ɍf���v�Ə��������A����͗��j�Ƃ����̏o�������`�e���鎞�̌��܂蕶��ł���B�����玄�����j�Ƃ́u���w�I�\���v�Ƃ��Ď~�߂Ă����B�܂���ۂɐV���������f����ꂽ�̂ł͂Ȃ��i���肟�A�P�{��Q�{�͗g�������̂����m��Ȃ����j�A���w�NjA���̑㖼���I�\�����Ƃ������Ă����B
�@�Ƃ��낪�A�u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v��ǂނƁA�����ł͂Ȃ��A���ۂɖ��B�S�y�ɐV���������|�����悤�Ȃ̂��B
�ȉ������o�X�V�̋L�q������������p���悤�B
| �w |
�������A���̍����łɒ��w�ǂ͓��{���̎��X�͓����������͂˂��A��V�R���̈ꕔ�ɂ��������Έӌ���}������`�ŁA�������{�̒����̓���𓌖k������邱�Ƃ����ӂ��Ă����B�����ĂP�X�Q�W�N�P�Q���Q�W���ɁA���k�S�y�̊����A�������{�̐V�������Ɏ��ւ���u�՛�i�������j�v��f�s�����B����ɂ��A���{�Ƃ̌��ʂ̎p����N���ɂ����̂ł���B
�@
| �i�� |
�ȉ��C���^�r���A�[�̎���j |
| �\ |
�u���̈՛�͒����̓���Ƃ����_���猩�āA���j�I�ɔ��ɏd�v�ȕ���_���Ǝv���܂����A���̈՛�̏����͂ǂ������ӂ��ɂ����̂ł��傤���v
|
| �i�� |
�ȉ����w�ǂ̓����B�����ɂ́u�v�͂Ȃ��B�j |
�@�u���͖��߂��Ă���R���Ԃŗp�ӂ����܂����B�핞�H��ŐV����������点���̂ł��B�����A�����͎�����ɋ���Ă��܂����B���͔��Ɍ������A���̌��������Ƃ͕K�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B�ł��Ȃ��ƌ������Ƃ͋�����܂���ł����B�������{�l�͎����������D��Ă���Ǝv���Ă����悤�ł����A�����̂��Ƃ��܂������������Ă��܂���ł����B���̂Ƃ�����������V�������Ɋ����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A���{�l�͋C�t���܂���ł����B�P�{�̊������ł͂Ȃ��A���k�S�y�̊��������鏀�������Ă����ɂ�������炸�ł��B���{�̒����͎��ɂ��e���ŁA���������̂��߂ɒ��������́A�S�Ă��ݔ��Ɏ̂Ă������R�ł����B�v�x |
�@�@
�@���̒��w�ǂ̘b�ɏo�Ă���u��V�R���̈ꕔ�ɂ��������Έӌ��v�Ƃ����̂͋�̓I�ɂ͗k�F軂̔��ł���B
�@�]���Ē��w�ǂ͗k�F軂Ƃ̑Ό��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@���̊m���̂��Ƃ́A�u�͖{��L�v�ɂ��o�Ă���B�ŏ��ɂ�������悤�B�����A�u�͖{��L�v�ł́A���}�G�g�Ȃ����Ƃ̏G���w�ǂɋ[���A�k�F軂��ƍN�ɋ[�����炢�̃Z���X������A�債�Ėʔ������͂ł͂Ȃ��B�������A�����̒鍑��`���{�E�֓��R���A�����ɓƑP�I�Ȏ�Ϙ_�̗��ꂩ�玖�Ԏ��E���l���Ă�������m��ɂ͊i�D�̍ޗ��ł���B
| �w |
�w�ǂ̗k�ɑ����ȋ^�͂����ɂ����Ă��悢��[���A�k�ɑ��Ċw�ǂ͂Ђ����ɊQ�ӂ������悤�ɂȂ����B
������������̗��N�i���P�X�Q�X�N�����a�S�N�j�S���A�w�ǂ́A��V�R�����ɗk�F軂��������B�����Ă��˂Ėd���Ă����A�q�����̖^�����āA���̏�ɗk���s�X�g���ŎˎE�����Ă��܂����B
�����m���Ă��˂Ċw�Ǘi�����l���Ă����`�����A��V�R�ɂ͂����Ă������珫�R�i�r�،ܘY�j���́A�����������̋@��𑨂��āA���w�ǂ��匠�҂ɐ����A�w�ǂ�e���ɓ�����Ɖ���B�������������łɊw�ǎ��͂̎Ⴂ�v�l�B�́A���ĂɐS�����āA���R��`�I����ɂ����āA�w�ǂ��܂������̎҂��u���C���Ƃ��ďd���p���Ă����̂ŁA�w�ǂ̋����́A�Q�X�Ɣr���ɕψڂ��A���ɂ͕����Ƃ܂Ői��ł������B�x |
�@���͖̉{�̔F���́A���Ȃ킿�͖{�����̘b��뎙�ɏ����Ƃ点���̂́A���ł���B���̎��_�ɂ����Ă��A�͖{��֓��R�͂Q�W�N�P�Q���̒��w�ǂ̈՛���A���m�Ȉӎv�\���Ƃ��ĔF�����Ă��Ȃ������B�܂����̂S������A�w�ǂ��A�e���h�ł���싞���{�ւ̍����Ɋ拭�ɔ����Ă����k�F軂�d�E�������Ƃ����m�Ȉӎv�\���Ƒ����Ă��Ȃ������B�֓��R���܂����l�ł���B
�@�͖{�͎������ɋ����u�����ʁv�ł���B�������A���̍��́u���V�A�ʁv��u�����ʁv���S���Ώۂɂ��ĉ����������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ͂������ڂɂ�����B����Ζ����ĐX�����Ȃ��A�Ƃ��u��m�����v�Ƃ������\�����悭���Ă͂܂錻�ۂł���B�܂��Ƃɒ��w�ǂ��u���{�l�͒����̂��Ƃ��S���������Ă��Ȃ������v�ƌ����Ƃ���ł���B
�@���ɉ͖{����ł͂Ȃ��A���̎���̑����̌R�l�A�����ƁA�W���[�i���X�g�A�w�҂ɂ��Ă�������̂����A���{����芪�����ۏ�̕��͂��A�͖{�������Ŏg���Ă��錾�t�A�u�����v�i����͗]�肨�߂ɂ�����Ȃ�����ǁj�A�u�r���v�u�����v�Ƃ������t�ɑ�\�����悤�ɁA�u���{�ɑ���ԓx�E�p���v�Ŕ��f����ɂ߂đe�G�ȔF�����傫�ȓ����Ƃ��Ă�������B |
|
 |
|
�@���́u�k�F軖d�E�����v�w�ǂ̑����璭�߂Ă݂�Ƃǂ��Ȃ�̂��H
�@�O�f���u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�ł͓��R���̎����̂��Ƃ��o�Ă���B�������{�Ƃ̍��́A���������ڎw�����w�ǂɂƂ��āA�i��œ��{�̘��S�ɂȂ邱�Ƃɂ���Čl�I�Ȑ����I��]���������悤�Ƃ���k�F軂́A�܂��ƂɊ댯�ȑ��݂ɂȂ邩�炾�B
�@�������Ȃ����Ƃ́u���B�̎x�z�ҁv�́A���{�̃W���[�i���Y�����u�A�w�����Ŋ��ҁv���̂Ƃ������ĂĂ����ɂ�������炸�i���ے��w�ǂ̓A�w���z���҂������B�j�A������悭�m����̂̒��ł́A���w�ǁA�ƏO�ڂ͈�v���Ă����悤���B�F�X�Ȑl�������ꂼ��̎v�f�������Ċw�ǂɐڋ߂��Ă����l�q���`����Ă���B�������A�����|��N�A�y�쌴����Ȃǂ̖��O���������Ă���B���̎����̓y�쌴�́A��V�R�̌R���ږ�ł��������A���w�ǂɖ��B�鍑�̍c��ɂȂ�A�Ə��߂��Ƃ����B��ɓV�Â��爤�V�o����V��S���o���āu���B�鍑�v�̍c��ɐ���������������S�l�����y�쌴�ł��邱�Ƃ��l����ƁA���̊w�ǂɑ���y�쌴�́u�����v�͋ɂ߂ċ����[���B
�@���łɊw�ǂ́A�u�����l�v�Ƃ��āA�����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃ͒����̓���ł���A���̒����̓���̂��߂ɂ͂��ׂĂ̂����i�������g�̖����܂߂āj������s�������ӂ�[���ł߂Ă�������A���炭�͂��̓y�쌴�́A���悻�������́u�����v�ȂǏΎ~�疜���������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B
�@���ėk�F軂̂��Ƃł���B�k�F軂��A�Ӊ�������{�̉��ɍ~�邱�Ƃ������Ƃ��Ȃ������̂́A����Ӗ����R�ł�����B
�@��q�̊w�ǂ̑��߂��������L�т́A���̎��̂m�g�j��ރ`�[���Ɏ��̂悤�Ɍ���Ă���B
| �w |
���w�ǂɂ͈����S������A�����ɓ��{�ɑΛ�����ɂ͓��k�n�������ł͕͗s���ŁA�S���I�ȗ͂��K�v���ƍl���Ă��܂����B�����ŐV���������f���邱�ƂŁA�������{�̎x�z���ɓ������̂ł��B��X�ɂƂ��Ă���͑�ςȂ��Ƃł����B
�������̕�V�R�ɂ͂R�O���̕��͂�����A�C�R�ɔ�s�@�������Ă����̂ł��B�����Ӊ�̌R���͂Q�O���ɉ߂����A�C�R����s�@������܂���ł����B�ł����琔���I�Ɍ���Ύ������̐��͂̕����傫�������̂ł��B�����������������Ă�����A�����č������{�ɕ��]���邱�Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ����ł��傤�B�������A���w�ǂ͍����̓���̂��߁A�w���ɑΛ����邽�߂ɂ͒����ꂷ�邱�Ƃ��K�v�ł���ƍl���A�B�R�Ƃ��ĐV���������f�����̂ł��B�x |
�@�����k�F軂̗��ꂩ�璭�߂Ă݂�A�ɂ߂ėU�f�I�ȏł������͂����B
�@�����A�k�F軂Ƃ����ЂƂ�L�͂Ȑl������V�R���̒��ɂ����B����Łi���傤�����j��http://ja.wikipedia.org/wiki/����Ł��ł���B����ł́A�R�l�����A��V�R���̉^�A���ł���B�P�X�Q�W�N�i���a�R�N�j�S���̒��O���ƐV��́u���܂����Ȃ��ė������F�̓S�����v��http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/ContentViewServlet?METAID=00102154
&TYPE=HTML_FILE&POS=1&LANG=JA���Ƒ肷��A�ڋL���̒��ɂ��o�ꂵ�Ă���B
�@��������ł́A�����S�����\�A���甃�����āA��V�R���̒��ɉ����悤�ƌ����v��������Ă����B��������V�R���E���B�̌o�ϗ͂̂��߂ɂ́A���R�̌v�悾���A�k���B����\�A�̉e���͂�r������ɂ��D�s�����B����������͏���ł̌��͂��������邱�Ƃł��������B���w�ǂ͂��̌v��Ɏ^�����Ȃ������B
�@�u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v����A���w�ǂ̔鏑����������i��イ�߂����イ�j�̘b�����p����ƁA
| �w |
�k�F軂Ə���ł́A�����\�A�����v�������Ă��������S���i�������S���̂��ƁB���͏��ł��Ă���̂�����A���̎��㓌���S���͂�͂肨�������킯�ŁA�����S���Ƃ������S�H�̕������������������Ƃ͎v���B�j�̌��v���������悤�ɒ��w�ǂɋ��߂܂����B��������ł͓��k��ʈ���̕��ψ��������Ă���A�����S����ނ̎蒆�Ɏ��߂��������̂ł��B���������w�ǂ͂���ɓ��ӂ��܂���ł����B����ł͓S���ē��Ƃ����@�\����ɓ���悤�Ƃ����܂����B���������w�ǂ͂�͂蓯�ӂ��܂���ł����B����Ɨk�F軂���ⳂɁu����ł�S���ē��̊ēƂ��Ĕh������v�Ə����A���w�ǂɏ��������v���悤�Ƃ��܂����B
���������k�F軂Ə���ł̂����͍������̂ł����B�E�E�E�����Œ��w�ǂ͂ӂ�����l�����邱�Ƃ����ӂ����̂��Ǝv���܂��B�x |
�@���w�ǎ��g�̓C���^�r���[�ɓ����Ď��̂悤�Ɍ����Ă���B
| �w |
�E�E�E�������́A�k�F軂Ə���ł̊�ĂɋC�����Ă��܂����B�ނ�͕���ƒe��𓐂�Ŕ������N�������Ƃ��Ă����̂ł��B���͂��Ƃ����O�������������N�����Ă��K���Еt���Ă݂���Ǝv���Ă��܂����B��������ōl�������A��͂肻�����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B���̐l����c���łЂǂ��l�Ԃ��Ǝv����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B���������̂܂�����܂˂��Ă��Ĕ������N����������A�܂��s����̂Ƃ��̂悤�ɁA���O�╔�����ꂵ�ނ��ƂɂȂ�ł��傤�B����Ȃ�Δ������N�����O�ɁA���Y���ׂ����ƍl�����̂ł��B���Ƃ����l�ɔl���A�c�����Ǝv���悤�ƁA���̂悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƌ��S�����̂ł��B�x |
�@�Ȃ��u���w�ǂ̏��a�j�Ō�̏،��v�̎��M�҂͗k�F軂����ł�̎����w��V�R���̐e���h�̏d���x�Ƃ����`�e�����Ă��邪�A���͂��̓�l���u�e���h�v���Ƃ͎v��Ȃ��B�k�F軂����ł͓��{�̒鍑��`�̌�돂�����҂��āA�l�I�ȉh�B��]�ɉ߂��Ȃ��B�܂����w�ǂ͎�����̗��v�◧������S�Ɏ̂ĂāA�u��������v���̂ݖ]�A�Ƃ������m�ȈႢ������B
�@�܂����w�ǂɑ��ẮA���{�̍����ɍ������ᔻ�����邱�Ƃ������ł���B���Ƃ��A���������Έ��p���Ă���u��ꎟ���E���v�Ƃ����T�C�g�ł́A�����{�̓����ӏ������p������A���̂悤�ɘ_�]���Ă���B
| �w |
����́A�����܂����ى��ł��낤�B�k�F軂͂Ƃ���������ł���������Ă闝�R�͑S���Ȃ��B����ł͂��܂��ܖ�������邽�߂̖ʎq�����邽�ߓ��������̂ł���B�Â����炠��A�d�����_���������ĂĂ���ɂ����Ȃ��B��i�́u���O�ی�_�v�ȂǏΎ~�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ����낤�B���B�̌��͂����邽�ߎE�Q�����Ɛ����ɂ����Ȃ��w�ǂ̓��ڍ������o�Ă���B
�������w�ǂ����S�����̂́A�������i�P�W�W�U�`�P�X�T�V�j���痊�R�z�́w���{�O�j�x��������ꂽ�Ƃ��������Ƃ�����������B���́w���{�O�j�x�ɂ́A����ƍN�ƖL�b�G���Ɋۂ��`����Ă����Ƃ����B��삪�Ȃ��k�F軎E�Q�������������Ƃ����A�u�ł���Ȃ�Β����������ē��O�Ȃɉ����������������ꂽ���Ɛe�g�ɍl����悤�ɂȂ����̂ł���܂��v�i���c�K�g�w���������m�̐��U�x�j�Ɩ{�l���������Ă���B�x |
�@�������̃T�C�g�̎��M��(�����̃T�C�g�ł́A���������ʔ����c�_��W�J���Ă���̂ɖ��O�𖼏���Ă���Ȃ��B�����s�ׂƎ����̂������A���邢�͖���m����̂��݂��鎖��X�͗����ł��邪�A����ł͐܊p�c�_���ł��Ȃ��B���̃T�C�g��������������l�ł���B)���A�c��_�Ȃǂƈꏏ�ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��B���̃T�C�g���͎����Ȃ�Ɍ��������A���̏�Ō��_���o���Ă���B������Ƃ͌������Ⴄ���A�����[����A���āA�c��_�ȂǂƂ����������傱���傢���g���Đ��_��U�����悤�Ƃ���w�ҁE�����҃O���[�v�Ƃ͖��炩�Ɉ���Ă���B
�@�P�ɓ������j�����A�������������Ă��������������Ă��邾�����B�����炱�������l�����Ƃ���ꂪ�A�s�����m�Ő^���ȋc�_�����čs�����Ƃ���Ȃ̂��Ǝv���B
|
|
 |
|
�@�Ƃ܂�A�������āA���w�ǂ́u�՛�v�́A���������E���������G�|�b�N���C�L���O�Ȏ����Ƃ��ċL�����Ă����˂Ȃ�Ȃ����낤�B���̎��A�܂���Ȃ�ɂ��������{�͒����ꂵ���̂��B
�@�P�X�Q�X�N�i���a�S�N�j����P�X�R�P�N�i���a�U�N�j�X�������Ύ������������A���B���ς��N����܂ł̂킸���Q�N���܂肾���A���B�͒����l�ɂƂ��Đ�O�ō��̉��������}����̂ł���B
�@�w�ǂ́A�����������̂P�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�U���A��V�R���ŗ��R�叫�ɔC�����Ă���A������̃i���o�[�c�[�������Ƃ����Ă����B�Q�W�N�i���a�R�N�j�U�����������E�����ƁA�������Ɂu��V�فv�ɏA�C��������̃i���o�[�����ɂȂ�B���̓������U���ɂ́A�Ӊ���k���ɓ��邵�A�����̕�̑O�Łu�k���v�̊��������B����͎����͂Ƃ����������̍�����������{�������ꂵ���`����邱�ƂɂȂ�B
�@���k�O�Ȃ̔e�ҁA���w�ǂ��Ӊ�ɔ����ł��|���Ȃ�����A�鍑��`���{�͂��́u��������v�Ɋւ��āA�����������͑S���Ȃ��B�u���������E�v���_�@�ɕ�V�R�������A����������Ɉꋓ�ɌR���s���ɏo�āA���B�S�̂��̂��悤�Ƃ����v����܂�������U��ɏI������B
�@�鍑��`���{�͂܂������\�ʁA�w�������Č��Ă��鑼�͂Ȃ������̂ł���B
| �i�� |
�������A���{�̎x�z�w�́A�������Ԃ����قǐ[���ɍl���Ă��Ȃ������B�ڍׂȘ_�͏Ȃ����A�傫���͂R�̌������������̂��Ǝv���B
| �P�D |
���w�ǐ������̂��̂ɑ���ߏ��]���B |
| �Q�D |
�Ӊ�������{�ɑ���ߏ��]���B |
| �R�D |
�鍑��`���{�̌R���͂ɑ��鎩�M�B�j |
|
�@�����ĂQ�W�N�P�Q���́u�՛�v�̂��ƁA�������{����́A���k�Ӗh�R�i�ߒ����ɔC������A�`�̏�ł͍������{�̒��ɑg�ݓ�����邱�ƂɂȂ�B
�@�w�`�̏�ł́x�A�Ƃ����̂́A�������{���̂��R���A���̂ł���A���̎��������Ē����l���̗��v���\�������{�ł͂Ȃ��������炾�B�]���āA���w�ǐ��������k�n���́u�R���v�Ƃ��āA�����̐��͔͈͂̊g���ɐ��͂𒍂�����Ȃ����A�܂����ꂪ�����Ƃ������ȓ��ł��������B
�@�����A�w�R���x�Ƃ��Ă̒��w�ǐ����́A�ق��̌R���Ƃ͒������Ⴂ���������B�����l���̂��߂̐����������Ȃ������Ƃ��B��ɂ́A���w�ǎ��g�̗��z��`���������낤���A���B���V�����u�o�ϔ͈́v�ł��������߁A�k����̃\�A�A������̓��{�������ƁA���̌R���̂悤�ɒn����ɁA����I�ɑ傫�������������ێ������i���Ƃ��Ο��]�����̂悤�ȁj�����݂��Ȃ������Ƃ����v�f���傫���̂�������Ȃ��B
�@�R�����r�A��w�}���ق̏�������u���w�Ǖ����v����ʂɌ��J���ꂽ�̂́A���Q�O�O�W�N������A�������牽���V����������o�Ă���̂����m��Ȃ��B
�@�������{�l�̓��̒��ɂ́A�u���B�͓��{���J�A�ߑ�I�ȍH�ƒn��ɂ����̂��B�v�Ƃ�������������A����͂���ň����x���������A���Ƃ��Ɩ��B�J�����s���āA��������鍑��`�I���D���s���̂��ړI�������̂�����A�ے肷�ׂ��łȂ����A���̂��ߒ������E���w�ǎ���ɍs��ꂽ�u���B�̋ߑ㉻�v�̑��ʂ������Ƃ������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���Ƃ��A�������E���w�ǎ���ɐ��i�����S���~�ݎ��Ƃł���B |
|
 |
|
�@�P�X�Q�V�N�ɂ͑Œʐ��i�ŌՁ\�ʗɊԁj�A�Q�X�N�ɂ͋g�C���i�g�с\�C���j���J�ʂ����A�����̋�����������������B���̂Q�̓S�����݂́A��قLj��p�������O���ƐV��̋L����http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/ContentViewServlet?METAID=00102154&
TYPE=HTML_FILE&POS=1&LANG=JA���ɂ��ƃh�C�c���{�ɂ������Ĕ��������Ƃ̂��Ƃ��B����ɂR�O�N�ɂ̓h�C�c���{����̎؊��ɂ���ċяB�i�ɔJ�Ȃ̓s�s�B�ɔJ�Ȃ͓�����V�ȂƌĂꂽ�B�j�̓�ɂ������b���ɑ�K�͂ȍ`�p�ݔ������݂��悤�Ƃ����B���ꂪ��������A�����]�Ȃ�g�яȂ̔_�Y���E�����͓얞�B�S������{���{�̎{�݂Ɉ˂炸�A�C�O�ɗA�o�ł��邱�ƂɂȂ�B
�@����́A���{��������𗁂т邱�ƂɂȂ����B�Ƃ����̂́A�������͓얞�B�S���Ƃ̓S�����s�������Ȃ��Ƃ���������������ł���B�u������͓얞�B�S���Ƃ̕��s���Ŗᔽ���B�v�Ƃ����̂����̔��̘_���ł���B����͓������{�̘_�d�ŁA�������E���w�ǂ����ޗ��Ƃ��Ďg��ꂽ�B
| �i�� |
�����ċ����ׂ����Ƃɍ��ł��A���̓S���~�ݖ�肪�A�������ᔻ�̍����̈�Ƃ��Ďg���Ă���B�j |
�@���������̔��̍����ƂȂ��Ă���u�얞�B�S���ɑ��ĕ��s����~�݂��Ȃ��v�Ƃ����́A�ǂ��ɗR�����邩�Ƃ����ƁA�P�X�O�T�N���I�푈��Ɍ��ꂽ�u�|�[�c�}�X���Ɋ�Â��������v�i�����Ԗ��B�Ɋւ�����j�Ȃ̂ł���B�Ƃ��낪�A���̖́u���S���s���v�̒�`���s���Ă��Ȃ��B
�@���łɌ����A���̏��ł͖��S�����n�̑d����茈�߂��Ă��邪�A�u���S�����n�v�̒�`���s���Ă��Ȃ��B��`�����Ȃ��̂́A��`������Ƃ��̒�`�ɔ����邩��ł������B�ʂȌ�����������A�u��`�v�͊g����߂̗]�n��D���Ă��܂��̂ł���B
�@���̏����́A�����������B�ɂǂ�ȓS������~���Ă��A�u����͖��S�̕��s�����v�Ƃ����咣�̗]�n���c�����̂ł������B���������݂͂��̂܂�_�Ƃ��Ȃ�B�u���s���v�ɑ����`���Ȃ��̂�����A�u���s���ł͂Ȃ��v�Ǝ咣����A����͂��̂܂咣�̘_���ƂȂ肤��B�����Ē��w�ǂ͂��������B���|�_�ɂ����̂ł���B�鍑��`���{�͒��w�ǂ������т��Ă����B������Ɨ����Ƃ������Ƃ���ނ̎v���͖{���������̂ł���B
�@���x�����p����u���w�ǂ̏،��v�ŁA���w�ǂ͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
| �w |
�@���͌�ɑŌՎR���獕���]�֍s���S����~�݂��܂����B�������k�̎�v�ȎY���͑哤�ł����B�������͍����]�̑哤���^�Ԏ��ɓ얞�B�S���i���S�j�����R�Ɏg���܂���ł����B�܂��얞�B�S���͎������̗A������ɖW�Q���܂����B�܂��얞�B���o�R����ƑS�đ�A�̕��֍s���Ă��܂��܂��B�ł����玄�����͎��������̓S����~�݂��邱�Ƃɂ����̂ł��B
���������̓S���͓얞�B�S���ƕ��s���Ă���Ƃ����A���{�Ƃ̊Ԃő傫�Ȗ��ƂȂ�܂����B���������͕��s���Ă���Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B�x |
�@���ɂ��̖{�̃C���^�r���A�[�͎��ɔn��������������Ă���̂����A��������āA
| �w |
�E�E�E���́A���{�̖��S�Ƌ������悤�Ƃ��Ă̂ł͂���܂���B�����A�����̓S�����Ȃ���A���S���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ŁA�����̓S�������݂����ɉ߂��܂���B���������̓S���ɂ���Ė��S���e���������Ƃ͔F�߂܂��B
| �i�� |
����͔F�߂�A�F�߂Ȃ��̖��ł͂Ȃ��A�����̖��ł���B�Ɛ莖�Ƒ̂ɋ����҂����ꂽ�̂�����e�����Ȃ��͂����Ȃ��B�����������͋��Q�̐^���Œ��ł���A�l�Ƃ��̂̓����͋ɒ[�ɗ�������ł����B�j |
���͂Ȃ�ׂ����{�l�Ƌ��͂����������̂ł��B���Ƃ��A�S���̌��݂ɂ��Ă��A���̑ォ��͂��߂Ă���A�����Ǝ��ɂ͂��߂����Ƃł͂���܂���B
�Ƃ��낪�A���{�ɂ́A���͂��悤�Ƃ������ӂ�����܂���ł����B���͂���ɂ́A���݂������݊�邱�Ƃ��K�v�ł��B����Ȃ̂ɓ��{�́A��X���R���g���[�����悤�Ƃ��肵�Ă��܂����B����ł͂ǂ����悤������܂���B�x
|
| �w |
�@���b���̍`�����݂������Ƃ����ɂȂ�܂����B�����������͓��k�ō̂��哤���C�O�ɗA�o���Ă��܂����B���̂��߂ɂ͎��������̍`���K�v�������̂ł��B��A�ł͓��{�̐������܂����̂ŁA�������͎����̍`���������������̂ł��B���{�l�͓��k�̌o�ϗ͂��蒆�Ɏ��߂Ă��������Ǝv�����悤�ł����A�����������R�A���������g�̌o�ςW�����悤�Ǝv�����̂ł��B���{�l�͊��S�ɕs�����ȗ���ɂ��������������Ă��܂����B���������������A���n�̂悤�Ɉ����Ă����̂ł��B�x |
|
|
 |
|
�@�����Œ��w�ǂ������Ă���悤�ɁA��V�����͓Ǝ��Ɍo�ϊE�J�����s�����Ƃ����B�ڂ����������ʂ��܂����肵�Ă��Ȃ��������n���̊J���Ȃǂ����ł��낤�B�܂����琧�x�̏[���ɗ͂����悤�Ƃ������Ƃ������ł���B��V�ɓ��k��w��ݗ������̂����w�ǐ��������A���B(���k)�e�n�ɒ��w�Z�����݂����̂����������B
�@��V�������C�R�������Ă��������Ȃ��R�����������Ƃ͐�ɂ��������A���O�̋�R���������B�C�R���R������Ƃ������Ƃ́A�P�ɍq��@��R�͂����ނƌ������Ƃł͂Ȃ��B����𑀍�ێ�����l�ނ������Z�p��l�ށA�{�݂����ƌ������Ƃł�����B���R�̂悤�ɖ��B�i���k�j�̍H�Ƌߑ㉻�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����������B
�@�c��_���_���̒��ŁA�u�_�ƈȊO�ɂ͂قƂ�ǎY�Ƃ̂Ȃ��������B�̍r��́A�i���P�X�R�Q�N�̖��B�������Ȍゾ�Ƃ���ƂP�R�N�Ԃ����j�킸���P�T�N�̊Ԃɓ��{���{�ɂ���Ċ��͂���H�ƍ��Ƃɐ��܂�ς�����B�v�Ə����Ă���̂́A�܂����������̂Ȃ��f�^�������Ƃ��Ă��A���ł��u���B���J�������͓̂��{�������B�v�Ɣ��R�ƃC���[�W���Ă���l�͑����̂ł͂Ȃ����B
�@�m���ɁA�ƎR���S�i���̌㏺�a���|���A���B���S�Ɩ��O��ς��邪�j�̂悤�ɓ��{�l���J�������H�Ƃ�����ɂ͂���B�������S�̂Ƃ��Ė��B�̋ߑ�o�ς������͕̂�V�R���������̂ł͂Ȃ����A���{�͂����������`�Łu���B���v�����������̂łȂ����Ǝ��͍l���Ă���B
�@�u���B�������ɂ��ߑ㉻�v�Ƃ������e�[�}�ł̊w�p�������]�茩������Ȃ��̂ŁA���̌����͂܂��z���ɉ߂��Ȃ����A����͓��{�̌����҂����̃e�[�}�ɑ傫�ȊS�������Ă��Ȃ��������߂ł����āA���ۂɂ͕�V�R���͑����Ȗ��B�̌o�ϋߑ㉻�������Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���̑S�����Ă����ۂƂ����킯�ł͂Ȃ��A���̂��Ƃ��������킹��T�͂���������B
�@��ɂ͕�V�R���̌R���͂ł���B�R�O���̌R���A���������C��R������ɂ́A�o�ϗ͂Ƃ�����x����H�Ɨ͂��������͂����Ƃ��������B
�@����Ɛl���̑����ł���B�O��w�����l�ɂƂ��Ắu�n���̖��B���v�x
��http://www.inaco.co.jp/isaac/back/023-9/023-9-1.htm��
��http://www.inaco.co.jp/isaac/back/023-9/023-9-2.htm��
��http://www.inaco.co.jp/isaac/back/023-9/023-9-3.htm���ŏڂ����݂��悤�ɁA���B�̐l���͂P�X�P�P�N����P�X�Q�W�N�̊Ԃɂ����Ƃ������Ă���B�傴���ςɂ����ĂP�T�O�O���l����R�O�O�O���l���B����ł͂��ꂪ���ׂāA���B���ϑO�A���{�̎x�z���Ă������S�����n�ő������̂��Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B���B�����V���E�P�X�R�V�N1���P�U���t���̋L�������Ă��A�O�N�P�O�������ݖ��B��v�s�s�l���͂Q�S�W���l�ɉ߂��Ȃ��B�]���đO�q�̐l�������́A���S�����n�ȊO�Ŕ������Ă���Ƃ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�c��_�́u�i�����B�鍑�́j���������̂P�X�R�Q�N�P���ɂ͂R�疜�l�̐l���ł��������A���N�P�O�O���l�ȏ���l�������������A�P�X�S�T�N�̏I�펞�ɂ͂T�疜�l�ɑ������Ă����̂ł���B�v�Ə����Ă������A����͑傤���ł��邱�Ƃ͐�́w�����l�ɂƂ��Ắu�n���̖��B���v�x�̒��ŏڂ��������B
�@���������ۂɂP�O�O���l�߂��������N���Ȃ��������Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B�m�F�ł���Ƃ���ł����ƂP�X�Q�V�N�i���a�Q�N�j�����l�J���҂̓������́A1,043,772�l�A������281,295�l�ō�������762,477�l�����A���Q�W�N�͂��ꂼ��967,154�l�A342,979�l�ō�������624,175�l�̑����A�Q�X�N�͂��ꂼ��941,661�l�A541,254�l�ō�������400,407�l�̑����ł���B�u���B���v�����̂P�X�R�Q�N�i���a�U�N�j�́A416,825�̓������ɑ���402,809�l�̗����҂ł��荷������14,016�l�����������Ă��Ȃ��B�u���B��������v�́A�u���B���v�������l�̓����������������߂������āA���B�̒����l�l���͌���n�߂Ă���B�P�X�R�X�N�ȍ~�͂܂������l�J���҂̓������͂P�O�O���l���x���ɖ߂�̂����A����͑O���悤�ɁA���R���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�u���B���v���\�Z��g��Łu�J���Ҏ����v���s�������ʂł������B���̂��ߗ����҂̐����삵���������ł́A���ɒ������E���w�ǎ���ɂ͋y�Ȃ������B�i���֘A�������@�����l�J���ғ��������̔N�x�ʓ��v��http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/china/roudousya.htm���Q�Ƃ̂��ƁB�j
�@���͂Q�U�N�ȑO�̐����͎����Ă��Ȃ����A�z������ɖ��N�T�O���l�ȏ�̃��x���ő����������ɈႢ�Ȃ��B
�@�v����ɖ��B�̐l�����͒������E���w�ǐ�������ɂ��̃s�[�N���}����̂ł���A�u���B��������v�́A�����͂͂����萊���Ă���̂ł���B |
|
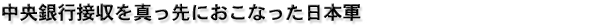 |
|
�@����ɁA��V�R���ɂ�閞�B�o�c�A�o�ς̋ߑ㉻����������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����T�Ƃ��Ă��������̂��A���B���ϒ���̓��{�R�̓����ł���B
�@�����Ύ����������Ƃ��āA���{�R�͈�ĂɌR���s�����N�����A���B�S�y���̂���̂����A���Ƃŏڂ�������悤�ɁA�ŋ��̌R���͂���������V�R�͌R���I��R���܂����������Ȃ������B
�@���ꂾ���ɓ��{�R�̓�������A���̐�̌v��Ƃ��̈Ӑ}���M���₷���B
�@�ȍ~�́A�É��N�v�́w���B���̌����x��P���u���B���v�̐�����Q�́u���B���v�̑n�o�A�Ƒ肷��_���ɉ����Č��Ă������Ƃɂ���B
| �i |
�É��̎�v�Ș_���́A���́A�قƂ�ǔނ̂v�����T�C�g���玩�R�ɖ����œǂނ��Ƃ��ł���B��http://www.furuyatetuo.com/��
�u�����A�v��http://www.furuyatetuo.com/goaisatsu.htm�������Ă݂�ƁA�u���A�É��N�v�́A2006�N12��2���ߌ�2��2���A���̐�������܂����B�v�Ɛ����l��H���������o���ł͂��܂��Ă���B
| �u |
�����̐l���́A�����̔\�͂��炷��Ώo���������B
���{�l�Ƃ��āA���߂Ĕs����o�����鎖���o���Ė������Ă���B
�_�l��������x���߂���l�Ԃ���点�Ă��ƌ����Ă��A��f�肵�āA���̕������������Ă����悤��肢�������B
���A���ƌ������̐��̉^��������A���̐��̐V�����^���Ǝ��g�݂܂��B�v |
�@�������A
| �u |
���a6�N3��21���A���́A���̐��ɐ��܂ꂽ�B
�@���̍��̓A�����J����n�܂������E�勰�Q�̔g�����{�ɂ������Ă��Ă���A���̒��͕s���̂��Ȃ��ł������B�����Ă��̔w��ł́A�R���͐푈�ւ̓��ɕ��ݏo�����Ƃ��Ă����B���̐��܂��O���ɂ́A�����ɏI�����Ƃ͂����A�R�����t�����邽�߂̃N�[�f�^�[���\�肳��Ă����B��Ɂw�O�������x�ƌĂ��悤�ɂȂ������̃N�[�f�^�[�v��́A�ɔ�̂����ɂ��ݏ�����Ă��܂������A�R������́A�w���N���x�ɂ��Ă̈Öق̗������A�R�������ɐ������������Ӗ����Ă����B�E�E�E�v |
�@�ǂ�ł��邤���ɌÉ��̎v�����`����Ă��Ėړ����M���Ȃ�B�É��́u���̐��̐V�����^���v�Ƃ͉����H���ɂ͕�����Ȃ��B�m���ɉ]���邱�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g����Ƃ����V���Ȏ���𗘗p���āA�É��͎����̌������L���s���Ɍ��J���A��������X�s�����ǂ�ōl���������邱�ƂŁA���������X�s�����w�сA���͂��x����Ȃ��A�����̓��ł��̂��l���邱�Ƃ̂ł���^�������`�Љ�̎s������l�ł�������肽�������ɈႢ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B�����É��̍D�ӂɂ������Ă����M�d�ȘJ������p�����Ă�����Ă���B
| �u |
���ꂩ���͒���E�_���Ŗ���܂��傤�B���p���Ē�����Ζ{�]�ł��B
�ł́A���悤�Ȃ�c�B�v |
�ƌÉ��͌���ł���B�j |
�@�É��_���̈��p����͂��߂悤�B
| �w |
�@�P�X�R�P�N�i�����a�U�N�j�X���P�W���ߌ�P�O���R�O���A�����Εt�߂̖��S�������j�����ƁA���{�R�͕�V�k��c�̒����R�ւ̍U�����J�n�A���P�X���ߑO�U���R�O����������S�ɐ�̂��Ă��邪�A���̏��R���s���ɂ��Ă͂��łɖ��炩�ɂ���Ă���Ƃ����Ă悢���낤�B�x�i���_���@�P���B�����̌`���@�o���_�Ƃ��Ă̕�V�R���j
|
�@�@
�@�Ƃ��낪�A�É��ɂ��A�Q�d�{���ҁu���B���ύ��o�߂̊T�v�v�i���쓰���X�����A�P�X�V�Q�N�j��
| �w |
�ߑO�T���R�O���������O�i���J�n�V�w�g��R����N���R�g�i�N�ߑO�U�����}�e�j�����i����s��V��̂��Ɓj������ǃm���j�i�o�V�ꕔ���ȃe��v�i�����ɁA��s������́x |
�@�Ƃ���Ƃ����B
�@�܂�A�֓��R�́A���B���ς̏����R���s���́A��V�����̎�s��V�ɂ�����R�����_�i�k��c�j��苒����v��Ɠ����ɁA�u��v�i�����ɁA��s���v���̖ڕW�Ƃ��A�قړ��������ɂ��̖ړI��B�������Ƃ����̂��B
�@�É��́A�u���ɏd�v�ȈӖ��������Ă���̂́A���O�Ȋ��⍆�Ȃǂ̋��Z�@�ւ̏����ł������Ǝv����B�v�Əq�ׂĂ���B
�@���O�Ȋ��⍆�́A��V�����̒�����s�̂悤�ȑ��݂ŁA�g�щi�t����K���i�g�яȁj�A�ӋƋ�s�i��V�j�A�����]���⍆�i�����]�ȁj�̂��ꂼ��̔�����s�ł������B |
|
 |
|
�@�u���B���v����������̂́A�P�X�R�Q�N�R���P���ł��邪�A���B������s�͑��������̂S������̂V���P���ɂ͊J�Ƃ���B���������w�ǎ��㓌�O�Ȋ��⍆�i�t����K���A�ӋƋ�s�A�����]���⍆�̎{�݁A�g�D��������������p���Ő�������̂ł���B
�i���Q�l���������B���Z�E�̍��́@�P�X�R�Q�N�P�P���@���������V���j
�@���������̖��B������s���فE�h����e�ɂ�邱�̋L���́A���w�ǎ���̋�s���Z�V�X�e���������ɗ����ŁA�l�����猙���Ă������������Ȃ���A�ˑR���̂悤�Ɍ����̂ł���B
| �w |
������s�̎����͌����A�����O�疜���ł��邪����������́A���Ɏ�������]�������Z���A���{���z�̖@���ɂ���s�������s����ɂ́A�O���̈�ȏ�̐��ݏ�����K�v�Ƃ��邪�A���̔���]�����̏������ɑ��āA�ꉭ�l��Z�S�]�����̋��������s�z�����Ă��邩��A���̏������͊��ɖ@������̏����z�̓�{�ȏ�ɒB���Ă���B
�����̔@�������̏[������͒P�ɓ��O�Ȃɂ����Ė��\�L�̂��Ƃɑ�����݂̂Ȃ炸�x�ߊe�n�̋�s�ɂ����Ă��܂�Ɍ���Ƃ���ł���B�x |
�@�����Łg�����R�O�O�O�����h�Ƃ����Ă���̂́A���B������s�n�݂̍ۂɓ��{�����{�������{���ł���B
�@���B������s�́A���{�ƓƗ������@�ւł͂Ȃ����߁A���B������s���͌����ɂ͒�����s���ł͂Ȃ��A�g�����h�ł���B���̂��߂��̋L���ł́u�����v�ƕ\�����Ă���B
�@�������������Ƃ��Ắg�����R�O�O�O�����h�́A���̎����̓ǂ݊ԈႢ�łȂ���A���{�{�����������邢�͊O���ʉ݂ȂǂŒ��B���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���N��s�Ƃ̑��ݕۏŒ��B���ꂽ���̂��B
�@�܂薞�B������s�������A�M���̂����鏀�����͂T�O�O�O�����������B�Ƃ������ƂɂȂ�B���̂T�O�O�O�����́A���w�ǐ�������̋�s���Y��ڎ����Ē��B�������̂��B���̂T�O�O�O�������������Ƃ��Ă݂�A�����s�z�P���S�U�O�O�����̑��������s�z�͋ɂ߂Č��S�ȏ�Ԃ��������Ƃ�������B
�@�܂�������o���̂R�O�O�O�����������Ȃ������A�悩�����̂ł���B����ɁA�Ɨ������@�ւłȂ����B������s���A���{�Ƃ͓Ɨ�����������s�ł��������w�ǐ�������̕������Z�V�X�e���Ƃ��Ă͂͂邩�Ɍ��S�������Ƃ����悤�B�@�@
�@���̎����́A�܂����B������s�̏������̒��ɁA����A�����A�V�Ë�A������Ȃǂ�ۗL���Ă������A�i�X�Ƃ��̌㎞�Ԃ��o�ɂ�āA�������̒��g�͓��{���A���{��s���A���B�����A���Ǝ�`�Ȃǂ��唼���߂�悤�ɂȂ�A���ꂪ���B���̒��C���t���̌����ɂȂ��Ă����B�i�O�f�Q�l�����Q�Ƃ̂��Ɓj
�@�܂������̑��̌R�������ł́A������s�ȂǂȂ������R�ł�������A�싞�̍������{�ł���A���t���̂Ȃ������������Ȃ������߁A�C���t���ɂ���Đl�������E���D���ꂽ���Ƃ��l����A��V�R���͋ɂ߂ė}���I�����S�ȋ��Z��������{�����Ƃ������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B |
|
 |
|
�@�����ɁA���B���ϓ�������֓��R���A���w�Ǒ̐��̒�����s�����������ڎ����悤�Ƃ����閧������悤�Ɏv����B�t�Ɍ����A�u���B���v�́A���S�Ȓ��w�ǐ����̋��Z�V�X�e�������̂܂�����A�Ō�ɂ͂����j�ł������Ƃ������������\�ł��낤�B
��قLj��p�����É��N�v�̘_���ɂ��A
| �w |
�E�E�E�]�����i�����{�R�j�ɂ����Z���Y�̕ی�Ƃ́A���̎��Y�w�ǐ������藣���āA�R���̈��艻�̂��߂ɗ��p�ł����Ԃɒu�����Ƃɑ��Ȃ�Ȃ������B�����Ă��̂��Ƃ͂܂��A���w�ǐ����̈��̈���x���A�ݕ���ʂ��ċz�����悤�Ƃ��邱�Ƃ��Ӗ������B
����������̖����A�P�X�Q�T�N�̊s������ڂ̂��������Ƃ��A�Ȍ�̒������R�̊֓��i�o�A�����v���R�i���k���R�j�ւ̔s�k�Ƃ������Ԃ̒��ŁA�u��V�[�̖\���v���ۂ��[�������Ă��������A���������E�����㖞�B�������������w�ǂ́E�E�E���̍��������E���đ������x�̕����̈�����������Ă����ƌ�����B���̖��ɂ��ẮA�������Y�̍ŋ߂̌����ɏڂ������A������������Y�͎��̂悤�Ɏw�E���Ă����B�x |
�@�������Y�͌����O���w�̋����Œ��������̌��Ђł����B��http://read.jst.go.jp/public/cs_ksh_012EventAction.do?action4=event&lang
_act4=J&judge_act4=2&code_act4=1000031855���܂��É����Q�l�ɂ��������́w���w�ǐ������̕������v-�u����m�[�v�̐����I�܈�-�x�i���m�j�����@�T�O���S���@�P�X�X�Q�N�j�̎��ł���B
�@�܂���������Y�͌����呍���Ōo�ϊw�҂̖�������Y��http://ja.wikipedia.org/wiki/��������Y���̂��Ƃł���A�É������p���Ă���_���́w���B����@�P�X�R�P�N�X���Q�S�t����e�_���x�̂��Ƃł���B
�@�É��͖���������̂悤�Ɉ��p����B
| �w |
�@�i���w�ǁj���{�͂P�X�Q�X�N�i���a�S�N�j�T���A���O�Ȋ��⍆�A�ӋƋ�s�A���ɒ����E��ʗ���V�x�X���ȂėɔJ�S�s�����s�����ɂ�g�D�����߁E�E�E�����������x�̉��Ɍ���m�[�����s���A���N�U������m�ꌳ�ɑ���[�U�O���̌��葊����߂��B����ɂ���V�[�͌���m�[�̕⏕�݂ƂȂ�A�V�ʉ݂��錻��m�[�̉��ɉݕ����l�͈ꉞ��������������̂ł������B�x
|
�@������A�̋L�q�́A�����Ɉ��p�������������V���̃v���o�K���_�L���L���Ƃ͑�������قɂ���B
�@�O���̋L�q�ɑ����āA�É��͎��̂悤�Ɍ����B
| �w |
�̂��̖��B���̕������ꂪ�A������������m�[�̈��萫����b�ƃX����̂ł��������Ƃ́A�R�Q�N���B������s�̔����ɂ������āA���O�Ȋ��⍆�̌���m���Ɂu���B������s�v�̎��������Ďb��I�Ȗ��B���ʉ݂Ƃ������Ƃ����Ă����炩�ł������B�x�i�R�Q�N�V���P���t���@���B������s�����B�Ȃ��A�O�f���������V���̋L���ł͂��̎����ɑS���G��Ă��Ȃ��B�j |
�u���B���v�́A���w�ǐ����̍��Y���������ăX�^�[�g�����Ƃ�������͑��ɂ�����B |
|
 |
|
�@��������b�g�������c���ɂ�����悤�ɁA���{�R�́A
| �w |
�i���P�X�R�P�N�j�X���P�X����V�苒�̒���A�x�ߋ�s�i������͐�ɂ��������w�ǐ������̊e������s�̂��Ɓj�A�S���������A�������Ǝ������A�z�R�Ǘ����������̓������͖�O�Ɍ�q��u���A�R���A����玖�Ƃ̍����I���͈�ʓI�̒����s��ꂽ��B�x
�i�O���ȉ���w���b�g�����S���x�����V���Ё@�P�X�R�Q�N�j |
�Ƃ���悤�ɁA�����̎�Ȋ����E�������𐧈����A�����ɓ��{�l�����𑗂荞��ŁA�����̃V�X�e�����ĊJ�����邾���ł��Ƒ��肽����ł���B
�@�������Č��Ă���ƁA�u�c��_�_���v�Ɏ����ꂽ�u���B�͖��Z�̍r��ł���A�P�X�R�Q�N���B�������ɂ���ď��߂ĊJ���ɒ��肳��A�킸���̊Ԃɋߑ�H�ƍ��Ƃɐ��܂�ς�����B�v�Ƃ����F���͑傢�ɉ������Ȃ��Ă���B
�@���̔F���͉����u�c��_�_���v�₻�̔w��œc��_�𑀍삵�Ă���u��Q�ϑz�j�ρv�̊w�ҁE�����҂����̔F���ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���������̓��{�l���A�u���B�v�ɑ��ĕ����Ă���C���[�W�ł͂Ȃ����낤���H
�@����܂Ō��Ă����悤�ɁA�������E���w�ǐ������Ŗ��B�́A�����Ȍo�ϊJ���ƁA�����̈�����������Ă����Ƃ������Ƃ��]����B
�@�鍑��`���{�́A�����������肵�����B���قږ����ŏ�����A����u�������v�̈�Y�̏�ɁA�u���B���v�Ƃ������S���Ƃ�ł����āA����ɐ펞�̐����́A�ɂ߂Ă��тȋߑ�H�Ɖ���i�߁A���D�ƍ����������Ȃ���A�ŏI�I�ɂ́A�u���B�v�����̍��ꂩ��j�Ă��܂����̂��Ǝv����B
�@���������������Ƃ���Ȃ�A���̑����̓��{�l�́A�u���B���H�Ɖ������͓̂��{�v�Ƃ���������F�����O�������т��Ď����������̂��E�E�E�B
�@�u�c��_�_���v�Ȃǂ������̕����Aꡂ��Ɋ�{�I�Ȗ�肾�Ǝv���ĂȂ�Ȃ��E�E�E�B
|
|
| �i�ȉ�����j |
 |
 |